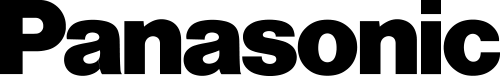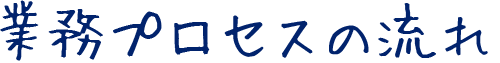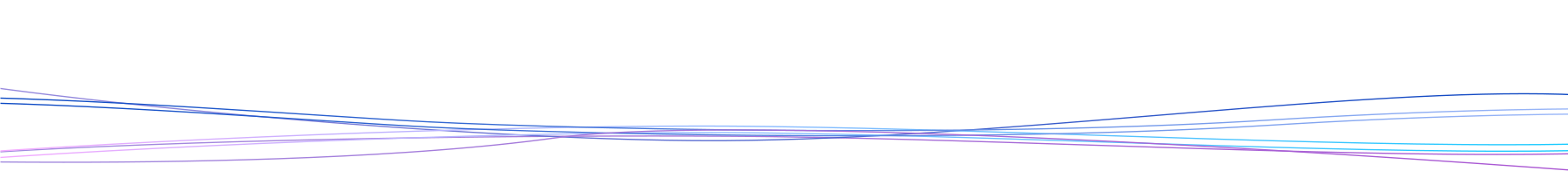戦略策定で抽出した課題を解決するために、具体的なITの企画を行います。「戦略策定で決められた改善策を実現するには、どのようなITソリューションが必要なのか」を前提に、予算やスケジュール、人員など様々な条件を考慮し、これまで培ってきたITのスキル・知識を総動員してお客様の課題解決に最適なITを提案します。

企画を通じ、お客様がシステムに求めるものやシステムに期待される役割や効果を明確にできたら、いよいよそれを実現するために必要な機能や性能等の要件を定義していきます。この“要件定義”は、システムの方向性を左右する非常に重要な工程です。システム開発が成功するか失敗するかは、この要件定義にかかっているといっても過言ではありません。

それぞれ設計書に落とし込む
要件定義が完了したら、次にシステムのユーザーインターフェースである外部設計を行い、設計書に落とし込みます。ユーザーインターフェースはシステムの見た目であり、利用者の使い勝手に大きく影響するものです。また、データの保存先やセキュリティについても、この段階で決めます。
システムの外部設計が完了した後、システムの動作などを検討する内部設計に進むのが一般的な流れです。内部設計では、技術者がプログラミングできるレベルまで細かく設計され、お客様からの視点でシステムの外部を設計する一方、技術者側からの視点でシステム内部を設計することが特徴です。

全体として正しく動作するかテストする
システム設計を通じて設計書が完成したら、実際にプログラミング(コーディング)していきます。プログラミングにより実際のシステムを開発したら、問題なく動作するかチェックするためにテストを実施します。テストによりシステムの動作に問題がなければ、いよいよお客様先へシステムを導入します。

効果的な利用を促進、新たな企画に結びつける
システムの移行が完了し実際にシステムが稼働した後は、運用・保守の段階に進みます。システムが停止しないよう監視するほか、効果的な利用を促進します。また、お客様から依頼されたシステム開発だけでなく、当社からご提案させて頂く新たな企画に繋げることも大切な仕事です。