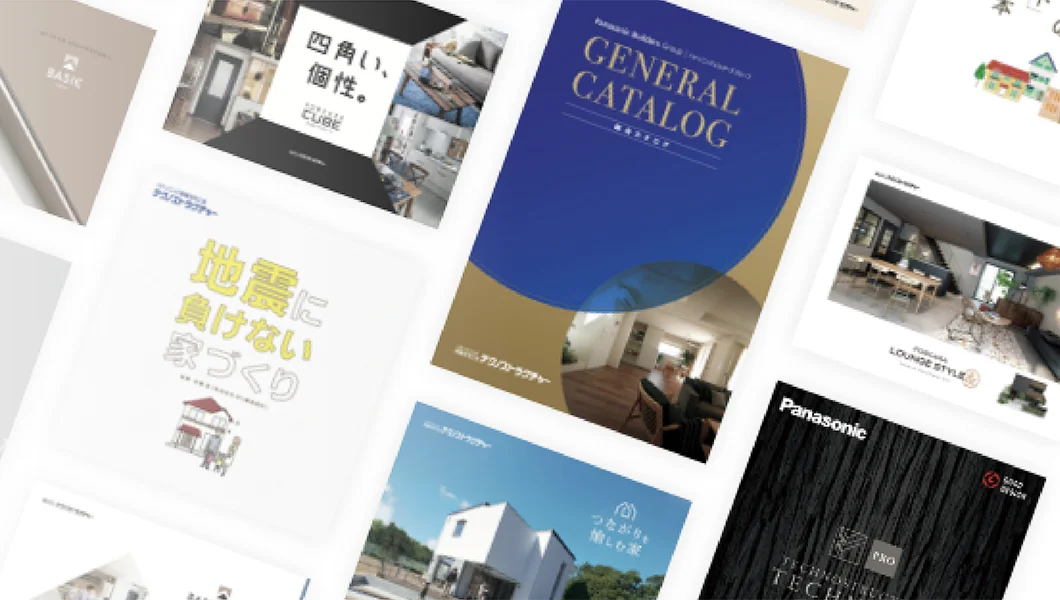超高齢社会の日本。バリアフリー化が住まいに与えるメリット
バリアフリーを考えた住まいは、高齢者になってからも住みやすいだけでなく、誰もが使いやすい住まいにです。
バリアフリー法は、正式名称を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」と言います。
2018年(平成30年)、そのバリアフリー法の一部を改正する法律案が閣議決定されました。
これは公共施設のバリアフリー化を推進するものですが、日本の住宅では以前からバリアフリーへの取り組みが進められています。
なぜ日本の家づくりでバリアフリー化が進められてきたのでしょうか?
日本の家づくりとバリアフリーについてご説明します。

バリアフリー
「「バリアフリー」という言葉は、国土交通省の公式サイトでは、次のように説明されています。
障害のある人が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを除去するという意味で、もともと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く障害者の社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも用いられる。
一般的に「バリアフリー」というと、建物の段差を取り除くことをイメージする方も多いでしょう。
住宅に関するバリアフリーには、以下のようなものがあります。
- 車椅子でも移動できるように、玄関や家の中の段差をなくす
- 高齢者向けに玄関、脱衣室、浴室、トイレ、階段などに手すりをつける
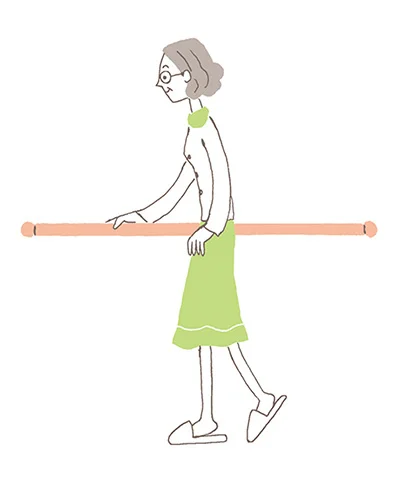
日本では2006年(平成18年)に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー新法)」が施行されました。
これによって、建築物だけでなく公共交通機関、公共施設、道路などでバリアフリー化が進んでいます。
日本でこうしたバリアフリー化が進められる理由の一つとして、「高齢化社会」が挙げられます。
高齢化社会から超高齢社会へ
わが国の総人口は1憶2550万人。そのうち65歳以上の人口は3,621万人で総人口に占める割合(高齢化率)は28.9%になっています。(2021年10月1日現在)
65歳以上の人口が、全人口に対して7%を超えると「高齢化社会」、14%を超えると「高齢社会」、21%を超えると「超高齢社会」と呼ばれます。今、日本は「超高齢社会」と呼ばれる状況に至っています。
さらに、2040年には、第二次ベビーブーム期に生まれた世代が65歳以上となり、総人口に占める割合が35.3%になると見込まれています。※
※国立社会保障・人口問題研究所の推計より
そんな「超高齢社会」に対応するため、高齢者が日常生活を送りやすいよう、住宅や公共施設などでバリアフリー化が進められています。

高齢になると足腰が弱くなる、体力が低下するといったことが要因で、歩く・立つ・座るといった日常の動作が負担に感じられたり、段差につまずいて転倒したりする恐れが増します。
また、車椅子を利用することになった場合、必要なスペースが確保されていないと、移動にも不都合が生じてしまいます。
そこで、高齢者が日常生活を送りやすいよう、住まいにも工夫が必要になります。
では、高齢者にやさしいバリアフリー化とは、どのようなものでしょうか?
その基準の一つに、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会による「住宅性能表示制度」における「高齢者等配慮対策等級」があります。
高齢者等配慮対策等級
高齢者等配慮対策等級には「専有部分」と「共有部分」の2種類があります。
このうち「共有部分」はアパート、マンションなどの共同住宅のみに適用されます。
高齢者等配慮対策等級は、専有部分と共用部分それぞれ1~5の等級があります。
その等級は、以下の項目の程度を組合わせて判断されます。
- 移動時の安全性に配慮した処置
- 介助の容易性に配慮した処置
廊下の幅や部屋の広さなどは、大規模な工事が必要になる場合が多いので、新築時点で考えておきたい対策です。
移動時の安全性に配慮した処置
-
垂直移動の負担を減らすための対策
階段に手すりを設けたり、勾配をゆるやかにする。利用する部屋と主要な部屋を同じ階に配置する。 -
水平移動の負担を軽減するための対策
段差を解消したり、少なくしたりする。段差がある場合には手すりを設ける。 -
転落事故を軽減するための対策
バルコニーや2階の窓などに手すりを設ける。 -
脱衣、入浴などの姿勢変化の負担を軽減するための対策(専有部分のみ)
玄関やトイレ、浴室、脱衣室などに手すりを設ける。
介助の容易性に配慮した処置
-
介助式車椅子(自走式車椅子)での通行を容易にするための対策
通路や出入り口の幅を広くする。廊下の段差を解消する。 -
浴室、寝室、便所での介助を容易にするための対策(専有部分のみ)
浴室、寝室、トイレのスペースを広くする。 -
自走式車椅子でのエレベーターの乗降を容易にするための対策(共用部分のみ)
エレベーターやエレベーターホールのスペースを広くする。 -
階段の昇降を容易にするための対策(共用部分のみ)
階段の幅を広くする。
等級は、これらの対策を組み合わせて、その手厚さの程度で評価します。
※一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 公式サイトより

具体的には、たとえば高齢者等配慮対策等級3では専有部分において次のような基準が設けられています。
- 日常生活空間のうち、便所を特定寝室のある階に設置する
- 日常生活空間内の床を、段差のない構造とする
また、階段の高さや幅、手すりの高さについても詳細に定められています。
こうした高齢者等配慮対策等級の基準に適合する家を建てるメリットとしては、転倒などのリスクを減らすことができることはもちろん、日常生活を送りやすくなる点があります。
高齢になった親と一緒に暮らす場合、介護する時のことを考えたら必要な仕様が多いですよね。自身がケガや病気になったり、高齢者になった時にも安心して過ごせます。
また、住まいのバリアフリー化を通して高齢者になった先の暮らしや家のことを考えると、ぜひ知っておいてほしい制度があります。
それは「長期優良住宅制度」です。
長期優良住宅
2009年(平成21年)6月に施行された『長期優良住宅の普及促進に関する法律』(長期優良住宅法)では、建物の構造や設備などが一定の基準を満たし、長期にわたって維持保全ができる住宅を「長期優良住宅」として認定し、税制上の優遇などが受けられるとしています。
その長期優良住宅の認定基準は、次の10種類です。
- 劣化対策
- 耐震性
- 維持管理・更新の容易性
- 可変性
- バリアフリー性
- 省エネルギー性
- 居住環境
- 住戸面積
- 維持保全計画
- 災害配慮
このうち、「可変性」「バリアフリー性」は共同住宅のみに適用される基準ですが、家自体が高齢になっても長く暮らせるような良質な家であれば安心できるのではないでしょうか。
そして長期優良住宅に認定されると、住宅ローン減税の控除額が大きくなるなどの優遇を受けることもできます。
一般住宅と長期優良住宅の差
| 住宅ローン減税 | 住宅資金贈与の非課税枠拡大 | |
|---|---|---|
| 一般住宅の場合 |
最大273万円控除 (年間最大21万円×13年間) |
非課税枠が500万円 |
| 長期優良住宅の場合 |
最大455万円控除 (年間最大35万円×13年間) |
非課税枠が1,000万円 |
| ※最大182万円の差 | ※500万円の差 |
※2023年までの情報です。住宅ローン減税や住宅資金贈与の非課税枠拡大については、税制改正により金額や期限が変更になりますので、利用される際は、住宅会社へ確認したり、国土交通省のサイトを確認してください。
まとめ

これから高齢者となった親と一緒に暮らすため、もしくは自身が高齢者になった時のことも考えて家を建てるなら、バリアフリー化について考えておくことが必須でしょう。
また、高齢になった時の暮らしを考えると家も長持ちする必要があります。
新築一戸建てを考えている方は、バリアフリー化について考えるとともに、ぜひ長期優良住宅仕様の家づくりを検討してみてください。