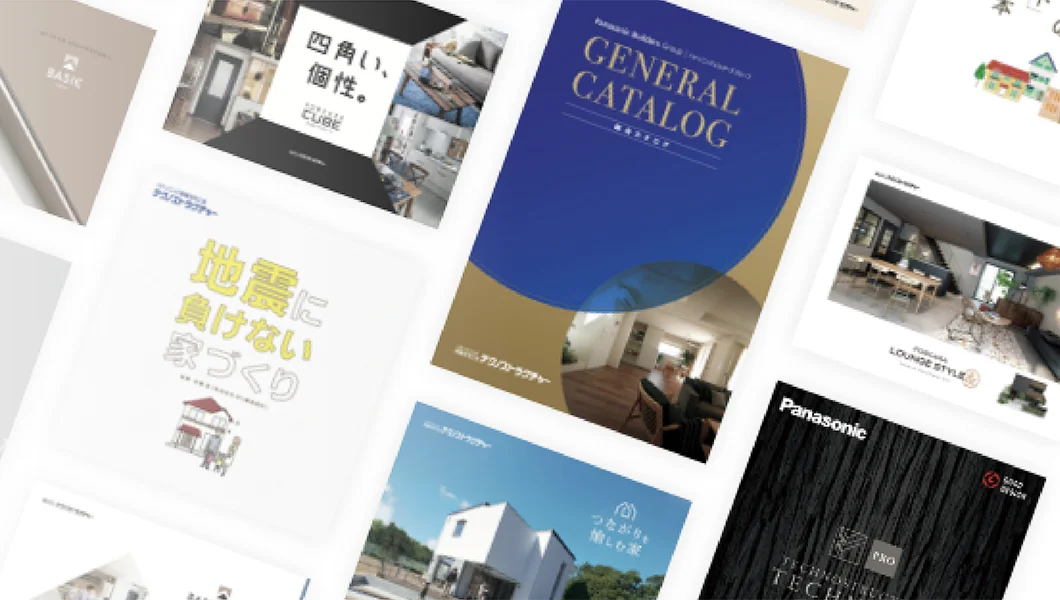地震に強い家を建てるために必要な「構造計算」「耐震等級」とは?
皆さん、新しく家を建てる際に最も注意している点は何ですか?
一番関心を持っているのは、どんなところでしょうか。
ここ数年、日本の家づくりにおいては「耐震性能」に注目が集まっています。
それどころか、いまや耐震性能が“必須事項”となっているでしょう。
ただ、一口に「耐震性能」と言っても、その基準をご存じの方は、それほど多くはありません。
一方で「耐震」について詳しくないため、建築業者から「耐震性能もバッチリの家を建てます」と言われながらも、実際のところは耐震性能が備わっていない住宅を建てられてしまい、トラブルに発展するケースも見られます。
このようなトラブルに巻き込まれないよう、家づくりで最も大切な「耐震」について知っておいてください。
ポイントは、「構造計算」と「耐震等級」です。

なぜ「耐震性能」が家づくりで必要なの?
「耐震」とは文字通り、その家がどれだけ地震に耐えられるのか、ということ。
1995年(平成7年)の阪神・淡路大震災、2011年(平成23年)の東日本大震災をはじめとして、日本では大規模地震が多数発生しています。
過去の数々の地震によって、膨大な数の家屋が倒壊しました。
日本は世界的に見ても有数の地震大国です。
そのため、家づくりにおいては「耐震性能」が必須となっています。
建築基準法では、昭和56年(1981年)より、新たな耐震基準が導入されました。
国土交通省の発表によれば、阪神・淡路大震災では、昭和56年以前につくられた建物の6割以上が「大破以上」あるいは「中・小破」の被害を受けています。
対して、昭和57年移行の新耐震基準でつくられた建物は「大破以上」「中・小破」が3割に満たず、7割以上が「軽微・無被害」であったというデータがあります。

さらに、2004年(平成16年)に発生した新潟中越地震を機に、2005年に耐震基準が改定されました。
構造計算とは?
では、家の耐震性能=その家が地震に強いかどうかは、どうやって判断すればよいのでしょうか?
地震に強い家かどうかを知るには、「家の強度確認」が必要です。
「家の強度確認」とは、以下の3つの分野を計算・検討するものです。
壁の強さ…壁量、耐力壁配置、床強度
部材の強さ…柱強度、梁強度、柱接合部強度、梁接合部強度
地盤・基礎の強さ…基礎強度
また、「家の強度確認」には、次の2つの方法があります。
- 壁量計算
- 構造計算
この2つの方法には、以下のような違いがあります。
壁量計算
文字通り、壁の量を計算します。
調べられるのは上記のうち「壁量」「耐力壁配置」「柱接合部強度」のみで、しかも全て簡易な計算のみとなります。
つまり、「壁量計算」では家の強度を細かく調べることはできないのです。
構造計算
対して、3つの分野全てを緻密に調べることができるのが「構造計算」です。

家の大きさや内容、地盤などは家ごとに異なります。
そのため、「家の強度確認」は家ごとの条件に合わせて行う必要があります。
「構造計算」は、家ごとに、その家がどれだけの地震に耐えられるかどうかを調べることができる、科学的で緻密な強度確認方法なのです。
実は「構造計算」は行われていない?
それだけ家づくりに関して重要な「構造計算」なので、どの住宅会社でも行っているだろうと考えている人が多いようですね。
しかし、実は構造計算を行っていない住宅会社が多いことをご存じですか?
構造計算は、2階建て木造住宅のうち、「小規模建築」とみなされる家屋では、法律上義務化されていません。
これらの家の強度確認は、壁量計算のみでもOKなのです。
とはいえ、ご説明したように家の強度を測るには、壁量計算より構造計算のほうが緻密で、安心です。

構造計算は調べる分野が多く、それだけに住宅会社にとっては建設コストがアップする要因にもなります。
それよりはコストダウンにつながる壁量計算で・・・と考える住宅会社があるのも現実なのです。
でも、せっかく建てた家が地震に弱いと、出来上がった後に分かったら・・・。
家づくりを考えている場合は、ぜひ構造計算をしっかり行っている住宅会社を選んでくださいね。
耐震等級とは?
もう一つ、地震に強い家を建てるために知っておきたいのが、「耐震等級」です。
「耐震等級」とは、地震に対する家の強さを示す指標のこと。
以下の3つのランクがあります。
- 耐震等級1
- 耐震等級2
- 耐震等級3
耐震等級1
建築基準法の耐震基準を満たす最低ライン。
その基準は「震度6強の地震が来たとき、傾きはしても倒壊しない」というものです。
もっと分かりやすく言うと、「家は傾いても、その間に人が逃げられたらOK」というレベルになります。
耐震等級2
耐震等級1の、1.25倍の地震に耐えられる強さ。
一般的な病院や学校で採用されている基準です。
耐震等級3
耐震等級のなかでは最高ランク。耐震等級1の、1.5倍の地震に耐えられる強さです。
これは、防災拠点となる消防署や警察書を新築する際に採用される基準と同等になります。

耐震等級1では家は倒壊する!?
耐震等級について注意しておきたいのは、建築基準法に基づいて設計されているとはいえ、耐震等級1では大規模地震に耐えられないかもしれない、という点です。
平成28年(2016年)4月に発生した熊本地震(最大震度7)では、多くの耐震等級1の家が倒壊し、さらに耐震等級2の家も被害を受けたと言われています。
対して同じ熊本地震でも、耐震等級3の家は全壊をまぬがれていました。
この結果から、大規模地震が来ても耐震等級3の家であれば安心、という考えが普及しつつあるようです。
構造計算と耐震等級で「地震に強い家づくり」

地震大国ニッポンでは、地震に強い家づくりが求められています。
安心・安全な家を建てるためには、様々な指標があります。
なかでも「構造計算」と「耐震等級」という、2つの指標が重要となります。
より安心できる家づくりのために、構造計算によって緻密な強度確認をすること。
そして、目指す強度の指標として、「耐震等級3」の基準を持つこと。
この構造計算と耐震等級は、住まいを建てる際には両方とも持っておきたい指標です。
大切な家族を守ることができる安心・安全な家を建てるためにも、構造計算と耐震等級について、ぜひ知っておいてください。