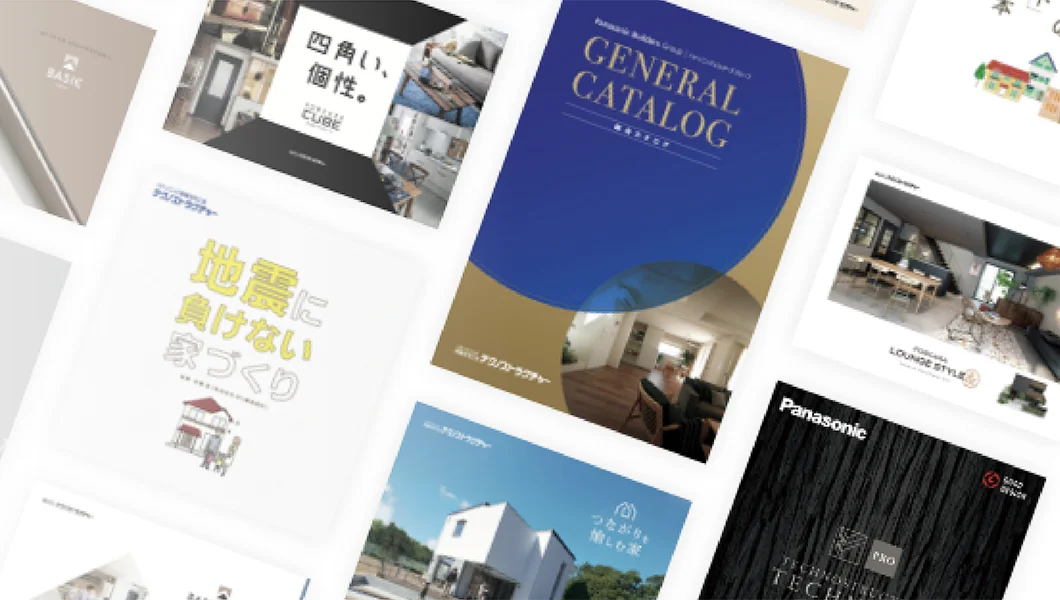3階建て住宅を選ぶうえで、知っておくべき高さや場所に関する規制
国土交通省の統計によれば、木造3階建て以上の住宅は、1年間に3万棟近く建てられています。
その大半は戸建て住宅です。
狭い土地であっても多くの部屋数が確保できるなどのメリットがある3階建て住宅。
しかし、3階建て住宅については、知っておかなくてはならない法律や規制があります。
どこでも3階建て住宅が建てられるわけではないのです。
そこで3階建ての住まいに関する重要な情報をお伝えします。

3階建て住宅に関わる法律・規制とは?
3階建て住宅は、都市部でよく見られる狭小地をうまく活用するためには効果的です。
同じ広さの土地でも、2階建てよりは3階建てのほうが、部屋数を増やせます。
しかし、どんな土地でも3階建て住宅をつくることができるわけではありません。
3階建て住宅を建てたい場合には、主に以下の規制について知っておく必要があります。
- 用途地域
- 斜線制限
用途地域
建物の高さには、様々な制限が設けられています。その一つが「用途地域」による制限です。
「用途地域」とは、その土地(地域)の利用目的(用途)が決められており、それぞれの地域で建物の種類や高さなどが決まっています。
住居に関わる用途地域には、次のものがあります。
第一種低層住居専用地域
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域。高い建物や不特定多数が集まるような施設など、騒音を出すような用途の建物は建築できません。3階建て住宅を建てることは難しい場所です。
第二種低層住居専用地域
主に低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域。第一種低層住居専用地域との違いは、店舗を建築できること。制限はありますが、コンビニなどの店舗が建築できます。第一種低層住居専用地域同様、3階建て住宅を建てることは難しい場所です。
第一種中高層住居専用地域
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域。建物の高さ制限はありません。2階建て以内で床面積が500㎡以下の店舗が建てられます。また、教育施設や病院、図書館などが建てられます。3階建て住宅も建てられます。
第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域。建物の高さ制限はありません。2階建て以内で床面積が1500㎡以下の店舗や事務所が建てられます。
第一種住居地域
住居の環境を保護するための地域。建物の高さ制限はなく、第一種・第二種中高層住居専用地域で建てられる建物以外に、3000㎡までの店舗や事務所のほか、ホテルも建てられます。
第二種住居地域
主に住居の環境を保護するための地域。第一種住居地域で建てられる建物以外に、ボーリング場やスケート場、床面積10,000㎡以下ならパチンコ店なども建てられます。
準住居地域
道路の沿道という特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための地域。第二種住居地域で建てられる建物に加え、車庫や倉庫、客席部分200㎡未満の映画館などが建てられます。
田園住居地域
農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域。2019年4月に用途地域に追加されました。住宅のほか、教育施設や図書館、病院などが建てられるほか、2階建て以下の農産物直売所や農家レストランなどが建てられます。
気に入った土地があり、「少し狭いけれど、3階建てにすれば問題ないだろう」と考えても、いざフタを開けてみると3階建ての住まいを建てることができない、というケースもあります。
そんなことにならないよう、事前にしっかり調べておくことが大切です。
斜線制限
「日照権」という言葉を聞いたことがある人は多いでしょう。
日照権とは、建築物の日当たりを確保する権利のこと。高層の建築物をつくり、周囲の住宅の日当たりを阻害すると、この日照権に関わります。
この日照権を考えるうえで重要なものに、北側隣家の日当たりを考慮した「北側斜線制限」があります。
また、道路の幅によって高さを制限する「前面道路斜線制限」についてもご説明します。
北側斜線制限
北側に設置する敷地の環境を保護するための制限です。
この北側斜線制限によっては、建物の高さだけでなく形も制限を受けることがあります。

ほかにも隣人の日射や採光、通風など良好な環境を保つため、高さを規定する「隣地斜線制限」、建物でできる影が周辺の土地に一定時間かからないように高さを制限する「日影規制」といったものもあります。
その土地にどんな制限が適用されているのか、また制限の数値・内容については住宅会社や不動産会社に問い合わせるだけでなく、管轄の役所で調べることもできます。
前面道路斜線制限
「道路斜線制限」とは、道路の採光や通風が確保されるように道路に面した建物の高さを制限するもの。敷地が接する道路の反対側の境界線から、どれだけの範囲に建物をおさめなければいけないか、という制限になります。
こちらも北側斜線制限と同じく、建物の高さと形に対して制限を受けることがあります。
土地選び、住宅選びの際は必ず敷地が接する道路についてもチェックしておきましょう。
敷地の東西南北どの方向に道路が接しているのかによって、家の間取りは大きく変わってきますし、土地の価格自体も差が生じるようです。
建ぺい率と容積率
これは3階建て住宅に限った話ではありませんが、家づくりにおいて最も注意しておかなくてはいけないものの1つが、「建ぺい率」と「容積率」です。
建ぺい率
敷地面積に対する建築面積の割合を「建ぺい率」と言います。
都市計画区域内では、用途地域の種類によって建ぺい率制限が設けられています。
住宅を建てる場合には、建ぺい率の数値をその制限内に収める広さにしなければいけません。

建ぺい率の計算式は次のとおりです。
建ぺい率(%) = 建築面積 ÷ 敷地面積 ×100
たとえば100㎡の敷地で、建ぺい率50%の場合、建築面積の上限は50㎡となります。
この制限は新築だけでなく、増築の場合も適用されます。
容積率
敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合を「容積率」と言います。
都市計画によって決められた数値と、前面道路の幅員(横の長さ)との、いずれか小さいほうの数値が容積率の限度として適用されます。
容積率の計算式は次のとおりです。
容積率(%) = 容積対象面積 ÷ 敷地面積 × 100
たとえば100㎡の敷地で、建ぺい率50%、容積率80%の土地の場合は、延べ床面積の上限は80㎡となります。
3階建て住宅の場合は、この容積率が重要です。

延べ床面積の上限が80㎡の場合、1階、2階、3階の延べ床面積の合計を、この上限の数値以内に収めなければいけません。
1階の面積を建ぺい率上限までいっぱいにすると、2階と3階の面積は必然的に小さくなってしまいます。
防火地域
地域によっては「防火地域」あるいは「準防火地域」の指定が行われています。都市部は建物が密集しているので、火災時に火の手が周囲に広がらないよう、建物の構造や材料に制限が設けられているものです。
これらの地域では、3階以上の建築物は防火に関する一定の基準に適合していなければ建てることができません。
まとめ

3階建て住宅を選ぶうえでは、ここまでご紹介してきた法律や制限だけでなく、耐震性能についても注意してください。
3階建て住宅は建物の総重量が重く、かつ構造も複雑になります。
地震では、上の階の重みに耐えきれなくなった1階から倒壊していくケースが多いようです。
そのため、しっかりとした耐震構造を考えることは、2階建て住宅以上に重要になります。
大切な家族と住む住宅として3階建てを選ぶ。その大切な家族を守るためにも、耐震構造の検討は必須です。