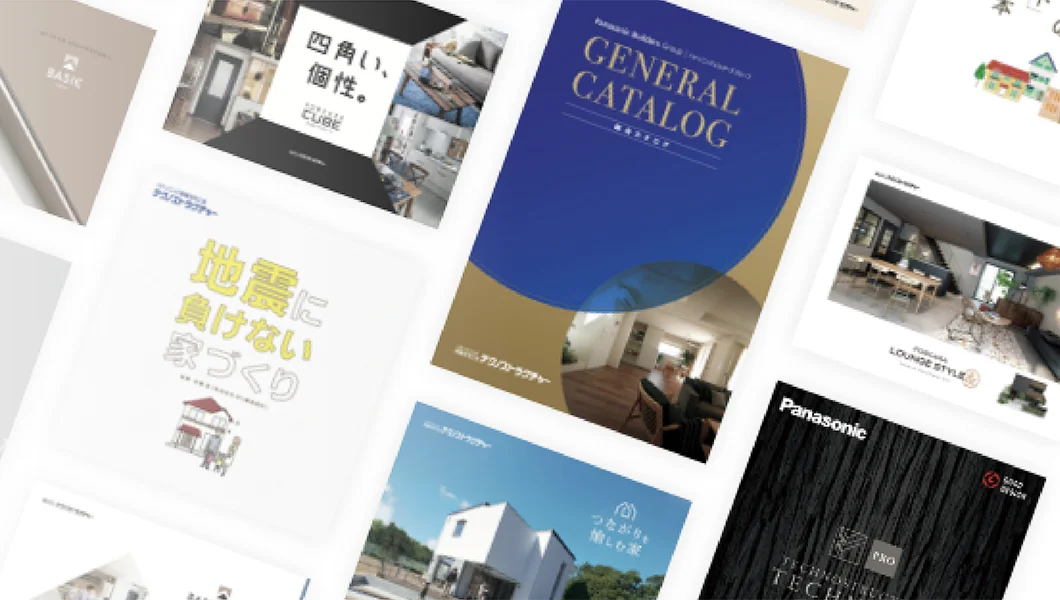地震に強い家をつくるために知っておくべき耐震・制震・免震の違い
地震に強い家とは、地震の揺れに耐えられるよう設計された家のこと。
地震大国の日本では、家づくりに耐震構造や強さが求められています。
そこで新築の一戸建てなど新居を検討しているのであれば、自分自身でも耐震構造について知っておくと、住宅会社選びの際に参考になるかもしれません。
たとえば「耐震」「制震」「免震」の違いはご存じですか?この3つの言葉には、実は大きな違いがあります。
地震に強い家を建てるために知っておきたい、この「耐震」「制震」「免震」の違いについてご説明します。

地震の揺れは「縦揺れ」「横揺れ」の2種類
そもそも「地震」とは一体何なのでしょうか? どうして地震は起きるのか。
気象庁ホームページでは、地震について次のように書かれています。
地震とは、地下の岩盤が周囲から押される、もしくは引っ張られることによって、ある面を境として岩盤が急激にずれる現象のことをいいます。この岩盤の急激なずれによる揺れ(地震波)が周囲に伝わり、やがて地表に達すると地表が「揺れ」ます。私たちはこの「揺れ」で、地震が地下で発生したことを知ります。
地震の「揺れ」には、以下の2種類があります。
- 縦揺れ
- 横揺れ
「縦揺れ」と「横揺れ」の違いは、文字通り
「縦揺れ」=上下に揺れる
「横揺れ」=水平に揺れる
というもの。
この2種類の揺れについては、インターネット上でも
「縦揺れのほうが先に来て、後から横揺れが来る」
「縦揺れよりも横揺れのほうが家屋の被害は大きい」
といったことが書かれている記事が見られますよね。
ただし、一概にそうであるとは言えません。

地震の揺れは、どの方向から来るか分かりません。
そもそも、いつ地震が起きるのか分からないなかで、その方向まで予測することは難しいでしょう。
世界的に見ても有数の地震大国である日本において、大切なのは「もしも」の時のためにしっかり備えておくことです。
特に日常生活を送る住まいには、耐震構造が必須なのです。
家には揺れやすい方向がある
地震が起きて家が倒壊しなくても、食器棚や本棚などが倒れて、ケガをしたり、被害につながったりすることもあります。
建物が長方形の場合には、長さが短い方向へ揺れやすくなります。家具も同様に、横に長い家具は、横揺れに強く、縦揺れには弱くなります。家具を置く場合は、建物の揺れやすい向きと家具の揺れにくい向きが平行になるように配置するなど、工夫しておきたいですね。
また、寝る場所や出入り口の近くなどに家具を置かないことも大切です。転倒防止マットや、固定器具で家具を固定して、家具が倒れてこないようにすれば、より安心です。
耐震・制震・免震の違いとは?
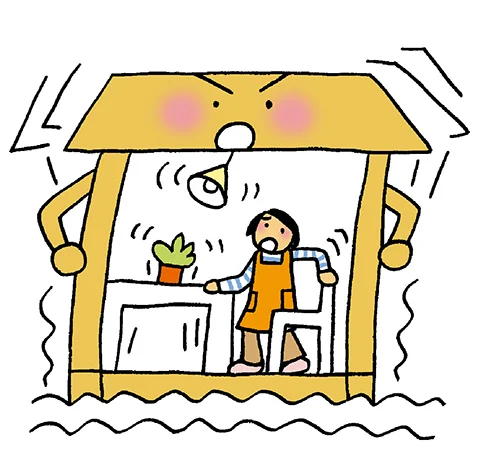
耐震:地震の揺れに耐える
「耐震」とは、文字通り「地震の揺れに耐える」構造を言います。地震対策の基本となる構造です。
接合部材や筋かいなどで建物の骨組みを強化し、建物が崩壊するのを防ぎます。
メリットは、「制震」「免震」に比べてコストが安いこと。また、免震構造の場合、地下室が作れないなどの設計に制約がでる場合がありますが、耐震構造は比較的自由に設計できます。
デメリットは、家具の転倒や落下の可能性が高く、地震の際の二次被害への対策が弱いことです。家具はタンスなどの背の高いものや、テレビ台に乗ったテレビなど、置かれた場所や条件で、さまざまな動きをします。家具を転倒させないために、揺れにくい向きに配置したり、固定したりすることが大切です。
制震:地震の揺れを吸収する
「制震」とは、建物の揺れを吸収する仕組みです。
地震による建物の揺れは、上の階に行けば行くほど大きくなります。
そこで下層階に「ダンパー」と呼ばれる制震装置を組み込み、地震の力を吸収することで、揺れを抑えるというシステムです。
メリットは、家の2階、3階の揺れは軽減され、地震が来たときに家具が転倒するといった不安もやわらげることができます。
デメリットは、地盤による影響が大きいことです。地盤が軟弱だと揺れを吸収できず、十分な効果が発揮できないケースもあります。また、耐震工法より費用が高くなることも、施主の負担につながります。

免震:地震の揺れを逃がす
「免震」とは建物と基礎部分の間に、免震装置(積層ゴムなど)を入れることで、地震の揺れをその免震装置が吸収し、建物に揺れが伝わるのを防ぐという、「耐震」「制震」とはまた別の仕組みです。
メリットは、地震による揺れを軽減できるため、建物への被害を抑えられることです。また、他の工法に比べて家具の転倒も防げます。
デメリットは、縦揺れに対して効果が薄いことや、他の工法に比べてコストが高いことです。
耐震+制震
「耐震」「制震」「免震」の違いは、お分かりいただけたでしょうか?
耐震性能や関連する技術は常に進化しています。現在ではこの3種類だけでなく、実は各性能を組み合わせた方法も提案されています。
たとえば、その一つが「耐震」と「制震」の組み合わせです。
地震対策の基本である「地震の揺れに耐える」耐震に加えて、さらに地震の揺れを吸収する制震システムを組み合わせることで、家に対する安心は増します。
耐震等級
地震に強い家、耐震構造を考えるうえで、「耐震」「制震」「免震」とは別にもう1つ、必ず知っておきたいのが「耐震等級」です。
耐震等級とは、住宅の耐震性能を評価する表示する制度。等級は1、2、3があり、基準は以下のようになっています。
耐震等級1
建築基準法の耐震基準を満たす「震度6強の地震が来たとき、傾きはしても倒壊しない」というレベルの家です。
耐震等級2
耐震等級1の「1.25倍」の地震力に耐えられる強さの基準です。
耐震等級3
耐震等級1の「1.5倍」の地震力に耐えられる強さの基準です。地震が来たときの防災拠点となる消防署や警察署を新築する時は、この耐震等級3相当の強さで建てられています。
耐震等級1でも建築基準法はクリアしていますが、地震大国である日本で家を建てるうえでは、地震対策としては不安が残りますよね。やはり、「もしも」のこと考えると、地震への備えとしては耐震等級3の家が理想的と言えます。
いつ来るか分からない地震への耐震対策を!
地震大国・日本では、いつ、どの場所を大地震が襲うかは分かりません。 過去の大地震を見ても分かるとおり、特に地震で家屋が倒壊したときの人的被害は大きなもの。
ずっと住んでいた家が、地震によっていきなり人を襲う“凶器”と化すのです。
そんな事態を防ぐためにも、家づくりに際しては耐震構造に注意を払っておかないといけません。
いつやってくるか分からない、「もしも」のために耐震構造は必要不可欠です。
「耐震」「制震」「免震」、そして「耐震等級3」、この言葉をしっかりチェックしてください。