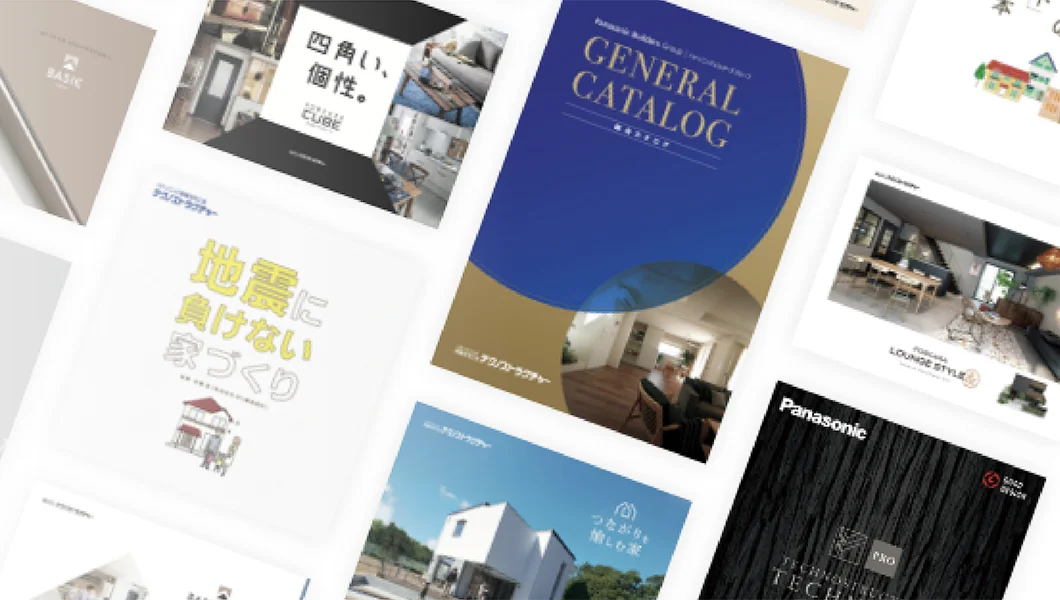木造住宅は地震に強い? 木造と鉄筋コンクリート造の違いとは?
巨大なプレートに沿う形になっている日本は、「地震大国」と言われています。
これまで阪神淡路大震災や北海道南西沖地震、東日本大震災、熊本地震、北海道胆振東部地震など、大地震に何度も見舞われてきました。
私たちの生活を守る、地震に強い家づくりの重要性が改めて見直されるきっかけにもなった大地震。
では、「地震に強い家」とは、どんな家なのでしょうか?
そこで、家づくりの代表的な3つの工法をご紹介するとともに、それぞれのメリット・デメリットについてもご説明します。

代表的な家づくり3つの工法
これから家を建てるとしたら、どんな家を建てたいと思いますか?
家づくりの代表的な工法としては、以下の3つが挙げられます。
- 木造
- 鉄筋コンクリート造(RC造)
- 鉄骨造
木造
日本国内の戸建ての多くが、木造住宅です。
日本の伝統的な木造軸組工法といえば、たとえば木の柱と梁で支える工法です。
この工法には、建築築費用を安く抑えられるというメリットがあり、比較的自由度の高い設計ができます。
木の家は、温かみを感じさせる空間を作り上げてくれる一方で、年数とともに劣化する点はデメリットといわれます。

特に建築素材としての木は、柱に使用する縦の力には高い強度を発揮するのですが、梁のようにして使用する横からの力には弱い、という面があります。
柱や梁が傷んでしまうと、家全体の構造ももろくなり、大きな地震には耐えきれず倒壊してしまうリスクも考えられます。
こういった理由から、「木造住宅の耐震性はどうなの?」といった疑問を持たれることもありますが、近年は耐震性の高い木造も開発され注目されています。
鉄筋コンクリート造(RC造)
鉄筋コンクリート造(RC造)とは、鉄とコンクリートのそれぞれの長所を生かした工法といわれます。
引っ張られる力に強いが、圧縮には弱い鉄と、圧縮には強いが引っ張りには弱いコンクリート。
この2つの素材を組み合わせることで、お互いの弱点を補いながら両方の長所を生かすことができます。

そのため、RC造では、高い強度をもった構造の住宅を作り上げることができます。 耐震性・耐火性にも優れているので、地震に強い家づくりができる工法の一つです。
一方で、鉄筋コンクリート造(RC造)は木造に比べて、工期とコストが掛かるという点がデメリットといえます。
鉄骨造
断面がH型や四角形をしている鋼材を柱や梁に用いた建築工法のことを、鉄骨造と言います。
RC造に比べ、シンプルな施工なので、工期も短く価格もRC造よりも安く抑えられるというメリットがあります。
しかし、鉄骨はさびやすいという特徴があるため、防錆処置などの施工が必要です。
また、RC造よりも耐火性が低いとも言われており、鉄骨造の場合は耐火被膜などの施工も求められます。
木と鉄の良い点を組み合わせた工法とは?
ここまでご説明してきたとおり、木造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造には、それぞれメリット・デメリットがあります。
木造住宅の耐震性は? と疑問を持つ方もいるようですが、それでも日本では木造住宅を好む方が多いですよね。
では、木造で地震に強い家を建てることはできないのでしょうか?
そう考える人には、こんな工法があります。
住宅ではありませんが、木造の歴史的建造物の中には、木だけでは支えきれなくなった屋根の重さを鉄骨で支える修繕工事を行った、という例があります。
つまり、これは木の弱点を鉄で補うという手法がとられたのです。
実はこの例と同じように、木の弱点を鉄の強さで補う手法が、住宅においても使われている工法があるのです。

木の弱点を鉄で補う工法のひとつに、梁として使用する木材の真ん中に鉄を入れて補強する、という手法があります。
木のたわみや変形を防ぎ、地震などの一時的な大きな力にも十分に耐えうる力を持っており、家全体の強度を高めることができます。
「耐震」のためには「構造計算」が必要です
日本で暮らす私たちにとって、地震被害は大きな脅威です。
特に大地震が頻発している昨今では、これからの家づくりも十分な耐震性を持った家を検討したいですよね。
そのためには是非、地震に強い家=材料や工法が強いだけではない、ということを覚えておいてください。
とても大切なのが、地震や台風に十分耐えうる家かどうかをチェックする構造計算を行うことです。
構造計算は、本来であれば、一棟ごとに行います。
しかし日本の建築基準法では、鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨造に義務づけられている構造計算が、2階建て以下のほとんどの木造住宅で義務づけられていません。
そのため、2階建て以下の木造住宅では、簡易的な壁量計算のみを行っている住宅会社も多いのが実情です。
本来は構造計算によって、基礎の強さや耐力壁の配置と量、床や柱の強さ、梁の強さ、接合部の強さなどの細かなところまで、シミュレーションによって、すべてチェックを行うことが理想的と言えます。

木造を希望する場合は木の弱点を鉄で補強する工法を用い、木造住宅では義務づけられていない構造計算を行えば、家の強さを確かめることができてより安心でしょう。
緻密なチェック項目例
柱の強度
すべての柱について地震や台風などの強い負荷がかかった場合、変形や破損する危険性がないか。
床の強度
地震などの横からの力に対しての強度は十分かどうか。
壁の配置バランス
壁の量はもちろん、間取りと設計に応じて壁の配置バランスも厳しい基準で設計されているか。
基礎の強度
地盤の強度に応じて基礎が緻密に設計されているか。
鉄筋の太さや本数なども、その住宅に最適なものを確認して使用されているか。
梁の強度
梁のたわみ量が一般的な木造建築の基準よりもさらに少なく抑えられているか。
柱接合部の強度
筋かいが取り付けられている柱の上下、それぞれが抜けないようになっているか。
梁接合部の強度
木材を組み立てていく木造住宅の接合部についての強度は十分か。
耐力壁の量
家の重さや形状などの条件を加味し、地震や台風に耐えうる耐力壁の量が計算されているか。
さらに、こうした構造計算を生かすのは、現場での施工技術です。
構造計算によって算出された計算結果と同じものを現場で実現できるかどうかが、重要なポイントになります。
まとめ

家づくりの代表的な工法には、「木造」「鉄筋コンクリート造(RC造)」「鉄骨造」の3つがあります。
どの工法にもメリット・デメリットがありますが、木と鉄の良い点を組み合わせた工法など、木造のデメリットが払拭された工法もあります。
また、耐震性を求めるには構造計算を行うことも重要なポイントです。
日本で好まれている木造住宅でも、木と鉄を組み合わせた工法を用い、緻密な構造計算で家の強さを確かめれば、「地震に強い家」を建てることができそうです。