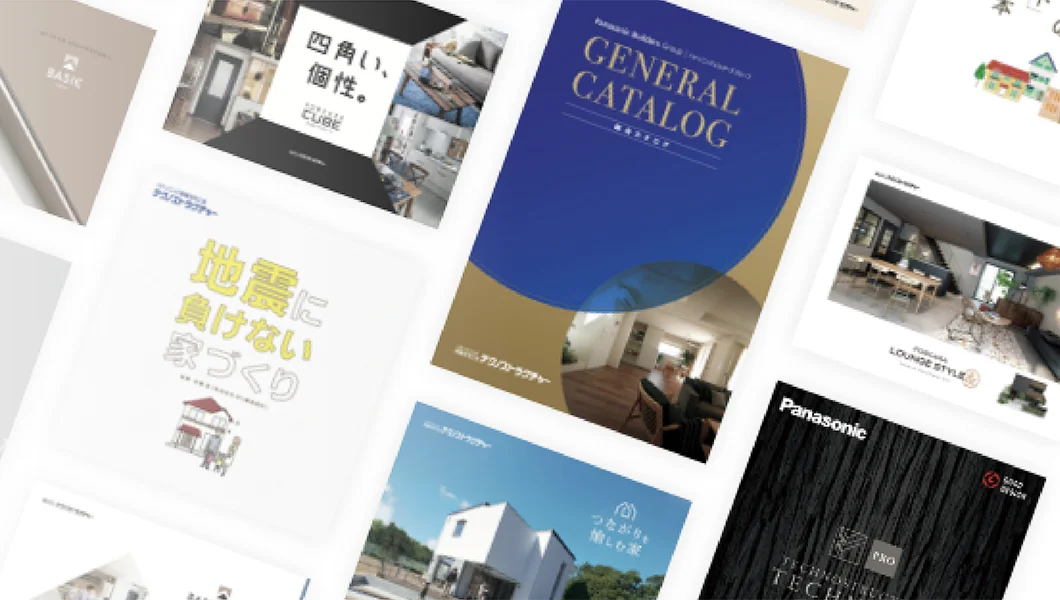構造計算って何? 地震に強い木造住宅をつくるためのポイント
日本の家づくりにおいて今、最も求められているものの一つが「耐震性能」、つまり“地震に強い家づくり”です。
では“地震に強い家づくり”とは、一体どんなものなのでしょう?
地震に強い=耐震性能が高い家をつくるためには、「構造計算」が必要です。
しかし、この「構造計算」というものがあまり知られていません。
そのため、建物の強さについての誤解を生み出したり、時にはトラブルに発展するケースもあるようです。
「構造計算」はなぜ必要なのでしょうか? そしてどのように行われるのでしょうか。

耐震性能=地震に強い家とは?
日本は世界でも有数の地震大国です。
1995年(平成7年)の阪神・淡路大震災
2011年(平成23年)の東日本大震災
2016年(平成28年)の熊本地震
2018年(平成30年)の北海道胆振東部地震※
をはじめ、日本では大規模地震が発生し、膨大な数の家屋が倒壊しました。
そのため、日本の家づくりでは「耐震性能」が求められているのです。
耐震性能を持つ家、地震に強い家とは、どんな家屋のことを言うのでしょうか?
それを知るためには、まず大きな地震が発生したとき、家がどうなるかを知っておく必要があります。
※2018年9月20日追記
大地震に襲われた家が倒れる仕組み
大地震に襲われた家が倒れるパターンのなかでも多いのは、次のようなものです。
2階建て以上の家屋で、2階以上の重みに耐えきれず1階から家が壊れていく
ただ、見た目には同じ形や同じ大きさの家あっても、実際は細かいところに違いがあるもの。
そのため、似たような家でも大地震で壊れてしまう家と、被害が少ない、あるいは被害を受けていない家があることをご存じでしょうか?

同じ地震の揺れを受けても、家が倒れる場合と倒れない場合があります。その差を生み出すのが、“家の強度”です。
地震に強い家をつくるためには、この“家の強度”を高める工夫が必要なのです。
どうやって家の強度を確認する?
耐震性能=地震に強い家かどうかを確認するには、以下の2つの方法があります。
- 壁量計算
- 構造計算
壁量計算とは、文字通り壁の量を計算するものです。
一方、構造計算は家づくりに必要な項目を全て緻密に計算します。
つまり壁量計算は、構造計算に対して“簡易な計算”と言うこともできます。
しかし家の強度の確認を、簡易的な計算ですませるよりも、構造計算によって科学的に、かつ緻密に確認するほうが、より耐震性能が高い家づくりにつながります。
なぜ家の強さを緻密に計算しなければいけない?
日本の建築基準法では、家の強さを保つために、必要な壁の量が定められています。
壁量計算は、その基準に沿って壁の量を検討する方法です。
すると「建築基準法で定められた基準に沿っているのだから、壁量計算でも良いのでは?」と思う人も多いかもしれません。
しかし、家ごとに大きさや形が異なります。
また、家は多くの要素が組み合わさって出来ているものであり、壁の量を数えるだけでその強度を確認しきれるものではありません。
家ごとに適した、家の強さを緻密に計算する必要があります。
ところが、日本国内では全ての家に対して構造計算が行われていない理由があるのです。
法律で構造計算が必須となる住宅とは
日本の建築基準法で構造計算が必須となっている戸建住宅は、主に以下の2つです。
- 鉄筋コンクリート(RC造)
- 鉄骨造

また、木造住宅でも以下の条件に当てはまる住宅は、構造計算書の提出が必須となっています。
- 3階建て以上
- 延床面積500㎡以上
対して、延床面積500㎡未満の木造住宅では、構造計算書の提出が免除されています。
2階建て・平屋の木造住宅は、延床面積500㎡未満であることが多いため、構造計算書の提出が免除され、家を建てるには壁量計算でもOKということになっています。
しかし、構造計算書の提出が免除されている=構造計算が必要ない、というわけではありません。
先にご説明したとおり、家の強さを確認するには、簡易的な壁量計算より緻密な構造計算のほうが安心です。
ところが構造計算書の提出が必須ではないために、実は構造計算を行っていない住宅会社が多いのです。
構造計算を行わない住宅会社が多い理由
構造計算を行っていない住宅会社が存在する理由としては、「法律で義務づけられていない」という点も含めて、主に以下のものが考えられます
- 木造住宅で構造計算を行うのは難しい?
- 日本古来の木造建築法が重んじられている?
- 構造計算はコストアップにつながる?
木造住宅で構造計算を行うのは難しい?
木造住宅は、鉄筋コンクリート(RC造)の住宅と比べて複雑な構造になっています。
壁や柱の量、その接合部などの数が大きく異なります。

さらに、木という自然素材は種類・品質や施工方法も様々で、その強度を緻密に数値化することは難しいとされています。
そんな木でつくる家の強度を測る、構造計算を行うには、住宅会社側にそれだけの技術や体制が整っていなければいけません。
日本古来の木造建築法が重んじられている?
昔々から日本で建てられる住宅の大半が木造です。
それは、日本の気候には木造建築が適していることも理由として挙げられます。
もちろん、そうした木造建築の歴史を経て、日本の建築現場では木造住宅に関する知識や経験が積み重ねられ、その知識や経験が重んじられている面もあります。
ただし家の強さは、その知識や経験だけで測れるものではありません。
その家がどれだけ地震に強いかは、科学的に数値化されてこそ、目に見えて分かるもの。
目に見えて分かってこそ、住む人の安心につながるのではないでしょうか?
構造計算はコストアップにつながる?
住宅会社が利益を生み出すために求められるものの一つに、「コストダウン」があります。
壁量計算に対して構造計算は調べる分野が多く、またそれだけの技術や体制が求められます。
結果、構造計算を行うことは、住宅会社にとって「コストアップ」につながることもあるのです。
となると、法律で義務づけられていないなら構造計算を行わず、コストダウンを図ろうとする住宅会社があっても、不思議ではありません。
家が建つ前に強度を知ろう!

家の構造は、完成後は見えなくなってしまいます。建った後では、その構造が地震に強いかどうかは分からないのです。
そのため、家を建てる前に家の強度を確認する方法が、構造計算です。
安心できる家づくりを進めていくために、ぜひ構造計算について知っておいてください。