
日本:Teachersセミナー実施(10/11)熊本県立教育センターと連携

![]()

パナソニックでは、2020年東京大会に向け、学校での実施が加速されると考えられているオリンピックおよびパラリンピック教育の動向を見据え、2015年に「オリンピックとパラリンピックを題材とした教育プログラム」を独自開発し、学校への提供を開始しました。また、2016年度からは、新たに学校での教育活動を支援する「Teacher's セミナー」をスタート。本年度も10月11日(火)に、熊本県立教育センターの菊川先生と「熊本県高等学校教育研究会 家庭科研究委員会」の場で実施いたしました。特に高校家庭科の「共生社会と福祉」の単元に使える教材として模擬授業と授業アレンジ例を紹介していだきましたので、以下、研修の実践の様子を詳しく紹介していきます。
《概 要》
研修タイトル: 熊本県高等学校教育研究会 家庭科研究委員会
活用プログラム: オリンピックとパラリンピックを題材にした教育プログラム
プログラム④ 「多様性と共生社会」
日 時: 2017年10月11 日(火)15:00~17:00
場 所: 熊本県立工業高等学校
授 業 者: 熊本県立教育センター 菊川 雅子 先生
参 加 者: 家庭科研究委員会 所属教員 7名
■先生方の手で作り上げる家庭科研究委員会の高校家庭科用副教材
熊本県の高等学校家庭科研究委員会では、熊本県独自の高校家庭科用の副教材を作成しており、現場の先生、ほぼ全員から教材に対する意見を吸い上げる形をとっています。先生方の意見をとりまとめ、教材にしている同研究委員会のなかで、「共生社会と福祉」の単元に活用できる教材として、プログラム④「多様性と共生社会」を熊本県立教育センターの菊川雅子先生から参加者の先生方へ模擬授業の形で紹介いただきました。さらに先生方が実践しやすいようにアレンジ例も合わせて考えていただいていたので、そちらも合わせてご紹介します!
■高校家庭科「共生社会と福祉」の単元の課題とプログラム④の親和性菊川先生や参加者の先生方は高校家庭科の「共生社会と福祉」の単元は「言葉や数字のみを追いかける学習」になりがちな単元でアクティブ・ラーニングも導入しづらい、という課題意識を持たれていました。その課題も踏まえて、パナソニックの教材は下記の点で優れていると評価をいただきました。
●ワークを通じた言葉のみで終始しない学び
●アクティブ・ラーニングを意識したワーク構成
●魅力的な映像と編集可能な教材
このような特長があるので、教材の活用により先生方が日頃感じている「共生社会と福祉」の単元で抱いている課題感も解決できるのではないか、そんな菊川先生の想いもあり、先生方に教材を紹介いただきました。
■導入:社会にはどんな個性を持った人がいるかな?
菊川先生の模擬授業は、とてもアレンジに富んだものでした。まずスライド教材については、一度映したスライドは次に進むと、残らないという欠点を、掲示物として別で貼ることで印象づけていました。また、冒頭の社会の様々な*個性を持った人々を提示するスライドでは、社会にはどんな人がいるか、「マインドマップ」で書かせていくことで、いろいろな個性を持つ人がいることを理解できると、アレンジ例も紹介いただきました。※ここでは身体的・精神的・環境的・社会的なものを含む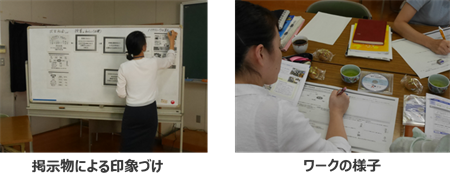
■展開①:障がいにあったコミュニケーションを考える
本プログラムには障がいのある方々の日頃の判断を「自分ごと」として感じてもらうワークがあり、「楽しみにしていた修学旅行の直前に骨折し車いす生活に、あなたは修学旅行に行く?行かない?」と問いかけ、周囲への影響と自分の楽しみを天秤に掛けるとなど、判断のジレンマを生み出す仕掛けがあります。 その際には、アレンジとしてペアトークをして、他人の意見とその根拠も聞くことで、自分の意見との比較や価値観の多様性の理解にもつながると伝えていただきました。また、次のワーク「学校の校門で最寄りの駅はどこかと、視覚障がいのある方、聴覚障がいのある方、それぞれに聞かれた場合、どう案内する?」ではロールプレイをさせることで、生徒はより実践的に考え、思考や想像だけでは見えてこない、新たに発見するものがある、とワークアレンジも紹介いただきました。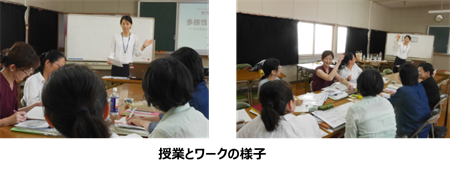
■展開②:重度障害者多数雇用事業所「パナソニック吉備」の映像
パナソニック吉備では障がい者と健常者がチームで映像機器の製造という仕事をしており、様々な施設・設備的な工夫、また他人に対する気遣いや心がけがあります。この映像を見た先生方からは「映像により生徒は言葉とは比にならない情報量を得られる。身近でない共生社会という言葉に少し具体的なイメージがもてる」と好評をいただきました。映像の中で知った工夫や心掛けは隣同士で共有させることにより、より網羅的にポイントを拾えるとワークの効果も伝えていただきました。
■展開③:「共生社会実現のために大切なことはなんだろう?」
最後のワークでは、共生社会実現に取り組むスペシャリスト達の取組みと課題を記した4種の資料を使い「日本にある共生社会実現に向けた課題」を考えます。ジグソー法としても使える本ワークですが、時間がない場合の対応例として、先生方には担当の資料を読み込んでもらったあと、別の担当の先生と「日本の課題」について話合いました。さまざまな習熟度の生徒を教えている先生達にむけて、習熟度に合わせて、ジグソー法にしてもよいし、資料の読み取りと意見交換としてもいいと活用の方法も合わせてお伝えいただきました。
■先生方の声
●「共生社会」の単元は座学中心になりがちだったので、アクティブ・ラーニングが盛り込まれた教材は使いやすいと感じます。
●資料が豊富なので、十分に話合いができると感じました。教材が編集できるので、教えている生徒たちにも、言葉をアレンジするなどできるので、活用できそう。
●工業系の生徒を教えているので、興味を引くと思う。車いす実習の際の導入で使用したい。
●映像教材を見れるのがいい。実際に、そういう環境(パナソニック吉備)で働いている方の言葉は生徒が聞いていても重みが違うと思う。
他にも先生方から「障がい者」という言葉だけでは見えづらいが、その障がいが先天的なものか、後天的なものかでぜんぜん違う。そのようなところまで踏み込めるものになれば、と教材に対する期待も寄せていただきました。模擬授業で教材とアレンジ例を紹介してくださった菊川先生、参加された熊本県高等学校教育研究会 家庭科研究委員会の先生方、どうもありがとうございました。教材が先生方の授業に少しでも役立つことを祈っております。
<関連サイト>
パナソニックのオリンピックとパラリンピックに関する教育支援
動画でわかる「教育プログラム」概要
パナソニックの企業市民活動
パナソニックセンター東京の「オリンピックやパラリンピックに関するイベント情報」










