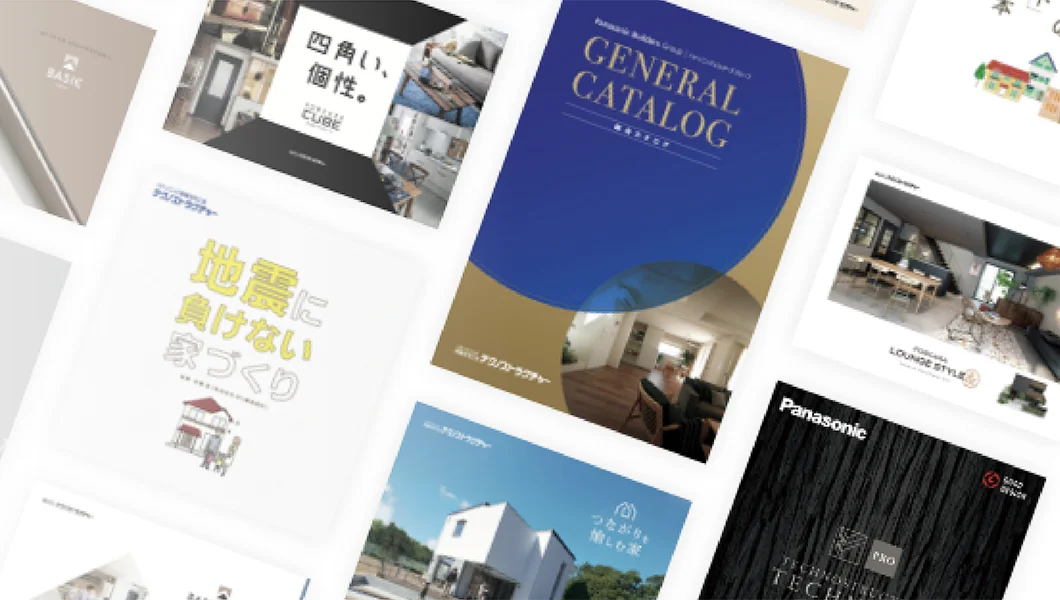省エネって何をすればいいの? 家づくりの基準となる「省エネルギー対策等級」とは
「省エネルギー」とは、エネルギーを省くこと。
住宅においては、生活のなかで使うエネルギー量を減らすことを指します。
しかし具体的に住宅の「省エネ」とは、どんなことをすればよいのか分からない方も多いかもしれません。
そこで、家づくりにおける省エネとは何か? 何を基準にどんなことをすればよいのかをご説明します。

家づくりにおける省エネとは?
石油、石炭、天然ガスといったエネルギーは、無限ではありません。
使い続けていると、いつか枯渇してしまう恐れがあります。
そこで、こうしたエネルギーを効率的に使う「エネルギー対策」が、地球規模で求められています。
そんななか、日本においては2015年(平成27年)7月に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が交付されました。
さらに2年後の2017年(平成29年)には、その具体的な適合義務、規制的措置が施行されています。
その概要は以下のとおりです。
-
大規模な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務
大規模な非住宅建築物(特定建築物)について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保することとする。 -
中規模以上の建築物に対する届出義務
中規模以上の建築物について、新築時等における省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができることとする。 -
省エネ向上計画の認定(容積率特例)
省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとする。 -
エネルギー消費性能の表示
エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができることとする。
※国土交通省 公式サイトより

なお2022年(令和4年)6月の建築物省エネ法の改正により、2025年(令和7年)までには省エネ基準が義務化されることになりました。
省エネについて、詳しくはこちらの記事もご参照ください。『「省エネ」って何? 日本のエネルギー問題と創エネ・ZEHとは?』
一方、住宅の「省エネ」を考えるうえで、参考にしたい目安もあります。
それは「省エネルギー対策等級」です。
省エネルギー対策等級とは?
「省エネルギー対策等級」は、「住宅の品質確保の促進に関する法律」(品確法)に基づいた住宅性能表示制度の評価分野のひとつです。
住宅性能表示制度について、詳しくはこちらの記事もご参照ください。
『良い家はどっち? 長期優良住宅制度と住宅性能表示制度の違い』
住宅性能表示制度の評価対象は、以下の10項目です。
- 構造の安定
- 火災時の安全
- 劣化の軽減
- 維持管理・更新への配慮
- 温熱環境
- 空気環境
- 光・視環境
- 音環境
- 高齢者等への配慮
- 防犯
このうち、「温熱環境」の評価基準として、「省エネルギー対策等級」が用いられています。

「省エネルギー対策等級」は、住宅に対して以下の2項目について審査し、5段階から6段階の等級で評価します。等級の数値が大きいほど性能が高くなります。
省エネルギー対策等級の評価項目
- 温熱環境(断熱等性能等級)等級1~7
- エネルギー消費量(一次エネルギー消費量等級)等級1~6
これらの省エネルギー対策等級のなかで、以下の等級と認定された場合は住宅ローンに関するメリットがあります。
断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級6の住宅、または断熱等性能等級5以上かつ一時エネルギー消費量等級4または5の住宅の以上の場合、長期固定金利型の住宅ローン「フラット35」の金利が当初5年間、年0.25%引き下げられる「フラット35 S(金利Bプラン)」の対象となります。
断熱等性能等級5以上かつ、一次エネルギー消費量等級6の場合、当初10年間、借り入れ金利が年0.25%引き下げられる「フラット35 S(金利Aプラン)」の対象となります。
なおフラット35Sは、省エネルギー性のほかに耐震性や高齢者配慮、劣化対策などの選択肢もあり、いずれか1つ以上の基準を満たせば対象になります。
※2022年10月現在の情報です。省エネルギー対策等級を基準に含む住宅の認定制度もあります。
それは「長期優良住宅認定制度」です。
長期優良住宅認定制度とは
長期にわたって住み続けることができる、質の良い家づくりを普及させるために設けられた長期優良住宅の認定基準は、以下の10項目です。
- 劣化対策
- 耐震性
- 維持管理・更新の容易性
- 可変性
- バリアフリー性
- 省エネルギー性
- 居住環境
- 住戸面積
- 維持保全計画
- 災害配慮
このうち「省エネルギー性」の基準のひとつが、「断熱等性能等級 等級4」となっています。
そして「省エネルギー性」も含めた10項目の基準をクリアし、長期優良住宅に認定されると、次の税について優遇措置を受けることができます。
- 所得税
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 固定資産税
所得税に関わるものとしては、住まいが長期優良住宅に認定され、世帯の合計所得金額が2000万円以下の場合、住宅ローン残高に基づいて所得税の控除を受けることできます。
これを一般的には「住宅ローン控除」あるいは「住宅ローン減税」と呼ばれています。
一般住宅と長期優良住宅を比較すると、住宅ローン減税の金額がこれだけ変わります。
| 住宅ローン減税 | |
|---|---|
| 一般住宅の場合 |
最大273万円控除 (年間最大21万円×13年間) |
| 長期優良住宅の場合 |
最大455万円控除 (年間最大35万円×13年間) |
| ※最大182万円の差 |
※2023年12月31日までの入居の場合
家づくりは人生最大のお買い物と言われ、その費用は何千万円にもなります。その家づくりの費用で最大182万円の差が生まれると、家計にとっても大きいですよね。
なお2022年度の制度改正によって新築住宅の控除額は4段階に分かれています。長期優良住宅は低炭素住宅と並んで、最大控除額はトップです。
まとめ

地球規模で環境対策、エネルギー対策が求められているなか、家づくりにおいても省エネ対策は欠かせません。
日本でも「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)、「住宅の品質確保の促進に関する法律」(品確法)といった法律や、住宅性能表示制度、長期優良住宅制度といったものにより、住まいや建築物の省エネ化を推進しています。
そんな省エネに関する基準の一つが、「省エネルギー対策等級」です。
この省エネルギー対策等級の基準を満たすことで、住宅性能表示制度や長期優良住宅制度に基づく、お金に関する優遇措置を受けることもできます。
さまざまなメリットがある省エネ対策、家づくりを検討している方はぜひ参考にしてください。
※2022年10月時点の情報です。住宅ローン減税や各種税金の優遇制度は税制改正により金額や期限が変更になりますので、利用される際は住宅会社へ確認したり、国土交通省のサイトなどを確認してください。