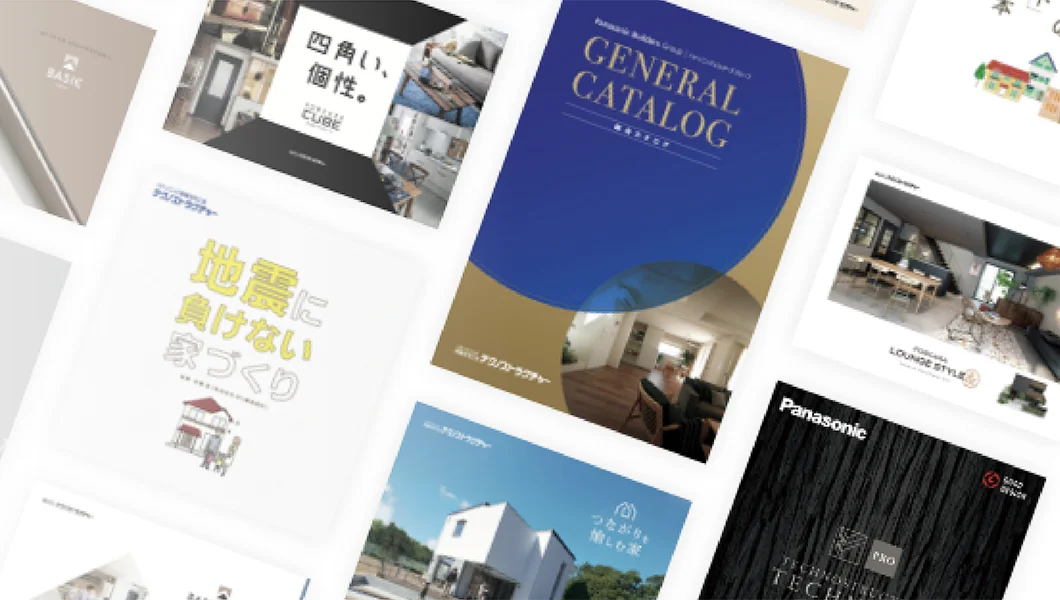良い家はどっち? 長期優良住宅制度と住宅性能表示制度の違い
新築一戸建てを考えている方なら、誰もが「良い家を建てたい」と思うでしょう。
しかし、その「良い家」とは、どんな家のことを言うのでしょうか?
「良い家」について考えるうえで、分かりやすい基準として「長期優良住宅制度」と「住宅性能表示制度」の2つが挙げられます。
では「長期優良住宅制度」と「住宅性能表示制度」、どちらの制度を利用すればよいのでしょうか。
2つの制度の違いなどをご紹介します。

長期優良住宅制度とは
長期優良住宅制度とは、2009年(平成21年)6月に施行された『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』(長期優良住宅法)に基づく制度です。
それまで一般住宅といえば「スクラップ&ビルド型」、つまり古くなった家は壊して新しく建て直すという概念に基づいて建てられていました。
対して、長期優良住宅制度は「ストック型」、長期にわたって住み続けることができる家づくりを普及させるために設けられたものです。
従来のスクラップ&ビルド型の家づくりに対し、ストック型は住宅を長期にわたり使用することで、住宅を解体する際に発生する廃棄物の量を抑えることができ、環境対策にもなるというメリットがあります。
また、建て替えを繰り返すと、当然のことながらその都度、高額の建築費用が発生します。ストック型の家づくりでは、そうした費用も削減できます。
さらに、長期優良住宅に認定された場合は、税制上の優遇を受けることができます。
つまり、環境にも経済的にもやさしい暮らしを実現することを目指して生まれたのが、長期優良住宅制度なのです。
住宅性能表示制度とは
対して住宅性能表示制度とは、2000年(平成12年)4月に施行された『住宅の品質確保の促進等に関する法律』(品確法)に基づく制度です。
長期優良住宅法より9年も前に誕生した制度です。
品確法は、以下の3つの柱で構成されています。
- 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
- 様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
- トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること
※一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 公式サイトより
この3本の柱の一つが、住宅性能表示制度です。
住宅性能表示制度の目的は、「良質な住宅を安心して取得できる市場を形成すること」、「質の良い家を建てること」と言えます。

長期優良住宅制度が、「長く住み続けることができる家」を対象としているのに対し、住宅性能表示制度は「長く住み続けることができる」ことも含めた、質の良い住まいを建てることを求めているわけです。
では、具体的に長期優良住宅制度と住宅性能表示制度の評価基準、メリットは、どんなものがあるのでしょうか。
2つの制度を比較してみましょう。
長期優良住宅制度と住宅性能表示制度の違い
基準の違い
長期優良住宅の認定基準、住宅性能表示制度の評価基準どちらも10項目あります。
それぞれの項目を一覧表にまとめてみました。
| 長期優良住宅の認定基準(10項目) | 住宅性能表示制度の評価基準(10項目) |
|---|---|
|
劣化対策 劣化対策等級3かつ構造の種類に応じた基準 |
劣化の軽減 |
|
耐震性 耐震等級2または、免震建築物であることなど |
構造の安定 |
|
維持管理・更新の容易性 維持管理対策等級3 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装や設備の維持管理がしやすい措置をする |
維持管理・更新への配慮 |
|
省エネルギー性 断熱等性能等級4 必要な断熱性能等の省エネルギー性が確保されていること |
温熱環境 |
|
可変性(共同住宅と長屋に適用) ライフスタイルの変化に応じて間取りなどの変更ができるような対策 |
空気環境 |
|
バリアフリー性(共同住宅に適用) 高齢者等配慮対策等級3(共用部分) 将来、バリアフリー対策ができるようにスペースを確保 |
高齢者等への配慮 |
|
居住環境 周辺の景観と調和、地域の計画に沿っているなど |
防犯 |
|
住戸面積 床面積の合計が75㎡以上 |
火災時の安全 |
|
維持保全計画 将来を見据え、定期的な点検や補修に関する計画がされていること |
音環境 |
|
災害配慮 災害のリスクのある地域においては、リスクの高さに応じて対策をすること |
光・視環境 |
長期優良住宅の認定基準と、住宅性能表示の評価基準を比較すると、太字の基準は内容について重なる部分があります。
住宅性能表示の「劣化対策等級」、「耐震等級」「維持管理等級対策」「断熱等性能等級」は、長期優良住宅の認定基準としても取り入れられているからです。

また、長期優良住宅制度の「可変性」「バリアフリー性」は共同住宅のみの適用ですが、その目的が住宅性能表示制度の「高齢者への配慮」と重なるところもあります。
つまり、長期優良住宅制度と住宅性能表示制度では、チェックする項目に似た項目が多いと言えます。
次に、それぞれ認定を受けるメリットをご紹介しましょう。
優遇措置の比較
長期優良住宅制度と住宅性能表示制度、どちらもメリットのひとつとして「お金」に関する優遇措置が挙げられます。
たとえば長期優良住宅の認定を受けると、住宅ローン減税の控除額や住宅資金贈与の非課税限度額に差が出ます。
■住宅ローン減税
|
住宅ローン減税 控除率 一律0.7% 控除期間13年 |
2023年入居まで | 2025年入居まで |
|---|---|---|
| 一般住宅の場合 |
借入限度額 3,000万円 最大控除額 273万円 (3,000万円×0.7%)×13年 |
0円※ |
| 長期優良住宅の場合 |
借入限度額 5,000万円 最大控除額 455万円 (5,000万円×0.7%)×13年 |
借入限度額 4,500万円 最大控除額 409.5万円 (4,500万円×0.7%)×13年 |
※2023年までに新築の建築確認がされている場合、借入限度額は2000万円になり、最大控除額は182万円。
■住宅資金贈与の非課税枠
| 一般住宅の場合 | 非課税枠が500万円 |
|---|---|
| 長期優良住宅の場合 | 非課税枠が1,000万円 |
※適用期限2023年12月31日まで
一方、住宅性能表示制度では、地震保険料の割引を受けることができます。
■地震保険
|
保険始期 2014年7月1日以降 |
||
|---|---|---|
| 免震建築物割引 | ▲50% | |
| 耐震等級割引 (構造躯体の倒壊等防止) | 耐震等級3 | ▲50% |
| 耐震等級2 | ▲30% | |
| 耐震等級1 | ▲10% | |
また、住宅性能表示制度では、民間金融機関の住宅ローンでの金利優遇などもあります。地震保険の詳細は損害保険代理店または保険会社にお問い合わせください。
長期優良住宅と住宅性能表示制度、どちらを選ぶ?
ここまで、長期優良住宅制度と住宅性能表示制度の内容をご紹介してきました。
評価基準は重なる部分がありますが、それぞれメリットがあります。
お金に関する優遇措置は、長期優良住宅の方が多いのですが、住宅性能評価制度では、建設中と完成時の合計4回(木造住宅の場合)、第三者機関のチェックが入る安心感があります。
そのため、長期優良住宅制度と住宅性能表示制度、どちらかを選ぶのではなく、2つの制度を両方とも利用するという選択肢もあります。
長期優良住宅制度と住宅性能表示制度、どちらも「良い家」をつくるために求められた制度であることは間違いありません。
一方あるいは両方の制度で認定を受けることができれば、それが「良い家」であることの証明になり安心感も高まります。

さらに、長期優良住宅制度と住宅性能表示制度のどちらも認定を受けると、家としての資産価値が高まり、中古住宅として売買する際も有利に働くことも期待できます。
新築一戸建てをご検討の方は、ぜひ長期優良住宅制度と住宅性能表示制度の利用について住宅会社に相談してみてください。