
日本:オリンピックとパラリンピックを題材とした教育プログラム 大阪府立泉北高等学校


パナソニックでは、2020年東京大会に向け、学校での実施が加速されると考えられているオリンピックおよびパラリンピック教育の動向を見据え、2015年に「オリンピックとパラリンピックを題材とした教育プログラム」を独自開発し、学校への提供を開始しました。
今回紹介するのは、平成27年度からスーパーグローバルハイスクール(SGH)にも認定されている大阪府立泉北高等学校の「グローバル課題研究I」で行われた実践事例です。2年生を対象とした社会課題解決に関する探究的な学習の授業で*SDGs(Sustainable Development Goals)をテーマにして行っております。その探究活動のカリキュラムの中で本教材を活用いただきましたので、以下、実践の様子を詳しく紹介していきます。
※先進国を含む国際社会全体の開発目標として、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、国連で採択された2030年を期限とする包括的な17の目標(ゴール)。
出典:外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/doukou/page23_000779.html
《概 要》
―実施プログラム: オリンピックとパラリンピックを題材にした教育プログラム―
プログラム①「大会の意義とそれを支える人々」
プログラム②「多様性と国際理解」
プログラム④ 「多様性と共生社会」
日 時: 2017年9月29日(金) 10:30~12:00 プログラム①、②、④を部分的に活用
実 践 者: 大阪府立泉北高等学校 藤原 和美 先生
教 科: 「グローバル課題研究I」
対 象: 高校2年生 10名 (類似テーマ選択者)
■探究的な学習:SGH特別カリキュラム「グローバル課題研究」
SGHでもある泉北高等学校では、「国際文化科」の科目として、2年生から3年生まで国際社会の課題に目を向け、探究していく「グローバル課題研究」を必修としています。各学年の国際課題に関する学習内容は大きく次のようになっています。
1年生:類似科目で、国際的な開発目標であるSDGsと国際社会の課題探究と発表
2年生:自分で社会課題を選択し、類似する生徒とグループを組んでの探究活動と中間発表
3年生:探究結果のまとめと成果発表
今回は、関連する「共生」「福祉」などの課題研究テーマを選んだ生徒対象に、よりテーマを広い視点で考える機会として、本プログラムを活用いただきました。特に「共生社会を考えるときに 障がい者 と 健常者 という狭い枠組みだけで捉えず、より広い視野で物事を見てほしい」という藤原先生の想いを反映した授業展開でした。
■オリンピック・パラリンピックを導入として「共生社会」について考える
はじめにオリンピック・パラリンピック競技大会をとりあげ、「共生社会の実現」などの大会の社会的価値の側面に気づかせることからはじめました。
まず、PG①の映像教材「オリンピックとはどんなもの?」を視聴し、各開催国でのオリンピックに対する印象を知ったあとで、「みんなの印象度は、オリンピックとパラリンピックで何対何ぐらいの割合かな?」と聞くと、「パラリンピックはあまり見ないので90:10ぐらいの印象」と声があがりました。そんな生徒たちは次にPG④の教材「パラリンピックとはどんなもの?」を視聴、パラリンピアンの躍動する姿と印象的なインタビューに釘付けになりました。そこから、オリンピック・パラリンピックムーブメントについて触れ、スポーツの祭典という側面だけでなく、「共生社会の実現」などの社会的な目的があることに生徒達は気づきました。 ■「共生社会」の実現に向けて必要なことを考える
■「共生社会」の実現に向けて必要なことを考える
「では、共生社会の実現に向けて必要なことはなんだろう?」と、先生が質問すると、生徒からは「それぞれの違いを受け入れる」「相手のことをよく知ることが大切」「気持ちが大切で否定から入らないこと」などの意見が出ました。一人ひとりが共生社会に対しての意見を持ったところで、それらを身近に捉えるための質問とワークに入りました。はじめの質問は「修学旅行直前で足を骨折し車椅子生活に、あなたなら修学旅行に行く?行かない?」。9割の生徒が「行く」と答えましたが、先生から「どうやって?車いすだよ?他の人についてもらわなくちゃいけないよね?」と次々に意見のゆさぶりが入り、生徒達は考え込みます。「このようなことを日常的に判断している人たちがいる」ことを擬似的に体験し、次の展開に移りました。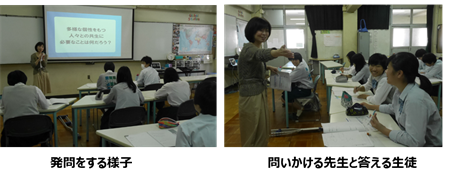 ■「共生」=「障がい者」「健常者」だけの話ではない
■「共生」=「障がい者」「健常者」だけの話ではない
次は「個性にあったコミュニケーション」の必要性に気づくワークで先生から「泉北高校の校門の前で、最寄駅までの道を聞かれました。その人が視覚障がいのある方だったら、また聴覚障がいのある方だったら、それぞれどう案内する?」と問いかけました。生徒たちはグループになって意見を交わし、お互いに案内の方法を検討しました。その後、PG④の映像教材、パナソニックの重度障がい者多数雇用事業所である「パナソニック吉備」の映像を視聴し、実際に「共に働く環境」で共生を実現するために必要なハード面(施設・設備など)の工夫やソフト面(心がけなど)の工夫を知りました。工夫を全体で共有したあと、このような心がけや工夫の姿勢は「障がい者」「健常者」に限った話ではないんじゃないかな?と先生からの質問もあり、次の国際理解の内容に入りました。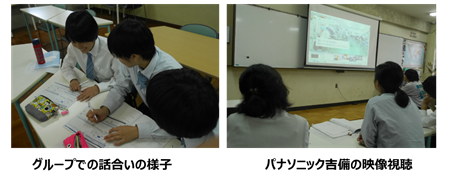
■2020年は海外から言語も文化も違う人を受け入れる
2020年の東京大会では日本人として国際的な「違い」に対応していく場面が訪れることを確認し、国際的な視点での「共生」を考えるため、PG②のワークを活用しました。このワークでは「海外からの留学生をおもてなしするために大切なこと」を考えます。それぞれグループごとに担当する国を割り振り、言語や文化、宗教など留学生のバックグラウンドについて、各生徒がタブレットなどを使用してインターネットで調べ、おもてなしをする上で大切にすることをグループで話し合いました。「中国」「インド」「マレーシア」「アメリカ」それぞれの担当から「イスラム教では豚を食べてはいけないから食事には気をつけないといけない」「中国の方が食べ物を少し残すのはお腹いっぱいで満足していることをあらわす慣習」など調べてわかった言語や宗教、文化の違いに応じた配慮についてそれぞれのグループが意見を出し合いました。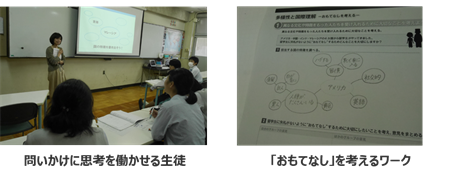
■広い視野で「共生社会実現」を考える
これらのワークを経て、初めの質問に立ち戻ります。「今までの授業を踏まえて共生社会実現のため、君たちはどう行動していく?」という先生からの問いかけに「まずは相手を知らなくちゃいけないから自分の知らない障がいについて調べたい」「国が違ってもコミュニケーションは重要だと思う」などの意見がでました。ある生徒が「外に出たときに障がいのある人が困っている場面に出くわしたら、本当に話しかけられるか分からない、断られたらどうしよう、と思う」という正直で真剣に自分ごととして捉えたからこその意見も出ました。それに対して、「断られたらどうしよう、と思うのは障がい者の方だけじゃなく、高齢者の方に席を譲るときも一緒。見た目じゃ年齢も分からないし。」「知らない、ことで怖くて行動できないことが増える。コミュニケーションや調べたりしてまずは相手を知ることは大切」と活発な意見交換がなされました。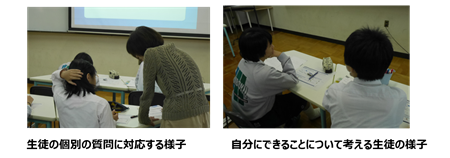
今回担当いただいた藤原先生からは「生徒たちは今後、課題研究として「共生社会」に関連するテーマを調べていくと、持続可能性というこれからの社会に大切なキーワードにもつながるので、より広い視野で物事を捉え、解決に向けて行動できるきっかけになってほしい」と声をいただいております。授業を実施してくださった藤原先生、大阪府立泉北高等学校の生徒のみなさんありがとうございました。 これからも様々な学校から当社のオリパラ教材を活用した様々な実践事例を紹介していきます。
<関連サイト>
パナソニックのオリンピックとパラリンピックに関する教育支援
http://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/citizenship/child/education.html
動画でわかる「教育プログラム」概要
http://channel.panasonic.com/jp/contents/17959/
パナソニックの企業市民活動
http://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/citizenship.html
パナソニックセンター東京の「オリンピックやパラリンピックに関するイベント情報」
http://panasonic.co.jp/center/tokyo/event/all/index.html#alc










