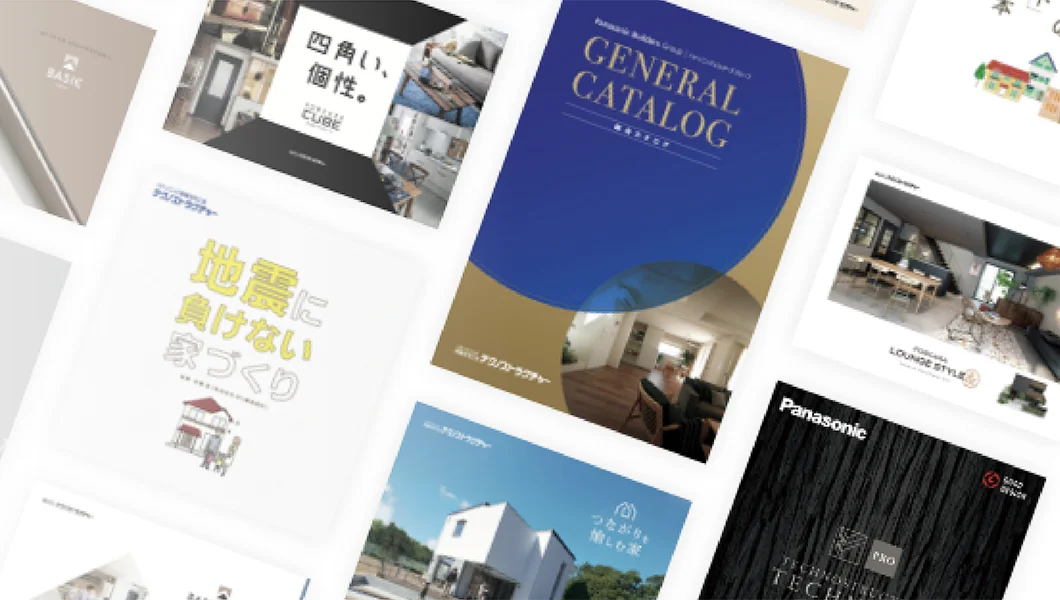耐震性能を調べるために構造計算でチェックしたいポイント
世界でも有数の地震大国である日本では、住まいに耐震性能が求められています。
どうすれば地震に強い家を建てることができるのか。
そのポイントは「構造計算」にあります。住まいの構造を緻密に計算することで、家の耐震性能向上につながります。
では、構造計算とはどのようなポイントをチェックするのでしょうか?
構造計算の内容についてご説明します。

構造計算で「家の強さ」を確認する
構造計算は家の間取りが決まる前、あるいは間取りが確定した時点で行います。
構造計算の内容は「構造計算書」として、お客様にお渡しする住宅会社もあります。
構造計算は法律上、鉄筋コンクリート造や鉄骨造、大規模な木造住宅には義務づけられていますが、小規模な木造住宅では必須にはなっていません。
しかし、法律で必須になっていないからといって、行わなくていいというわけでもありません。
耐震性能が高い家を建てるためには、緻密な構造計算が必要です。
構造計算で調べるチェックポイント
家の強さを知るため計算・検討するポイントのチェックポイントを、以下の3つの分野・8つのチェックポイントに沿ってみていきましょう。
■地盤・基礎の強さ
・基礎の強度
■部材の強さ
・柱の強度
・梁の強度
・柱接合部の強度
・梁接合部の強度
■壁の強さ
・耐力壁の量
・耐力壁の配置
・床の強度
500㎡以下の小規模な木造住宅で必須とされている基準をクリアするだけであれば、このうち「壁量」「耐力壁の配置」「柱接合部の強度」を調べる壁量計算でもよいでしょう。 しかし、壁量計算はあくまで簡易的な計算です。
しっかりと家の強さを確認するためには、上記8つのポイントを全て緻密に計算する構造計算を行うほうが安心です。

そこで、構造計算で調べるポイントについて、具体的にご説明します。
基礎の強度
住宅を支える地盤と基礎についてチェックします。
地盤の強度に応じて、自重だけでなく地震などの水平荷重に対して、基礎に最適な鉄筋が配置されているかなどをチェックし、基礎の強度を確保することが望ましいでしょう。
具体的には
・建物の重さに地面が十分に耐えられるか
・地震や風で家全体が転倒してしまわないか
などです。
柱の強度
柱1本1本にかかる力を計算し、その力に耐えられるかをチェックします。
建物の自重や家具の重さ、雪、風などの荷重により、柱の強度を上回る力が加わると、柱自体が曲がったり折れたりしてしまいます。
そこで全ての構造柱の強度を確認し、適切な柱の配置を行わなければいけません。
具体的なチェックポイントは
・柱が引っ張られる力に対する強度
・柱のめり込みに対する強度
・柱の圧縮に対する強度
・柱の曲げに対する強度
などです。
梁の強度
住宅の要となる梁1本1本にかかる力を計算し、その力に耐えられるかをチェックします。
梁は建物の自重、地震、台風などの荷重により、強度を上回る力が加わると、“たわみ”が生じる場合があります。
梁のたわみが大きいと、引き戸や窓の開閉が困難になることもあります。すると日常生活にも影響を及ぼしてしまいます。
具体的なチェックポイントは、
・梁の曲げに対する強度
・梁のせん断に対する強度
・梁のたわみに対する強度
などです。

柱接合部の強度
地震や台風などの力によって、柱が接合部から抜けたりしないように安全性をチェックします。
柱に木材を使用する木造住宅の場合は、継ぎ目である接合部が建物の構造上の要です。
耐力壁に水平力(建物に加わる地面と水平方向の力)がかかると、筋かいなどを介して、柱に上方向の「引き抜き力」と横方向の「せん断力」が働きます。
その「引き抜き力」と「せん断力」に対する強度を確保しておく必要があります。
具体的なチェックポイントは、
・柱の引き抜きに対する強度
・柱のせん断破壊に対する強度
などです。
梁接合部の強度
梁をつなぐ全ての接合部について、破壊の危険がないかどうかをチェックします。
壁量計算では、この梁接合部の強度を調べないこともありますが、耐震住宅をつくるためには強度確認が必要な部分です。
具体的なチェックポイントは、
・梁のせん断力に対する強度
・梁の引張力に対する強度
などです。
耐力壁の量
耐力壁とは、地震や台風など水平方向からの力を受け止める役割を果たします。
住まいごとに間取りは大きく異なります。さらに、その間取りごとに必要な耐力壁の量も違います。
そこで、建てる家の間取りに、どれだけの耐力壁が必要かをチェックすることが重要です。

耐力壁の配置
耐力壁は量が十分でも、配置バランスがよくないと不十分な効果になってしまいます。
例えば、偏った耐力壁の配置は、建物のねじれの原因になります。
また、建物の上下階で耐力壁の配置に偏りがあると、剛性(変形のしにくさ)が弱い階に変形や損傷が集中してしまいます。
その結果、耐力壁の配置バランスが悪い建物は、横からの力を受けると大きく揺れて、倒壊する危険性があるのです。
だから、耐力壁は量だけでなく配置もチェックすることが必要なのです。
床の強度
地震による水平力が、各耐力壁に均等に伝わることで、家の耐震性能は高まります。
そのためには、床や屋根などの強度が十分でなければいけません。
たとえば、間取りに凹凸や大きな吹き抜けがあると、床・屋根の強度が低くなります。
地震に襲われると、強度の低い箇所が弱点となり、家全体が大きく揺れて倒壊してしまう危険性があるため、強さを補う必要があります。
対して、床・屋根が強いと地震などの力が一箇所に集中せず、力を分散させて地震に耐えられるようになります。

耐震等級と調べ方
どのくらい地震に強い家なのかを示す指標が、耐震等級です。
耐震等級は1・2・3がありますが、耐震等級1では一度の大地震で住めなくなる可能性も…。最もレベルが高いのが耐震等級3。消防署など、災害時の防災拠点を新築する際に求められるレベルと同等の強度です。
耐震等級は、住宅性能評価書で確認することができます。地震保険料の割引や長期優良住宅の優遇制度を活用したい場合は、早めに住宅建設会社や工務店に確認しましょう。
緻密な構造計算が耐震につながります
構造計算の内容は、間取りや階数、建物の形状によって異なる場合があります。
また、法律や基準の改正により、構造計算の内容が変更されることもあります。
さらに、法律で定められた基準だけで、必ずしも耐震性能を備えた家をつくることができるとは限りません。
より厳しい基準で構造計算を行うことこそ、地震に強い家づくりにつながります。
もし新居の建設を検討している場合は、住宅会社に構造計算の基準を聞いてみるのも、安心・安全な家づくりへの一歩かもしれませんね。