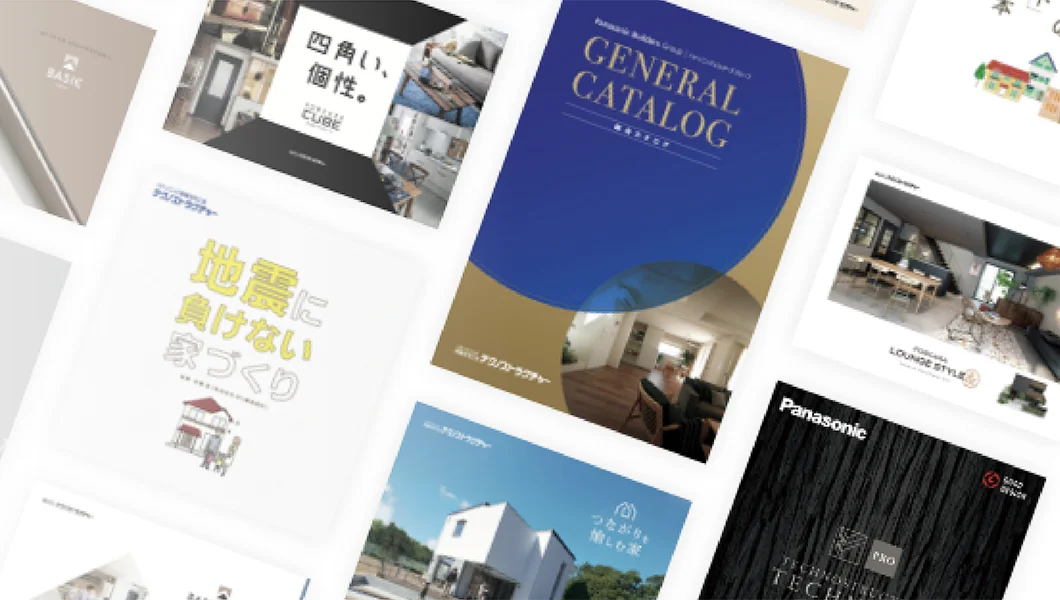換気が家族の健康を守る!? 結露・シックハウスと換気の関係とは
「結露」という現象をご存じでしょうか?
日本の家では夏・冬どちらでも結露が発生します。そして、この結露が住宅の劣化を進めてしまう、という問題が発生しています。
そんな結露を防ぐための手段が「換気」です。
また、「換気」はこちらも大きな問題となっている「シックハウス」も防ぐことができます。
そこで結露と換気、シックハウスと換気の関係についてご説明します。

結露とは?
雨が降っていないのに、あるいは水をかけたりしていないのに、家の窓が濡れているのが気になったことはないですか?
そうした現象の多くは、「結露」と呼ばれるものです。
結露とは、空気中の水蒸気が凝縮する現象のことを言います。
たとえば冬は室内が暖かく、外が寒いといったように家の中と外の気温差が激しいと、結露が生まれます。
また、夏は冷房を使用したり、夜になって冷えると結露が発生したりします。

この結露がもたらす水分が、家の構造体や断熱材を腐食・劣化させるなど、住宅の性能に大きな影響を及ぼしてしまうのです。
また、結露は家の中にダニやカビを発生させ、その家に住む人たちの健康にも被害をもたらすことがあります。
そのため、家づくりにおいては、結露によって発生するカビ・ダニを防ぐため、「換気による結露対策」が必須です。その結露対策の1つが「換気」というわけです。
換気によって空気の流れをつくり家の中の湿度を抑えることで、結露・カビ・ダニが発生するのを防ぎます。
シックハウス症候群とは?
もうひとつ、住宅に関して人の健康に悪影響を及ぼす例として、「シックハウス症候群」があります。
厚生労働省の公式サイトでは、「シックハウス症候群」について次のように説明されています。
近年、住宅の高気密化などが進むに従って、建材等から発生する化学物質などによる室内空気汚染等と、それによる健康影響が指摘され、「シックハウス症候群」と呼ばれています。
住んでいる家が原因で健康状態に影響があるなんて、怖いですよね・・・。
そんなシックハウス症候群の症状としては、主に次のようなものがあります。
- 頭痛
- めまい
- 咳・喉の痛み
- 吐き気
- 目がチカチカする
- 疲労感
- 皮膚の刺激・湿疹

こうしたシックハウス症候群を生み出す要因の一つに、家の部材に使われている化学物質があります。
「ホルムアルデヒド」という物質の名前を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか?
ホルムアルデヒドは毒性の強い有機化合物で、シックハウス症候群を引き起こす化学物質の代表的な存在として知られています。
このホルムアルデヒドは、かつては建築材料に多く使われていました。
結果、建築材料からホルムアルデヒドが発散され、体の異常を訴える人がいたのです。
そこで日本では建築基準法の規程が改正され、2003年(平成15年)7月1日以降に着工する建物には、シックハウス対策が義務づけられました。
ホルムアルデヒドの使用に対しては、以下の3つの面から規制されています。
- ホルムアルデヒドを発散する内装仕上げの面積を制限
- 常時換気できる設備の設置を義務づけ
- 天井裏や床下、収納部材の内部の制限
このうち②については、ホルムアルデヒドを発散する建材をまったく使用しない場合でも、すべての建築物に常時換気ができる設備の設置が義務づけられています。
それは購入した家具からホルムアルデヒドが出る可能性があるからです。
つまり、結露対策と同じように、シックハウス症候群を防止するためには、家の中の換気設備を整えることが重要だと言われています。
ここからは、結露対策とシックハウス対策に必要な換気についてご説明しましょう。
結露・シックハウス対策として必要な換気とは
近年、住宅の性能は大きく向上してきました。
たとえば、昔の家では「すきま風」が入ってくることがありました。
対して性能が向上した現代の住まいでは、「すきま風」が入ってくるようなことは少なくなっています。
もちろん、すきま風が入ってこないというのは、人々の暮らしにとって良いことです。
ただ、すきま風が入ってくるというのは、“自然な換気”ができていたということでもあります。
つまり、現代の家はすきま風が入ってこない分、結果的に自然な換気ができにくい家になっているという側面もあります。
換気が不十分になると、室内は雑菌やウイルス、ダニや化学物質が飛びまわり、人の体に害を及ぼす環境になることがあります。
かといって、窓を開けて換気しようにも、外から花粉やPM2.5といったものが入ってくる可能性もあります。

そこで、外の余分な物質は室内に入れないようにしつつ、室内環境を悪化させる不要な物質を外へ排出するためには、換気設備の助けを借りるのがよさそうです。
先にご紹介したとおり、2003年(平成15年)に建築基準法が改正され、シックハウス対策が強化されました。
そのシックハウス対策の一つが、「常時換気」です。
建築基準法では住宅居室の場合、1時間あたり0.5回以上の常時換気設備が必要とされています。
どのようにして、この「常時換気」を実現するのでしょうか?
常時換気を実現するためには?
換気の方法には、主に以下の3つの種類があります。
- 第1種換気
- 第2種換気
- 第3種換気
第1種換気
給気:換気扇
排気:換気扇
換気方式のなかで最も確実な換気が可能。
給気と排気の両方を機械で行うため、空気の流れを制御しやすいタイプです。
それほど気密性が高くない住宅でも、安定した換気効果が得られます。
第2種換気
給気:換気扇
排気:自然排気
換気扇によって外気を室内に取り込み、排気は機械ではなく自然に行われるようにするタイプです。
第2種換気の課題は気密性。湿気が壁内へ進入し、内部結露の発生も懸念されます。
自然排気ができる構造でありながら、気密性能の確保が求められます。
第3種換気
給気:自然給気
排気:換気扇
他の2種の換気方式と比べて、低コストで計画換気が可能です。
ただし、自然給気のため気密性が低い住宅では、計画換気が行われない可能性もあります。
自然給気口からの効率の良い給気は難しいのが現実です。
以上のことから、住まいの計画換気には第1種換気方式がおすすめです。
給気と排気どちらも機械で行うことにより、空気の流れをコントロールしやすく、計画的な換気で室内の空気環境を快適に保つことができるからです。
まとめ

家の中と外の温度差が大きいと生まれる結露は、ダニやカビの発生につながります。
また、ホルムアルデヒドのような化学物質が家の中に発散されると、シックハウス症候群に繋がる可能性があります。
そこで結露やシックハウス症候群を防止するためには、換気が不可欠です。
クリーンな空気環境を整えることは、家族の健康にもつながります。
ぜひ空気の質にもこだわって、室内の空気環境を保つことができる換気方式を選んでください。