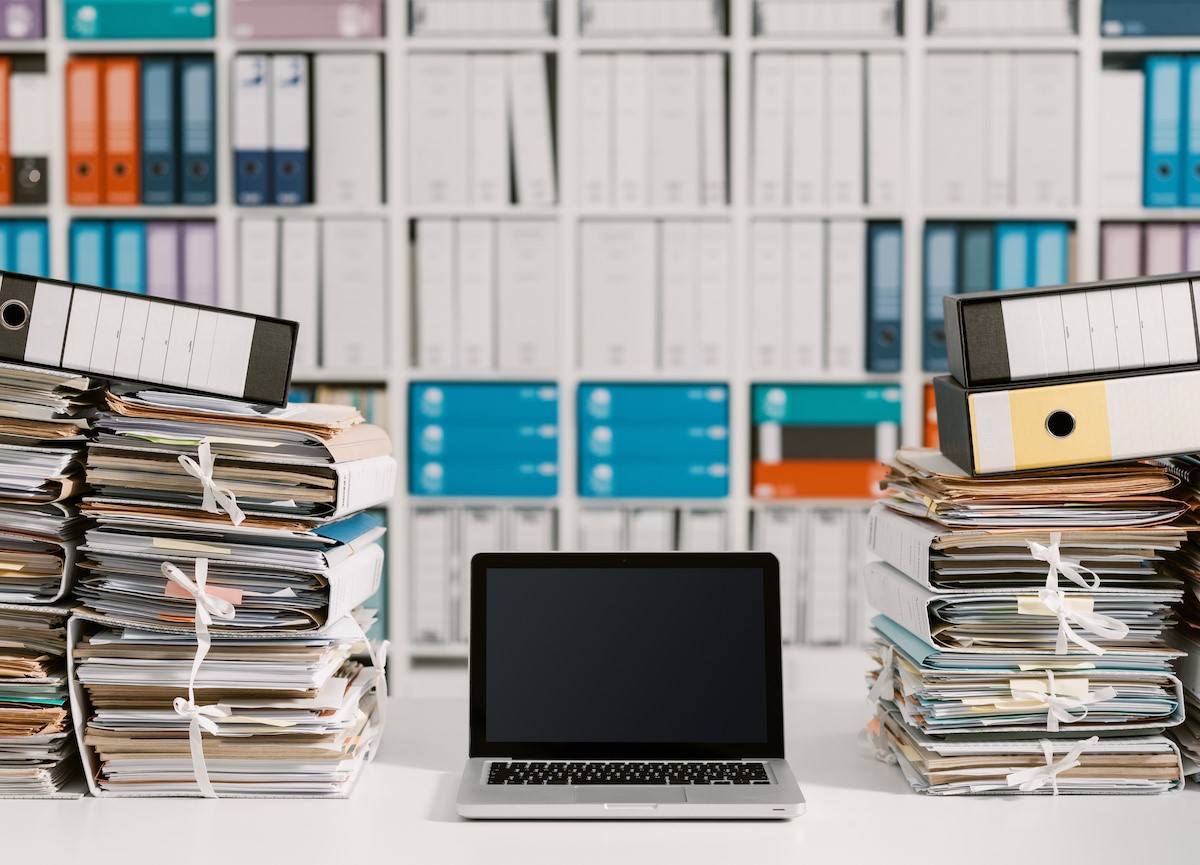ここから本文です。
監視カメラ映像を見る方法は?録画方法や保存期間について解説

ネットワークシステム、入退室管理システム、カメラシステム構築に関するお問い合わせはこちら
監視カメラ映像の記録媒体の種類
オフィスやビル、店舗などに設置して不審者の侵入を抑止する監視カメラ。これらのカメラの記録媒体には、どのような種類があるでしょうか。
HDD
HDD(ハードディスクドライブ)は、パソコンやレコーダーなどに広く利用されている円盤状の記録媒体です。容量あたりのコストが低く、大容量のデータ保存に適しているのがHDDのメリットです。一方で、比較的サイズが大きく、衝撃や振動に弱いのがデメリットです。そのため、防犯カメラに内蔵するのは難しく、外付けのレコーダーと組み合わせて使われるのが一般的です。
HDDの容量は製品によって異なりますが、1TBのHDDの場合、フルHD画質、1秒あたり30コマ(フレームレート)の映像で約75時間分の記録ができます。より長時間の記録が必要な場合は、容量の大きいHDDを使うか、HDDを増設する必要があります。
SDカード
SDカードは、デジタルカメラやポータブルゲーム機などで広く使用されている小型のカード状記録媒体です。非常にコンパクトで、コストパフォーマンスに優れているのがSDカードのメリットです。サイズが小さく、取り扱いやすいため、多くの防犯カメラやレコーダーにSDカードが使用されています。一方で、静電気や物理的衝撃に弱いのがデメリットです。また、データの長期保存に向かないため、定期的な交換が推奨されています。
SDカードの容量は製品によって異なりますが、128GBのSDカードの場合、1秒あたり30コマ(フレームレート)、フルHD画質の場合で約15時間分の映像データを記録できます。短期間の録画や時間帯を限定した録画に適した記録媒体だと言えるでしょう。
SSD
SSD(ソリッドステートドライブ)は、HDDより衝撃や振動に強く、サイズ的にもHDDよりコンパクトな記録媒体です。防犯カメラやノートパソコンなどで広く使用されています。SSDは、HDDに比べ耐久性に優れており、屋外に設置する防犯カメラでの使用にも適しています。また、動作音が静かで電力消費が少ない点もSSDのメリットです。一方で、HDDに比べ容量あたりの価格が高いのがデメリットです。
SSDの容量は製品によって異なりますが、1TBのSSDの場合、1秒あたり30コマ(フレームレート)、フルHD画質の場合で約75時間分の映像データを記録できます。データの保存容量はHDDと同等ですが、衝撃や振動に強く、故障リスクが低いという点ではHDDより優れた記録媒体だと言えます。
クラウド
クラウドは、データをインターネット上の仮想スペースに保存する仕組みです。上述した3つのような「記録媒体」ではなく、「データ保存サービス」「クラウド録画サービス」と言ったほうが適切です。クラウドは記録媒体と違い、月額料金を支払って利用するのが一般的です。
レコーダーの購入や故障時の修理が不要で、物理的な破壊や盗難からデータを守れるのがクラウドのメリットです。いつでもどこからでも映像データを確認できるのも、クラウドならではの利点だと言えるでしょう。一方で、インターネット環境が必須であり、接続が不安定なときはデータが保存されないことがあります。なお、防犯カメラの映像は契約日数分、録画することができます。
監視カメラの録画方法
次に監視カメラの録画方法について見てみましょう。監視カメラの録画データは、高画質になるにつれ大きくなるため、最近はデータを圧縮して保存する方法が多くなっています。
Motion JPEG
JPEG形式の静止画を保存し、これをつないでいくことで動画にする方法。1フレームごと映像を確認したいとき、画像が比較的鮮明に確認でき、編集しやすいメリットがあります。ただ圧縮効率はMPEG-4より落ちます。
MPEG-4
連続するフレームで変化のある部分だけ保存するのがMPEG-4方式です。圧縮効率が Motion JPEGより良いため、録画できる容量が大きくなります。
H.264
ビデオ通話、ハイビジョン放送などに幅広く利用されている方式で、動画ファイルの国際規格です。圧縮効率が良く、画質を損ないません。
H.265
H.265は、H.264を改良し2倍の圧縮率を実現した方式です。つまりH.264と同じ画質を維持しながら、データのサイズは半分になります。
監視カメラの録画映像を見る方法
監視カメラの録画映像を見る方法には、いくつかの種類があり、それぞれで必要な機器も異なります。
PCに記録装置を接続する
PCに記録装置を接続し、PCの画面で確認できます。記録装置は上述したHDDのほか、クラウドに映像を保存した場合は、ネットワークに接続する際に使われるNAS(ネットワークアタッチドストレージ)があります。
SDカードなどのメディアをPCに接続する
SDカードなどの記録メディアで録画映像を保存した場合、そのSDカードをPCに接続して映像を確認できます。
インターネット経由で見る
監視カメラにはインターネットに接続できるタイプが増えてきており、そのようなカメラの場合、インターネットを経由してオンラインで映像を見ることができます。インターネットに接続する機器なら、PC、スマートフォン、タブレット端末でも確認でき、場所を問わず外出先からもリアルタイムで映像を確認できます。しかしインターネット速度が遅いと、映像が確認できないこともあります。
監視カメラ映像の開示請求の際に設置者が知っておくべきこと
監視カメラを設置していると、「カメラの映像を見せてほしい」と言われることがあるかもしれません。そのようなとき、監視カメラの設置者はどのように対応すべきでしょうか?
個人情報保護法
監視カメラに移った映像は、個人を特定できることから、個人情報保護法に該当します。例えば警視庁では街頭防犯カメラシステムについて、「運用責任者の管理の下、国民の権利を不当に侵害しないよう慎重を期しています」といった文言を明記し、街頭防犯カメラ設置区域には表示板で明示する等の工夫を行っています。監視カメラの設置と運用には、方針を定めておくと良いでしょう。
開示請求依頼があった時の対応方法
「監視カメラの映像を確認したい」と言われた場合の対応法は、本人の場合と第三者の場合で異なります。映像に映っている本人からの要求に対しては、開示に適切に対応することが、個人情報保護委員会の資料に明記されています。ただ本人以外が映っている映像は、他者のプライバシー侵害になる可能性がありますので、注意が必要です。
第三者からの要求には対応する必要はありませんが、警察や消防のほか、災害などに関連する場合は協力するといいでしょう。
監視カメラ映像の保存期間はどれくらい?
監視カメラの映像データは、どのくらいの容量を保存できるのでしょうか。また目安となる保管期間はどのくらいでしょうか?
監視カメラの映像のデータ量を決める要素
監視カメラの映像データ量が大きくなると、録画データを保存できる期間も短くなります。映像データ量を決めるのは、フレームレートと画素数。フレームレートとは、1秒あたりののコマ数のことで、画素数はディスプレイ上に見える点の数のこと。フレームレートや画素数が大きいほど、クリアな映像になりますが、データ量が大きくなります。
HDDなどで録画可能な時間
防犯カメラ・監視カメラの記録媒体である「HDD」「SDカード」「SSD」「クラウド」について、容量ごとの録画可能時間の目安をまとめています。
| 記録媒体 | 容量 | 録画可能時間 |
|---|---|---|
| HDD | 1TB | 約75時間 |
| 2TB | 約150時間 | |
| 4TB | 約300時間 | |
| SDカード | 32GB | 約4.5時間 |
| 64GB | 約9時間 | |
| 128GB | 約15時間 | |
| SSD | 1TB | 約75時間 |
| 2TB | 約150時間 | |
| 4TB | 約300時間 | |
| クラウド | 契約日数分、録画可能。 ただし、サービスによっては上限容量が設定されている。 |
|
録画可能時間は、1秒あたり30コマ(フレームレート)、フルHD画質で録画した場合の目安です。画質設定によって録画時間は変わってきます。高画質にするほどデータ量が増えるため、録画可能時間は短くなります。また、使用している圧縮方式によっても録画時間は変わります。その他、常時録画、動体検知録画、スケジュール録画などの録画モードによっても録画可能時間は変わります。
監視カメラ映像の保管期間の目安
防犯カメラ・監視カメラの映像は、犯罪や事件が起きたときに証拠として利用するため、データを一定期間、保管しておく必要があります。映像データの保管期間は、法律などの規定はありません。企業、あるいは個人の判断によって保管期間を決めましょう。
防犯カメラ・監視カメラの設置場所ごとに、映像データの保管期間の目安をまとめています。金融機関や公共施設など、監視の信頼性が重要になる場所は比較的長めに保管するのが一般的です。また、自治体によっては映像データの保管期間に関するガイドラインを設けているところもありますが、概ね1ヶ月くらいです。
| 防犯カメラ・監視カメラの設置場所 | 映像データの保管期間の目安 |
|---|---|
| 戸建住宅 | 1週間~1ヶ月 |
| マンション | 1ヶ月~3ヶ月 |
| オフィス・事務所 | 1ヶ月~3ヶ月 |
| コインパーキング・月極駐車場 | 1ヶ月~6ヶ月 |
| 店舗・コンビニ・スーパー | 1ヶ月~3ヶ月 |
| 工場 | 3ヶ月~6ヶ月 |
| 保育園・幼稚園・福祉施設 | 1ヶ月~3ヶ月 |
| 病院 | 1ヶ月~6ヶ月 |
| 公共施設 | 3ヶ月~12ヶ月 |
| 金融機関 | 6ヶ月~12ヶ月 |
| 建設現場・工事現場 | 1ヶ月~3ヶ月 |
監視カメラ映像のバックアップについて
監視カメラの映像データは、バックアップを取っておくと安心できるでしょう。SDカードやNASの場合は、カードリーダーでPCにつないでバックアップできます。映像データをクラウドに保存している場合は、専用ソフトやアプリでダウンロード可能です。
監視カメラの映像のセキュリティ対策

監視カメラの映像は、多くの個人情報が含まれており、流出や情報漏洩には注意が必要で、次のような対策を行う必要があります。
映像開示における条件
監視カメラの映像について開示請求があった場合、どのような条件で開示するか事前にガイドラインを作っておくべきでしょう。安易に録画データを開示すると、それが情報漏洩につながる可能性があります。
インターネット経由での映像漏洩
インターネット経由で録画データを確認したりダウンロードを行ったりする場合、不正アクセスのリスクがあります。簡単なパスワード設定だったり、アクセス権限の設定が緩かったりすると、不正アクセスを引き起こす可能性があります。
従業員向けのガイドライン
監視カメラを管理する従業員に対しても、データの取り扱いについてガイドラインを定めておくべきでしょう。故意の場合でも、そうでない場合でも、従業員から映像データが流出しないリスクはゼロではありません。
監視カメラと録画機の選び方
監視カメラと録画機を選ぶ際は、以下のポイントをチェックし、用途に最適なものを選ぶといいでしょう。
監視カメラの接続台数
監視カメラを複数台設置する場合、ひとつの録画機に何台のカメラを接続できるか確認しましょう。
屋内または屋外
監視カメラを設置する場所が屋内か屋外かによって、適したカメラが異なります。屋外向けなら、雨風などに強いタイプを選ぶといいでしょう。
監視カメラと録画機の接続方法
監視カメラと録画機が離れている場合は、無線接続できるタイプが必要です。遠隔地の監視カメラに接続する場合は、インターネット接続できるタイプが向いています。
画質
監視カメラの用途によって、どの程度の画質が求められるか異なります。カメラの画素数を確認し、できればそのカメラの映像を実際に確認してから購入するといいでしょう。
保証期間
監視カメラや録画機を使っている際、なんらかのトラブルや故障が起きた場合、どのような保証があるか確認しておくといいでしょう。
監視カメラの費用相場
監視カメラは安価なものなら5,000円程度から購入でき、屋外設置用の防水効果などがついたタイプなら数万円ほどが相場でしょう。なかには、10万円以上の高額のものもあります。
監視カメラの映像に関するお問い合わせはこちら
パナソニックEWネットワークスでは、オフィスや官公庁、工場、病院などへ監視カメラやレコーダの選定、画角調査から構築まで行っています。監視カメラの設置のみならず、セキュリティ対策全般についてアドバイス致します。監視カメラシステムの構築やセキュリティに関することは、以下よりお問合せください
関連するサービスはこちら
関連情報はこちら
効率的な監視カメラを管理・運用へ
監視カメラを設置しても、用途に見合ったカメラや録画機が使われていなかったり、適切な管理がなされていなかったりすれば、意味がありません。万が一に備えて、ここでご紹介したポイントなどを抑え、効率的に監視カメラを運用してリスク管理しましょう。