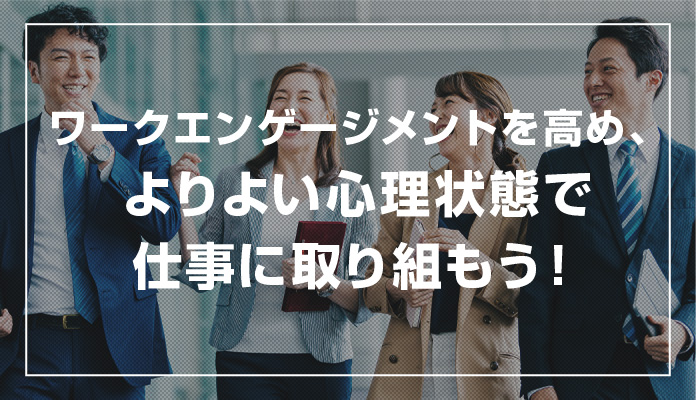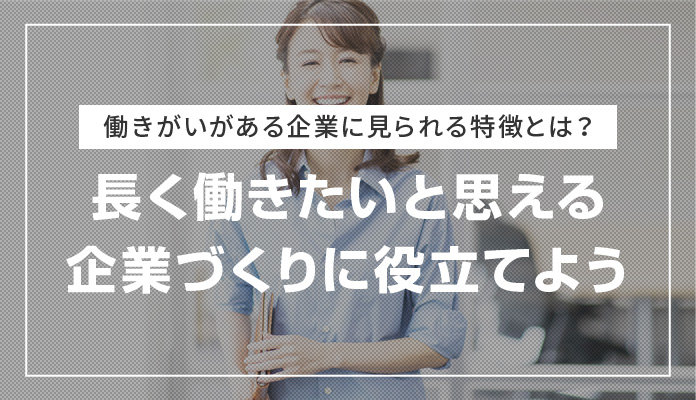職場改善
2021.07.21
セレンディピティはビジネスにも応用できる!新たな発見につなげよう
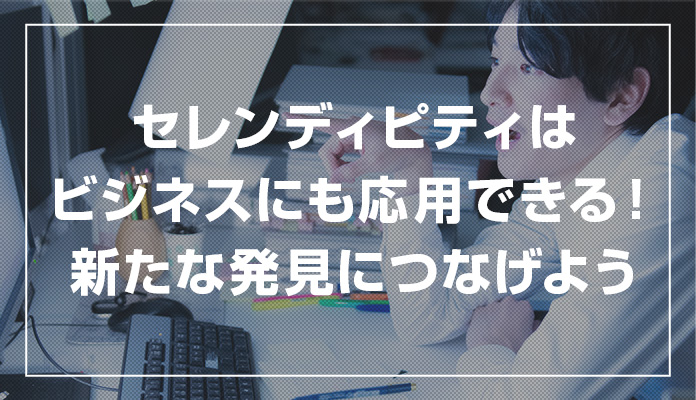
多くの人が、仕事の最中に良いアイディアが偶然ひらめいた経験を持っているのではないでしょうか。これは単なる偶然でなく、幸運を引き寄せる力として広く知られています。
この能力は「セレンディピティ」と呼ばれており、科学者や研究者の方たちが研究中に良く口にする言葉です。セレンディピティの概念は、研究だけでなくオフィスにおける業務にも役立てられることが分かっています。
今回は、セレンディピティについて詳しく解説しますので、気づきの大切さについて学んでいきましょう。
セレンディピティとはどのような意味の言葉なのか?
最初に、セレンディピティという言葉が生まれた経緯や、込められている意味などを解説します。
「予想外の幸運が偶然手に入る」という意味
セレンディピティとは、予想していなかったものが発見できたり、ひらめきによって新たなアイディアが浮かんだりするなどして起こることで、「思いもしなかった偶然がもたらす幸運およびその才能」をさします。
科学の世界では、偶然から大きな発見につながることが多いため、この言葉が良く用いられます。単に幸運や発見が起こるのではなく、発見にいたるまでの観察や知識などが、セレンディピティを形成すると言われています。
ペルシャ童話が起源
セレンディピティという言葉は、スリランカの旧名である「セレンディップ」が語源となっています。イギリスの小説家ホレス・ウォルポール氏が、ペルシャ童話「セレンディップの3人の王子たち」を読み、感銘を受けたことがきっかけで考案した造語だと言われています。
この童話は、3人の王子が旅に出て、優れた能力や幸運を引き寄せる力などを存分に発揮し、人生が好転していくというストーリーです。作られたのは5世紀ごろだとされていますが、16世紀ごろにヨーロッパに伝わりました。
ウォルポール氏は、1754年に「serendipity」という造語を生み出し、現在使われている意味の言葉として広まったのです。
ペニシリンの発見や万有引力の法則も、セレンディピティに含まれる
セレンディピティの具体例で良く知られているのが、「ペニシリンの発見」や「万有引力の法則」などです。それぞれの例を見てみましょう。
ペニシリンの発見とは、イギリスの細菌学者であったフレミング氏が、1928年にペニシリンを偶然発見したものです。ペニシリンは青カビに含まれる抗生物質で、細菌を繁殖させない性質を持っています。ブドウ球菌の研究中に、シャーレの中に偶然発生させてしまった青カビからペニシリンが抽出され、治療薬に役立てられました。この発見で、フレミング氏は医学に大きな功績を残したのです。
万有引力の法則とは、同じくイギリスの科学者であったニュートン氏が、木から落ちるリンゴを見て発見した法則だと言う説があります。全ての物体に重さがあるのは、物体が互いに引き合う力を持っているからというもので、偶然と気づきによる発見と言えるでしょう。
セレンディピティは呼び寄せられるものなのか?
セレンディピティは、偶然の幸運を手に入れる才能と先述しましたが、自らの意思でつかみ取ることはできるのでしょうか。
広くアンテナを張り巡らせ、行動する準備
セレンディピティを起こすための能力は、ひとつではありません。
「Action(行動)」「Awareness(気づき)」「Acceptance(受容)」は、セレンディピティの3要素と言われていますが、その中で最も必要なのは「Action」、つまり行動する能力です。
ただ座っているだけで幸運がやってくるのではなく、さまざまな環境下において自ら行動することで試行錯誤を繰り返し、その結果偶然が起きる可能性が生まれます。行動するためには、環境を察知するためにアンテナを張り巡らせつつ周囲を観察し、準備しておくことが大切です。
行動のほかにも、気づきと受容が必要
行動以外の要素についても、詳しく見ていきましょう。
気づきは、偶然起きた出来事がセレンディピティなのかを判断する行為をさします。先述した万有引力の法則を例にしましょう。ニュートン以外の人物が、木からリンゴが落ちるのを見たとしても、必ずしも万有引力の法則を導き出したかとは明言できません。ニュートンが見たからこそ、法則が生まれたという見方もできるのです。
受容は、新たに生まれた変化をセレンディピティとして受け入れられるかどうかをさしています。この判断をするには、知識や経験、スキルなどを持ち合わせていることが大切です。
セレンディピティがビジネスに取り入れられた事例を紹介
セレンディピティは、ビジネスの場面で活かされることも増えており、さまざまな新商品やサービスの誕生につながっています。具体的な事例をいくつか紹介します。
ポストイット
化学メーカーである3M社では、強力な接着剤の開発が思うように進まず、粘着力が弱い接着剤ができあがりました。この接着剤を見た同社の研究員が、本から落ちないしおりが作れるのではないかと考え、ポストイットが誕生するきっかけとなったのです。
SNSのひとつとして、世界中で利用者が増えているTwitterは、Twitter社が運営しています。Twitter社は、当初オブビアウス社という名称であり、2006年に開発された段階ではTwitterはショートメッセ―ジの交換ツールという位置づけだったのです。しかも、社員が遊びで作ったものでした。
社内での人気に気づいた幹部が、ツールの中毒性を発見し、改良を重ねて現在の形式となり普及しました。現在では、Twitterを含むSNSやブログを「セレンディピティエンジン」と呼ぶことがあります。
コカ・コーラ
コカ・コーラは、「フレンチ・ワイン・アンド・コカ」という製品が前身で、コカ・ワインというアルコール飲料のひとつでした。アメリカで絶大な人気を集めたのですが、1886年にアトランタで禁酒法が制定されたために販売不可能となってしまったのです。
薬剤師のペンバートン博士が、ワインの代わりに水を入れようとして、間違えて炭酸水を入れたところ、人気を博しました。これが現在販売されているコカ・コーラの起源です。
カッター
カッターと言えば、紙を切るための道具ですが、カッターがなかった時代には紙を切るためにカミソリが使われていました。しかし、カミソリではすぐに紙が切れなくなってしまい、両刃を使ったらすぐに捨てられていたのです。
刃物の製造販売を行っている「株式会社オルファ」の創業者・岡田良男氏は、印刷会社での仕事中にカミソリの刃をすぐ捨てることをもったいないと感じていました。
岡田氏は、路上で靴底を削るのにガラスの破片を使い、切れ味が鈍るとまた割って使っている靴職人を見た際、終戦後に進駐軍の兵隊たちが折り筋の入った板チョコをかじっているのを思い出し、カッターも同じように折っていくという発想を思いつきました。 現在では、この形式のカッターが、国内外で広く使われるようになっています。
ラップフィルム
ラップフィルムは、第二次世界大戦中にアメリカ軍兵士が水虫を防ぐために、ブーツの中敷きとして使われていました。戦後、とある主婦がレタスをラップフィルムに包んだことから、食品を衛生的に持ち運べるとして大ヒットしたのです。
電子レンジ
かつてアメリカにあった軍需製品メーカー・レイセオン社に、スペンサー博士という人物がいました。博士は、1945年にレーダーの実験をしている最中、自身のポケットに入っていたチョコレートが電波によって柔らかくなるのを発見し、これが電子レンジの原理となりました。
セレンディピティを起こしやすくするための行動は?
セレンディピティは、ふとしたきっかけで起きることが多いものです。より多くのセレンディピティを起こすためには、次の行動が有効的とされています。
企業をあげて、保守的にならずに新たなチャレンジを行う
従業員が、社内にあるさまざまな考え方や価値観などと触れ合えるよう、企業でも取り組みを行っていきましょう。
例えば、会議のメンバーに異なる部署の人物を招き、新たな目線で意見をもらうと、今まで思いもよらなかったアイディアが浮かぶ可能性があります。ときには意見が取り入れられないこともありますが、これも大切な気づきのひとつなのです。
従業員が社外の人と接する機会を増やす
社内だけでなく、社外の人とも積極的に関わる機会を設けることも重要です。セミナーやイベント、異業種交流会など、人が多く集まりそうな場所へ積極的に参加を促し、多くの人と触れ合えるような体制作りを目指しましょう。
まとめ
セレンディピティを特定の人のみが持つ才能や幸運とだけ考えるのではなく、新たなアイデアを手にするために持つべきビジネススキルのひとつと捉えてみましょう。従業員の成長や企業の業績向上のための取り組みを考える際に、セレンディピティの概念を説明した今回の記事を参考にしていただければと思います。
関連記事
-
ワークエンゲージメントを高め、よりよい心理状態で仕事に取り組もう!
職場改善
2021.07.05
-
働きがいがある企業に見られる特徴とは?長く働きたいと思える企業づくりに役立てよう
職場改善
2021.07.05