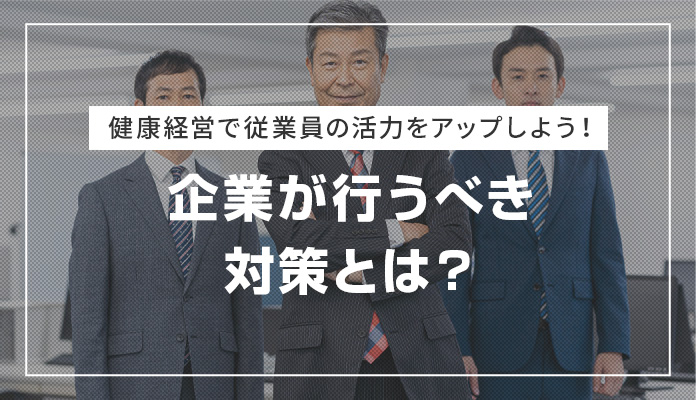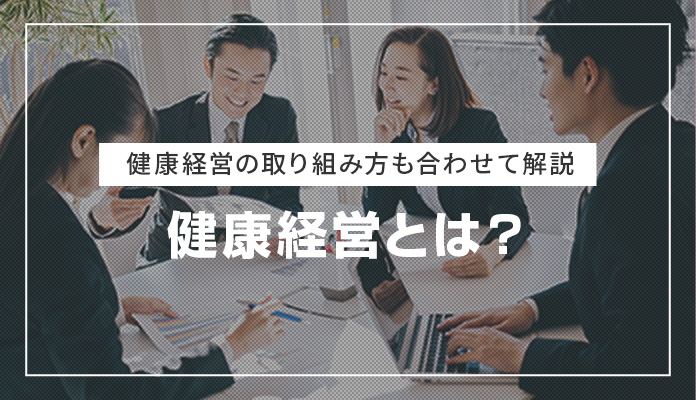健康経営
2021.07.30
健康経営はメリットが大きい!内容を理解し導入検討につなげよう
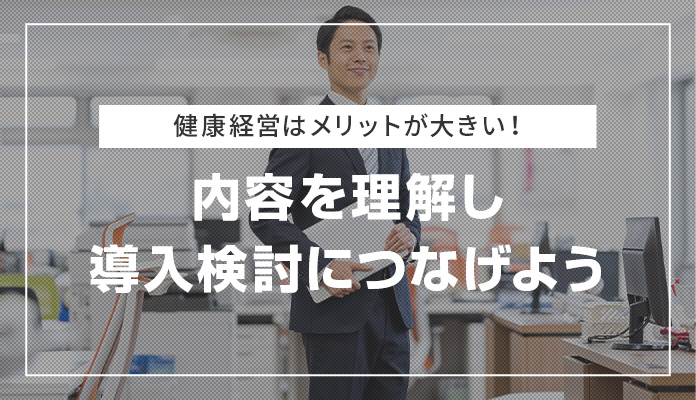
労働人口の減少や、生産性向上をはかる面などから、多くの企業で従業員の健康を重視する取り組みが行われています。これを「健康経営」と言い、従業員の健康は企業の経営にとって必要不可欠な要素となっています。
健康経営を取り入れることで、企業及び従業員はどのようなメリットを受けられるのでしょうか。また、注意すべき点にはどのようなことが挙げられるのでしょうか。今回の記事で詳しく解説します。
健康経営とは?
まず、健康経営とはどのような取り組みなのかを詳しく見ていきましょう。
企業の生産性を上げるために、従業員の健康管理を行う
健康経営とは、経営的な視点から従業員の健康管理を行い、企業の生産性や業績を上げていく取り組みをさします。従業員が健康な状態を保って働けることで、企業も業績を上げていけるという考えです。
従業員の健康管理を投資と捉え、将来に向けてのリターンを期待することで、生産性や業績の向上、従業員のモチベーションアップなどを目指しています。つまり、企業が率先して従業員の健康管理を行うことで、企業の活性化を生み出し、業績の向上及びイメージの増加につなげていこうとするものです。
健康経営では、従業員の健康度合いと企業の生産性が、密接に関係しているとの考え方が主流となっています。
アメリカのロバート・H・ローゼンが提唱した概念
健康経営の概念を提唱したのは、アメリカの経営学及び心理学の専門家ロバート・H・ローゼンだと言われています。彼が1980年代に提唱した概念「ヘルシーカンパニー」及び、1992年に記した著書「The Healthy Company」の内容に基づいているとされています。
アメリカは日本によりも医療費が高いとされている上、日本のような国民皆保険の制度がありません。そのため、従業員が病院にかかる回数が増えると、医療費にかかる企業負担が大きく増えてしまいます。そのため、経営にも影響が及んでしまいます。
健康経営の概念をローゼンが提唱した当時のアメリカも、従業員が怪我や病気で医療を受けた際に企業が行う金銭負担が高騰していました。経営にも負担が出るほどの高額だったことから、医療費を抑える目的として、健康経営という言葉が広がったという説があります。
企業にとって、社員の健康維持を管理することで、長期的に見て大きなメリットがあるというのが、健康経営の考え方です。
日本で健康経営が広まった背景とは?
日本でも、健康経営の取り組みが大きく注目されるようになってきました。その背景には、次のような理由が挙げられます。
労働人口の減少や高齢化が進み、人手不足が深刻化している
日本では、少子高齢化が進むことで、長期にわたって労働人口の減少が深刻な問題となっています。さらに、働き方改革の影響で長時間労働も難しくなっています。従業員が、個々の能力を企業で発揮するためには、健康維持がひとつの大きな鍵となっています。
日本における医療費の増加
少子高齢化に伴い、日本でも医療費の増大が大きな問題となっています。2018年に、政府が社会保障給付費の見通しを発表していますが、それによると2040年の医療費が2018年のおよそ1.7倍(70兆円程度)に達すると予想されています。
医療費の増大は、財政の圧迫に直結するため、医療費を抑制することが緊急の課題とされています。
政府も「健康経営優良法人認定制度」を導入
日本でも、2009年頃から健康経営の取り組みが始まりました。理由として、長時間労働の横行や、ブラック企業の存在など労働環境の悪化が背景にあったことが挙げられます。
2013年から、日本政府は毎年健康経営についての取り組みを行っていますが、このとき経営者の意識の低さと健康増進方策の不十分さが課題として挙げられました。この課題を解決すべく、顕彰(業績や功績をたたえて広く知らしめること)制度の設定が決まったのです。
2014年から制定された健康経営銘柄は、この顕彰制度を取り入れた制度で、健康経営に取り組む企業を評価するために始まりました。これらの取り組みにより、健康経営に対する企業の関心が少しずつ高まったことから、2016年に経済産業省が中小企業向けに「健康経営優良法人認定制度」を創設しました。
健康経営優良法人認定制度は、中小企業だけではなく上場していない大企業も選定対象となっています。幅広い企業を認定することで、健康経営の取り組みをより広めていこうという目的があります。
企業側から見た健康経営のメリットとは?
健康経営を取り入れることで、企業側・従業員の双方に大きなメリットがあります。まず、企業側から見たメリットを確認してみましょう。
生産性の向上につながる
従業員が健康で働けることと生産性の向上は、直結しています。従業員が、健康な状態であれば、モチベーションやパフォーマンスを高く保ったまま、業務に集中することができるためです。
さらに、従業員の健康が保たれると、欠勤率や長期休業の割合も下がるため、生産性がさらに高められます。これらは企業にとって大きなメリットとなります。
企業のイメージを上げられる
健康経営に取り組む企業は、従業員を大切に考えている企業だという印象を与えます。印象が良くなると従業員が安心して勤務できるようになる上、求職者が受ける印象も良くなります。
さらに、健康経営優良法人に認定されると社会的な評価を受けられるようになり、取引先や株主からの評価が上がると、株価上昇も期待できるようになります。これらのことから、社会的に企業のイメージを上げる結果につながるのです。
医療費の削減につながる
健康経営を行うと体調を崩す従業員が減り、病院の受診が減ることから、医療費や薬代が抑えられます。これにより、企業が負担する医療費も削減でき、医療費の抑制効果が大きくなります。
医療費を含む社会保障費は、「見えない人件費」と呼ばれることもあります。健康経営の取り組みによって従業員の健康を促進し、医療費の削減を行うことが、日本の企業に課せられた喫緊の課題です。
従業員の離職率を下げられる
健康経営の導入は、労働環境の改善につながるものです。これにより、働きやすいと感じられる環境が整えられます。よって、従業員の定着率が上がり、離職率の低下に繋がります。
企業の多くが人手不足に悩んでいる中、離職率の改善は大きなメリットとなります。
資金調達のきっかけになることがある
金融機関の中には、健康経営格付に基づいた融資を行っているところがあります。日本政策投資銀行など、政府系の金融機関が中心であり、健康経営の普及及び促進を目的としています。
このような融資条件に該当することで、健康経営に取り組む企業であると対外的に認められるメリットがあります。
従業員側から見た健康経営のメリットは?
続いて、従業員側から見た健康経営のメリットを確認しましょう。
健康への意識が高まる
企業全体で健康経営に取り組んでいることで、自分一人では続けられない取り組みも継続できるようになり、健康への意識を高めることができます。同僚同士で励まし合うと、さらにやりがいが生まれるでしょう。
健康への意識が高まると、食生活や運動習慣の改善につながり、ひいては生活習慣病を予防改善できる効果が期待できます。
企業に対して誇りを持って前向きに働ける
健康経営に取り組んでいくと、企業が自分の健康まで気にかけてくれているという安心感と信頼感を抱けるようになり、誇りを持って働くことができるようになります。肉体的な健康と精神的な健康は深いつながりがあるため、一方の健康が保たれると、もう一方の健康にも良い影響をもたらします。
この考えが広まっていくと、他の従業員にも良い影響を与え、職場に活気が生まれるでしょう。
注意点もふまえて導入を検討しよう
健康経営は、導入により大きなメリットが得られますが、導入前に注意点もふまえておかなければなりません。どのような注意点があるのでしょうか。
コストがかかる
健康経営を行うには、さまざまな種類のコストがかかります。データを収集するコスト及び管理するコスト、データの分析を専門家に依頼する際のコストなどが挙げられます。
さらに、企業内の人事データも管理しなければならないため、企業の人事総務担当者が健康経営の業務に携わる際の人的コストも発生します。
結果が見えるまでに時間がかかる
営業成績などとは違い、健康経営の成果は目に見えてはっきり分かるものではありません。さらに、効果が見えたとしても、ある程度の時間がたたないと実感しにくいと言われています。
健康経営の導入には経営者の承諾が必要ですが、コストがかかる上に効果が分かりにくいという点で、経営者の理解を得られない企業も見受けられます。
従業員のプライバシーを守らなくてはいけない
健康経営を行うには、従業員の健康診断の結果やメンタルチェックの内容など、プライバシーに踏み込む内容も、企業が管理する必要性が生じます。
これらの情報は、たとえ同僚であっても知られたくないものです。また、従業員が管理状況に不安を抱いていると、健康管理に必要な情報が入手できなくなることもあります。従業員が安心して、情報を提示できるような環境づくりが重要です。
従業員の業務が滞ることがある
健康経営を行うためには、勤務時間中にさまざまな取り組みを行わなければなりません。定期的な健康診断を始め、ストレスチェック・アンケートの回答・各種イベントの参加などがありますが、これらのほとんどは仕事中に時間を割いて行うことが必要です。
場合によっては、従業員の通常業務が滞ってしまう恐れがあります。そのようなことが起こらないよう、上司の配慮が求められます。
まとめ
健康経営のメリットや注意点などを詳しく紹介してきました。双方を精査した上で、企業に健康経営を導入するかどうかを検討する必要があります。
ただ、コストや労力などの懸念はありますが、それ以上に健康経営の導入によって得られるメリットは計り知れず、企業として一考の価値がある取り組みだと言えるでしょう。
企業における「ウェルビーイング」教育を考察|ビジネス現場に求められる要素とは
企業におけるウェルビーイングの考え方や要素、教育について紹介しています。ウェルビーイングは医療や福祉だけでなく、学校における授業や企業での教育にも導入されています。今後企業の利益向上や優秀な人材の確保を実現するうえでは企業もウェルビーイングを取り入れるのが重要です。
関連記事
-
健康経営で従業員の活力をアップしよう!企業が行うべき対策とは?
健康経営
2021.05.31
-
健康経営
2021.03.30