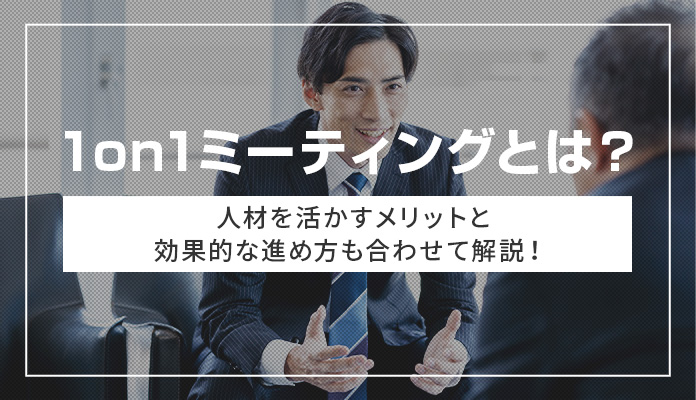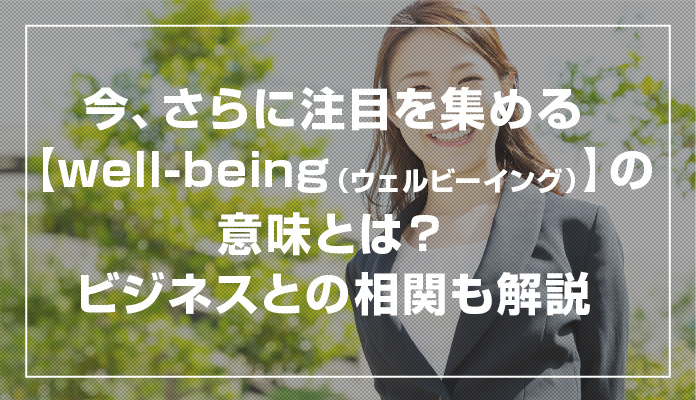ウェルビーイング
2022.07.12
1on1で主に話すこととは? ミーティングのテーマや話の具体例も合わせて解説!
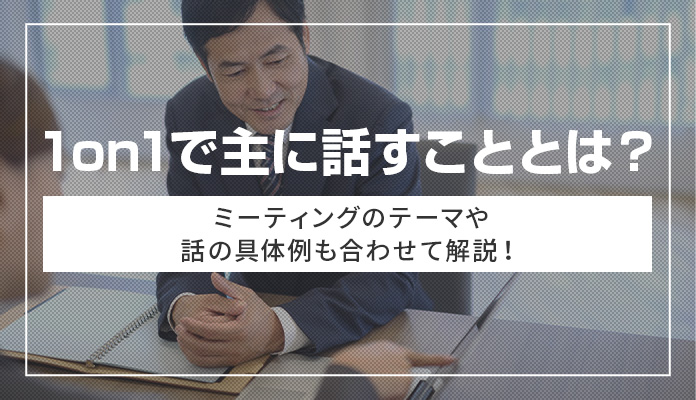
1on1ミーティングが広がりを見せる2022年、1on1で話すことはどのような内容であるべきなのかといった疑問や関心の声が聞こえてきます。1on1で話す内容に統一的な決まりはなく、実施する企業によってマチマチですが、大きくは目的によって決まるものです。この記事では1on1で話すことについて、効果や話すことの具体例なども含めて解説します。
▼1on1ミーティングの基礎知識については、あわせてこちらの記事もご覧ください。
1on1ミーティングとは? 人材を活かすメリットと効果的な進め方も合わせて解説!
1on1で話すことの大枠は目的によって決まる
何を目的として1on1をするのかを明確にする
1on1ミーティング(以下1on1とします)の大きな目的は課題解決を通じた人材(部下)の育成と相互理解による上司と部下の信頼関係の強化、従業員エンゲージメントの向上です。会社によっては人材育成に重点を置いているかもしれませんし、従業員エンゲージメントの向上を第一に考えているかもしれません。どちらにしても、1on1を行う目的を明確にすることが、効果的な実施の第一歩となります。
上司と部下が2人だけで行う面談、対話という部分だけに目をやると、1on1とその他の2人で行うミーティングの違いがわからなくなってしまうため注意が必要です。1on1は部下のために定期的かつ計画的に実施するミーティングであり、上司は部下から話を引き出して情報を共有します。同時に、コーチングやティーチング、フィードバックを行う場である点がその他の面談やミーティングとの大きな違いです。
テーマは何かを決める
1on1ミーティングの目的が明確になったら、目的達成に向けてそれぞれの回で話すテーマを決める必要があります。テーマ決めが必要な理由は時間を無駄にしないで有効なミーティングにするためです。一般的な1on1は1回あたり30分~60分程度という限られた時間の中で行われます。
時間が無駄になる主なケースは、あれもこれも詰め込もうとして話が散逸し、まとまらなくなるケースと、何を話せば良いかがわからず時間だけが過ぎてしまうケースです。どちらもテーマを決めることで解決に近づきます。
回ごとのテーマは、その時点で部下が抱えている課題や悩み、希望によって決まるものです。上司が管理職としての都合で話したいことをテーマにしてはいけません。テーマを考えるのは上司でも部下でも構いませんが、1on1を効果的なものとする点を重視して決めます。
また、回ごとのテーマとは別に毎回共通のテーマを設定することも可能です。テーマというよりは冒頭のあいさつや確認に近いイメージだと考えると良いでしょう。確実にコミュニケーションをとることで、上司と部下の信頼関係を深める効果が期待できます。したがって、前回以降に生じた悩みや健康不安、直近のモチベーションといった毎回聞いても違和感のないものとすることが重要です。ビジネスに直接関係なくても構いません。
必然的に話すべき内容が絞られる
テーマが決まれば、必然的に話すべき内容が絞られます。たとえば、テーマがキャリアプランの場合は、部下自身が描く未来像や今後就きたい役職、関わりたい職務や自己の能力といった話が該当するでしょう。
1on1で話すテーマは多岐にわたる
仕事に少しでも関係していればテーマは自由
1on1の大きな目的が人材育成や相互理解を深めることによる信頼の強化、従業員エンゲージメントの向上であることから、間接的または少しであっても仕事に関係していれば話すテーマとなり得ます。1on1には決められたテーマがあるわけではなく、自社や部署に必要なテーマであれば自由に設定可能です。
仕事や職場そのものに関係するテーマ
仕事や職場そのものに関係する主なテーマを以下に示します。
- ・業務上の問題点
- ・関係者との人間関係
- ・人事評価への疑問点や不満点
- ・キャリアに関して思っていること
- ・職場の環境への満足度
それぞれのテーマの中には細かい確認事項が多く含まれており、1回の1on1ですべてを確認することができないケースもあるでしょう。その場合は、2回3回と必要に応じて1on1を実施します。すべてを1回で終わらせようとして、長時間のミーティングにならないことが重要です。
開催頻度が高い会社の場合、たとえば毎週1回行われている1on1が長時間になると、日常業務に支障をきたす恐れがあります。また、1on1の開催自体が億劫になってしまうかもしれません。
間接的に影響を及ぼすテーマ
以下は間接的に仕事に影響する主なテーマです。
- ・健康上の問題点や不安に感じていること
- ・プライベートでの悩み
- ・休日の過ごし方
- ・熱心に取り組んでいる趣味
こちらも話す内容的には細かく分かれますが、仕事と直接関係がないテーマだけに、職権が及ばない部分が多いといえ、上司ができる対処は限られています。また、繊細な分野でもあり、「部外者が立ち入り過ぎだ」との批判を受けないためにも、コミュニケーションの取り方には注意が必要です。
1on1で話すことがもたらす効果
上司への信頼とコミュニケーションが強化される
毎回の1on1で上司との円滑なコミュニケーションをとることにより親近感が生まれます。それが信頼につながり、コミュニケーションがより強化される点が1on1で話すことがもたらす大きな効果です。
また、的確なコーチングやティーチングが受けられ、効果的な話ができたと感じられれば、部下にとっては有意義な時間です。部下のために実施する1on1に部下が満足すれば、上司や会社にとっても1on1が成功したといえるでしょう。その結果としてもたらされる効果は他にも多数あります。
会社の理念やビジョンへの理解が深まる
なぜこの業務が必要なのか、会社が目指しているところはどこかといったテーマや疑問点を話すことで、会社の経営理念やビジョンについての理解が深まります。
人事制度への不満がなくなりやる気が出る
自身の働きがどのように評価され、リターンとなるのかといった疑問が1on1によって解消されます。その内容が適正であれば不満が無くなりモチベーションアップにつながります。キャリアアップのプランについても同様です。
問題解決能力が向上する
上司によるコーチングが気づきを導き、ティーチングが知識を補完することに加え、1on1の話の中で自分自身を振り返ることにより成長し問題解決能力が向上します。また、客観的なフィードバックも正しい判断の役に立つでしょう。
自身の業績がアップする
上記の効果が重なることで、自身の業績アップにつながります。ここまでは部下にもたらされる個人的な効果です。
上司のマネジメント能力がアップする
部下の話を引き出し、さまざまな内容の課題や問題に対して的確な対処をすることで、マネジメント能力を磨くことができます。次に示す部下への理解もマネジメント能力のアップに貢献する要素です。
部下への理解が深まる
個人の内心に関わる部分をしっかりと聞くことで、部下の仕事の理解度を知ることができ、部下がどのような疑問や悩み、課題を抱えているのかなど、部下に対する理解が深まります。ここまでの2つは上司個人の主な効果です。
職場環境が改善される
ここからは、部下にも上司にも関係するとともに、会社にとって大きな効果です。まず、上司が気づかなかった職場環境の問題点を聞き出すことで、働きやすい環境に改善することができます。会社全体のパフォーマンスを高める可能性が大です。
エンゲージメント数値が向上し人材が定着する
各社員のエンゲージメントが向上し、総体としての従業員エンゲージメントが向上することで人材の定着が進みます。
業績がアップする
上記の効果が組み合わさることで生産性が向上し、企業としての業績アップが可能です。
具体的な話すことの例
導入・プライベート
ここからは、テーマの分野別に話すこと(上司が部下の言葉を引き出すために使用する質問、問いかけ)の具体例を紹介します。まずは、1on1の導入部分やプライベートに関する話の例です。テーマとしての主な効果は会話のキッカケ作りや相互理解を深める点にあります。
- ・昨日(先週)は忙しかったね?
前日(先週)の業務量が普段より多かったり、イレギュラーな業務が発生していたりした場合に使います。部下をねぎらう気持ちが込められている問いかけです。
- ・最近興味のあることは?
人は自身が興味のあることに関しては話しやすい傾向があることから、会話のキッカケとして有効な問いかけです。同じ趣味であれば相互理解が進むでしょう。
- 連休はどこかに行った?
同様に旅行やイベントを楽しんだ話は場の空気をリラックスさせるのに役立ちます。上司が行ったことのある場所や催事の話題であれば、より相互理解を深める効果がありそうです。
仕事関係
次に、仕事の内容に関係する問いかけです。こちらのテーマは、相互理解と部下の育成に関係しています。
- ・いま抱えている仕事に不満はない?
- ・進行に問題は出ていない?
上記2つは仕事に対する直接的な不満や進捗に絡む問題点をストレートに引き出す問いかけです。部下が仕事を正しく理解しているか、業務量や段取りに問題はないかといった課題を見つけてサポートや改善につなげることができます。また、部下の仕事の状況を気にかけている上司の視点を伝えることが可能です。
- ・仕事にやりがいを感じるのはどこ?
仕事に対する意識、取り組む姿勢や適性を見ることができる問いかけだといえるでしょう。また、自分のやりがいを再認識し、積極性を強めることが期待できます。
- ・新しい評価制度でわからない点はない?
- ・取得を目指している資格は何かある?
- ・10年後はどんな姿を目指している?
- ・こんな部署があったらいいなと思うことは?
この4つは人事制度への理解度や不満、希望するキャリアプランを把握するための問いかけです。同時に、部下は自分が話すことによって、キャリアに関する意識について気づきを得ることがあります。
- ・チームに感じる改善すべき課題はある?
率直にチームに関する課題を聞けると同時に、人間関係の問題を引き出すこともできる問いかけとして使えるでしょう。チームに対する自分の姿勢に関する気づきになる可能性もあります。
- ・経営戦略の具体策をどう考える?
具体策がなくても考えることで経営戦略への理解を促し、成長につなげることが可能です。
- ・会社への要望は?
会社に対するあらゆる要望をストレートに聞いてみることも、相互理解を深めるためには必要だといえるでしょう。話が大きすぎると上司の立場では回答できないケースもあるでしょうが、組織人として間違ったものでなければ同意はともかく一定の理解を示すことが重要です。
健康面
最後は健康面の問いかけです。テーマとしては部下の健康状態に対する気配りと仕事への影響に備える点に意味があるといえるでしょう。
- ・最近疲れてない?
- ・どこか身体で気になるところはない?
- ・家に持ち帰ってまで仕事をしていない?
どの問いかけも健康とオーバーワークを絡めたものとなっています。健康面の変化は早めにキャッチすべきであり、毎回問いかけても良いでしょう。
「話すことがない」と返事をされたときの対処法
自分の姿勢を見直す
1on1は上司と部下が1対1で向き合うため、「肩の力を抜いて」といっても一種の緊張感があるのは仕方がないことです。しかし、それがコミュニケーションを阻害するほどなら問題があります。また、問題となるのは緊張感だけではありません。
- ・(周囲の様子も含めて)部下が話しやすい状況になっているか
- ・遠慮していえないのではないか
- ・上司ばかりがしゃべっていると思われていないか
このようなチェックポイントを意識しながら、1on1の環境づくりも含め、上司としての自分の姿勢を見直すことが重要です。
テーマが明確かを確認する
テーマがぼやけていると何を話していいのかわからないといった状況が生まれやすいため、再確認してみる必要があります。ただし、そのときになって慌てて明確化しようとしても話すことが生まれるとは限らないため、次回への戒めの意味が強いといえるでしょう。
テーマが明確にもかかわらず話すことがないと返事をされた際には、前記「具体的な話すことの例」を参考に問いかけて進めてみると良いかもしれません。また、クローズドクエスチョン(イエス・ノーで答えるような質問)ばかりだと話が途切れがちになるため、自由な言葉で回答ができるオープンクエスチョンを活用すると良いでしょう。
信頼関係を構築
いくら1on1が信頼関係を強化する場だといっても、ベースとなる信頼関係の構築ができていない上司に本音を話すとは思えません。最初にある程度の信頼関係がなければ1on1は始まらないと考えるべきです。まずは1on1の目的が部下のためであることや、部下のために真剣にマネジメントする点を伝えることから始めます。
話すことを生み出す事前準備
話すことを用意する
1on1が始まってから「~~について、~~はどうですか?」と聞かれても、パソコンで答えを検索するようなわけにはいかず、すぐには思い浮かばないケースが少なくないようです。目標とする会話が具体的に成立するための資料等の事前準備や、話すテーマの事前告知が大切といえます。事前準備は上司だけでなく部下にも必要です。
話すことで注意したい点として、避けた方が無難な話題があります。話す中身としては多いかもしれませんが、政治や宗教に関する話題は事前準備であろうとぶっつけ本番であろうと関係悪化を招きやすく避けるべきでしょう。スポーツに関する話題はそこまで神経質になる必要がありません。ただし、応援しているチームや嫌いなチームがあるため、1on1ではケースバイケースといえます。業務外の雑談時には話題になったとしても、1on1では慎重な姿勢で臨むと良いでしょう。
1on1帳票などの活用
1on1は定期的かつ計画的に実施されます。したがって、事前に日時がわかっており、早めにテーマを決めておくことも可能です。そのうえで、たとえば簡単な質問回答票を準備し、1on1までに記入しておくことが有効といえます。質問回答票を参考に進行することにより、話すことを忘れてしまうといったリスクを回避でき、有効な会話ができるでしょう。
注意すべきは、質問回答票を事前に部下から受け取ったとしても、その内容を見てすべて理解したつもりになってはいけない点です。1on1は部下の口から聞き出すことが重要であり、双方向コミュニケーションを行うことが大前提となっています。質問回答票だけではわからないことがあるだけでなく、紙ベースで対応するのであれば1on1の意味がなくなってしまうと考えるべきでしょう。
話すこと以上に重要な聞くことと活かすこと
1on1は聞き出すことが重要
1on1で部下が話すことは、上司が聞いてアドバイスやフィードバックを行う、対策を打つために必要な情報、活かすための情報です。つまり上司は聞くことが重要で、失敗しないために先走って回答するよりも最後まで黙って聞くくらいでちょうど良いのが1on1だといえます。
フィードバックはお互いに
コミュニケーションの強化と相互理解の観点から、上司だけでなく部下からのフィードバックも望ましいのが1on1です。部下の率直な感想や意見がなければ、上司の1on1マネジメントが適切だったかどうかを確認して精度を上げる機会が少なくなるかもしれません。お互いに忌憚のないフィードバックをすることで、1on1がより良いものとなり、さらなる話すことにつながると考えられます。
PDCAサイクルの利用
1on1は企業戦略にとって大切な施策であり、計画と実行だけでなく検証と改善も一連の流れとして実行する必要があります。そのための方法として望ましいのが、PDCAサイクルの利用です。
1on1で話すことは事前に整理しておくことが重要
1on1を効果的に進めるには、話すことを事前に整理しておくことが重要です。質問回答票のような形式でまとめておくのも良いですし、他に使い勝手がよいと思える方法があれば積極的に活用しましょう。
1on1のために用意した時間を実りあるモノにするためにも、しっかりとした準備が欠かせません。求める結果を出すためには行動あるのみです。
関連記事
-
1on1ミーティングとは? 人材を活かすメリットと効果的な進め方も合わせて解説!
ウェルビーイング
2022.07.12
-
今、さらに注目を集める【well-being(ウェルビーイング)】の意味とは?ビジネスとの相関も解説
ウェルビーイング
2021.05.31