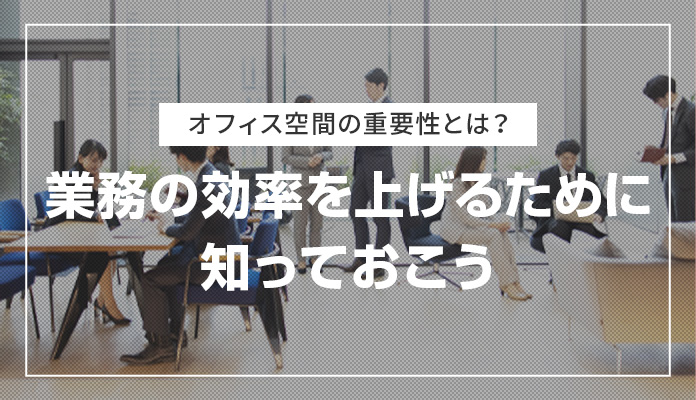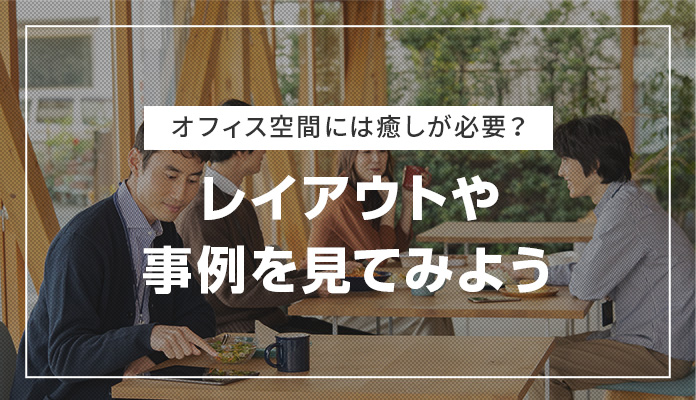オフィス
2022.03.24
世界と日本におけるオフィスの歴史を大解剖! 働き方のトレンドを紹介
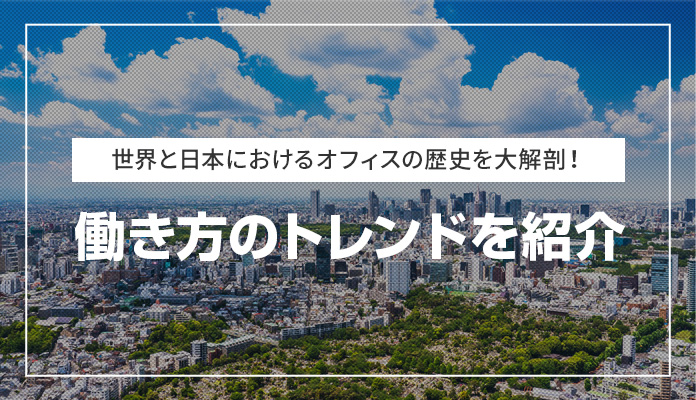
多くの人が当たり前のように行う、“会社へ行き仕事をする”という「オフィス」の概念。働き方改革やIT化などに伴い、オフィス環境も多様化していますが、そんなオフィスの歴史をご存じでしょうか?
本記事では、世界におけるオフィスの誕生から、今日に至るまでの日本のオフィスの移り変わりや働き方に関するトレンドの変化について紹介します。オフィスの歴史について紐解いていく中で、これからのオフィスの在り方のヒントを探っていきましょう。
世界におけるオフィスの歴史
まずは、世界のオフィスの成り立ちを紐解きながら、「会社へ行き、仕事をする」という在り方のルーツを辿っていきましょう。
オフィスの誕生
現在のオフィスの原型とも言える「決められた時間に決められた場所に人が集まり働く」という概念・ワークスタイルが確立されたのは、約700年ほど昔の14世紀ルネサンス時代と言われています。
産業革命期のイギリスで、人々が集まって働く場所のことを「オフィス」とカテゴライズされたのが始まりと言われているのです。オフィスで働くという概念が定着する前は、雇い主の家で働くスタイルが主流だったとされています。
世界初のオフィス専用ビルは1729年に誕生
当時は、今のようなオフィスビルはありませんでしたが、オフィスの概念が広まり、オフィス専用ビルが誕生し始めます。
このオフィス専用ビルの誕生も、オフィス生誕の地とされるイギリスが始まりと言われており、1729年に貿易を行う企業が世界初となるオフィス専用ビルを立てたとされています。その後、労働者がオフィスや工場に集まって、業務を行うワークスタイルが定着していったそうです。
今のような超高層ビルは、アメリカが始まりと言われています。1888年竣工した地上12階、高さ55mの「ルッカリー・ビル」は、最初期の鉄骨造による高層ビルといわれており、翌年1889年には、当時世界一の高さを記録したとされる高さ106mのオーディトリアムビルが完成しました。以後、オフィスの需要の高まりを受け、アメリカでは超高層ビルの建設ラッシュが始まり、新宿のビル群をはじめとした、今のような超高層ビルが主流の時代へと突入していきます。
世界におけるオフィスレイアウトの変化
オフィスの誕生から今日のような高層ビルができるまでの流れを見てきましたが、当時のオフィスフロアはどのようなレイアウトだったのでしょうか。
オフィスが誕生した当時は、管理者が従業員を監視できるようなスクール式レイアウトが主流で、学校の教室のように雇い主と向かい合うように座って働いていたそうです。その後、会社としての機能が広がるにつれて、働く環境も多様化し、プライバシーを確保するためのパーテーションで仕事スペースを区切るブース型のレイアウトデザインが登場します。
このように、世界におけるオフィスレイアウトは、その時代の考え方や働く環境、人に合わせて変化しており、現代のオフィスデザインの進展へとつながっているのです。
日本におけるオフィスの移り変わり
ここまで世界におけるオフィスの歴史について見てきましたが、日本ではどのようにして現代のようなオフィスへと進展したのでしょうか。ここでは、日本のオフィスビルの始まりから2010年代のオフィスデザインまでを紹介していきます。
日本初のオフィス専用ビルができたのは1894年
まず、日本初のオフィス専用ビルは、丸の内に建てられた「三菱一号館」が始まりと言われています。丸の内と言えば、東京屈指のオフィス街です。
1914年(大正3年)に東京駅が完成し、駅周辺に各企業の事業所が新設・移転されたことをきっかけに、オフィス街へと発展していったとされています。
1960~1970年代初期(高度成長期)の日本
オフィス専用ビルの誕生から約70年後の日本では、高度成長期を迎えます。このころの日本では、プライバシーを重んじたオフィスレイアウトを採用し始めた欧米とは異なり、今のような島型レイアウトが採用されていました。
ただ、まだこのころは手作業による事務処理がメインであったこともあり、組織図をそのまま再現したような階級に応じた対向式や学校式レイアウトも多く、オフィス環境の改善にはまだ目が向いていませんでした。
1970年中期~80年代前半の日本
1970年中期以降は、事務処理用のオフィスコンピューターや電卓、複写機などが登場し、手作業から機械を活用した作業へと進化します。事務処理専用機器の普及によって作業効率が大幅にアップし、働く環境についても考慮され始めるようになり、社内インテリアにも目が向き始めます。
1980年後半~90年代初期の日本
1980年代後半には、ワープロ、PCなどの登場で、OA化(Office Automation:事務的作業の自動化)され、さらに事務処理面が向上しました。
ただ、バブル期ということもあり、経済の急拡大で人材不足になり、遅くまで仕事することが常態化するようになります。すると社員のストレスも増大し、オフィス環境の整備が求められるようになっていきました。
このような時代背景もあり、PC作業に対応するデスクレイアウト、人間工学を考慮したイスなどを採用する例が増加し始めます。
バブル崩壊後の90年代の日本
バブル崩壊後の日本では、オフィスコストの削減を中心に体質改善する企業が増加します。スペース効率向上や、組織変更に対して柔軟に対応するようになり、省スペースを目的としたレイアウトなど、オフィスデザインも多様化していきました。
働き方では、ネットワークPCが一般化し、文書作成ツールの中心はワープロからパソコンに移り変わります。携帯端末を使ったモバイルワークも出現し、会社以外の場所でも仕事をするというケースも増え始めます。
2000年代~2010年代の日本
2000年代は、来客や役職待遇を重視する傾向が見られるようになり、会議室や受付といった見えるところにコストをかける傾向がありました。しかし、世界を代表するAppleやGoogle、Facebookといった海外のソフト・IT関連の企業の多様性な働き方が日本へ伝わり、近年はコミュニケーションや創造性を生み出すことを重視したオフィスデザインが増え始めています。
日本における働き方や働く環境に関するトレンドの変化
日本も従業員がオフィスへ行き、仕事をするのが主流でした。しかし、2020年代以降の今日では、働き方改革が進み、多様化しています。ここでは、そんな働き方や働く環境に関するトレンドの変化について見ていきましょう。
テレワーク
近年の社会情勢の影響もあり、日本でもテレワークを取り入れる企業が増えています。
テレワークとは、情報通信技術(ICT)を活用し、自宅で仕事を行う働き方のことです。日本では、1984年ごろからテレワークを新しい勤務形態として取り入れる企業が出現し始めました。最も本格的にテレワークを導入したのは、NEC(日本電気)だったと考えられています。
PC の普及や女性の社会進出が本格的になり、働きながら育児や介護ができる環境を設けることで優秀な人財を確保しようという考えが広まり、テレワークが普及していきました。
昨今も感染症対策として、社員の感染リスクを軽減するため、導入する企業が増えています。
フリーアドレス
今注目されているフリーアドレスは、1987年に世界で初めて「清水建設技術研究所」が採用したオフィスレイアウトです。1日の大半を社外で過ごす営業職のデスクスペースを有効活用できないかという発想から生まれました。デスクの場所が決まっていない形態で、90年代に本格的に導入する企業が増え、2000年代にかけて浸透したと言われています。
その後、組織変更の際にデスクなど物は動かさず、働く人が動いて対応するユニバーサルプランも登場し、組織変更や増員にも柔軟な対応ができるようなレイアウトも注目されるようになりました。
コワーキングスペース
コワーキングスペースとは、「Co(一緒に)」「Working(働く)」の2語からなる言葉で、簡単に言うと共有オフィスのことです。
現在のようなコワーキングスペースが誕生したのは 2005年頃とされており、アメリカを中心に急速に拡大していきます。ただオフィスを共有するのではなく、人的交流の中で情報やスキルも共有し、刺激し合うことで生産性も高まることから、フリーランスや小規模事業者だけでなく、企業の在宅ワーカーなどにも多く利用されています。
オフィスの歴史を知って時代と自社に合ったオフィス環境を模索しよう
14世紀にオフィスの概念が生まれてから今日まで、世界情勢や当時の人々の考えが反映されたオフィスの歴史があります。つまり、オフィスという概念にとらわれるのではなく、柔軟に対応させていくことが大切だということです。
オフィスの在り方を考える際は、最新のトレンドを把握し、現代社会と自社に合ったオフィス環境を実現しましょう。
関連記事
-
オフィス空間の重要性とは?業務の効率を上げるために知っておこう
オフィス
2021.08.31
-
オフィス
2021.08.31