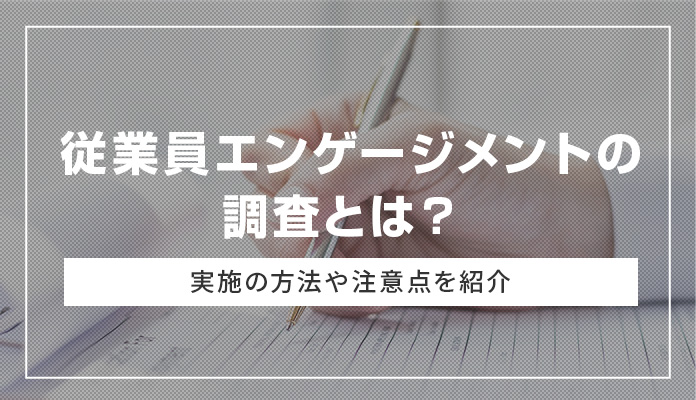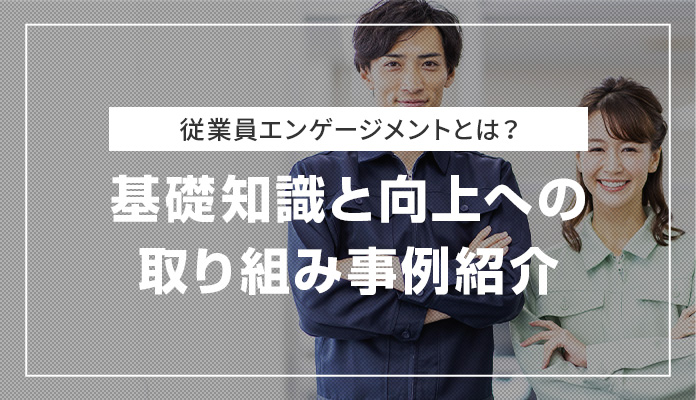健康経営
2022.08.31
従業員エンゲージメントを高める方法とは? 得られるメリットや施策をすべき企業の特徴とともに解説
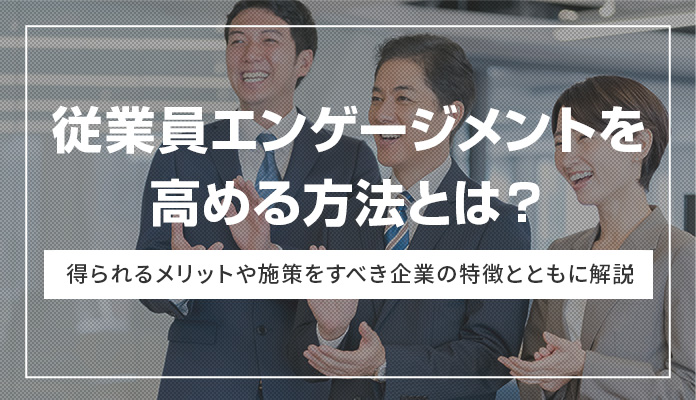
働き方の多様化により、従業員エンゲージメントを重要視する企業も多くなりました。従業員エンゲージメントは会社の財産のひとつである人材にかかわる要素です。高めることにより多くのメリットが得られるだけでなく、企業と社員が同じ方向を向き、企業理念や事業を理解したうえで利益をもたらすためにも重要な要素となります。
この記事では、従業員エンゲージメントの向上がもたらすメリットや高めるための施策をすべき企業の特徴、要素ごとに従業員エンゲージメントを高めるための具体的な方法について紹介します。
従業員エンゲージメントを構成する3つの要素
共感度=働きやすさ
従業員エンゲージメントを構成する要素のひとつである「共感度」は、組織への愛着や帰属意識を指します。精神的に安定して働ける職場は、社員に大きな安心感や信頼感を与えるでしょう。社員が企業に対して働きやすいと感じれば従業員エンゲージメントは上がり、働きにくいと感じると従業員エンゲージメントは下がります。
上司や同僚など社員同士が円滑にコミュニケーションできる風通しの良い職場環境は、働きやすさにつながります。たとえば個人対個人の一方的ではない、双方でのやりとりができる、業務以外の雑談の機会が多いなどです。さらに社員ひとりひとりの能力や個性に合った業務内容や業務量を与えることなどで、社員の働きやすさが定着するでしょう。
行動意欲=やりがい
行動意欲とは求められる以上の結果を出そうとする意欲を指します。行動意欲のもととなるのが、仕事へのやりがいです。社員は自分の努力や会社への貢献が明確な結果となって返ってくると、仕事へのやりがいを感じます。明確な結果とは、売上や収益などの具体的な数値での結果、同僚、上司、チームなどの周囲からの反応や評価などの心理的な効果のふたつです。両方を実感すると社員の大きなやりがいにつながります。
仕事へのやりがいや意欲があれば、会社での自分の存在価値を見いだせるため会社への貢献度が高まり、従業員エンゲージメントの向上につながります。一方社員の自己肯定感が低い、仕事にやりがいを感じないと従業員エンゲージメントは下がるでしょう。
理解度=企業理念やビジョンへの共感
社員が会社の考え方や進む方向を理解し、共感や支持する気持ちが「理解度」です。理解度の指標となるのが企業理念やビジョンに共感しているかどうかとなります。企業理念とビジョンは具体的に何かを明確に示しているか、社員にとって自分自身のキャリアやビジョンと一致しているかによって理解度は左右され、従業員エンゲージメントに影響します。企業理念やビジョンに共感することで会社への貢献度が上がりますが、企業理念やビジョンに共感していないと、仕事や企業を他人事として考えるため、貢献度と従業員エンゲージメントは下がります。
従業員エンゲージメントを高めることで得られるメリット
生産性が上がる
従業員エンゲージメントが高いと、社員は仕事で要求以上の成果を上げようとしたり、失敗せず成し遂げようとします。仕事への取り組みも集中しているためミスの防止や、予定通りの仕事の完了につながります。同じ時間でも多くの成果が出せるようになり、仕事の生産性が上がります。
離職率が下がる
従業員エンゲージメントが低い社員は、職場への愛着や仕事へのやりがいがないことで、ほかの企業への転職の機会を考えるようになります。平成30年度産業経済研究委託事業( 企業の戦略的人事機能の強化に対する調査)によると、従業員エンゲージメントスコアの高さ上位25%の企業と下位25%の企業の離職率を比較すると、離職率の高い組織間での比較においては24%、低い組織間での比較においては59%の差が生じています。
欠勤率が下がる
従業員エンゲージメントが高いと、仕事への意欲や関心、向上心が高い状態となります。仕事をするために会社へ行きたい、という気持ちから健康のための自己管理を行う社員も増え、欠勤率も下がるでしょう。
会社の業績が上がる
仕事の生産性の向上による品質の高い仕事、離職率の低下や欠勤の減少による安定的な成果を発揮することで、会社にも大きな利益をもたらします。経済産業省主催の「平成30年度産業経済研究委託事業(企業の戦略的人事機能の強化に対する調査)」(※1)によると、従業員エンゲージメントスコアが高い上位25%の企業では、生産性、売上、利益率と業績を表すいずれの指標も高くなっているという事例があります。
※1 出典:【経済産業省】平成30年度産業経済研究委託事業(企業の戦略的人事機能の強化に対する調査)
顧客満足度が上がる
従業員エンゲージメントの高い社員が多くいる企業は、顧客に対して品質の高い仕事や商品、サービスを提供することにもつながるため、顧客満足度の向上も期待できます。同じく前述の調査によると、従業員エンゲージメントスコアの高い上位25%の企業では、顧客満足度も高いという結果が出ています。
従業員エンゲージメントを高めるべき企業の特徴
従業員が仕事にやりがいを感じていない
仕事に対するネガティブな発言が多い、無気力な状態で業務にあたるなど、仕事にやりがいを感じていない社員が多くみられる企業は従業員エンゲージメントが低い状態です。仕事へのやりがいが分からずモチベーションの低い状態で働いているため、職場環境の悪化や離職率の上昇、企業の進む方向を理解していないことからの品質の低下などを招く恐れがあります。
離職率が高い
給与や立地条件、福利厚生など働く上での好条件が整っていても離職率が高い企業は、従業員エンゲージメントが低い状態にあります。優秀な従業員が、やりがいを感じられる仕事があったり、ビジョンや考え方に共感を持てるようなほかの企業へ移ってしまうのが理由です。
従業員同士のコミュニケーション不足
社員間でコミュニケーションが十分に取れていない職場は、休暇が取りにくい、無駄な作業が発生しやすく残業が多いなどの理由で、働きにくいと感じるようになります。また、コミュニケーション不足はトラブル発生時の問題解決に時間がかかる、丁寧な対応ができないなど、顧客満足度を下げる要因にもなるでしょう。顧客満足度が下がることで、企業の売上や信頼も落ち、経営にも悪影響を与えてしまいます。
時間報酬制度を採用している
時間報酬制度とは、労働時間の長さによって賃金が決められる制度です。2022年現在、日本企業の多くで導入されています。時間労働制度のもとでは長く働けば働くほど給料が高くなります。従業員は仕事の効率化や業務改善など仕事を早く終わらせて多くの成果を上げるための工夫をせず、時間をかけてゆっくり仕事を進めるようになってしまうケースが多くあります。本来仕事が早く、多くの成果が出せる優秀な社員も能力を存分に発揮できず、意欲やモチベーションが低下してしまい、従業員エンゲージメントは下がり続けることになるでしょう。
過剰経営の傾向にある
計画、分析、法令遵守の3つは経営において重要な要素ですが、それぞれを忠実、過剰に行うことによって起きる弊害が「オーバープランニング」「オーバーアナリシス」「オーバーコンプライアンス」として今日問題となっています。
過剰な計画、分析、法令遵守は規制を増やし、社員の自由な挑戦や知識創造が阻害されるため、新しい付加価値が創造できなくなります。リスクマネジメントは重要ですが、過剰に行うことで社員は挑戦をやめ、従業員エンゲージメントが低下してしまうでしょう。
組織が複雑化している
組織が大きくなると組織形態が複雑化するため、縦割りの従業員関係が構築されます。手続きやルールの増加により調整にも多くの時間がかかりやすくなるでしょう。上司から部下への業務上必要なコミュニケーションも一方的であることからストレスを与えやすく、職場の風通しが悪くなるため従業員エンゲージメントも低くなります。
仕事が細分化されている
組織の複雑化によって仕事が細分化されると、他部署の業務内容が把握しづらくなります。自分の企業内での立ち位置や、仕事の方向性や目的なども見えづらくなり、意欲ややりがいとともに従業員エンゲージメントが低くなるでしょう。
職能型人事制度を採用している
職能型人事制度とは、年功序列や終身雇用を前提とした日本企業のスタンダードな人事制度です。仕事(職務)の能力ではなく人材を評価し、人事異動や転勤などにも対応できる汎用的な能力が求められます。
職能型人事制度は仕事に対する専門性がないのがデメリットです。従業員は注力すべき仕事や自分の役割が分からなくなり、仕事への意欲やプロ意識を持ちにくくなるため従業員エンゲージメントも低くなる傾向にあります。
従業員エンゲージメントの「働きやすさ」を高めるための施策
ワーク・ライフ・バランスの推進
ワーク・ライフ・バランスの推進により多様な働き方が認められる職場は、従業員の働きやすさにつながります。テレワークや短時間勤務などを導入すれば、ライフスタイルに合わせた働き方が選択できます。福利厚生制度の充実も有効でしょう。また、長時間に及ぶ残業やスキルに見合わない膨大な業務など、従業員に悪影響のある要素の見直しに取り組むことも大切です。
上司と部下のコミュニケーションの機会を増やす
上司と部下のコミュニケーションの機会が多ければ、働きやすい職場づくりにつながります。たとえば上司と部下のコミュニケーションが業務の話のみ、話す機会は決められた面談のみ、という場合は業績悪化や欠員が出たときなどの問題発生時、原因の把握や問題解決が難しくなります。上司と部下がふだんからいつでも相談しあえる体制を整えておくことで、問題発生時のスムーズな解決や、上司と部下がともにキャリアを積める土壌の形成など、働きやすさのほかにもさまざまなメリットが得られます。
意識的に上司と部下のコミュニケーションの機会を増やすことがおすすめです。以下のような取り組みを活用してみましょう。
- ・1on1ミーティングを高い頻度で実施する
- ・上司と部下の距離を縮めるためのレイアウトに変更する
- ・フリーアドレスを導入する
従業員同士の横のつながりを強化
上司と部下といった縦のつながりだけでなく、従業員同士の横のつながりを強化することで居心地の良い職場づくりが実現します。以下のような、従業員同士の親睦が深められる機会を設けてみましょう。
- ・イベントを開催する
- ・クラブ活動を活発化する
- ・同じ職種・同じ趣味などで有志で集まれるオンライン懇親会グループを作る
従業員エンゲージメントの「やりがい」を高めるための施策
タレントマネジメントによる適切な人員配置
社員それぞれによって、やる気の元となる内発的な動機は異なります。組織全体で一気に従業員エンゲージメントを上げることが難しい場合、社員それぞれの内発的な動機に合わせて、やりがいを高めるための施策を展開していくとよいでしょう。
適切な人員配置を行うのはやりがいを上げるうえで有効です。そのためには、社員の持つ個々の能力やスキルを十分に発揮するためのタレントマネジメントの施策が有効となります。以下の手順で施策を行いましょう。
- ・ひとりひとりに合った提案を行う
- ・必要に応じて職場環境や業務内容を変化させる
- ・社員の企業での役割や仕事の意義などを見いだせる人員配置を行う
新しい人事評価制度の構築
社員の努力による成果が正当に評価されることで、仕事への大きなやりがいにもつながります。また、長く働ける職場と感じて愛着がわき、従業員エンゲージメントの向上も期待できるでしょう。公平かつ公正な評価や報酬が得られる新しい人事評価制度を設けるのも重要です。たとえば目標管理制度である「MBO」や、上司のほかにも同僚、部下など複数の立場からの評価を受ける「360度評価」などを取り入れる方法が有効です。
多くの適正な評価の機会を持つ
発揮した成果を評価されるだけでなく、公表することで称賛される表彰制度などの機会を設けることで、異なるモチベーションを持つ社員の従業員エンゲージメントを高められます。たとえば役職名や称賛などは、ステータスを重視する社員にとって重要な要素です。結果がはっきりと公表されることで競争性の高い社員が働きやすい環境となります。自分の行いが他の従業員にどれだけの影響を与えているかが可視化できるため、利他性を重視する社員にも有効です。
営業成績などの利益に直結する成果だけでなく、企業文化を体現したなど多角的なポイントで評価をすることで、いろいろな切り口から社員を称賛できるようになるでしょう。
研修やOJTなどの人材育成
社員が成長を感じられる職場は、大きなやりがいや仕事への意欲にもつながります。社員が自発的にキャリアを築けるように、積極的にキャリア設計やスキルを磨ける環境や制度を整えましょう。研修やOJT、セミナーなどの人材育成の機会を多く設けることがおすすめです。社員自らがスキルや能力を向上させることで、離職率の低下や会社にとっての優秀な人材の創出にもつなげられます。
従業員エンゲージメントの「ビジョンを共有」するための施策
リーダーシップのある人材の育成
リーダーシップのある人材の育成は従業員エンゲージメントの向上につながります。リーダーシップのある人材は、企業にとってのロールモデルを示すことにもなるためです。リーダーシップを発揮したことによる成果に対して正当に評価を行えば、やる気や意欲にもつながるため、多角的な従業員エンゲージメント向上につなげられるでしょう。
積極的な経営目標の共有・開示
社内告知、企業研修、面談などで経営理念、企業の目標やビジョンを明確にする機会を多く設けましょう。企業の理念やビジョンと社員の持つ認識とのすり合わせを行うことで、「企業の目標やビジョンが従業員の自己実現にもつながる」という、共感や理解が得られます。社員のモチベーション向上も期待できます。
自社の魅力に気づかせる
自社が社会からの評価や信頼、認知度が高いことが社員に伝われば「自分は誇りをもって働ける会社の一員である」との自覚につながり、会社への愛着や貢献度の向上につながります。自社の事業や業務が大きな社会的意義を持っている、社会から注目されているなどの要素を社内外に告知することにより、自社の魅力に気づかせる機会を設けましょう。
会社のPR担当などが社員を取材する機会を設ける、またはPR担当に任命して自社のPR活動をさせるのも効果的です。自社の魅力に気づけない社員へ情報を発信できるほかにも、取材やPR活動を行う本人の会社理解にもつなげられます。
従業員エンゲージメントの向上のための施策はPDCAを回すこと
エンゲージメントを高めるための施策を取り入れても、文化や状況、抱える問題は企業によって異なります。施策によってすぐに状況が改善するのではなく、逆に会社独自の深刻化している課題が浮き彫りになることもあります。
従業員エンゲージメントを高めるための施策は一度で終わらせず、定期的に従業員のエンゲージメントレベルをエンゲージメント・サーベイなどでチェックし、人事上の課題を明確化しましょう。課題への施策を行い効果をチェックする、といったPDCAサイクルを回すのが重要です。自社の課題に合った施策を把握することで、従業員エンゲージメントの向上にも有効となります。
従業員エンゲージメントは企業の価値を高める要素
従業員エンゲージメントを構成する3つの要素から見た、従業員エンゲージメントを高めるための施策を紹介しました。従業員エンゲージメントは社員のやる気だけでなく、企業としての組織力や利益、顧客満足度をも左右する重要な指標です。
企業の価値向上に向けて、従業員エンゲージメントを高めるための施策をぜひ取り入れてみましょう。
関連記事
-
従業員エンゲージメントの調査とは? 実施の方法や注意点を紹介
健康経営
2022.08.31
-
従業員エンゲージメントとは? 基礎知識と向上への取り組み事例紹介
ウェルビーイング
2021.12.27