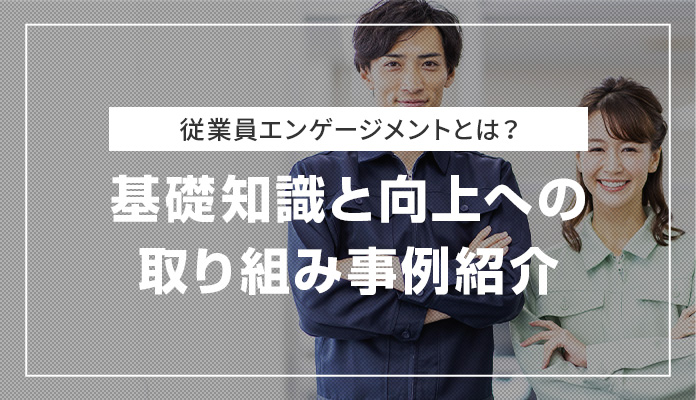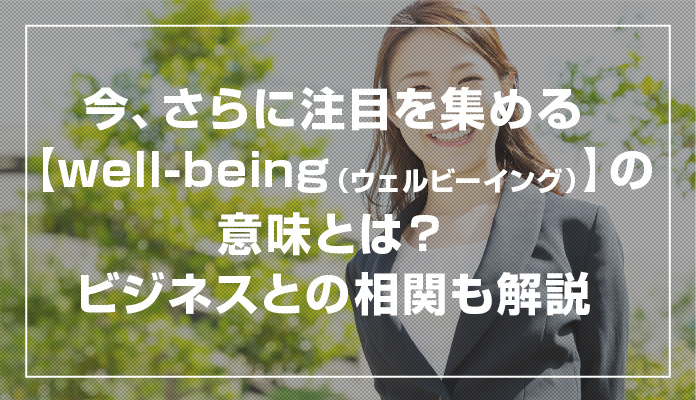ウェルビーイング
2022.06.03
会社が重視すべきエンゲージメントとは? 従業員エンゲージメントの必要性や要因・向上させる方法を解説
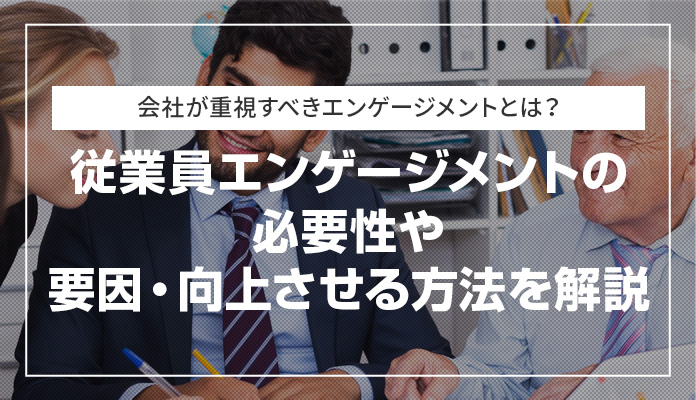
会社が活動するうえでエンゲージメントは無視できないものです。エンゲージメントという言葉にはさまざまな使い方があり、会社では人事領域における愛社精神に近い概念としての従業員エンゲージメントを指すことが多いといえるでしょう。当記事では、主に従業員エンゲージメントについて必要性や向上策などを解説します。
会社にとって重要な2つのエンゲージメント
従業員エンゲージメント
会社・企業の経営にかかわりの深い言葉であるエンゲージメントには、重要な2つの意味があります。主に使われているのが、人事領域において従業員が会社に対して持っている愛社精神とも呼べる意識や気持ちを指す「従業員エンゲージメント」です。記事中では基本的に従業員エンゲージメントの内容を扱っています。
従業員エンゲージメントは会社に対する社員、従業員の内心における結びつきの強さを示しており、近年になって多くの会社で注目されているワードです。
従業員エンゲージメントは会社の理念やビジョンへの共感や経営への信頼、自発的に貢献したいという意欲を重要な構成要素としています。ポイントはこの自発的な貢献意欲です。従業員エンゲージメントが高くなければ生まれないモノだと考えられています。注意したいのは、従業員エンゲージメントが高い従業員が必ずしも高い成果を上げているとは限らない点です。しかし、会社の発展には従業員エンゲージメントの高い人材が欠かせません。
一方、会社組織への貢献ではなく仕事に対する意欲は従業員エンゲージメントが低くても生まれ得るモノです。昇進したいとか、歩合給を多く稼ぎたいといった動機があればバリバリ働くこともあるでしょう。
しかし、そういった動機では現在所属している会社に拘る必要がありません。従業員エンゲージメントが低ければ、会社に対する貢献には関心が薄くなります。他社からポストを用意されたり、高給を提示されたりすれば転職する可能性が高いでしょう。
カスタマーエンゲージメント
もうひとつの重要なエンゲージメントがカスタマーエンゲージメントです。営業領域、マーケティング領域におけるエンゲージメントで、顧客を対象としています。顧客にとってメリットが大きく、会社にとっても利益となる良好な関係性を示す言葉です。従業員エンゲージメントが愛社精神と呼べるのに対し、カスタマーエンゲージメントはブランディングを通じた会社や商品・サービスへの愛着やファン意識と呼べます。
カスタマーエンゲージメントが向上することでリピーターが増加し、会社の業績アップが見込めるでしょう。
従業員エンゲージメントが重視される理由
従業員が会社に求めるモノは時代とともに変化している
従業員エンゲージメントが重視されるようになった理由として大きいのが、多様性と働き方改革の時代となり、従業員が会社に求めるモノが給料と安定だけではなくなっている点です。働く会社を選ぶ際に、給料の額を気にするのは当然ですが、生活できるだけの金額が確保できていれば、プラスアルファの部分に注目が集まります。
プラスアルファが何かは人によって異なり、休日や休暇の多さであったり、フレックスに代表される勤務時間帯の柔軟さであったり、福利厚生の内容であったりとさまざまです。2020年からの新型コロナウイルス感染症拡大を契機に一気に拡大したリモートワークへの対応状況も会社選択の要素となっています。
終身雇用が過去のモノとなったこともあり、人材の流動化が進んでいることに加え、忘れてはならないのが少子化社会に入っているという事実です。人口の減少による労働力の供給不足が懸念されており、多様化したニーズに応えることができなければ、人材を集めることが難しい時代だといえるでしょう。新陳代謝が欠かせない会社にとって、人材の採用が困難な状況は望ましいものではありません。
しかし、従業員エンゲージメントが高い会社なら人材採用で優位に立てる可能性があります。多様化しているニーズへの対応は、従業員エンゲージメント向上の必要条件でもあるためです。
長期的な人材定着との関連が深い
従業員エンゲージメントが低い会社であっても、人材採用に成功することはあるでしょう。しかし、ただ人材が集まれば良いというわけではありません。会社が競争力を発揮し、長期にわたって安定した成長を続けるためには、経験とノウハウを持ち、意欲的な人材が揃っていることが前提です。
したがって、人が集まりやすい会社を作ることと集めた人材を戦力化すること、離職を防ぐことが求められます。
そこで重要になるのが従業員エンゲージメントの向上です。仮に優秀な人材を採用したとしても、個人のニーズにマッチしておらず、すぐに転職されてしまっては短期的な成果しか期待できません。また、長期の展望を描けなくなります。
会社への思い入れが弱ければ、個人が重視するのは仕事内容そのものや給与などの報酬面といった、他社と比較可能な条件です。その結果、離職率が悪化しやすくなります。長期的な人材定着には、会社に対する自発的な貢献意欲を要素とする従業員エンゲージメントの向上が重要です。
合理性と効率化が働きやすい職場をつくる
従業員エンゲージメント重視の企業活動を行うことは、会社への共感や理解、信頼を得る活動を行うことでもあります。そのひとつが、無駄や理不尽を排し合理性と効率化によって働きやすい職場をつくることです。
ところで、従業員エンゲージメントが高くて働きやすい職場といえば満足度の高い職場ともいえますが、「従業員満足度が高い職場」とはイコールではありません。
従業員満足度が高い職場とは、その時点において仕事や人間関係、給与その他の各種条件に満足している割合が高い職場です。必ずしも各自の心の中に会社への理解や共感、信頼があるとはいえない面があり、将来に向けた自発的な貢献意欲とは無関係である点が、従業員エンゲージメントが高い職場との大きな違いとなっています。
カスタマーエンゲージメントに影響する
従業員エンゲージメントの高い職場で生み出される商品やサービスは、一般に高品質であるといえます。また、従業員エンゲージメントが高いスタッフであれば、生産性が高いだけでなく、顧客対応業務においても正確で迅速かつ丁寧な行動を心掛けているでしょう。その結果として、カスタマーエンゲージメントにも好ましい影響をもたらします。
相乗効果で業績アップと繫栄につながる
従業員エンゲージメント向上のメリットには、離職率の改善や新規採用に対する好影響への期待感、業績アップと会社の発展などがあります。カスタマーエンゲージメントも含めてそれぞれが密接な関連性をもっており、連鎖的な効果も見込めるでしょう。つまり、エンゲージメント重視の会社経営を行うことで、それぞれの相乗効果によって会社の業績アップと繁栄につながる期待が大きくなります。
エンゲージメントを左右する2つの要因
エンゲージメントの高低を左右する要因はさまざまありますが、動機付け要因と衛生要因の2種類に大別できます。動機付け要因とは、その存在によって満足を覚え、その存在がなくてもすぐさま不満になるわけではない要因のことです。衛生要因は、その存在がなければ不満を感じるものの、あるからといって必ずしも満足するわけではない要因を指します。
ちなみに、動機付け要因と衛生要因という言葉はアメリカ人のフレデリック・ハーズバーグによる「二要因理論」で提唱されたものです。動機付け要因として「達成する」「承認される」「仕事自体」「責任と権限の拡大」「昇進と成長」などが、衛生要因には「会社の方針」「給与」「人間関係」「作業条件」などがあるとされています。
現在の日本では、それぞれの実情に合わせた動機付け要因と衛生要因を考慮しており、以下で解説する動機付け要因と衛生要因も、現状を反映してピックアップしたものです。
得られることで満足度がアップする動機付け要因
企業文化・風土
会社にはそれぞれの企業文化や風土と呼ばれる性質があります。いうなれば、その会社らしさです。自社らしさは動機付け要因になり得る要素です。
企業文化は価値観や仕事上のルールなど、会社として意図的に作られたものであり、経営理念やビジョンに通じます。個人の能力を重視するかチームプレーを重視するかといった仕事のやり方の違いは企業文化の違いによるものです。
企業風土は自然発生的に生まれた習慣や暗黙の了解事項のようなもので、土地柄を反映しているケースがあります。一般的には明文化されたものではありませんが、会社の理念やビジョン、規則に影響を受けて形成されることもあるようです。
もうひとつ、社風と呼ばれる概念があります。企業文化や企業風土とは異なり、その会社で働く人々が感じる「明るい職場」「緊張感が漂っている」といった雰囲気・特徴といえば良いでしょうか。企業文化や風土の影響がないとはいえませんし、経営理念やビジョンが直接的に社内の雰囲気を左右するケースもあるでしょう。
経営理念やビジョンへの共感は従業員エンゲージメントを向上させる要素です。その経営理念やビジョンと深いかかわりがある自社らしさは動機付け要因のひとつだといえます。
認知度
良い意味で会社の社会的認知度が高まることも、大きな動機付け要因のひとつです。会社の事業成果の広報や、SNSでの発信などを含む代表者の知名度アップが会社への注目度を高めることで満足感が大きくなります。
達成と承認
適切な数的目標の達成や、事業の成功に対する貢献度の承認がもたらす動機付け要因としての影響は小さくありません。容易ではないものの不可能ではないことが数的にハッキリと示されている目標は、達成に向けた意欲を高めるとともに達成時の満足感をより強くするものです。また、貢献度の承認はやりがいを生み出す要因となります。貢献する相手は社の内外を問いません。
仕事への関心
仕事への関心の深さは、自発的な就労意欲に直結する動機付け要因です。関心が深ければ深いほど、誰かにいわれるまでもなく積極的に仕事に取り組み、満足感を得ます。
ポジションと成長
仕事の結果に対する昇進や責任と権限の拡大といったポジションアップ、人材としての成長は、大きなやりがいを感じることができる要因です。また、キャリアアップのプランが明確になっていれば、自分なりに目標を設定して突き進むこともできるため、より満足感を高められます。
不足すると不満に直結しかねない衛生要因
経営方針
会社が活動する以上、経営方針が明確になっているのが当たり前といえます。当たり前の経営方針が曖昧だったとしたら、自分たちがどこを向いて何をすれば良いのか迷ってしまいかねません。この状態では不安を抱えたままで仕事をしなければならないため、不満を招いてしまいます。
経営方針は数ある衛生要因の中でも重要な要因です。また、仕事をした結果が求めていた結果とは異なるとなってしまえば、より不満が大きくなることから、経営方針はしっかりと示す必要があります。
上司や同僚との人間関係
誰しも会社でギクシャクした人間関係は望んでいません。仕事を完遂するためにも、上司や同僚との人間関係はよくて当然です。悪ければ不満にしかならないため、会社側としては常に社内の人間関係に気を配っておき、悪化を未然に防ぐ必要があります。
とはいえ、会社の規模が大きくなれば経営陣が末端まで見ることは事実上不可能です。そこで、専門部署による相談体制の導入が有効となります。
専門部署を設けるほどの規模ではない場合や、そこまでの余裕がない場合には上司による相談も一手です。ただし、人間関係の直接の相手方である上司にはしっかりとしたマネジメント研修を実施するなどの配慮が必要でしょう。また、指揮命令系統にない上役による相談も考えられます。
職場環境
職場環境が悪ければ仕事がしにくくなるだけです。具体的には、職場のスペースが狭くて圧迫感がある、照明が暗い、建物が古くて汚いし傷んでいる、仕事に必要な設備が整っていないなどさまざまなケースがあります。不具合は直ちに改善されるべきです。ただし、衛生要因であるため改善してもあるべき姿に戻るだけで満足するわけではありません。
例外的に、仕事に必要なレベルを超えて快適な職場環境を実現した場合は満足感が生まれる可能性があります。しかし、慣れてしまえばその環境が当たり前になってしまい、モチベーションアップにはつながりにくいでしょう。
報酬
仕事には対価となる報酬があって当然です。ここでいう報酬は給与や賞与、手当などの金銭的報酬のことであり、なければ不満どころの話ではないでしょう。したがって、どの程度の報酬なら不満を解消できるかが問題となります。このとき、妥当な金額よりも多ければ満足を得られるのではないかと考えるかもしれません。たしかに、一時的には満足感が生まれる可能性があります。
しかし、金銭的報酬はより多くを望むものであり、欲望に上限があるわけではないため、一過性の満足しか得られず、すぐに低下しかねません。報酬はあくまでも衛生要因の一種です。
福利厚生
福利厚生には法令で義務付けられている法定福利厚生とは別に、会社独自の法定外福利厚生があり、近年では福利厚生の充実度や内容を比較して会社を選ぶ人が増えているといわれています。とはいえ、福利厚生は報酬と同様に絶対的な満足を得られるものではないと考えるべきでしょう。最低限このくらいは必要だと判断されるものとして考えておきます。
エンゲージメント指標と測定
エンゲージメントの3大指標
従業員エンゲージメントの向上を考えるなら、現状を知る必要があります。従業員エンゲージメントを知るための指標は主に3つです。
・エンゲージメント総合指標
従業員エンゲージメント全体のレベルを知るための指標です。満足感や継続勤務の意向、eNPSと呼ばれる他者に対する自社の推奨度など、各自が会社に対して抱いている気持ちを示します。
・ワークエンゲージメント指標
ワーク、つまり仕事にスポットを当てたエンゲージメントの指標です。熱意の程度や没頭具合、やりがいの有無といった部分について示します。
・エンゲージメントドライバー指標
仕事の成果への関りや貢献度に関する自己判断の指標です。人間関係の状況や仕事の難易度、自己の資質が仕事に与える影響などを示します。
エンゲージメントサーベイとパルスサーベイ
従業員エンゲージメントの測定に用いられる調査方法には、主としてエンゲージメントサーベイとパルスサーベイがあります。
・エンゲージメントサーベイ
従業員エンゲージメントをしっかりと調査するためのサーベイ(調査・測定)です。数十問に及ぶ比較的長い時間をかけて行うサーベイで、頻繁には行いません。一般的には半年や1年といった長い間隔で実施されています。仕事とは別に時間を設けて行われることも多く、質問への回答に記述式を含めるケースもあるなど、本格的なサーベイです。
・パルスサーベイ
ンゲージメントサーベイとは異なり、週や月に1回程度の頻度で焦点を絞った調査を行います。質問数は多くて10問程度で、少なければ1~2問のケースもあり、短時間で手軽に実施できるサーベイです。
エンゲージメントスコアと調査項目
従業員エンゲージメントの評価はサーベイでの回答をスコア化することで行います。個人で見た場合、スコアが高いほうが従業員エンゲージメントの高い人材です。また、全員のスコアを集計した結果が高ければ、その会社は従業員エンゲージメントの高い会社だといえます。
主な調査項目(質問)例は以下のとおりです。
- ・エンゲージメント総合指標に関する質問…「この会社を他の人に推奨したいですか?」「親切な上司や同僚はいますか?」「これからもこの会社で頑張りたいですか?」
- ・ワークエンゲージメント指標に関する質問…「仕事に適した環境整備ができていると感じますか?」「仕事に熱中していると感じますか?」
- ・エンゲージメントドライバー指標に関する質問…「理念やビジョンを理解していますか?」「適正な評価を受けていると感じますか?」
会社が取り組むべきエンゲージメント向上施策
動機付け要因に対応する向上策
動機付け要因を強化することでエンゲージメント向上につなげる施策や制度の主な例を以下に示します。
・ビジョンの浸透
経営理念やビジョンを浸透させるための説明やリーフレットなどの資料の配布といった工夫を行うことで共感や信頼を覚え、企業文化や風土、社風による自社らしさを強く意識し、従業員エンゲージメントの向上につながります。
・社会貢献
地域社会をはじめとする社外に目を向け、小さなことであっても貢献を行う機会を設けて評価されれば、その一員である個々の従業員も貢献による承認欲求が満たされ、高いエンゲージメントを示すようになります。
・適材適所の人事
能力や適性に応じた適材適所の人事を行うことで、達成感や承認欲求が満たされます。また、ポジションや成長への意欲にも応えることができ、従業員エンゲージメントの向上につながるでしょう。
・キャリアプランの明示
キャリアプランを明示して、そのとおりに運用することが成長に対する欲求や成果に応じたポジションを求める気持ちを満足させ、従業員エンゲージメントを向上させます。
衛生要因に対応する不満防止策
衛生要因の不備による不満を防止してトータルでエンゲージメント向上に資する施策や制度の主な例を以下に示します。
・フレックスタイム
フレックスタイムやリモートワークなどワークライフバランスを考慮した勤務形態の実施は、多様化する働き方への対応策であると同時に、労働条件への不満解消に役立ちます。
・ボーナス
成果に見合ったボーナスやインセンティブを支給することで、金銭的報酬に対する不満の解消が可能です。
・1on1
1on1による上司と部下の面談体制は、職場における人間関係の不満などを解消する効果が期待できるだけでなく、そのために会社が動いていることを感じてもらえる効果も期待できます。
・社宅
法定外福利厚生の一環として社宅を用意することで、転勤者の不満解消などが実現可能です。その他、福利厚生の充実は従業員エンゲージメントの向上に役立ちます。
カスタマーエンゲージメントの向上策
契約先である既存顧客との良好な関係を示すカスタマーエンゲージメントの向上を図るにあたって有力とされる施策を紹介します。
・各種システムの活用
顧客ごとにきめの細かい対応を行うためにMA(マーケティングオートメーション)やCRM(顧客関係管理)、さらにはSFA(営業支援システム)を活用します。手作業では実現できないレベルの迅速で的確な対応ができ、カスタマーエンゲージメントの向上が可能です。
・コミュニケーション手段の工夫
顧客によって使用するコミュニケーション手段はさまざまです。それぞれに合わせてSNSやチャット、メールといったツールを使い分けることで、より親密な関係を構築できます。特別なオファーで、ブランディングも可能です。
・従業員エンゲージメントの向上
前述したように質の高い従業員による高品質な商品・サービスの提供と顧客対応が顧客満足度の向上をもたらし、カスタマーエンゲージメント上昇が期待できます。
効果を検証しながら改善する
エンゲージメントを向上させる施策は打って終わりではなく、どの程度の効果が出ているかを確認しつつ、より良いものにする必要があります。各種の事例を見るとPDCAサイクルの活用が有効だといえるでしょう。注意したいのは、必ずしもサーベイを行って施策を打つわけではない点です。サーベイは現状の把握と評価で課題を明確にするために行うものであり、課題が見えている場合はスピーディに施策を打つといった考え方もあります。
会社の繁栄はエンゲージメントの向上にかかっている
従業員エンゲージメントに大きな注目が集まっている理由を簡単に表すと「会社の繫栄がかかっているから」となります。人材確保が難しくなっている中で、長期にわたって業績を上げ続けるためには、優秀な人材を失わないことが重要です。そのために必要となるのが、まさに従業員エンゲージメントの向上だといえます。
カスタマーエンゲージメントの向上も組み合わせて戦略的に実施すれば、会社の内外から繁栄を図れるでしょう。
関連記事
-
従業員エンゲージメントとは? 基礎知識と向上への取り組み事例紹介
ウェルビーイング
2021.12.27
-
今、さらに注目を集める【well-being(ウェルビーイング)】の意味とは?ビジネスとの相関も解説
ウェルビーイング
2021.05.31