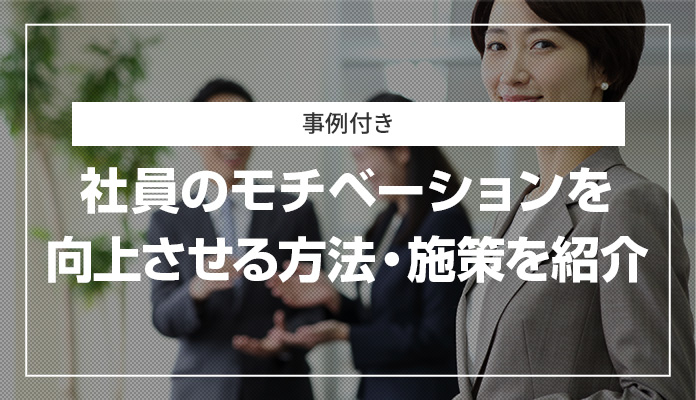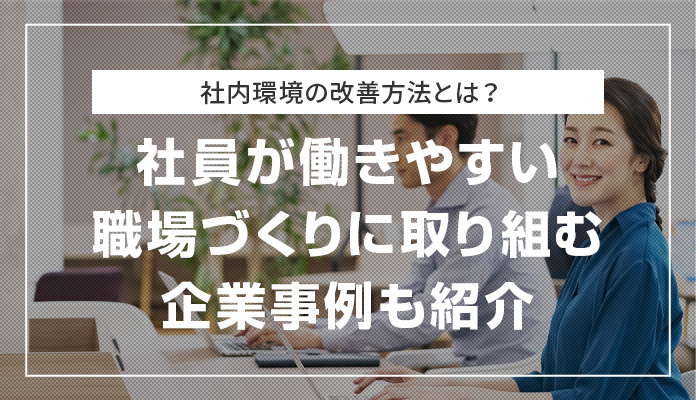職場改善
2022.11.08
社内コミュニケーションを活性化するアイデア・施策の解説と成功事例6選を紹介!
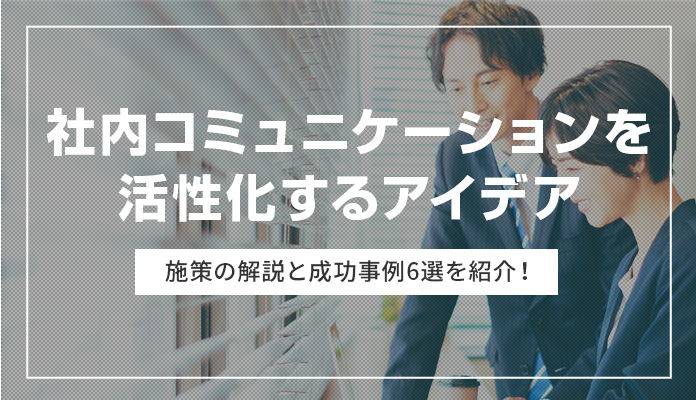
社内コミュニケーションを活性化する事例はさまざまです。たとえば、オフィスのレイアウトを変更して接しやすくしたり、社員が集まれるオープンスペースを設置したりといった事例があります。また、テレワーク時代のオンライン事例も豊富です。当記事では、社内コミュニケーションを活性化する事例が増える要因の解説と個別事例6選を紹介します。
社内コミュニケーション活性化の取り組み事例が増える要因
組織の規模増大
少人数でお互いの顔を見ながら仕事をしている企業・組織では、社内コミュニケーションが活性化しやすいといえます。しかし、規模が拡大するにつれてコミュニケーション不足が起こりやすくなるといえるでしょう。
人数が増えることでフロアが分散したり、パーテーションで区切ったり、さらには建物が別になったりすることで、近くにいないメンバーと顔を合わせる機会が減ってしまうことは避けられません。仕事で直接的な接点をもたないメンバー間では、コミュニケーションどころか顔と名前が一致しないといったことも起こり得ます。
会社内の全員とコミュニケーションをとる必要はないかもしれませんが、チームや関連部署との必要なコミュニケーションまで十分にとれない環境は問題です。コミュニケーション不足から生産性やエンゲージメントの低下につながれば、離職率の上昇・人材流出も懸念されます。そのため、社内コミュニケーションの向上・活性化の必要性を感じている企業・経営者は多いようで、取り組み事例が増える要因となっています。
専門分化した職場
ゼネラリストよりスペシャリストといったように、仕事の内容が専門分化したり、部署が細かく分かれたりすることにより、コミュニケーションがとりにくくなっているケースが少なくないようです。部署が違えば、先に述べたようなフロアや建物が異なる状況になるなど、物理的な距離が生じる可能性があります。
また、それぞれが自分の専門的な担当業務を持つことによって、自分しか知らない属人的な職務遂行になってしまうことが、社員同士のコミュニケーション不足を加速させる要因の一つです。やっている仕事の中身が違うため、他のメンバーと協議したりサポートしたりする場面が少なくなっても不思議ではありません。仕事上の必要性から最低限の話をすることはあっても、それ以上のコミュニケーションは難しくなることが考えられます。
例外はあるとしても、専門分化しているからこそ、会社としてその仕事を完成させ、目標を実現するには他部署との円滑なコミュニケーションと情報共有が重要となるケースは少なくない筈です。しかし、逆にコミュニケーションがとりにくくなっている状況や、視野が狭くなってしまう問題点があります。多くの社内コミュニケーション活性化の取り組み事例が、そういった問題や課題の解消に役立っているといえるでしょう。
テレワークの推進
ワークライフバランスの重視や働き方改革の名のもとに進められている出勤形態の多様化や在宅勤務・テレワークにより、社員やメンバー間の物理的な接触機会が従来とは比較にならないほど減少しています。しかも、新型コロナウイルス感染症への対策としてテレワークが一気に拡大したことで、社内コミュニケーションへの悪影響が無視できないレベルになっていると感じている企業では、社内コミュニケーション活性化への取り組みが急務です。
スピードが重要な時代にコミュニケーション不足は避けたい
タイムイズマネーは古くからある言葉ですが、現代の企業活動は中身とともにスピードが重視されています。通信インフラではモバイルが4Gから5Gへと進化する過程にあり、高速大容量のデータ処理が当たり前になりつつある中で、報告や相談、質問といったコミュニケーションの遅延や不足は致命的なトラブルにつながりかねません。これも社内コミュニケーション活性化の取り組み事例が増えている要因だといえるでしょう。
オフィスで話しやすくする事例で使われる施策
オフィスレイアウトの変更
社内コミュニケーション活性化の取り組みには、オフィスでの会話をしやすくする施策の事例が数多くあります。オフィスレイアウトの変更は比較的取り組みやすい施策だといえるでしょう。
長く日本では、横並びで向かい合わせとなっている部下の机がいくつかあり、その端を押さえるように部下の机に向かって上司の机が配置されているのが一般的な基本レイアウトとなっています。この場合は、机の上に置いている資料や備品などによって邪魔されない限り、近くの仲間とコミュニケーションをとることは難しくありませんが、机の台数や設置位置の関係もあり、活発なコミュニケーションに適していないケースがあるでしょう。
しかし近年では、外資系企業に多く見られるといわれる、それぞれの机が異なる方向を向いており、机と机の境界にパーテーションがあるレイアウトが増えてきました。この手のレイアウトは、どちらかといえばコミュニケーションの促進ではなく抑制につながりそうです。
オフィスレイアウトの変更で必要に応じて机の向きや配置を変え、隣の部署とのパーテーションだけでなく、隣の席との間仕切りも取り払うことで、顔が見えやすくなります。長机を並べることで隣席との境界線を無くすレイアウトもアリです。
また、部署ごとに机を並べるのではなく、現時点における仕事での関係性が近いメンバーと机を並べるといったレイアウトもあります。オフィスレイアウトの変更は、場合によっては一時的に仕事を中断する可能性がある施策です。大掛かりなものとなると、オフィスを使えない日や社内での引っ越し作業もあるでしょう。しかし、根本的な社内コミュニケーションの活性化を図れるなら取り組んで損はない施策です。
さらに、そもそも自分の座席を決めないフリーアドレスも広がりを見せています。フリーアドレスの大きなメリットは、その日、その時間に効率のよい場所で仕事をできる点です。各種オフィスレイアウトの変更による社内コミュニケーション活性化への取り組み事例が知られている実施企業には、日本マイクロソフト株式会社やカルビー株式会社などがあります。
オープンスペースの設置
それぞれのオフィス、デスクはそのまま使用しながら、オフィスに新しいコミュニケーションのための区画を設ける事例が増えています。自然に人が集まるスペースを確保し、話しやすい環境を作るための什器美品などを設置するオープンスペースの設置です。オープンスペースを設置する場所は自社の実情を踏まえた配置となっており、部署間の移動で通る通路の途中であったり、エントランスからすぐの場所であったりします。
また、休憩を兼ねてリラックスした雰囲気でのコミュニケーションができるように、ソファや椅子に拘ったり、お茶やお菓子を備えている企業も珍しくないようです。さらには、社内報の撮影に使ったり、広いスペースを確保している場合はセミナーに使ったりもできます。
オープンスペースの活用は、株式会社博報堂プロダクツなど多くの事例が確認できます。オープンスペースとオフィスレイアウトの変更はどちらか一方でも効果がありますが、両方一緒に実施すれば大きな環境改善となり、より効果的でしょう。
オフラインミーティングの開催
オフィスレイアウトの変更やオープンスペースの設置は、コミュニケーションしやすい環境を作るものです。それに対し、日時を指定して集まるコミュニケーションの実践手段として、オフラインミーティングの開催があります。テレワークが進んでいる中では、普段はオフィスにいないメンバーも少なくないため、出社日にコミュニケーションの機会を作る意味もあります。
より強制的な対面でのコミュニケーションをとる手段として、ヤフー株式会社が先発として知られる1on1ミーティングも近年注目されている手法の一つです。1on1は部下のために行うミーティングで、上司と部下が1対1で定期的にコミュニケーションをとります。
人事交流
通常の人事異動とは別に、部署間のコミュニケーションを強化するための施策として、短期間の移籍や一定年限で複数部署での勤務を経験するといった人事交流が行われています。それぞれの部署の仕事を経験したり、メンバーとの人間関係づくりを行うことで、信頼関係を深めることが可能です。
その結果、相手先部署での仕事期間中だけでなく元の部署に戻ってからの各部署とのコミュニケーションにも役立ちます。このような人事制度上の施策は、クックパッド株式会社や株式会社ヤクルト本社などの事例にみられます。
オンラインその他でコミュニケーションを活性化する施策
バーチャルオフィス
テレワークが進んでいる現在では、オフィスでコミュニケーションをとろうとしても無理な場合があります。バーチャルオフィスの豊富な機能を使えば、メンバーの在席状況などオフィス全体の状況を素早く確認可能です。オンライン上の仮想空間で仕事をすることで、実際のオフィスにいるように、必要に応じて遅滞のないコミュニケーションが可能となるでしょう。バーチャルオフィスではエン・ジャパン株式会社などの導入事例があります。
オンラインミーティング
日時を決めて各自の居場所から参加できるオンラインミーティングは、コミュニケーションのハードルが下がる事例として注目できる施策の一つです。画面上で顔を見ながらの一般的なミーティングだけでなく、株式会社ブイキューブのオンラインランチ会のような派生形の施策を行う企業もあります。オンライン上で集まりさえすれば、使い方はそれぞれの発想次第でもあるため、さまざまな活用方法が考えられ、社内コミュニケーションの活性化に役立つでしょう。
金銭支援その他の施策
オフライン・オンラインを問わず、社員間のコミュニケーションを目的とした集まりや部活動などに対し支援を行う事例も多くなっています。実例としては、1回1人につき1,000円を実費補助する株式会社SmartHRのオンライン部活支援などがあります。また、アイデアの募集などに役立つ社内ブログや社内カフェなどさまざまな施策が生まれており、それぞれが各社の特徴を活かしたものです。
シナジーカフェ GMO Yours~GMOインターネットグループ株式会社
食事でコミュニケーション
GMOインターネットグループ株式会社(GMO Internet Group, Inc.)のパートナー向け「シナジーカフェ GMO Yours」は、仕事の合間の楽しい食事の時間を有意義なコミュニケーションの時間にもできるカフェであり、コミュニケーションスペースです。「シナジーカフェ GMO Yours」では、いつでも無料で食事ができます。世界一の人財による世界一のサービスの提供を掲げる同社が、パートナー間の情報交換や相互刺激によって新事業などの創出につながる場として設置しています。
24時間休みなく利用可能
グローバル展開をしているGMOインターネットグループには、時差のある海外や深夜に対応するパートナーが多数います。グループの多様な働き方に対応できるよう、365日24時間利用可能で、本格的な食事だけでなく軽食やドリンク利用も可能です。食事を無料で提供している企業は他にもありますが、何を食べても飲んでも24時間いつでも無料というのは、どの企業にでもできることではない特徴的な施策です。
ランチタイムミーティングのような使い方だけでなく、ちょっと一息入れたいときに、ドリンクを片手に隣のパートナーと語らうといった使い方もできます。また、社内コミュニケーション活性化のための定期的なイベントにも利用されるなど多目的な施設です。
社外にも貸し出し
同社では、自社での利用にとどまらず、自社とのシナジー効果が期待できる外部に対しても、無償でイベント用の貸し出しを行っています。そこから社内コミュニケーションの活性化につながるきっかけもありそうです。
社内留学制度~クックパッド株式会社
視野を広げ新たなチャレンジに向かう
クックパッド株式会社(Cookpad Inc.)には社内留学制度があります。人事異動をするわけではなく、所属部署はそのままで、最大2ヶ月他部署に留学して他部署の仕事を行うという内容です。この施策はキャリア形成に関わる施策であり、留学した社員個人の視野が広がるとともに新たなチャレンジへの意欲につながるなどの効果が期待できます。
すべてのエンジニアが対象
社内留学制度はクックパッドのエンジニアなら誰でも留学できる制度で、2019年4月にスタートしています。もちろん、社内コミュニケーションの活性化においても、エンジニア個人のみならず双方の部署にも役立つ、おすすめできる施策です。
両方の部署で働いたエンジニアがいることで、部署間のコミュニケーションが留学前よりも円滑になり得ることは間違いないでしょう。しかも仕事の中身や部署の事情を理解したうえでのコミュニケーションとなるため、うまく進めばそのメリットは大きなものとなりそうです。
留学して初めてわかることがある
他部署として外部から見ているのと、内部に入って見るのとでは見え方や理解度が違い、留学したからこそわかることや気づくことがあるものです。異動ではなく留学であることから、留学を終えた後の仕事に留学先での経験を活かせるといったメリットがあります。留学といっても同じ社内であるため、その後の交流が容易です。それも社内コミュニケーションを活性化させる要素になるでしょう。
イドバタtable~株式会社博報堂プロダクツ
事業本部間のコミュニケーション活性化
株式会社博報堂プロダクツ(HAKUHODO PRODUCT'S INC.)には、「イドバタtable」と呼ばれている社内コミュニケーション活性化のための施策があります。「イドバタtable」はオープンスペースの一種です。気軽に事業本部間のコミュニケーションをとれる場所を確保し、有効な連携をとる働き方により、新たな発想やモチベーションアップ、可能性の拡大を目指しています。
メインの導線に設置
「イドバタtable」をオフィスのメインとなる導線上に設置することで、誰もがスムーズに立ち寄れ、自然に雑談や情報交換が可能となっています。社内コミュニケーションを活性化させる場であり、大人数での利用はもちろん可能です。1人で仕事に利用すれば、フリーアドレス代わりにもなります。単独でも大人数でも利用可能な理由は、広いスペースと考え抜かれた配置、テーブルやカウンター、椅子やソファの充実です。
カウンターやソファで最新情報に触れる
「イドバタtable」では、リラックスできるソファやカウンター席に座り、備え付けの情報誌やオンラインで送られる最新情報に触れることができます。ゆったりとした気分でリフレッシュしながら過ごすことで、より良いアイディアを生み出すことも可能になるでしょう。また、そうした環境だからこそ、有効なコミュニケーションもとれそうです。
オンラインオフィスデー~株式会社ブイキューブ
原則テレワーク環境におけるコミュニケーション確保
株式会社ブイキューブ(V-cube, Inc.)では、テレワークが推奨されている社内のコミュニケーションを意識的に確保するため、オンラインオフィスデーを設定しています。同社では毎月21日をブイの日と定めており、その日がオンラインオフィスデー当日です。ちなみに、21をブイと読む語呂合わせは、ポケモンのプロジェクト・イーブイでも見られます。
自社のプラットフォームEventIn
オンラインオフィスデーには、普段顔を合わせる機会が少ない社員が、自社開発によるオンラインイベントのプラットフォームである「EventIn」を活用して集まります。チャットやビデオ通話、コンテンツの視聴も可能で、リアルなオフィスを感じながら会議室移動も楽にできるプラットフォームです。
終日開放とイベント
オンラインオフィスは1日中開放されており、4つに分かれたフロアでコミュニケーションをとるとともに、第1回ではイベントとしてパパママ会が行われ、社内コミュニケーションの活性化に役立っているようです。
オンラインランチ会~株式会社ウィルゲート
気軽にコミュニケーションをとること
コンテンツマーケティング事業などを手掛けている株式会社ウィルゲート(Willgate, Inc.)では、オンラインランチ会を導入しています。コロナ禍によるテレワーク推進で、ちょっとしたコミュニケーションの機会が減ったことへの対策として導入したものです。ランチ会の名称は「オンラインRoom0」で、実在する社内のフリースペースの名前からとっています。
Google Meetを活用
週1回開催されるオンラインランチ会では、プラットフォームにGoogle Meetを採用しています。大人数の従業員が一堂に会するわけではなく、事前に4~6名の単位で専用URLによって割り振られた部屋に入る仕組みです。当日参加も可能となっています。
少人数でタテ・ヨコ・ナナメに展開
部署や先輩後輩といった垣根を超えたコミュニケーションを活性化するために、ランチ会では、各回いくつか決められているテーマに沿ったトークが交わされている点が大きな特徴です。業務以外の話題で盛り上がれば、その後のビジネスシーンでも壁を感じることなくコミュニケーションができるでしょう。
社内ブログ~株式会社ユニクロ
本部と店舗間の情報共有
株式会社ユニクロ(UNIQLO CO., LTD)では、本部と店舗間の情報共有を目的としたブログ、社内情報ウェブの利用により、現場の声やアイデアが円滑に上がってくる仕組みを構築しています。同社のシステムでは、本社が書き込む質問に対し、店舗側が回答を書き込むといった形式です。具体的な質問があることで、回答しやすいといえるでしょう。
パソコンと携帯で運用
店舗側がコミュニケーション手段として使用している機器は2台あるパソコンですが、携帯電話が使用可能となっている部分もあります。ビジネスユースではあるものの、スマホ世代が増える今後はスマホの活用部分を増やすことで、さらなる利便性アップが期待できそうです。
ブログだから使いやすい
本部からの情報伝達や本部への意見具申は、電話でもメールでも何かとハードルが高いと感じることがあります。オフィスコンピュータの画面のようなシステムであれば、より考え込んでしまうかもしれません。しかし、同社はこのシステムに庶民的なツールであり、誰にでも使いやすいブログを採用しています。ブログはMovable Typeで、ニーズに合うようにカスタマイズしています。
社内コミュニケーションの活性化は先発事例を参考に!
社内コミュニケーションの活性化には多くの先発事例があります。自社の状況に照らしてすぐにできる事例や時間はかかるもののできそうな事例、できない事例やマッチしていないと感じる事例などいろいろある筈です。
社内コミュニケーションの活性化を進めるために、複数の事例を参考にしたうえで、自社にマッチする活性化施策を導入しましょう。
関連記事
-
【事例付き】社員のモチベーションを向上させる方法・施策を紹介
職場改善
2022.06.03
-
社内環境の改善方法とは? 社員が働きやすい職場づくりに取り組む企業事例も紹介
職場改善
2021.12.27