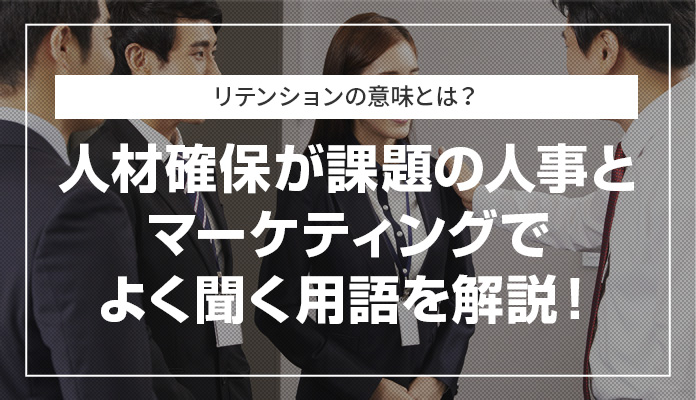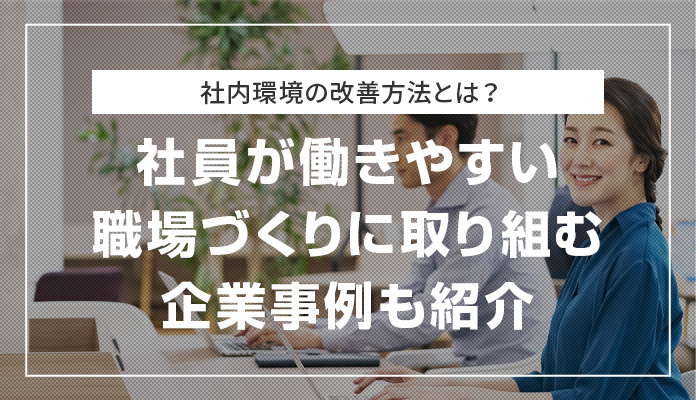職場改善
2022.06.03
【事例付き】社員のモチベーションを向上させる方法・施策を紹介
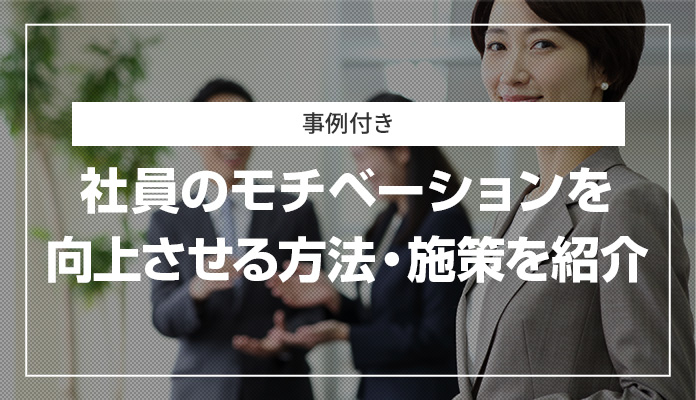
人材不足が深刻化しており、企業においては、優秀な人材を定着させ、生産性を高めていくことが課題となっています。その課題をクリアするためにポイントとなるのがモチベーションです。モチベーションとは、「刺激」「やる気」「動機づけ」という意味がある言葉で、仕事や人材育成において重要な要素とされています。
本記事では、社員のモチベーションを向上させた企業事例を紹介しながら、なぜ社員のモチベーション対策が必要なのかを解説します。効果的に社員のモチベーションを高める方法についても紹介していますので、経営者や人事担当者はぜひ参考にして実践してください。
社員のモチベーションを向上させた企業の事例一覧
業務を円滑に遂行し、生産性を高めていくためには、社員の協力が必要不可欠です。「どのようにして社員のモチベーションを高めようか」と考える企業経営者も多いと思います。
そんな悩みに応えるため、この章では社員のモチベーションを高める工夫が良い影響につながっているという企業の導入事例を取り上げ、注目のポイントを紹介していきます。
【事例①】株式会社ユナイテッドアローズ
「株式会社ユナイテッドアローズ」は、衣類や小物を販売するセレクトショップ「ユナイテッドアローズ」を運営する会社です。
具体的な施策としては、次の2点があげられます。
- ・自分の意志に合わせて幅広いキャリアにチャレンジできる「社内公募制度」
- ・異動する際に配属部署の希望を出せる「キャリア自己申告制度」
社員自身が主体的にキャリア形成を行い、チャレンジする機会や挑戦しやすい環境を作る工夫により、社員のモチベーションを高めています。
【事例②】ザ・リッツ・カールトン
世界規模でチェーン展開する有名ホテルのひとつ「ザ・リッツ・カールトン」では、従業員同士のコミュニケーション法として、「ファーストクラス・カード」という制度を導入しています。
「ファーストクラス・カード」は、仕事を手伝ってくれたときなど、感謝を伝えたいときに手渡すカードです。人事査定の参考資料にもされており、褒め合うことを習慣化することで、褒められた社員のモチベーションを高めています。
【事例③】サイボウズ株式会社
クラウドベースの業務改善サービスを軸に事業を展開する「サイボウズ株式会社」では、多様な働き方を実現できるような取り組みを積極的に行っています。
例えば、最長6年間サイボウズへの復帰が認められる「育自分休暇制度」という復職制度を2012年から導入しています。退職する人がまた戻ってこれるという安心感を持って次のステップへ進めるのは、働く人にとって嬉しいポイントでしょう。
組織や評価制度の見直しにより、最大28%だった離職率が3%前後(※1)にまで下がっており、数値にも社員のモチベーションが高まっている状況が現れています。
【事例④】株式会社サイバーエージェント
メディア事業やインターネット広告事業などを行う「株式会社サイバーエージェント」では、「リフレッシュ休暇 休んでファイブ」という休暇制度を設けています。
「リフレッシュ休暇 休んでファイブ」は、さらなるチャレンジができるよう、心身のリフレッシュをしてもらうことが目的です。入社3年目以上になると、毎年5日間の年次有給休暇が取れるため、気兼ねなく休める環境が、社員のモチベーションを維持するひとつのきっかけとなっています。
【事例⑤】面白法人カヤック
「面白法人カヤック」は「社員が面白がって働ける環境」を心がけているだけあり、他の企業では類を見ないユニークで特徴的な制度や福利厚生、行事が豊富です。
例えば、半年に1度実施される「ぜんいんで報酬を決定」では、社員同士で相互投票を行い、ランキングに比例して月給の昇給額が決められています。
この楽しみながら昇給アップを目指せる仕組みが、社員のモチベーション向上においてもよい効果を与えていると言えるでしょう。
なぜ社員のモチベーション対策が必要なのか?
各企業の事例を見てきましたが、「なぜ社員のモチベーション対策が必要なのか」を理解していなければ、自社に合った取り組みを実行できない可能性があります。この章では、社員のモチベーション対策の必要性について、掘り下げてみていきましょう。
生産性の向上につながる
社員のモチベーションが高ければ、エンゲージメントも向上します。その結果、会社や仕事に対しての愛着信が生まれ、積極性や主体性の向上につながり、企業の生産性の底上げが期待できるのです。
仕事に対して「やらされている」と感じている状況では、作業をだらだらと行ってしまう要因になり、生産性を下げてしまいかねません。一人ひとりのパフォーマンスを向上させるためにも、社員のモチベーションを高めることが重要と言えるでしょう。
企業のイメージアップが期待できる
モチベーションが高い社員は、丁寧な仕事を行いやすく、商品やサービスなどの質を高める要因になります。その結果、取引先企業や顧客からの評価が高まり、企業やブランドの価値も向上する可能性があるため、企業イメージ向上のためにも、社員のモチベーション対策は欠かせないでしょう。
離職率低下・定着率向上につながる
モチベーションが上がらない環境では、「ほかにいい職場・仕事があるはず」と考える社員が増えてしまうかもしれません。優秀な人材が転職や離職をしてしまう状況を避けるためにも、社員のモチベーションが上がる工夫は必要と言えるでしょう。
ただ事例をマネするだけでは思ったほどの効果が得られない
社員のモチベーション対策が必要だと分かったところで、他社の事例をそのまま活用しても期待している効果が得られない可能性があります。なぜなら、企業によって仕事内容も働く環境も違うからです。
従業員が抱えるニーズも異なるので、成功事例をただマネするだけの施策はお勧めできません。「社員のモチベーションの向上」における本質的な部分を知って、対策することが重要です。
仕事におけるモチベーションには2種類ある
では、仕事における社員のモチベーションは、どのようにして上げていけばいいのでしょうか。モチベーションといってもさまざまで、大きく分けると2種類あります。
| 内発的動機づけ | 外発的動機づけ |
|---|---|
| 内発的動機づけとは、本人の内側にある欲求から発生している「やる気」「動機づけ」のこと 例) ・好奇心 ・探求心 ・向上心など |
外発的動機づけとは、行動の要因が人為的な刺激によって発生している動機づけのこと 例) ・人からの評価 ・強制 ・報酬など |
| 内発的動機づけを増やすことが、モチベーションの維持につながる | 外発的動機づけによる行動が、内発的動機づけのきっかけになることがある |
以下で詳しく解説します。
内発的動機づけ
内発的動機づけは、行動の要因が自分自身の内面にある興味や関心による動機づけのことです。内発的動機づけを高めることで、仕事に対しての集中力がアップし、クオリティの向上も期待できます。
簡単に言うと、誰かに言われてするのではなく、「自分がしたいからする」という状態です。例えば、「仕事に対するやりがい」「成長しているという実感」などが内発的動機づけになります。
次に紹介する外発的動機づけだけでは、モチベーションを高め・維持することが難しくなってきており、本人の内にある好奇心や向上心といった内発的動機づけを高めることに注目が集まっています。
外発的動機づけ
外発的動機づけは、自分発信で行動する内発的動機づけとは異なり、外部からの働きかけによる動機づけのことです。身近なものでいえば、昇給や昇進、人事評価などが上げられます。
外発的動機づけもモチベーションの向上が期待できますが、一般的には一時的な効果しか見込めません。持続的なモチベーションを実現するためには、外発的動機づけをきっかけにして、徐々に内発的動機づけへ導いていくことが大事と言われています。
内発的動機づけの具体例
内発的動機づけと言われても、どのようなものかイメージしづらい人もいるでしょう。そこで、ここでは具体例を紹介します。
例えば、
- 「ゲームソフトの販売だけでなく、子だちも大人も夢中になれるようなゲームソフトを開発したいから、営業職からエンジニア職にチャレンジしたい」
- 「自分の仕事(物流)が、人々の生活必需品を届ける一翼を担っている」
上のような好奇心や挑戦、やりがいなどが内発的動機づけの要因です。
外発的動機づけの具体例
外発的動機づけの具体例についても見ていきましょう。
外発的動機づけは、金銭報酬、賞賛などが動機づけの要因です。
- 「目標を達成したら給与が上がる」
- 「嫌な仕事だけどインセンティブをもらえる」
- 「『ありがとう』という言葉がうれしい」
このように、内発的動機づけよりも分かりやすい目標や目的があげられます。
【管理職向け】部下のモチベーションを向上させる3つの方法
内発的動機づけと外発的動機づけの具体例を見て、社員のモチベーションを高めるためにどのような対策をすればいいのかイメージできたと思います。
この章では、具体的にどのような方法でモチベーションを向上させると良いのかを見ていきましょう。まずは、管理職向けに部下のモチベーションを高める方法を3つ紹介します。
部下の個性や適性、やる気に合った目標設定をする
仕事に対して前向きになるためには、まず「仕事そのものに対して“楽しい”と思えること」が大事です。
そのため、管理者となる上司は、部下の個性や能力、適正、仕事に対するやる気などを見極め、本人のレベルに合った仕事量や作業内容を与え、目標達成までのビジョンを示してあげる必要があります。
「簡単ではないが、難しくもない」難易度を見つけるのは難しいかもしれませんが、うまくいけば外発的動機づけから内発的動機づけへシフトできる可能性もあります。小さな成功体験を積み重ねられるよう配慮し、「自分は有能な人材だ」という意識を芽生えさせてあげましょう。
部下が相談しやすい関係性を築く
仕事に対するモチベーションを高めるためには、段階的に成長していくことも重要な要素です。しかし、チャレンジしなければならない状況は、挫折がともないます。
信頼して仕事を丸投げし、部下の「自分はできるんだ」という自己効力感を育てることも大事ですが、ほったらかしにするのは好ましくありません。周りからのフォローがなく、相談もしづらい状況では、「できない」という現実をきっかけに仕事に対するモチベーションを下げてしまいかねないからです。
そのため、部下が「自分では対処できない」「困った」というときに、上司や先輩に対して気軽に相談できる環境や関係性を築くことも大切と言えるでしょう。
業務は結果だけではなくその過程を含めて評価する
部下の仕事に対するモチベーションを高めたいのであれば、“結果”だけでなく“その過程”を含めて評価するように心がけてみてください。
掲げた目標を達成したことは、素直に喜ぶべきことだと思います。しかし、そこに至るまでの過程も重要です。以下の例をご覧ください。
- Aさん「片っ端から営業をかけて、売り上げ目標を達成した」
- Bさん「売り上げ目標は達成できなかったが、取引先と信頼関係を結び、新しい取引先を紹介してもらえた」
「売り上げ目標の達成」だけに注目するとAさんの評価が高いですが、企業全体の利益として考えると、Bさんの行動も大きな成果と言えます。
もちろん、分かりやすい数字も人事評価における基準のひとつですが、社員にも個性があるため、総合的な評価で社員のモチベーションを高めてあげることも重要です。
効果的に社員のモチベーションを向上させる5つのポイント
管理者における部下のモチベーションを高める方法について触れましたが、効果的に高めるにはポイントを押さえることが大事です。特に次の5つのポイントに注目しましょう。
従業員満足度を調査する
社員のモチベーションを高めるには、まず従業員のリアルな声を収集することが大事です。ニーズが分からなければ、効果的に施策を実施できません。
ニーズの把握には、制度・待遇や業務内容などに関連するアンケート調査がおすすめです。素直な本音を聞き出せるよう、匿名のアンケート調査を実施し、モチベーション低下の原因や理由がそれぞれどこにあるかを把握し、状況を打開するポイントを探りましょう。
外発的動機づけから始める
企業や業務内容に対して、何らかの内発的動機づけがあって入社してくる人ばかりではありません。仕事に対して、まだ好奇心や探求心などを持てていない人もいるので、そのような人たちには、外発的動機づけから示してあげましょう。
先ほど、外発的動機づけの具体例でもあげましたが、人為的な刺激としては、次のような動機づけがおすすめです。
- ・昇給や昇進
- ・インセンティブ
- ・代休
目に見えて分かりやすいゴールを設定してあげることで、それを目標にやる気をだしてくれるでしょう。
欲求5段階説をもとに、段階的に欲求を満たしていく
「欲求5段階説」は、アメリカの心理学者アブラハム・H・マズローが提唱する心理学理論です。
人間は、「生理的欲求」が満たされると「安全欲求」「社会的欲求」「承認欲求」「自己実現欲求」の順に次々と欲求を持つようになると言われています。
この段階的な欲求は、仕事に対するモチベーションを高める際にも見られます。
はじめは、必要最低限の給与があればいいというところから始まり、安心してくらせるだけの収入が欲しい、周りから認められる仕事をして適切に評価されたいというように徐々に欲求がエスカレートしていくため、その欲求をひとつずつしっかりと満たしてあげることが大切です。
マネジメント・フォローアップを徹底する
部下の意思を尊重した仕事の割り振りをしたり、社内研修や訓練の後も社員の理解度を上げたり、マネジメントやフォローアップを徹底することも社員のモチベーションを高めるポイントです。
細かな状況に応じて必要なフィードバックを与えることで、「しっかりと見てもらえている」という安心感を与えることができ、内発的動機付けにつながる可能性があります。
制度や環境を整える
さまざまな企業の事例からも分かる通り、社員がやる気やモチベーションを維持できるような制度や環境を整えることも重要と言えるでしょう。
社員一人ひとりが納得して働ける環境がベストです。そのためにも、会社の評価制度や働きやすさ、報酬などを見直し、外発的動機づけから内発的動機づけへ結びつけましょう。
【社員向け】仕事のモチベーションを高める3つの方法
最後に、社員自身ができるモチベーションを高める方法を紹介します。「なかなかやる気が出ない」「どうすれば仕事を楽しめるようになるのか知りたい」という人は、ぜひ参考にしてください。
できることから着実に達成する
モチベーションが上がらないという人は、まず小さな成功体験を積み重ねられる状況を作りましょう。
ビジネス社会では人と比べられることも多く、自分のレベルを理解しないまま、つい大きな目標を立ててしまう人がいますが、それではスランプから抜け出しにくくなります。
自分のタスクを抜き出し、できそうなことから着実にこなしていきましょう。そうすることで、できたという達成感、喜びが生まれ、モチベーションの向上につながります。
目標を達成した際の自分へのご褒美を設ける
目標の先に嬉しいことがあれば、頑張れるものです。目標を決め、それを達成したら、頑張ったご褒美に「スーツを新調する」「旅行に行く」などで自分を甘やかせてあげましょう。
お手本とする社員を見つける
まだ「どうなりたい」という目標が定まっていない人もいるでしょう。そのような人は、モチベーションが高い身近な先輩や同期などをロールモデルにしてみてください。
モチベーションの高い人がどのような行動・言動をしているのかを参考にすることで、外的な刺激を受けることができ、それをきっかけに自分のやりたいことが明確になり、内発的動機づけに発展する可能性があるからです。
すべてをマネする必要はないので、できそうな行動・言動を実践することから始めましょう。
事例を参考にして自社に合った方法で社員のモチベーションを向上しよう
社員のモチベーションを向上する事例や方法などについて紹介してきました。従業員にとって働く目的や理想の働き方などが異なるため、モチベーションを高めることは簡単ではないでしょう。しかし、工夫次第でやる気をアップさせることができ、個々人の士気が上がることで組織全体も活性化します。
今回紹介した事例やポイントを参考にしながら、自社に最適な方法を模索し、社員のモチベーションを向上させましょう。
関連記事
-
リテンションの意味とは? 人材確保が課題の人事とマーケティングでよく聞く用語を解説!
職場改善
2022.06.03
-
社内環境の改善方法とは? 社員が働きやすい職場づくりに取り組む企業事例も紹介
職場改善
2021.12.27