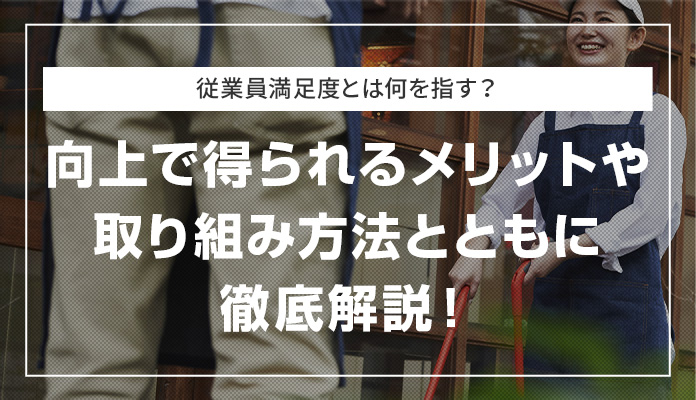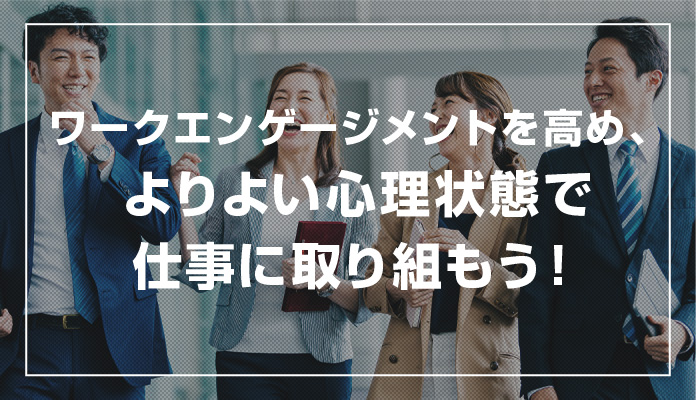職場改善
2022.1.31
従業員エンゲージメントの向上が重要な理由とは? 具体策や事例も含めて徹底解説!
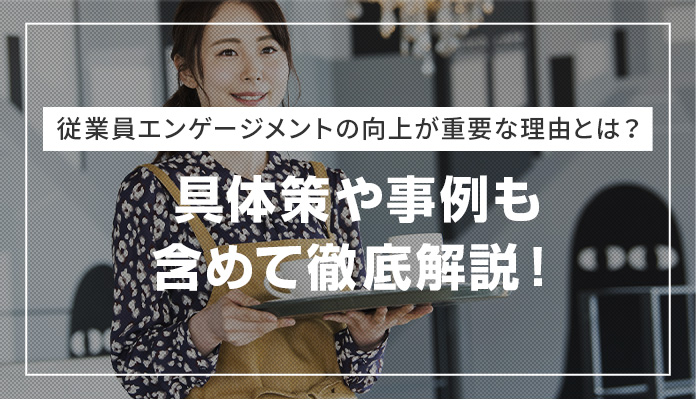
2021年~2022年現在、経営者の間で注目を集めている概念に従業員エンゲージメントがあります。経済関係の記事などで「従業員エンゲージメントの向上なくして企業の発展はない」とまでいわれている理由は何なのでしょうか。この記事では、従業員エンゲージメントの基礎知識や、向上が重要な理由、向上のための具体策などについて事例を含めて解説します。
従業員エンゲージメントの基礎知識
従業員エンゲージメントは企業理念への理解と信頼・貢献意欲
従業員エンゲージメントは自分が働く会社や団体(以下企業と呼びます)の理念への理解、信頼の度合いや貢献意欲からなる概念で、企業への愛着の尺度ともいえます。数値化によって、従業員の帰属意識を図る明確な指標となるものです。engagement という単語の意味は契約や雇用などで、企業と従業員のつながりやその強度を指しています。
強制ではなく自発的に芽生えるのが従業員エンゲージメント
従業員エンゲージメントとは、企業で働く従業員それぞれの心の中に芽生えるもので、所属企業に対する理解と信頼、そして貢献意欲からなるものです。あくまでも自由な内心に芽生えるものであり、企業や管理者からの強制的な求めや誘導、他人の行動などによって感じるものでも意識するものではない点が重要です。
個人がもつ従業員エンゲージメントと企業トータルでの従業員エンゲージメント
従業員エンゲージメントは基本的に個々の従業員がもつものです。その集合体が企業トータルでの従業員エンゲージメントであり、企業として従業員エンゲージメントの向上を目指すなら、個々の従業員エンゲージメントを向上させることを考えなければならないといえます。
ただし、従業員に迎合して個人的な要求や希望を聞き入れるということではありません。従業員エンゲージメントの向上は、あくまでも社内の従業員全体に一般化できる範疇の、企業として合理的な方法によります。これは部下のマネジメントにおいても同様です。
従業員エンゲージメントと似て非なる3つの概念
従業員エンゲージメントを考えるとき、比較対象としてよく示される概念が3つあります。従業員満足度とモチベーション、それに忠誠心です。これらは従業員エンゲージメントと似てはいますがまったく異なります。
従業員満足度はあくまでも満足しているかどうかを示すものであり、企業に対する理解や信頼、貢献意欲の有無とは関係なく上下し得るものです。モチベーション、つまり動機付けは自分にとっての経済的、精神的その他の利益によるところが大きいといえます。
また、忠誠心に至っては主従関係を前提とするものです。たとえ自社に貢献する意欲が大きく上がるものだとしても、形式的にも実質的にも強制力を前提としない従業員エンゲージメントとは同列には語れない概念です。
従業員エンゲージメントの向上が重要な理由
指示待ちではなく能動的に動ける組織でなければ生き残れない
従業員エンゲージメントの向上を図らなければ、これからの企業は生き残りが厳しくなるといえます。
サービス競争が激化する現在においては、例えば与えられた仕事だけをこなす「指示待ち」の人材が多くいるような状態ではなく、企業という観点で能動的に動ける従業員の集団となることが重要です。そうした従業員集団を目指していくためには、価値観が多様化している社会における従業員の内心の変化にも着目した従業員エンゲージメントの向上が不可欠なのです。
従業員エンゲージメントが低い状態にある企業は、経営ビジョンに対する従業員の理解や信頼、そして貢献意欲が低い企業であり、自ら積極的に動こうという意欲ある従業員が少ない状態であるといえます。
目標に向かって横道にそれることなく邁進するため
従業員エンゲージメントの向上は、自社の目標に向かって横道に逸れることなく邁進するために必要不可欠です。ビジョンへの理解や共感が不足していれば間違った方向に進んでしまう可能性があります。また企業や上司への信頼感が乏しければ、業務内容や指示に不満を持つなど、自発的な企業への貢献意欲を低下させる一因となります。
企業とともに戦い続けてくれる従業員集団を作るため
もうひとつ、従業員エンゲージメントを向上させなければならない大きな理由は、どの部署であっても企業とともに戦い続けてくれる従業員集団を作ることです。一時的に企業と従業員が一体となって目標を達成したとしても、それが高い従業員エンゲージメントを前提としていない場合はいつまで続くか不安が残ります。
従業員エンゲージメント向上で期待できる4大メリット
優秀な人材の確保と離職率の改善
従業員エンゲージメントを向上させることで企業が発展するメカニズムとして、大きく4つのメリットがあります。
まずは優秀な人材の確保と離職率の改善です。従業員エンゲージメントが高い企業では、業務内容や待遇への満足度はもちろんのこと、“その企業”での自発的な貢献意欲が高い従業員が多く働いています。
就職活動・転職活動中の人材にとって、定着率が高くて従業員が自分から積極的に貢献したいと思えるような企業であれば、入社先企業の選択肢として有力となることは間違いないでしょう。また、 高い従業員エンゲージメントをもつ人材にとって、今の企業を離れる合理的な理由は考えにくいものです。
優秀な人材を採用し離職率の上昇を防ぐことで、人材育成にも力を入れやすくなり、企業の発展にとって大きなメリットとなります。
意欲的で明るい職場環境の実現
従業員エンゲージメントの高い人材が集まっていると積極的な意見交換が行われたり、助け合いが活発化したりと、人間関係もよくなり職場環境が明るくなります。 明るい職場では全員が一体となって仕事に取り組みながら、それぞれが自分の役割を果たして貢献する意欲が強固になりやすいといえるでしょう。つまり、従業員エンゲージメントが向上する好循環が生まれます。
生産性と業績のアップ
従業員エンゲージメントの向上に成功することで、必然的に無駄な作業が少なくなります。各自が効率の良い業務を行うことで生産性がアップし、業績が向上する仕組みです。
経済産業省の資料で紹介されている調査によると、従業員エンゲージメントスコアが高い 企業の方が、営業利益率・労働生産性ともに高いという傾向・関連性が示されています(※1)。
顧客満足度の上昇
従業員エンゲージメントが向上することにより顧客満足度が上昇します。その大きな理由は顧客に対する従業員の対応がよくなることです。明るく意欲的な従業員が対応することで、顧客が受けるイメージも好意的になります。また、従業員エンゲージメントの高い中で生産された商品や提供するサービスの品質がよくなる点も、その商品やサービスを利用する顧客の満足度を上げる要因です。
※1 出典:参考資料集 令和2年7月(経済産業省 産業人材政策室)P.43
従業員エンゲージメントの向上失敗と想定される好ましくない状況
調査結果の数字を整えることが目的になる
従業員エンゲージメントが高いか低いか、それを知るためには従業員に対する調査が必要 となります。ここで注意しなければならないことは、調査で高い点を取ることが目的ではないということです。実態としての従業員エンゲージメントを向上させることが重要であり、テクニックによって整えられた数字は必要ないどころか、従業員エンゲージメントの向上を失敗させる阻害要因になります。
その結果、経営判断を誤り企業の発展からかけ離れてしまっては本末転倒です。従業員エンゲージメントスコアを調べる際には、本当の姿を映し出す強い意思が必要です。
よくいえばビジネスライクな労使関係になる
従業員エンゲージメントの向上に失敗すると優秀な従業員から辞めてしまうといった事態が起こりかねません。残るのは貢献意欲が低く現状に満足してしまっている指示待ちの従業員です。
優秀な従業員を高給で引きとめたとしても限界があります。懸念されるのは、よくいえばビジネスライクな労使関係となることであり、理解や信頼、貢献意欲よりも費用対効果を重視する従業員が増え、雇用が流動化してしまう状況です。
チームプレーよりも個人プレー主体の仕事
従業員エンゲージメントの向上に失敗した企業ではチームプレーよりも個人プレー主体の仕事が幅を効かせます。自分の利益優先となり、チーム一体で成し遂げるといった感覚の欠如やフォロー体制の危機といった弊害が心配です。
クレームが増える
従業員エンゲージメントの向上が見込めない企業では、やがてクレームが増えます。個人プレーで結果が出ているうちはまだ良いですが、職場の雰囲気が悪く生産性が低下する中で提供される商品やサービスの品質が劣化するのを回避することは困難でしょう。
業績と価値の低下
以上のような理由から、従業員エンゲージメント向上の失敗は、結果として業績の落ち込み、企業価値の低下を招きかねない点に注意が必要です。
早急に従業員エンゲージメントを向上させるべき企業とは
人材不足が慢性化している企業
人材不足が慢性化している企業は、早急に従業員エンゲージメントを向上させる対策を進めるべきでしょう。優秀な人材が集まらず離職率が高い状況であれば、企業の発展は難しくなります。
業績が伸び悩んでいる企業
業績が伸び悩んでいる企業も従業員エンゲージメントの向上が欠かせません。業績が伸びない理由はさまざま考えられますが、従業員エンゲージメントを向上させることで生産性が向上し、企業としての競争力がアップすれば業績にも良い影響を及ぼすことは間違いないといえます。
組織に活気がない企業
組織に活気が無い企業はチームワークの形骸化や消極的な取り組み姿勢の蔓延による深刻な事態が懸念されます。一刻も早く従業員エンゲージメントの向上に取り組むべきでしょう。
顧客対応が多い企業
顧客対応が多い企業は、そうでない企業に比べて従業員エンゲージメントの影響が早く出てしまうといえます。たとえば、毎日多く消費者と接する小売業です。従業員の一挙手一投足が顧客の評価に直結します。そのため、従業員エンゲージメントの向上が急務です。
日本企業こそ従業員エンゲージメントの向上が急務
実は、上で挙げた企業だけでなく多くの日本企業は従業員エンゲージメントの向上が急がれる事実があります。
2017年の米ギャラップ社の調査結果で、熱意あふれる社員の割合が日本は他国に比べても非常に低い、6%(139ヶ国中132位)(※2)という数字が出ています。
ここまで日本企業の従業員エンゲージメントが低い理由として、日本型の雇用環境の影響を指摘する声があります。長く続いた年功序列型の終身雇用です。波風立てず企業に所属していれば、それなりの待遇が得られて解雇のリスクもほとんどない環境下において、従業員エンゲージメントが向上する要素は乏しいと考えられています。
また、日本企業の経営者の多くが従業員エンゲージメントの重要性を認識していないためだとする意見にも要注目です。
※2 出典:参考資料集 令和2年7月(経済産業省 産業人材政策室)P.42
従業員エンゲージメントの向上に欠かせない意識調査
自社の従業員エンゲージメントを正確に把握する
従業員エンゲージメントを向上させるには、まず自社の従業員エンゲージメントの実態を正確に知ることが第一歩です。調査で出てくる従業員エンゲージメントスコアが客観的な位置を示してくれます。従来はes、つまり Employee Satisfaction(従業員満足度)の調査が盛んでしたが、現在では従業員エンゲージメント調査がより重要です。
エンゲージメントサーベイ
エンゲージメントサーベイは、企業と従業員の結びつきの状態、両者に横たわる課題を可視化して把握する調査方法です。
エンゲージメントサーベイは、半年や1年、2年といった間隔で行われ、ときには100問にも上る多くの質問が設定される本格的な調査です。質問内容も理解や信頼、貢献意欲といった大きな項目に加え、企業に対する満足度に関する項目も含まれます。ただ、ボリューミーで濃い内容の調査となっていることから、正確な回答を得るための調査スキルが必要ともいえます。
パルスサーベイ
エンゲージメントサーベイに対し、回答者の負担が少なく、その都度の短期的な状況を把握しやすいのがパルスサーベイです。調査は毎日実施するケースもあり、長くても1ヶ月程度の間隔です。設問は多くても10問程度で、少なければ1問だけでも構いません。ポイントは短時間で終わることです。
eNPSによる数値化
eNPSは Employee Net Promoter Score の略で、従業員が自分の所属する企業に感じている 推奨度(知人・友人などに自分の職場をどれくらい勧めたいか)を意味します。eNPS調査による従業員エンゲージメントの数値化は、より正確な従業員エンゲージメントの測定を可能にするものです。
家族や友人に自分の職場を推奨したい気持ちを点数化すると0~10のどこになるかといった設問で、10に近いほど従業員エンゲージメントが高いといえます。単に満足度を0~10で示すだけなら、満足以外の気持ちを知ることはできませんが、家族や友人に推奨するとなれば、理解や信頼、貢献意欲が高くないと10に近い回答はできないでしょう。
アプリの利用で効率よく調査できる
従業員エンゲージメントの調査は手間のかかるものです。しかし、アプリを活用すれば効率の良い従業員エンゲージメント調査が可能です。様々な切り口からの調査が質問を考える手間もなく簡単にできます。
また、分析にもアプリの機能を 活用すれば業務効率のさらなるアップが可能です。調査を受ける従業員にとっても、スマホで簡単に回答できるなど、アプリのメリットがあります。従業員エンゲージメント向上に向けて、便利なツールの積極的な活用が望まれます。
問題点を把握できれば次のステップへ
従業員エンゲージメント調査の目的は、現状の問題点の把握から課題の解決につなげて、従業員エンゲージメントを向上させることにあります。調査をしたことで満足してしまうことなく、次のステップへと進むことが重要です。
スタートから従業員エンゲージメントを向上させる手段4例
理念やビジョンを示して浸透させる
最初にやっておかなければならない従業員エンゲージメントを向上させる重要な手段を4例紹介します。
まず、理念やビジョンを正しくしっかりと伝えることです。訓示やペーパーの配布、掲示など、どのような方法であれ正しく伝わってこそ従業員エンゲージメントの肝である理念やビジョンへの理解が得られます。浸透するまで繰り返し伝えることが重要です。
社会的な存在価値を示す
企業への信頼や貢献意欲の高まりには、企業がそれに見合う価値のある存在であること感じられることも重要です。とくに、社会的に存在価値のある企業であると認識できれば、その企業を通じて自分も社会に貢献できる存在と考えられ、気持ちが前向きになります。また、新しい価値づくりをすれば、良い企業イメージを生み出せます。
風通しの良い環境を作る
従業員エンゲージメントの向上にとって風通しの良い環境は欠かせません。コミュニケーションがとりにくい職場で企業や上司、あるいは同僚が何を考えているのか分からない環境では、理解も信頼も貢献意欲もわかないというものです。
キャリアアップの道筋を示す
この仕事をすることによってどのようなキャリアアップが望めるのか、その道筋を示しておくことは、従業員エンゲージメントの向上に重要な要素です。企業と二人三脚で発展に邁進することは、イコール企業だけの発展ではなく、自分のキャリアアップも当然に含まれるためです。
結果や状況に応じて従業員エンゲージメントを向上させる手段3例
成果に見合った報酬を約束し実行する
従業員エンゲージメントを向上させる手段として、結果や状況に応じた対策も重要です。
まず、成果に見合った報酬の約束と実行です。企業と従業員が一体となって発展するためには、適切な報酬が確実に支払われるという信頼関係が大事なポイントになります。
能力に応じたポストの用意や評価制度を実施する
報酬と共に重要なのが適正な評価制度・人事制度の実施です。能力に応じてポストを用意する公正公平さが従業員エンゲージメントを高める要素となります。
多様な働き方に対応し福利厚生を充実させる
多様な働き方が一般化している社会に対応し、福利厚生を充実させることもさまざまな状況下に置かれている従業員にとって、従業員エンゲージメント向上の大きなポイントです。
従業員エンゲージメント向上に取り組む企業の実例
TGIFとOKRそしてGoogleガイスト~Googleの場合
世界的企業のGoogle社では、TGIFと呼ばれる社員全員を対象としたミーティングを毎週行っています。情報共有に加え誰でも可能な質疑応答が行われている点が特徴です。また、OKRと呼ばれる目標設定と主要結果報告により、企業と従業員が目標に向かって進む仕組みを作っています。Googleでは独自のサーベイであるGoogleガイストによる従業員エンゲージメント向上にも取り組んでいます。
出典:経済産業省 主催 経営競争力強化に向けた人材マネジメント研究会「平成30年度産業経済研究委託事業(企業の戦略的人事機能の強化に関する調査)」P.12
mertip(メルチップ)~メルカリの場合
株式会社メルカリでは、従業員間で成果給を贈り合うことが可能なmertip(メルチップ)制度を導入しています。円滑で活発なコミュニケーションと従業員の一体感を強化し、結果として従業員エンゲージメント向上につながる優れた制度だといえるでしょう。
出典:mercari
骨髄ドナー休暇や裁判員休暇~ユニ・チャームの場合
ユニ・チャーム株式会社では、最大7日間の骨髄ドナー休暇や全日数分の裁判員休暇を有給で実施しています。従業員が自社の社会的価値を認められる点と従業員自身が実際に社会貢献できている点が重なることで、従業員エンゲージメント向上効果は期待大です。
出典:社員と会社が元気になる休暇制度を導入しませんか?(厚生労働省)P.12
ボランティア休暇と1万ドルの寄付~セールスフォース・ドットコムの場合
株式会社セールスフォース・ドットコムでも社会貢献の一環として有給のボランティア休暇を実施しています。さらに、上位10人のボランティアとなればCEOからの感謝が贈られるなど、より有効な施策とセットです。
出典:株式会社セールスフォース・ドットコム株式会社 公式サイト
従業員エンゲージメントの向上は多様な価値観を認めるところから始める
各社の事例を見てもわかるように、業務そのものに関する制度だけでは従業員エンゲージメントの向上を期待できない時代になっています。企業の理念やビジョンに理解を得て、信頼され、自発的な貢献意欲をもってもらうためには、従業員の間にある多様な価値観を認めるところから始めることが重要です。
企業の成長へとつなげるためにも、始められるところから始めてみましょう。
関連記事
-
従業員満足度とは何を指す?向上で得られるメリットや取り組み方法とともに徹底解説!
職場改善
2022.01.31
-
ワークエンゲージメントを高め、よりよい心理状態で仕事に取り組もう!
職場改善
2021.07.05