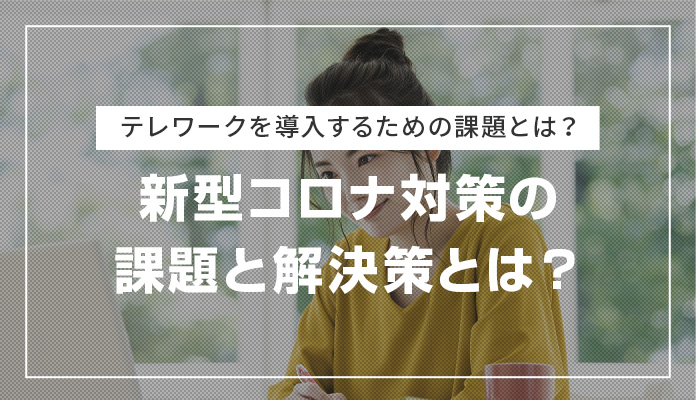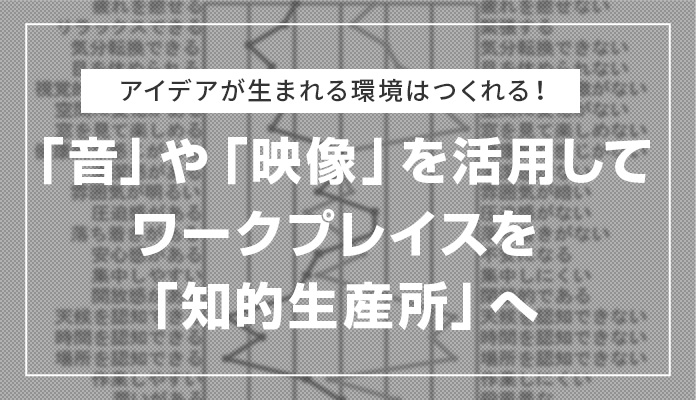テレワーク
2021.07.30
テレワーク導入の企業負担を軽減できる!助成金制度について解説
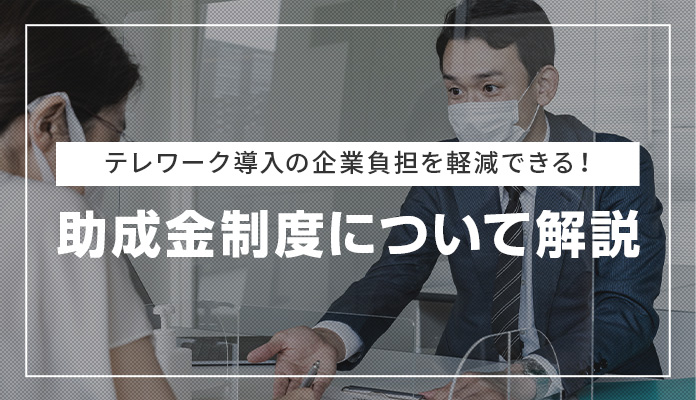
テレワークを行うには、必要な機器を揃えるための購入費や毎月の電気代など、さまざまな費用がかかります。これらの費用は、企業もしくは従業員どちらが負担すべきなのでしょうか。また、費用負担を軽減する制度はあるのでしょうか。
今回の記事では、テレワークの費用負担や助成金制度について詳しく説明します。企業負担の軽減に、ぜひお役立てください。
テレワークの導入および実施にはどのような費用がかかる?
テレワークを導入および実施していくのにかかる費用は、どのような内訳となっているのでしょうか。各項目の詳細について解説します。
機器購入費
機器購入代金に含まれるのは、パソコンやスマホおよびその周辺機器など、業務上で必要な設備の購入費用です。機器については、企業から貸与するケースが一般的ですが、購入するとかなり高額になってしまうため、近年では従業員個人が所有しているものを使うケースも多くなっています。
従業員個人の所有物を使うと、設備の購入費を軽減できるとともに、従業員が使い慣れた機器で業務ができるメリットもあります。ただし、情報漏洩などセキュリティ面のリスクがあることも忘れてはなりません。
ビジネスツールの契約費用および月額利用費など
設備が整っているオフィスとは違い、テレワークではさまざまなリスクが考えられます。これらのリスクを回避し、テレワークのメリットを最大に生かした業務ができるように、ビジネスツールの導入が必要です。
厚生労働省が、テレワークに関するポータルサイトを公開しており、次のツールの導入が推奨されていますので、参考にしてください。
リモートアクセスツール
外部から、xデータやソフトウェアにアクセスするためのツールです。いくつか方式がありますが、中でもリモートデスクトップ方式が導入しやすいと紹介されています。データをダウンロードせずに、外部のパソコンからサーバーを経由してデータを表示がするシステムです。情報漏洩の危険性が低いとされるうえ、利用料の安さ・導入の簡便さにも優れています。
コミュニケーションツール
テレワークにおけるスムーズなコミュニケーションを行うためのツールです。Web会議システムやテレビ会議システム、Eメール、チャット、・SNSなどが使われています。
労務管理システム
従業員の勤務状況が直接確認できないため、テレワークを行うのに労務管理システムは非常に重要です。システムによっては、勤務中の様子をランダムにキャプチャーするものや、離席ボタン・着席ボタンで勤務状況を知らせる機能がついたものなどがあります。
ペーパーレス化ツール
ペーパーレス化は、テレワークには必要不可欠な取り組みです。紙の文書を電子化してクラウドサーバー上に入れておくと、どの場所からでも文章を見られるようになります。また脱ハンコを始め、紙・印刷代などの削減も可能となります。
全ての文章をすぐにペーパーレス化するのは困難ですので、少しずつペーパーレス化を進めていきましょう。
安全なモバイルテレワークツール
スマホやタブレットなどのモバイル端末が、紛失や盗難にあった時のリスクに対応するツールです。データを安全な領域で表示するセキュアブラウザや、安全な領域を作成するセキュアコンテナなどのシステムがあります。これらを利用し、企業の大事なデータを保護することは欠かせないでしょう。
通信設備費および通信費・通話料
自宅のネット回線が使用できれば、回線の開通にかかる費用はかかりません。回線がなければ、新たに契約や開通工事などの手続きをしなくてはならないでしょう。
かかる費用としては、工事代・契約手数料・機器代(モバイルWi-Fiルーターなど)などがあります。これらの負担を、企業もしくは従業員のどちらが持つかは、事前に決めておく必要があります。
工事が終わって使用を始めてからは毎月の通信費もかかりますが、自宅で使っている場合には、仕事とプライベートの線引きが困難です。そのため、企業がモバイルwi-fiを契約したり、毎月の給与に「在宅勤務手当」という項目で上乗せしたりするなど、企業によって対応を決めています。
業務で電話を使用する際には、通話料がかかります。個人の携帯電話を使うのは、プライベートの電話番号が知られてしまうデメリットがあるため、会社の携帯電話を使用するケースが多いです。IP電話サービスを利用すると、仕事とプライベートの使い分けがしやすくなるうえ、かかる費用も抑えることができるため、導入する企業が増えています。
水道光熱費
仕事を行う場所では、電気代や水道費などの水道光熱費が発生します。オフィスで仕事をしていれば、オフィスでこれらの光熱費がかかっていましたが、自宅でテレワークを行うと、仕事用とプライベート用の区別がつきにくくなります。
水道光熱費の支給に関しても、勤務時間に応じて精算する・在宅勤務手当に含むなど、あらかじめ対応を調整しておく必要があります。
備品および消耗品
オフィスと同じように、テレワークで仕事をするには、消耗品の購入が必要です。ノートやボールペン・付箋の購入費など、消耗品の一つ一つはそれほど高額なものではないため、個人で購入することがあるかもしれません。
ただ、これらの消耗品がオフィスでも支給されていたのであれば、テレワークでも同じように支給するか、もしくは経費精算する必要があります。
また、取引先に荷物を送付する際の宅配費用などが発生した場合にも、同じように経費として精算しましょう。
テレワークによって削減できる費用は?
テレワークで、新たにかかる費用がある反面、削減できる費用もあります。どのような費用が削減できるのでしょうか。
交通費
従業員がオフィスに通勤するために使っていた通勤定期代などの交通費は、テレワークによって必要がなくなり、大幅な経費削減につなげられます。業務中に場所を移動する必要もないため、取引先や打ち合わせ場所などへの移動費用も削減できます。
オフィスの賃料および水道光熱費
従業員がオフィスに出勤しないことで、オフィスを利用する人数が減ると、それに伴いオフィスの水道光熱費が減少します。テレワークを継続する場合には、小規模のオフィスへ移転することで、オフィス賃料も削減できることになるでしょう。
企業都合によるテレワークの実施費用は企業負担が原則
企業からの指示によるテレワークでは、費用負担は企業が行うものと定められています。この内容について、詳しく見てみましょう。
労働基準法で規定されている
業務に必要な用品の費用負担に関しては、労働基準法の第89条で詳しく定められています。
常時10人以上の労働者がいる事業場では、就業規則を作成しなくてはなりませんが、定めをする場合に記載すべき事項のひとつとして、「食費・作業用品等を負担させる場合には、これに関する事項」と明記されています。つまり、テレワークにかかる費用を従業員に負担させる場合は、就業規則を修正するか、もしくは従業員に通知しなければなりません。
費用が、従業員もしくは企業どちらの負担になっているかを明確にするには、就業規則を確認する必要があります。ただし、企業都合によるテレワークであれば、経費は企業負担とするのが望ましいと言えます。
中小企業では費用負担が大きくなる場合が多い
中小企業がテレワークを導入しようとすると、初期費用がどうしてもネックとなってしまいます。中小企業がテレワークに充てられる予算は限られているため、次に紹介する助成金を使うのもひとつの方法です。
テレワーク導入で受けられる助成金を活用しよう
テレワークを促進するため、国および自治体が助成金の制度を定めています。ぜひこれらの制度の活用を検討してください。
IT導入補助金2021(特別枠:C・D類型)
経済産業省が監督している支援事業です。テレワーク環境を整備するのに必要な費用の助成が受けられますが、非対面化を可能とするツールであることが条件です。
申請対象となる事業者等は、細かく規定されていますので、自社が規定に該当するかどうかを確認してから手続きを行いましょう。
人材確保等支援助成金(テレワークコース)
質の高いテレワークの導入実施により、人材確保や雇用状況の改善に効果をあげた中小企業に支給されます。支給対象とされる経費の範囲や受給条件などが、細かく規定されていますので、自社に該当するかどうか確認してみてください。機器等導入助成および目標達成助成の2種類が制定されています。
自治体の助成金も確認してみよう
自治体においても、独自のテレワーク助成金制度を導入しているところがあります。東京都を例にして紹介します。
東京都では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と経済活動を両立させるために、テレワークの更なる定着を目指しています。この取り組みを促進するため、都内企業において令和3年5月より、「テレワーク促進助成金」の募集が開始されました。
助成対象となっているのは、都内の中堅・中小企業等が、テレワーク機器やソフト等の環境整備を行った際にかかる経費です。助成金額や助成率は次の通りです。
- 常用する労働者が2人以上30人未満の企業…助成金額:最大150万円(助成率:3分の2)
- 常用する労働者が30人以上999人以下の企業…助成金額:最大250万円(助成率:2分の1)
東京都以外の自治体でも、同様の助成制度が制定されている可能性があります。詳しくは、テレワーク相談センターなどの相談窓口へお問い合わせください。
まとめ
テレワークの導入には、就業規則の見直しや費用面など、さまざまな課題があります。特に、費用に関しては、企業側での負担が大きいため、企業にとっては少しでも負担を減らしたいところです。
テレワークの導入までに、就業規則の記載内容を今一度確認し、企業も従業員の両者が納得・安心してテレワークに臨めるようにしましょう。今回ご紹介した助成金が活用できるかどうか、一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。
関連記事
-
テレワークを導入するための課題とは?新型コロナ対策の課題と解決策とは?
テレワーク
2021.05.31
-
アイデアが生まれる環境はつくれる!「音」や「映像」を活用してワークプレイスを「知的生産所」へ
テレワーク
2021.06.04