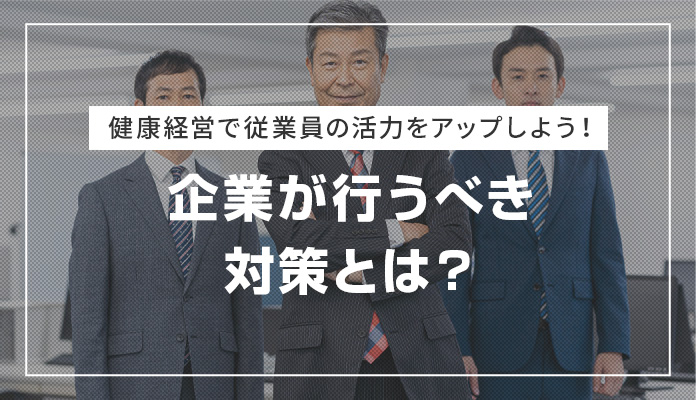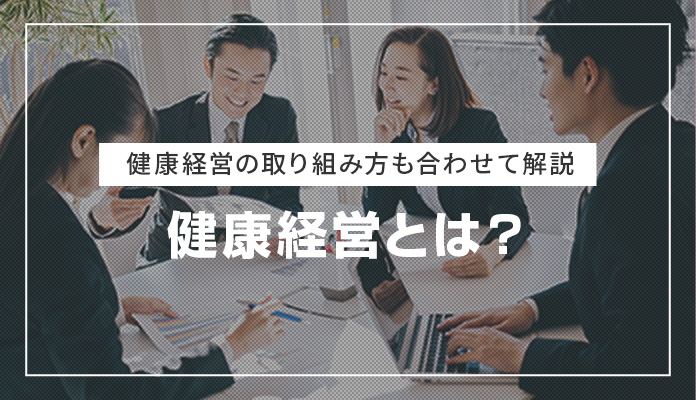健康経営
2022.08.10
心理的安全性のつくりかたとは? その方法とチームにおけるメリットや注意点も含めて徹底解説!
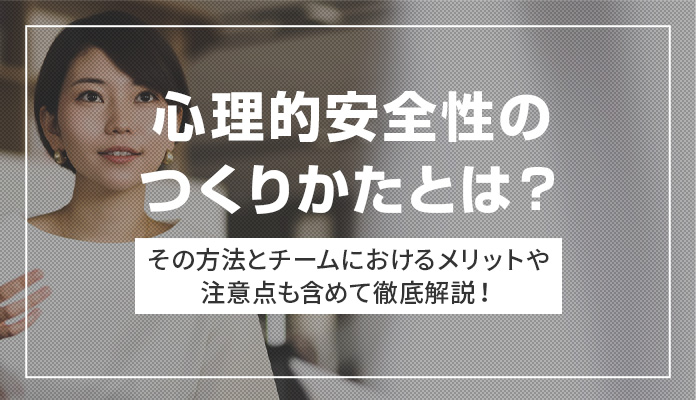
心理的安全性に注目が集まっています。心理的安全性を高めるメリットが大きいといわれているものの、つくりかたがわからないといった声も少なくないようです。当記事では、組織・チームのメンバーが積極的に行動するために必要とされる心理的安全性の具体的なつくりかたについて、主なメリットや注意点なども含めて紹介・解説します。
心理的安全性の要素と定義
立場に関係なく発言できる
心理的安全性とは、組織・チームの内部における自身の地位や立場、階級に関係なく、メンバーの誰もが率直に発言したり、行動したりできる状態のことです。また、その状態がどのレベルにあるかを指し示す物差しとして使われることもあります。とくに気兼ねのない発言が注目されており、単に発言できるだけでなく、意見交換や議論ができることが重要です。
発言が不利益にならない
心理的安全性をつくる前提となるのが発言によって不利益を生まないことです。形式的に自由な発言が許されているといっても、発言自体が不利益になるようでは、意見を述べたり疑問に感じていることを質問したりできなくなってしまいます。発言自体ではなく発言した内容に問題がある場合は不利益になる可能性があるでしょう。しかし、一般的に考えて許容されるべき発言内容が問題視されるようでは、心理的安全性を損ねてしまいます。
チームの一員として安心安全に行動できる環境
心理的安全性のレベルが高い組織・職場では、思うように発言させてもらえなかったり、頭ごなしに否定されたりといったネガティブな状況がなく、マイナスの感情を抱く必要がありません。自由な発言が可能で、自分の意見が尊重されることにより、チームの一員として安心安全な心理状態につながり、積極的に行動できる環境といえます。
心理的安全性の始まり
psychological safety
心理的安全性は、1999年にハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授によって世に出された概念です。論文で使われている「Psychological Safety」の日本語訳が、心理的安全性となっています。
注目度が高まっている2021~2022年の時点では比較的新しい概念といえる心理的安全性は、各メンバーがお互いの発言を尊重する気持ちがあってこそ成り立つものです。また、必ずしも各メンバーが同じように心理的安全性を感じているとは限らないため、より注意深く見る必要があります。
Googleの取り組みで有名に
心理的安全性が有名になるきっかけとなったのが、アメリカのGoogle社による研究結果です。Googleのリサーチチームは、心理的安全性が高いチームの離職率の低さや、収益性の高さ、評価の高さを発見しました。Googleでは、心理的安全性の重要性に着目し、心理的安全性を高める行動や逆の行動のシナリオを示すワークショップを実施するなどの取り組みを行っています。Googleの研究については、以下の特集ページ「「効果的なチームとは何か」を知る」にて無料で見ることが可能です。
▶Google re:Work『「効果的なチームとは何か」を知る』
心理的安全性が重視される背景
組織の拡大による風通しの悪さ
組織・チームが大きく成長すると上下関係や縦割りが生じ、発言しにくい状態になりかねません。さらに、声の大きさが発言権を左右するなど、風通しの悪さが生まれやすいといえるでしょう。そこでは、力を持つ者が議論を誘導するといった弊害が考えられます。
たとえば、疑問に対して「そんなことも理解できないのか」と非難したり、自分の考えと異なる部下の意見を「未熟な考えだ」と遮ったりといった状況です。その結果、意見交換ができなくなってしまいかねません。
スピード重視で議論が疎かになりやすい
ビジネスの現場ではタイムイズマネーということで、クイックレスポンス、スピード感のある業務が重視されると、議論が疎かになる可能性があります。考えるよりも行動するといえば聞こえはよいですが、そのため必要な意見や報告ができなくなるリスクがある点には注意が必要です。
だらだらと無駄な会議をする風潮を改めることは重要ですが、結論を急ぐあまり大事な話ができない状態になってしまっては困ります。
嫌なことに蓋をする組織の存在
心理的安全性が重視される背景には、嫌なことや都合の悪いことを聞きたくない、だから発言させないといった組織や上司の存在があります。うまくいっている話だけを聞いていれば心地よいでしょう。嫌な話や都合の悪い話をするメンバーを疎ましい存在だと感じたり、彼らの話を遮ったり、叱責したりしていれば、そのうち誰も本音で話さなくなってしまいかねません。
それが問題の先送りにつながり、深刻化につながってしまうことを考えれば、心理的安全性の重要視は必然といえるでしょう。
心理的安全性を高めるメリット
組織に活気が生まれる
心理的安全性が高くなれば、組織・チーム内のコミュニケーションがとりやすくなり活気が生まれます。「これを話せばマイナスの評価をされるのではないか」とか「どうせ話を聞いてもらえないだろう」などと考える必要がないためです。常識的な範囲であれば何を喋っても不利益にならないという安心感があることで、各メンバーの気分が明るくなります。
組織に活気が生まれれば、単に職場の雰囲気が明るくなるだけではありません。率直な意見が飛び交うことで、たとえば抱えている問題についてさまざまな視点で考えることが可能になります。さらに、建設的な話し合いができるチームでは、新しいアイディアを考える励みにもなるでしょう。アイディアを出し合い、それについて思うことを話し合うことで、よりよい結果につながりやすくなります。
エンゲージメントの向上
リスクを考えずに自由に率直な発言ができることで、メンバーは前向きな気持ちになれます。誰からも発言を否定されることがない環境では、人間関係の悩みも少ないといえるでしょう。もちろん、話して終わりではただの無駄話と同じになってしまうため、仕事に活かされることが大前提です。自分の発言によって仕事が捗る、成果につながるとなれば、従業員エンゲージメントが向上します。
従業員エンゲージメントが向上すれば、チームのメンバーとして積極的な貢献を行う意欲が増し、離職率が低下するでしょう。各メンバーの個人的なパフォーマンスの向上だけでなく、メンバー間の協力体制ができあがる点も大きなメリットです。その結果、業務効率のアップや業績の向上も期待できます。
リスクを未然に防げる
心理的安全性が高ければ、さまざまな意見を拾うことが可能です。心理的安全性が重視される背景のひとつに、嫌なことを聞きたくない組織・上司の存在がありました。よい話しか聞かない、発言させないとなれば、報連相が機能せずに改善すべき問題点が隠れてしまいます。ミスを犯したときに責められるのを回避するために報告が遅れたり、隠蔽を図ったりといった事態が起こりかねません。
心理的安全性を高め、些細な問題であっても逃さずに拾い集めることで、企業にとって致命傷ともなりかねないリスクを未然に防ぐことが可能です。その際、対策についての意見交換も重要となります。
リスクの低下は、問題の早期発見だけではありません。コミュニケーションが活発化することで、相談や質問が当たり前にできるようになり、問題が起きにくい状況を作れる点も見逃せないでしょう。
心理的安全性のつくりかたのポイント
4つの不安要素を取り除く
心理的安全性をつくるにあたってポイントとなるのが、不安要素を取り除くことです。不安要素とは、立場の弱いメンバーが組織・チーム内で発言する、意見を述べる際に感じるもので、主に4つあります。
・無知と切り捨てられることへの不安
わからないことを質問したいと思ったとき「こんなことも知らないのか」「無知な奴だ」と切り捨てられることに対する不安です。この不安を抱えていると「いまさら聞けない」と諦めてしまい、わからないまま仕事を進めてしまうことになりかねません。質問には丁寧かつ明確に回答する必要があります。
・能力が低いと評価されることへの不安
結果が出なかったときやミスが発生したときに「こんなこともできないのか」「大きな仕事は任せられない」「処分を検討しよう」といった評価をされることへの不安です。報告を躊躇うなど、問題の発見が遅れる恐れがあります。責めるよりも解決を優先する姿勢が重要です。
・仕事の邪魔だと思われることへの不安
他のメンバーの意見と異なる意見を述べることで「邪魔をしている」と思われることに対する不安です。また、自分の仕事が予定通り進んでいない場合に「応援を要請すると邪魔になるのではないか」と考えるケースもあります。消極的な姿勢につながってしまう不安です。表情も含めて発言を歓迎する姿勢が求められます。
・考え方が後ろ向きだと思われることへの不安
他のメンバーのアイディアに対する疑問や問題点を示すことが「ネガティブな奴だ」と思われるのではないかといった不安です。貴重な意見が埋もれてしまう恐れがあるため、積極的に意見を求める姿勢が重要といえるでしょう。
現状を正しく把握する
心理的安全性をつくるといっても、実際の状況がわからないことには効果的につくれないでしょう。そのため、現状を正しく把握することが重要です。つくった後の検証も含めて、前述の不安要素を踏まえた一覧形式のアンケート調査が有効です。
エドモンドソン教授は、心理的安全性の状況を知るために以下の7つの質問を使っています。
- 1.チームの中でミスをすると、たいてい非難される。
- 2.チームのメンバーは、課題や難しい問題を指摘し合える。
- 3.チームのメンバーは、自分と異なるということを理由に、他者を拒絶することがある。
- 4.チームに対してリスクのある行動をしても安全である。
- 5.チームの他のメンバーに助けを求めることは難しい。
- 6.チームメンバーは誰も、自分の仕事を意図的におとしめるような行動をしない。
- 7.チームメンバーと仕事をするとき、自分のスキルと才能が尊重され、活かされていると感じる。
出典:Google re:Work『「効果的なチームとは何か」を知る』
心理的安全性のつくりかたの具体策
基本的な人間関係を重視する
心理的安全性は人間関係の一部ともいえるため、組織人やチームメンバーである前に、基本的な人間関係を重視、構築する必要があります。つまり、立場に関係なく挨拶をキチンとする、相手の発言を遮らない、忙しいからといってそっけない態度を取らないなど、当たり前ともいえる接し方を定着させることが重要です。
仮に発言内容が自分の意見と異なるとしても、最後までキチンと聞いて議論することが求められます。自分のほうが上の立場だったとしても、抑えつけるような話し方は厳禁です。
発言の機会を保証する
自由に発言してよいといっても、初めから全員が活発に意見を述べるとは限りません。その時点での上下関係や個人の性格などが影響する可能性もあるため、会議などの場では意識して全員の発言機会を保証することが重要です。最初は1人最低1回発言してもらうなどの工夫も必要でしょう。また、上司は日ごろから必要に応じて意見を聞く姿勢を見せておく必要があります。
1on1を実施する
あらゆるシーンで意見を出せるメンバーであれば問題はありませんが、大勢の前では意見を述べることが苦手な部下がチームにいる可能性があります。指名して意見を求めてもうまく話せないケースが考えられるでしょう。また、会議の席では時間切れで話せなかったことがあるかもしれません。さらに、人に聞かれたくない話も考慮すれば、1on1ミーティングの実施が効果的です。
目標や価値観の共有
意見を求める前には、各メンバーが何のために意見を出す必要があるのかを認識していることが重要です。経営理念やビジョンといった大枠は当然として、部署やプロジェクトの目標、目の前の業務の目的、そのタイミングで解決すべき課題などを正しくチームのメンバーで共有し、関連する意見が必要であることを周知します。話すべきことが明確になれば、不安が払拭され発言意欲を生むとともに、その内容の正確性につながるでしょう。
発言のインセンティブを高める
心理的安全性が高ければ、不安感から発言を控えるといったケースは少なくなります。そして、よいアイディアを持っているメンバーの発言意欲は高まるでしょう。しかし、誰もがよいアイディアを持っているとは限りません。また、話したいこと、話さなければならないことがないと思っているメンバーもいるでしょう。
とくに話すことがないと考えるメンバーが多く、それが主流になってしまうと心理的安全性を高めるメリットが半減してしまいます。そこで重要となるのがインセンティブの導入です。発言に好意的な反応を示すことで、もっとよい意見を出そうという気持ちが引き出せます。また、積極的な発言や内容によって査定をよくしたり、報奨を出したりすることで、消極的な姿勢を変える助けとなり、活発な議論を生むことが可能です。
メンバーを入れ替える
人間関係で重要なポイントに相性の問題があります。正しいとか間違っているということではなく、「この人がいると意見を出したくない」「この人の話は聞くのも嫌だ」といった相性の問題だけは理屈では解決できないケースが少なくありません。表面的には問題ないように振舞っていても、悪いほうに影響している可能性はあります。相性問題が発覚し、無視できないレベルになれば、人事異動によってメンバーを入れ替えることも考える必要があります。
心理的安全性のつくりかたにおける注意点
自由な発言にも規律が必要
発言には責任が伴います。心理的安全性によって発言することに不安がなくなったとしても、好き勝手に放言してよいわけではない点に注意が必要です。ほとんどのメンバーが弁えているとしても、そうではないメンバーがいるかもしれません。最低限の規律を守ったうえで意見を述べあうマネジメント、心理的安全性づくりが重要です。
仲良しグループではない
お互いを尊重した活発なコミュニケーションが明るいチームづくりに役立ちます。とはいえ、チームのメンバー間にあるのは仕事を進めるうえの関係性です。心理的安全性はあくまでも業務のためにつくるものであって、業務効率を下げてしまうような仲良しグループにならないように注意する必要があります。上司と部下の役割を踏まえたうえでの責任感や、よい意味での緊張感は必要です。
チームの雰囲気に気を配る
会議などで活発に発言が出ると、心理的安全性づくりが成功しているように感じることでしょう。しかし、可能性は低くても表面的なものになってしまっている可能性がある点に注意が必要です。「会社や上司は自由に発言するように求めるけれど、ここまででやめておこう」とか、「ポーズだけ合わせておこう」といった空気があるかもしれないため、実践にあたってはしっかりと気を配って観察する必要があります。
これからの組織は心理的安全性を重視した運営を
心理的安全性は組織・チーム内の活発な意見交換や、情報の共有と活用に欠かせない要素だといえます。目標に向かってアイディアを出し合うとともに、疑問点の解消や課題の解決を促進するだけでなく、メンバーのエンゲージメントにも寄与するなどメリットは大きいといえるでしょう。
これからの組織は、製造業やサービス業などの業種にかかわらず、心理的安全性を重視した運営が求められます。
関連記事
-
健康経営で従業員の活力をアップしよう!企業が行うべき対策とは?
健康経営
2021.05.31
-
健康経営
2021.03.30