瞑想空間がホテル滞在を変える。
(MU)ROOM
- デザイン本部 未来創造研究所
- 齋藤 直輝
- デザイン本部 未来創造研究所
- 安久 尚登
- ビジネスソリューション本部プロジェクトオーナー
- 金子 司
- テクノロジー本部
- 森田 幸弘
- マニュファクチャリングイノベーション本部
- 田端 大助
- アプライアンス社 事業開発センター ミスト事業推進室
- 尾形 雄司
あるホテルの客室に用意された瞑想空間、(MU)ROOM(ムルーム)。ストレス社会においてホテルの客室ではどのような時間の過ごし方が求められるのか。様々な可能性を検討していく中で、パナソニックは“瞑想空間”に新しい事業の可能性を見出した。なぜ瞑想というテーマを選んだのか。精神的な世界に対してテクノロジーはどうアプローチしていったのか。数年間に及ぶ (MU)ROOM開発プロジェクトの全貌を紹介する。
何もないからこそ、自分と向き合う。
「無のroom」というコンセプト。
パナソニックが瞑想?なぜ心に焦点をあてるのか?(MU)ROOMプロジェクトについて初めて聞いたとき、誰もが思い浮かぶ疑問だろう。心の豊かさや健やかさが求められる時代、瞑想を体験したいというニーズはあるかもしれない。しかし「瞑想」という、テクノロジーが足を踏み入れたことのない世界をどのように価値にしていくのか。(MU)ROOMプロジェクトメンバーは、開発をスタートさせる前に何度も話し合いを重ね、瞑想空間のコンセプトを固めていった。

- 金子:
- 私たちビジネスソリューション本部(以下、BS本部)は、パナソニックの様々な技術を掛け合わせ、他社との協業により新たなビジネス創出を行う本社組織です。その中でこのプロジェクトは我々自身がこれからの宿泊のあり方自体に目を向け、社会課題解決に繋がるビジネスモデル起点で発想する初の取組みとして2019年に始まりました。その際、今後も変わらない価値ある宿泊=“そこでないと体験できない特別な宿泊”とはどの様なものがあるか、そのアイデアを求め当社デザイン部門にある未来創造研究所(以下、未来創研)にプロジェクトへ参画を依頼しました。

- 齋藤:
- BS本部から依頼を受け、未来創研内部でワークショップを行い、そこから出てきた複数のアイデアをBS本部と共にそれぞれに時間をかけて検討を繰り返しました。その中で当初、瞑想はそれらアイデアの1つに過ぎませんでした。IoTや映像などの技術を駆使して疑似体験型の宿泊はどうかという案もありましたが、新規性に乏しく設備にも費用がかかり、事業化への壁が見えていました。みんなで頭を悩ませていたとき、「いっそのこと全部なくして、無の空間をコンセプトにしたらどうなるだろう。」と真逆の考えが浮かびました。多くの人は、ホテルにチェックインした後、部屋で暇を持て余し、何も考えずテレビや映画やネットなど与えられる情報をただ選択して享受するだけ。多くの人がストレスや不安を感じる世の中で、ホテルの居室を無の空間にする事で、自分の心と向き合うことができるのではないか。このコンセプトを発見したことがプロジェクトのブレークスルーとなったのです。
- 金子:
- いきなり何もない空間に案内されて、自分と向き合って下さいと言われても困ってしまいますよね。そこで自分と向き合う手段として、多くの論文とメソッドが確立されている瞑想に着目。そこにパナソニックの技術を使って、初めての方でも簡単に瞑想へと誘う空間づくりと、正しく瞑想が出来たかをスコア化する事はできないか。そんな思いで齋藤を中心とした創研メンバーとコンセプトを固めた上で、それを実現する社内・外の技術や知見を探し集めるというアプローチをとりました。
コンセプトをエンビデンスへ。
瞑想を生理データとして可視化した。
瞑想空間を実現するためには、そもそも本当に瞑想ができているのかを科学的根拠に基づいて評価できなければならない。しかし人はどのような状態になったら瞑想していると言えるのか。果たして瞑想しているとき、人はどのような状態になるのだろうか。未来創研の齋藤は、瞑想状態を可視化するにはどうすればいいかを考え続けた。瞑想のエビデンスを揃える。そのためにはできるだけ数多くの「瞑想を会得した熟練者」から、瞑想中の生理的な状態をデータとして集める必要がある。エビデンスがないものをテクノロジーで実現することもできない。齋藤はプロジェクトの協力者を探すために奔走した。

- 齋藤:
- 仏教の一部では修練の一つとして瞑想があり、熟練者であれば瞑想状態をしっかりと自覚できることもわかりました。そこで、瞑想について長年研究されてきた京都大学の藤野助教にご協力をお願いし、フェイスブックを通して、全国の瞑想熟練者に実験への参加を呼びかけていただきました。同時に、人のストレス値を計測する研究を大阪大学と連携して進めてきたテクノロジー本部の森田に連絡をとりました。

- 森田:
- 私は国家プロジェクト(大阪大学COI拠点)に参画し、心身の状態を計測する研究に8年間取り組んできました。ですので、これまで蓄積したノウハウが活かされ、社会に実装される日がついにきたことにワクワクしました。京都大学の藤野助教の呼びかけで平均して5000時間を超える瞑想経験をもつ熟練者十数名に集まっていただき、瞑想中の生理データが計測できたことは、研究者としてもとても貴重な経験です。また、瞑想の計測データの精度を高めるため、心拍や呼吸の計測デバイスを開発するアフォードセンス社の協力を得て、その計測アルゴリズムを磨きあげるということも行いました。嬉しかったのは、瞑想の熟練者のみなさんが、パナソニックが瞑想の研究を進めることに強く共感してくださり、喜んで実験に参加してくださったことです。また、瞑想経験のない社員にも実験に参加してもらい、熟練者の結果と未経験者の結果を合わせて、瞑想のスコア化を検討しました。

事業的な観点からも瞑想の見える化は重要だと考えられた。一般の方には、瞑想がうまくできたかどうかを自覚することは難しい。ならば、瞑想体験をスコア化し「あなたの瞑想が何点だったか」を示せないか。森田は、生理的なエビデンスをもとに瞑想の達成度を精度高く判定する独自のアルゴリズムを開発した。このアルゴリズムは特許申請中だ。
ミスト・光・音・香り。
テクノロジーを使って、瞑想をサポートする空間。
どのようなテクノロジーを組み合わせれば、瞑想しやすい環境をつくり出せるか、誰もわかっていなかった。事業、デザイン、技術の全員が感覚を共有しなければならない。まずはパナソニック浜松町ビルの一角に、キューブ型の小さな試験空間がつくられた。その空間を開発の拠点として、微粒子ミスト、照明制御、ハイレゾ音源など、パナソニック独自の技術が集められ、(MU)ROOMの姿が少しずつ形になっていったのである。

- 安久:
- 瞑想は、姿勢を整え呼吸を観察していくことからはじまります。早稲田大学の熊野教授にお願いして、初心者でも瞑想をスムーズに始めるためのガイダンスを作成していただきました。そして、環境を制御し変化させることで、ゆるやかに日常の感覚を奪い、非日常の世界に誘うことを考えました。具体的には、瞑想に適した微細な変化と空間演出性を備えた照明装置や、聴覚を通して自然の中にいるような感覚を呼び覚ますためのハイレゾ空間音響など、テクノロジーの効果を試験空間で検証していきました。中でもパナソニックの微粒子ミスト技術と出会ったことは大きな収穫でした。

- 尾形:
- 私は事業部門で新規事業の立ち上げを担当しており、オリンピックパラリンピック東京大会に向けた暑さ対策としてミストソリューションの事業化を進めていました。その中で、微細なミストの空中に漂う特性を活かしたスモーク演出の可能性を探っていたときに、(MU)ROOMの話を伺いました。ミストが充満した空間では緩やかに視界が遮られるので、瞑想に誘うのに適しています。
我々のような部門が参加することで、技術部門の連携を図りながら、プロジェクトの事業化を検討していきたいと考えています。
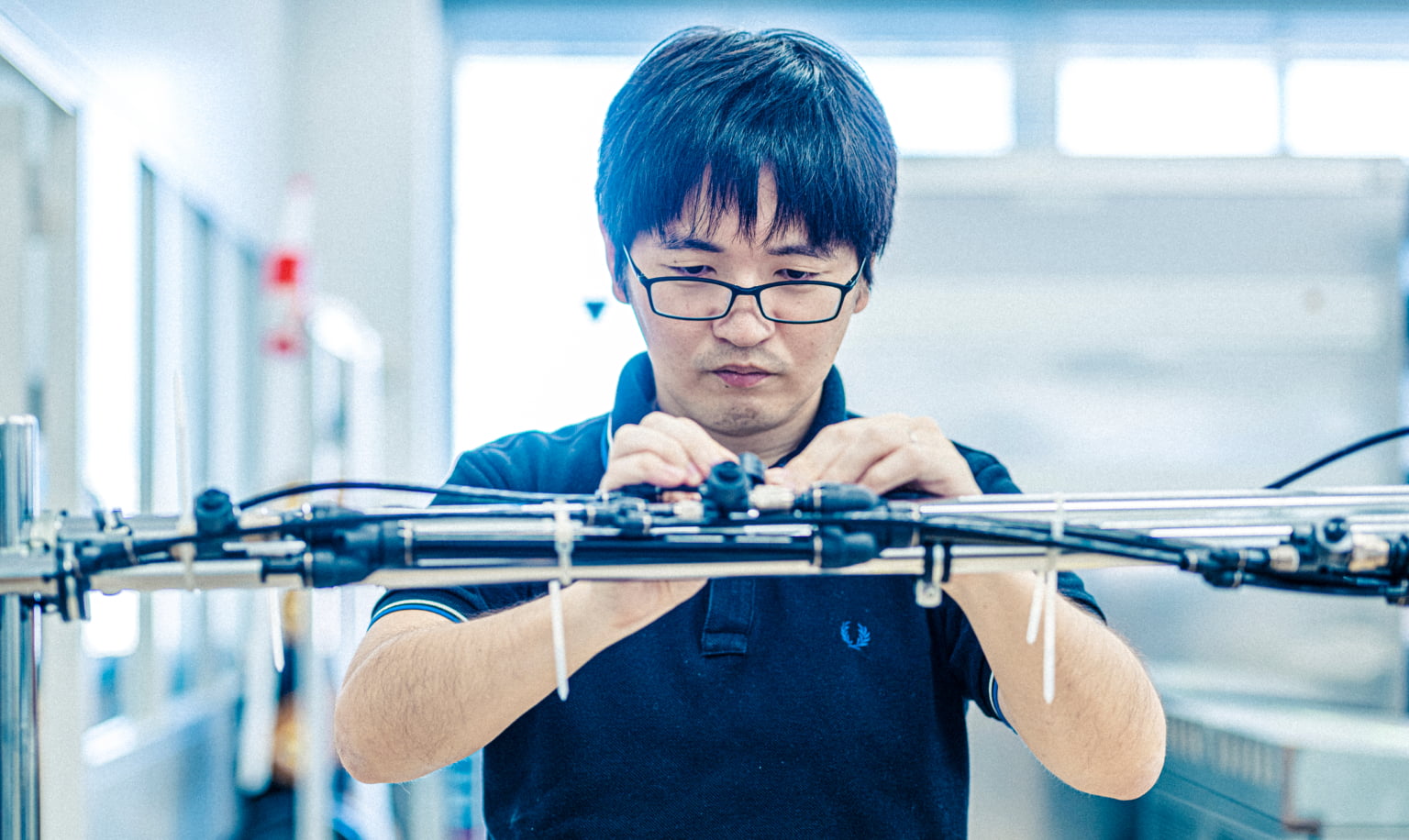
- 田端:
- 参加したきっかけは斎藤の熱意ですかね。話を聞くうちにマインドフルネスでのミスト活用に興味が沸いてきましたし、以前から空間や環境制御といった分野には注目していたこともあります。今回のプロジェクトでは、従来の開発で作成していたプロトタイプを参考にしながら、「瞑想」にふさわしいミストの発生と香りの制御について、斎藤と細かく調整しました。
明確なコンセプトのもとに開発を進め、ふだん接点のない技術部門間の連携が図れてたのは、これまでにない新たな取り組みでした。

齋藤が社内のさまざまな部署にアプローチをするなかで、ホテルアンテルーム京都(UDS株式会社)の紹介を受けた。ホテル側に (MU)ROOMの構想を伝えると、期間限定で1室改修した共同実証計画が合意された。アーティストが手掛ける客室を設置するなど、カルチャーやアートを積極的に取り入れるホテルのコンセプトと (MU)ROOMが合致したことが大きい。2021年3月からの2022年1月までの間、宿泊ゲストによるサービスとしての受容性評価、ホテル運営における導入メリットなどの評価を行っている。実際に体験したホテルのゲストからは、リラックスとも違う、爽やかですっきりした心持ちが得られるという声が上がっており、様々な業界関係者からの引き合いも多い。
- 齋藤:
- 瞑想は継続することで高い効果を生みます。今後は、ホテルと家を繋ぐ (MU)ROOMアプリを接点として、トータルな体験ブランディングを提供したいと考えています。また、瞑想の他にも新たなテーマで「くらしの豊かさを生み出す空間」を創り出そうと思います。
(MU)ROOMのプロジェクトが際立っているのは、未来創研というデザイン部門が新規事業開発部門と時間をかけてコンセプトと事業化の方向性を練り上げていることだ。何がやりたいのか。そのためには誰のどんな力が必要なのか。明確なメッセージは、社内外の人たちを巻き込みながら、大きな推進力となっていく。瞑想のように未知なる領域を切り開くためには、デザインコンサルティングの役割は重要になってくるだろう。

Share the Project