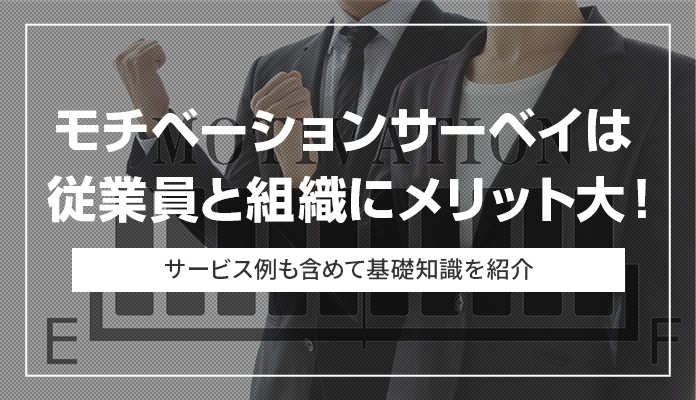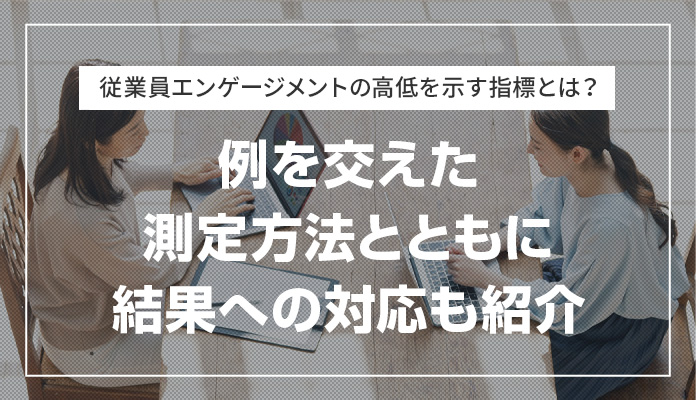職場改善
2022.4.29
リテンションマネジメントとは? 離職を防止して人材を確保する具体的事例も含めて徹底解説!
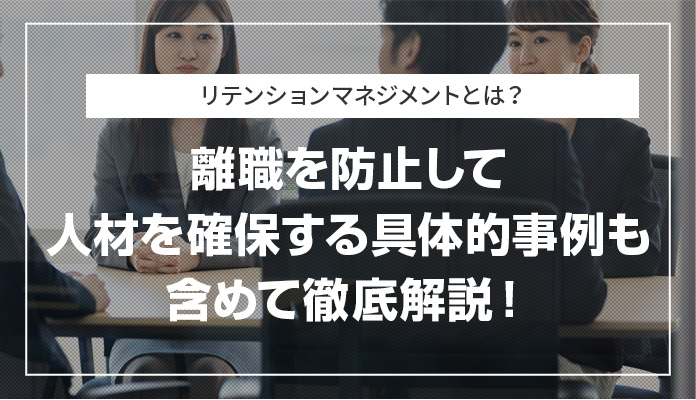
リテンションマネジメントは人材が流動化している昨今において、人材確保に必要な取り組みとなっています。少子高齢化社会で働き方が多様化している中で、貴重な社員をつなぎとめるためには何が必要なのでしょうか。
当記事では、リテンションマネジメントに取り組むことで得られるメリットや各種施策などの基礎知識を解説するとともに、個別の事例を紹介しています。
人材確保に役立つリテンションマネジメント
人事分野でリテンションといえば人材確保
リテンション(retention)には保有や維持、引き留めなどの意味があり、人事分野で使う場合の対象は人材です。つまり、リテンションは人材を流出させないこと、確保することを意味しています。リテンションマネジメントは、人材確保のために実施される取り組み全般を指す言葉であり、現代の企業にとって注目すべきワードのひとつです。
リテンションマネジメントの効果は離職率で測れる
リテンションマネジメントを行っている企業にとって、効果の確認は欠かせません。代表的な効果の確認手段が離職率のチェックです。離職イコール人材の流出であることから、離職率が高ければリテンションマネジメントの効果が否定されます。逆に低ければ引き留めに成功している可能性が高いと考えて差し支えないでしょう。
可能性にとどまっているのは、離職にまでは至っていないものの離職を考えている従業員が多いケースが考えられるためです。単に離職率が低いだけでは、必ずしもリテンションマネジメントが成功しているとは断定できません。より精度の高い検証を行うためには、後述する各種サーベイなどの実施が望ましいといえます。
確保したい人材の定義は企業次第
リテンションマネジメントで確保する人材の範囲は企業によって異なります。自社にとって必要不可欠な人材の定義が企業によって異なるためです。そこでリテンションマネジメントの対象とする人材の範囲が問題となります。
従業員を1人も減らしたくないと考えるのか、特定のスキルの持ち主など、一部の優秀な人材に絞って流出防止を考えるのかによって、実施する施策や企業の負担が変わってくるでしょう。確保対象の人材とそれ以外の従業員とでインセンティブに差を設けるなどが好例です。ただし、露骨な待遇差を設けると会社に対する不信感を生み出す懸念があります。
リテンションマネジメントが必要になる理由と背景
少子高齢化による人材不足
少子高齢化社会の到来により、そもそもの労働力が不足しているといわれています。個別の事情では異なる部分があるものの、全体的に見ると各企業が人材の争奪戦を繰り広げている状況です。求人を出しても入社を希望する応募者が集まらないといった採用活動の困難さが指摘されている中で優秀な人材が流出した場合、補充が困難になることは容易に想像できます。
新規採用が困難な以上、自社の業務に精通しており戦力として活躍している貴重な人材を失うわけにはいきません。そこで注目されているのがリテンションマネジメントです。
年功序列と終身雇用制度の崩壊
年功序列型の賃金体系と昇進環境、終身雇用による経済的な安定がほぼ崩壊したことにより、現在の日本において同じ企業に継続勤務することが当たり前とはいえなくなっています。転職へのハードルが低くなっており、ヘッドハンティングに限らず、より好待遇の職場や自分を活かせる仕事を求めて転職を考え、実行する人材は増える一方です。
さらに、人材と企業のマッチングを支援する転職サイトや転職エージェントなどのサービスが拡大しており、各企業にとっては人材流出を招きやすい社会になっているといえます。
一方、流出があってもマッチングサービスなどの活用による採用で挽回できるのではないかとの考えもあるでしょう。しかし、人材の絶対数が少なくなっている以上、流出を招く企業が希望するマッチングを実現できる可能性が高いとはいえない問題があります。
多様化する働き方
現代社会は多様な価値観が共存する社会であり、働き方においても多様化が進み、働き方改革が叫ばれている状況です。全員が同じ時間に同じ職場に出勤し、昼休みも一斉にとり、退勤時間も一律で、下手をすればサービス残業まで横並びといった従来型の働き方だけでは人材確保が難しくなっています。企業にとって、多様化する働き方の要望に対応することが急務です。
現代の若者に見える傾向
転職が一般的な事象となっており、企業にとって人材の確保が困難になっているといっても、実際の傾向がどうなのかが気になるところです。
厚生労働省が公表している平成30年の調査データ(※1)によれば、若年労働者(15~34歳)が最初の企業に勤務している割合は50.9%しかありません。約半数が34歳までに転職を経験しているか、少なくとも最初の企業を辞めているという事実を示したものです。辞めるまでの勤続期間では3年未満が63.2%となっており、短期間での離職が多いこともわかります。
また、社歴が浅い人の離職理由では条件面の不満が多いのに対し、勤続期間が10年以上と長くなると結婚・子育てが離職理由のトップに来る点に注目です。
少し古いですが、平成21年の調査(※2)によると若年労働者の24.9%が現職で最後まで勤務するのではなく転職したいと思っているなど、リテンションマネジメントの重要性が感じられます。
出典 ※1:平成30年若年者雇用実態調査結果の概況(これまでの就業状況)
出典 ※2:平成21年若年者雇用実態調査結果の概況(現在の就業状況)
リテンションマネジメントのメリットは多数
採用と教育のコスト削減
リテンションマネジメントの目的は人材の確保です。リテンションマネジメントが成功して人材確保を達成すれば、さまざまなメリットが生まれます。そのひとつが、コストの削減です。
人材の確保に成功すれば、欠員が生じにくくなります。その結果、補充のための新規採用コストを抑えられる点が大きなメリットです。また、採用の度に必要となる教育コストも抑えられます。
業務の継続性確保
多くの人材が長い期間にわたって勤務する職場では、人の入れ替わりを最小限に抑えることができます。メンバーが頻繁に入れ替わる状況では、引継ぎの負担が増え、ミスが起きやすくなるでしょう。
しかし、リテンションマネジメントが効果を発揮して、お互いに業務に習熟しているメンバーによって構成される職場なら安定感が違います。無理なく業務の継続性を確保できる点が大きなメリットです。
また、人材の入れ替わりを考慮する必要性がなければ、長期の計画を立案しやすい点もメリットとなります。
経験豊富な人材による競争力アップが見込める
リテンションマネジメントによって人材確保が成功し、経験豊富な人材が多くなることで業務効率のアップ・生産性の向上が見込めます。職場による違いはあるものの、個々に蓄積したノウハウや習得した技術が活かされることは間違いないでしょう。その集合体である企業としての競争力アップも期待できます。
対外的なイメージアップにつながる
従業員の定着率の高さは、外部の評価と無関係ではありません。離職率が低く人材が育っている企業は優良企業とのイメージにつながります。「人材が辞めない企業」は「働いてみたい企業」となって、人材の採用にも好結果をもたらす期待大です。
さらに、一般社会における企業イメージがアップすれば、顧客からの信頼獲得にもつながり、業績アップが見込めます。
従業員エンゲージメントを高める要素になる
リテンションマネジメントによって人材が流出しない企業になることは、従業員から見れば働き続けたい企業になることです。つまり、実施する施策はやる気のある従業員にとってプラスとなるものでなければなりません。プラスの施策が実施され、従業員が恩恵を感じられるようになれば、従業員エンゲージメントを高めることが可能です。
従業員エンゲージメントが高い企業になれば、全社一丸となって目標に突き進む状況が生まれやすく、企業の将来性がさらにアップすることも大きなメリットだといえます。
リテンションマネジメントの実施や改善が急務となる企業とは?
離職率が高いか高くなり始めている
これまで見てきたように、現代の企業にとってリテンションマネジメントは避けて通れないものだといえます。リテンションマネジメントを早急に実施するべき企業、実施しているものの効果が見られず改善が急務となる企業の代表的なパターンは3つです。
まず、離職率が高いか上昇傾向にある企業はリテンションマネジメントをしっかりと実施するべきだといえるでしょう。離職率が高い理由として考えられるのが、企業そのものや仕事内容に魅力がない、待遇が悪い、上司が嫌いといった不満を抱えている従業員が少なくない点です。これらの課題が存在する可能性は大であり、早急にリテンションマネジメントを行わなければ、事態はもっと悪化する恐れがあります。
ただし、離職率は従業員の実数によって振れ幅に差があるため、少人数の企業では必ずしも課題を示すものとはいい切れない面がある点に注意が必要です。とはいえ、人材が辞めてしまう理由は把握しておく必要があります。
募集しても人が集まらない
募集しても人が集まらないケースでは、積極的に働きたいと思える魅力が他社に比べて少ないことが考えられます。外から見て魅力が少なければ、内部の人材も同じように感じている可能性は小さくないでしょう。現時点で人材の流出がなかったとしても、やがては離職率のアップにつながる恐れがあります。
また、単に外部への伝え方が下手なだけで人材の流出が少なかったとしても、人が入らない企業が先細りになる恐れはなくなりません。リテンションマネジメントは新規採用にも好影響を与えるものであり、早めに取り組んだほうが良いといえます。
会社の体制や取り巻く環境が大きく変わった
組織では各部の構成や雇用形態の多様化、人事その他の制度に加えて組織を取り巻く社会環境の大きな変化などがあると、それまでなかった不満が生じる可能性があります。思い当たる部分があるなら、早期の課題把握と解決のためにもリテンションマネジメントが急務です。
施策の実施前に確認しておくべき自社の状況
各種サーベイの活用
リテンションマネジメントを導入するにしても、自社に存在する課題とその背景がわからなければ有効な対策が打ちにくいため、まずは自社の状況を確認することが重要です。各種サーベイを活用することで、自社が抱えるさまざまな課題が浮かび上がってきます。
離職率が高いとか、従業員から不満の声が聞こえてくるといった場合でも、その他の問題も含めてより正確な状況を把握するために、各種サーベイの活用が有効です。
各種サーベイにはパルスサーベイやエンゲージメントサーベイ、モチベーションサーベイ、組織サーベイなどさまざまな種類があります。ただし、サーベイの名称が重要というわけではありません。名称によってサーベイの内容が異なるものの、重なる部分がある点や公的な区分けがあるわけではない点に注意が必要です。
したがって、コンサルティング会社などが提供しているサーベイサービスを利用する場合は、名称だけでなくサービス内容をしっかりと確認する必要があります。納得できるまで説明を受けて、自社にマッチすると思えるサービスを選択しましょう。
従業員アンケート
各種サーベイを利用しない場合や、時期的に間が開いている場合などでは従業員アンケートの実施も有効な手段のひとつです。設問を含めて有効なアンケートの実施方法に不案内な場合は、サーベイツールの活用が選択肢となります。また、良い機会だと捉えて、コンサルティング会社が提供する一貫したサーベイサービスを検討しても良いでしょう。各種サーベイにおいても、従業員への調査部分は主としてアンケートを用いて行います。
引き留めが可能な離職といえば、一般的には待遇や職場環境、その他に対する不満が要因です。従業員個人のプライベートに関する原因の場合は引き留めが難しいといえるため、アンケート調査の内容としてはES(従業員満足度調査)が妥当といえます。
結果分析
各種サーベイサービスでも独自のアンケートでも、従業員に調査しただけでは課題が明確になりません。集計した結果を分析し、評価をすることで自社の課題が明確になります。この課題の明確化こそが、リテンションマネジメントの第一歩といえる作業です。分析と評価を正しく行うことで、より効果的なリテンションマネジメントの実施が可能となります。
リテンションマネジメントで重要となる施策
当事者意識の自然な強化
アンケートの分析によって浮かんだ課題に従業員の当事者意識の希薄さがある場合、考えられるリテンションマネジメントの施策のひとつが経営理念やビジョンを浸透させることです。経営理念やビジョンが浸透していなければ、自社で目標に向かって仕事をする意識が希薄になってしまうのは仕方がないことだといえます。その結果、転職を考えるということになりかねません。
経営理念やビジョンを浸透させるためには、情報の積極的な開示に加え、トップが語りかけたり、経営理念やビジョンを目に付く場所に掲示したりといった方法が有効です。
待遇改善
「これだけ働いて貢献している割に給料が少ない」といった待遇面への不満がある場合、その不満が正当な根拠に基づくものかどうかを検討する必要があります。正当な不満に対しては、適正な報酬で報いることが重要です。固定の給与だけでなく、賞与やインセンティブによる待遇改善も検討しましょう。
報酬体系が明確になっていない場合は不満を生みやすいといえます。体系を明確にして、不公平のない運用を行うことが重要です。
金銭面以外の待遇に関しても基本は同様です。不満が根拠のないものであれば、現状の待遇が悪いわけではないことを理解してもらう必要があります。
人事評価制度の整備
人が人を評価する以上、ばらつきや恣意的な評価の疑いをもたれることがあります。そこで重要となるのが人事評価制度の明確化と周知徹底です。何をしてどうなれば高く評価されるのか、昇進の基準は何かといったことがハッキリしており、確実に運用されていれば不満が出ることも少ないといえます。また、個人の成長に伴うキャリアプランを描く道筋を示すことが重要です。
同時に、1人の上司が部下を査定する形式ではなく、複数の目で見た評価を導入することも一案となります。上司だけでなく、同僚からの評価や、場合によっては部下からの評価も効果的です。
職場環境の改善
人が集まれば人間関係の軋轢や、コミュニケーションの過不足といった問題が生じる可能性があります。また、仕事場の衛生状態や窮屈さなど物理的な意味での職場環境が課題となる可能性も少なくありません。ちょっとしたことが大きな不満へとつながりかねないため、職場環境については細かくチェックし、総合的に改善することが重要となります。
上司のマネジメント能力向上
上司が適切なマネジメントを行っていれば、人材の有効活用が進み、従業員本人の充実感にもつながります。その逆に、上司のマネジメントがまずかったり、上司に不満があったりすると退職を選択する可能性が高くなりやすいでしょう。
マネジメントの失敗は能力と業務内容のミスマッチや、仕事への意欲低下を招きかねません。また、日常的に直接指示・命令を受け、第一に報告・連絡・相談をする相手である上司への不満は、会社へ来ること自体を憂鬱にさせかねない要因となり得ます。1on1のミーティングを導入しても、嫌な上司では逆効果になりかねません。
リテンションマネジメントにおいて、上下関係を前提として部下に接する上司の、マネジメント能力の向上は重要なポイントです。管理職向け社内研修の充実などの施策が望まれます。
福利厚生の充実
近年は福利厚生の内容で企業を選ぶという求職者が珍しくありません。そのため、福利厚生の充実に力を入れている企業が増えているといわれています。リテンションマネジメントにおいても、福利厚生の充実が有効です。
福利厚生には健康保険や厚生年金などに代表される法定福利厚生と、企業が任意に用意する法定外福利厚生の2種類があります。法定分は適用企業には欠かせないものであり、差が付くのは法定外の部分です。企業によって各種手当や社宅、特別休暇や保養所など多種多様な内容となっています。自社に必要な福利厚生を考えて実施することが、リテンションマネジメントの有効施策です。
また、健康な働き方が注目されている現在では、経営面から従業員の健康に積極的に投資する健康経営も含めて福利厚生を考えるべきだといえます。
ワークライフバランスの重視
核家族化と夫婦共働きが進んだことによる子育てや家事と仕事の両立問題や、高齢化社会となって介護と仕事の両立問題が広がっています。また、地域での活動や自己啓発など自分の時間を確保したいニーズの高まりなど、変革する社会と従来型の働き方の間に生じた大きなズレの解消が社会全体の課題です。こうした状況の中にあって、ワークライフバランスを考慮した働き方の多様化への対応が企業にとって急務となっています。
実施事例
新規学卒者指導員制度~カネテツデリカフーズ株式会社
新人を十分な教育のないまま職務に就かせることで離職率が高くなっていたカネテツデリカフーズ株式会社では、研修を充実させることで離職率の大幅な低下を実現しています。「新規学卒者指導員制度」による6ヶ月間のマンツーマンフォローなど、全社的な取り組みが功を奏しました。
また、企業としては珍しい「家族参観」を採り入れるなど、企業風土の改善を進めています。当事者意識の強化や職場環境の改善、上司のマネジメント能力向上などに関する事例として参考になります。
支援ツールHR OnBoardの導入~株式会社鳥貴族ホールディングス
株式会社鳥貴族ホールディングスでは、人事による入社後フォローを強化することで入社後半年の時点における離職率の高さを大きく改善しています。人事部員がフォローのために店舗を訪問するに当たり、支援ツール「HR OnBoard」の導入が大きかったとのことです。
また、無断残業や休日出勤を禁止しており、上級店長で最高750万円の年収を得られるなど安心して働ける環境づくりも行っています。待遇面などの参考になる事例です。
働き方宣言制度~サイボウズ株式会社
サイボウズ株式会社では、従業員自らが何曜日はどこで何時から何時まで勤務するといった具合に勤務場所・勤務時間を決定する「働き方宣言制度」を実施しています。宣言する働き方に個人の事情を絡めることが可能な制度で、ワークライフバランスを考慮した施策の参考になる事例です。
同社ではコミュニケーションの活性化や評価などの制度とあわせて、離職率を大幅に改善させています。
リテンションマネジメントは自社の課題を知ることから始まる
リテンションマネジメントを効果的に実施することで、人材の確保ができるとともに、さまざまなメリットが生まれます。待遇や評価制度の改善、上司のマネジメント能力向上や福利厚生の充実など複数の施策がありますが、課題の有無に関係なく、すべてをより良いものにすれば完璧といえるでしょう。
とはいえ、費用対効果や実務の負担を考慮した場合、優先度の高いところから先に実施することが現実的です。そのためにも、自社の課題を知ることから始まるのがリテンションマネジメントだといえます。
関連記事
-
モチベーションサーベイは従業員と組織にメリット大! サービス例も含めて基礎知識を紹介
職場改善
2022.04.27
-
従業員エンゲージメントの高低を示す指標とは? 例を交えた測定方法とともに結果への対応も紹介
職場改善
2022.03.24