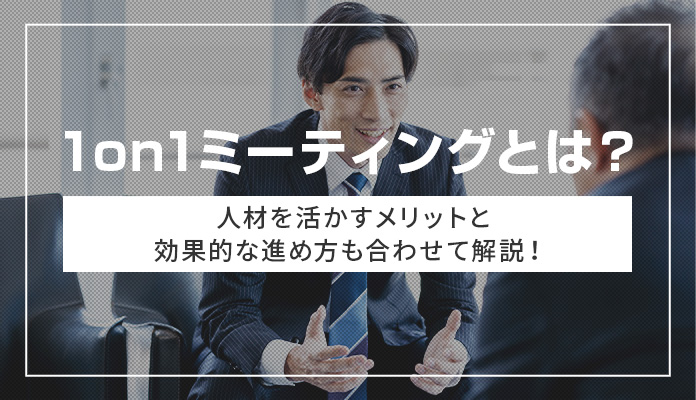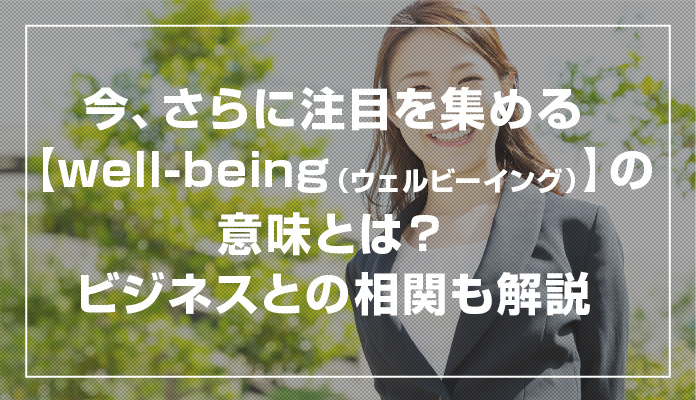ウェルビーイング
2022.11.08
【事例付き】ウェルビーイングの上手な使い方! 定義を理解して推進しよう
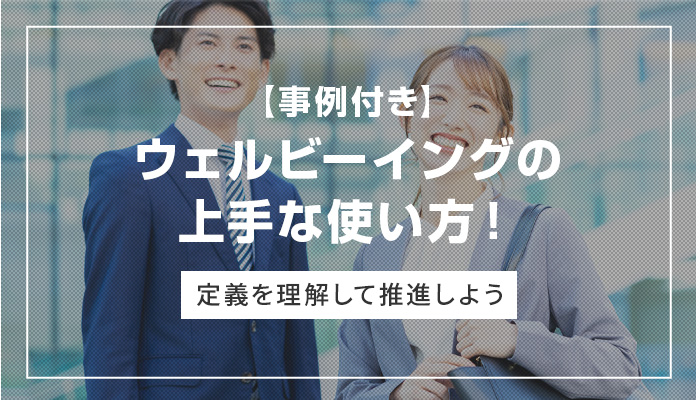
「ウェルビーイング(well-being)」とは、心身と社会的な健康を意味する概念のことです。働き方改革や新型コロナウイルス感染症の拡大により、「場所」や「時間」に捉われない働き方も定着し、企業のあり方や従業員のワークライフバランスへの関心が高まったことで「ウェルビーイング」が注目されています。
しかし、ウェルビーイングという言葉を見聞きしたことがあっても、いまいちどういう概念なのかや、使い方を理解できてないという企業担当者も多いことでしょう。そこで今回は、ウェルビーイングの定義から使い方が学べる企業の導入事例までを取り上げて紹介します。企業経営に取り入れるヒントになれば幸いです。
ウェルビーイングの使い方次第で働き方が変わる
日本でも認知され始めつつあるウェルビーイング。直訳すると、健康や福祉、幸福などを意味しますが、「ウェルビーイング」はハピネスのような瞬間的な幸せではなく、肉体や精神、社会的にも満たされた状態を意味します。
厚生労働省も「雇用政策研究会報告書 概要(案)」(※1)で『「ウェル・ビーイング」とは、個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念。』と定義づけしています。
※1 引用)厚生労働省:雇用政策研究会報告書 概要(案)
あわせて、ウェルビーイングの定義を考える際によく引用される、世界保健機関(WHO)憲章の一節も見ておきましょう。
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity
“健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが 満たされた状態にあることをいいます。”(※2)
※2 引用)日本WHO協会:健康の定義
そんなウェルビーイングが、なぜ今注目されているのか。それは、ウェルビーイングが企業への貢献意識や働きがいにつながると考えられているからです。
「World Happiness Report」(※3)の情報によると、日本は世界幸福度ランキング(2019〜2021)で54位に位置しています。世界の中では上位ではありますが、先進国だけに注目すると、残念ながら日本は最下位です。このデータから、日本には働きがいを感じている人が少ないことが伺えます。
※3 参考)World Happiness Report
そんな幸福度の低い日本ですが、企業や従業員がウェルビーイングを意識すると、
- ・幸福を前提に仕事に取り組めるため、自分が主体となって業務に専念できる
- ・自分だけでなく周囲の幸福や健康・快楽や不快に気づいたり、感じたりする力が身につく
このようなメリットを得ることができ、相手基準ではなく、自分基準で仕事に取り組めるため、受け身だった姿勢が能動的になり、仕事も主体的に専念できるようになります。
現在の日本では高齢化が進み、労働力人口の減少により労働力不足が深刻化しています。このような背景から、従業員一人ひとりの生産性を高めることが重要視されていますが、現代は仕事とプライベートとの両立を求められるようになってきている現状があります。
そのため、日本国内でもウェルビーイングの必要性が高まり、今後働き方も大きく変化していく可能性が考えられます。
次章では、ウェルビーイングを推進する上で理解しておきたい、ウェルビーイングを構成する主な要素5つについて解説します。
ウェルビーイングを構成する要素1:キャリアウェルビーイング
ウェルビーイングを構成する要素の1つ目が、キャリアに対する幸福度を表した「キャリアウェルビーイング(Career well-being)」です。
キャリアというと、仕事における出世や能力と捉えられがちですが、キャリアウェルビーイングでは私生活で費やすさまざまな時間も含めた総合的なキャリアの幸福度を指しています。
仕事としてのキャリアはもちろん、家事や育児、勉強などに費やす時間もキャリアとして捉えるということです。そのため、個人のウェルビーイングを高めるためには、仕事とプライベートの両方の幸福を構築することがポイントとなるでしょう。
ウェルビーイングを構成する要素2:ソーシャルウェルビーイング
ウェルビーイングを構成する2つ目の要素は、「ソーシャルウェルビーイング(Social well-being)」です。直訳すると「社会的な幸福」ですが、簡単にいうと人間関係に対する幸福ということになります。
ソーシャルウェルビーイングは、交友関係や交流の量だけではなく、信頼や愛情のある関係を築けているのかというところがポイントです。
ビジネスにおいては、同僚はもちろん、上司や部下、経営陣などとの関係において、「深い関係を結べているのか」「広い交友関係があるか」などが重要視されています。
ウェルビーイングを構成する要素3:フィナンシャルウェルビーイング
ウェルビーイングを構成する要素の3つ目が「フィナンシャルウェービング(Financial well-being)」です。経済的な幸福という意味になります。
「自分が満足できるだけの報酬が得られているか」ということに加え、「安定した生活を送るための資産の管理や運用をできているか」といった内容もフィナンシャルウェルビーイングに含まれます。
経済事情は、精神的な余裕にも影響しやすい部分です。経済的な不安があると、仕事や対人関係においてもマイナスな影響を与えてしまうため、「報酬を得られているか」「自己資産の管理ができているか」「報酬に納得しているか」などは、経済的な幸福を構築する上で重要なポイントとなるでしょう。
ウェルビーイングを構成する要素4:フィジカルウェルビーイング
ウェルビーイングを構築する4つ目の要素は、「フィジカルウェルビーイング(Physical well-being)」です。身体的・精神的な幸福度を指します。
健康でも、仕事や対人関係でストレスがあれば、それは幸福な状態とは言えません。自分がしたいと思う仕事や生活を不自由なく取り組める健康状態やエネルギーがある状態が望ましいとされています。
仕事や生活においては、ポジティブな感情を持って活動できるかというところも重要なポイントです。
心身ともに健康でエネルギーに保ち溢れていれば、仕事に対するモチベーションの向上が期待できるでしょう。
ウェルビーイングを構成する要素5:コミュニティウェルビーイング
ウェルビーイングを構成する要素の5つ目は、「コミュニティウェルビーイング(Community well-being)」です。
家族や親戚、所属部署やチームなどの小さなコミュニティから、職場や居住地などの地域社会における広いコミュニティまで、私たちは、生活する上でさまざまなコミュニティに属しています。
コミュニティウェルビーイングは、そんな自分の周りにある身近なコミュニティへの関わりや親密であるかということが、幸せを測る判断基準となります。ビジネスシーンにおいては、社内はもちろん、所属する組織やチームといった小さなコミュニティの形成がうまくいっているかなどが重要視されます。
ウェルビーイングを上手く使うために意識すべきこと
ここまで、ウェルビーイングを構成する5つの要素を見てきました。
ご覧いただいた通り、ウェルビーイングは、仕事やプライベートに限らず、体も心も健康で社会的にも良好な状態になって初めて達成できます。
現在、ワークライフバランスを意識した働き方改革が行われていますが、ビジネスシーンにおいてウェルビーイングを実現するには、「従業員の心身の健康」と「働きがい」のバランスを保つことが重要です。
どちらか一方だけを進めても、身体や精神に異常が生じたり、仕事に対する本質を見失って仕事をする意味を見出せなくなったりする可能性があるからです。
しかし、先述の通り、高齢化・少子化が進む日本は、労働人口が減少傾向にあります。個人の負担やストレスが大きくなりつつある中で、「従業員の心身の健康」と「働きがい」のバランスを保つためには、その限られた人材が能力を十分に発揮し、健康でやりがいを持って活躍する環境を整える必要があります。
具体的には、「労働環境」「オフィス環境」「従業員の健康管理」がポイントとなってきます。
どのような取り組みを行えば、ウェルビーイングの実現に近づけられるのか、次章以降でそれぞれ詳しく解説したいと思います。
ウェルビーイング実現のポイント1:労働環境を見直す
ウェルビーイングの実現に向けて、まず取り組みたいのが「労働環境の見直し」です。
近年は、働き方改革の一環で残業時間の上限が設けられるなど、これまで常態化していた長時間労働が是正されつつあります。また、感染症の拡大により、リモートワークや在宅勤務へシフトする企業も増え、柔軟な働き方ができるようになりました。
しかし、人手不足という状況は変わらず、「まだ長時間の残業をお願いせざるを得ない状況だ」という企業もあることでしょう。
もし、まだ長時間残業をしている状況があれば、まずは労働時間のモニタリングや勤務状況を確認する社内アンケートなどを実施し、実態を確認してから、自社の状況にあった施策をひとつずつ行うのがおすすめです。
また、それと同時に残業に対する意識改革も行いましょう。内閣府が行った意識調査(※4)によると、「上司は残業をしている人に対して高い評価をしている」と感じている人が多いという状況があるためです。
残業に対して、「頑張っている人」「責任感が強い人」といったポジティブなイメージを持つ傾向にあり、「仕事が遅い人」「残業代を稼ぎたい人」などのマイナスなイメージを抱きにくいという背景があります。
それでは、企業がどれだけ働きかけても労働環境が改善されないため、残業に対する意識を変える働きかけも必要と言えるでしょう。
※4 参考)内閣府:「ワーク・ライフ・バランスに関する意識調査」結果速報について」
ウェルビーイング実現のポイント2:オフィス環境を見直す
ウェルビーイング実現のポイント2つ目は、「オフィス環境を見直す」です。
テレワーク推奨や在宅勤務、短時間勤制度の導入など、働き方が多様化することで、オフィスのあり方も変化してきています。そのため、オフィス環境も時代に即したレイアウトや空間作りを行うことでウェルビーイングの実現ができるようになる可能性があります。
特に、オフィスレイアウトの見直しは、効率の良い働き方やコミュニケーションの悩みが改善されやすいため、うまく取り入れることでウェルビーイングにつながります。
例えば、従来の固定席からフリーアドレスに変えると、他部署との交流の機会が増え、コミュニケーションも活性化し、社内におけるコミュニティの形成に役立ちます。
また、従業員が自由に席を選んで座れるため、チームやプロジェクトに合わせて気軽に集まりやすく、連携強化も期待できるでしょう。
フリーアドレスの導入によりできた余剰スペースに、リフレッシュスペースや1人で集中して作業できる個室ブースなどを用意すれば、仕事の進め方に対する悩みも解消できます。
ウェルビーイング実現のポイント3:健康・メンタルサポートを行う
ウェルビーイング実現のポイント3つ目は、「健康・メンタルサポートを行う」です。
フィジカルウェルビーイングでもお話しした通り、心や体に異常がある状態では、ウェルビーイングとは言えせん。そのため、従業員自身が自分の健康やメンタルの状態を把握し、悩みや課題を改善できるよう、企業側からアプローチをしてサポートしてあげることが大切です。
身体面とメンタル面の2つに分けて見ていきましょう。
身体面
身体面では、次のようなサポートがおすすめです。
- ・定期的な健康診断の実施
- ・外部の検診費用の補助
- ・予防接種の補助
- ・ジムやフィットネスの利用補助(割引)といった福利厚生の充実
継続的に仕事を続けるためには、体の健康維持が欠かせません。従業員自身が健康に対して意識できるようなサポートを充実させましょう。
メンタル面
メンタル面で問題を抱えていると、本来のパフォーマンスができず、生産性も向上しません。そのため、次のような方法でメンタルチェックを行いましょう。
- ・産業医や保健師との個別面談
- ・ストレスチェック
従業員のメンタル面をサポートする際に重要なのが、メンタル状態を定期的に把握して置くということです。理由としては、トラブルや問題の早期発見と解決につながるからです。個別面談やアンケートなどを実施し、従業員の精神面でのストレスを軽減しましょう。
また、テレワークにより出社していない従業員も、オンライン面談などを行うことでフォローが可能です。どのような環境下でもフォローできる体制作りも進めましょう。
企業事例を参考にして使い方をイメージしよう
ここまでウェルビーイングについて見てきても、自社でどのように取り入れればいいのかイメージしづらいという人もいると思います。
そこでこの章では、有名企業の事例を3社紹介します。「ウェルビーイングを進める上で具体的なイメージをしたい」という人はぜひ参考にしてください。
株式会社アシックス
株式会社アシックスは、競技用のスポーツシューズやウェアなどを製造、販売する企業です。スポーツ文化や健康的な生活に関連した商品を提供する企業であることから、特にフィジカルウェルビーイングの参考になる施策が行われています。
株式会社アシックスでは、従業員の健康を大切にすることを重要視し、従業員の健康的な生活を実現するための健康経営を行なっており、2022年3月には、経済産業省から優良な健康経営を行なっている企業のひとつとして選出されるほどです。
具体的な取り組みとしては、保健師による全員面談に加え、ノー残業デーやプレミアムフライデーなどを活用し、従業員が運動に取り組める機会として運動促進セミナーなども開催し、メンタル面とメンタル面の両方からサポートを行なっています。
楽天株式会社
楽天株式会社は、インターネット関連の事業やサービスを中心に展開する企業です。
楽天グループでは、ウェルビーイングを「組織」「個人」「社会」の3つの層から捉え、それぞれ層にあった施策を行う専門の部署を3つ設けています。
そのひとつがエンプロイー・エンゲージメント部です。エンプロイー・エンゲージメント部では、楽天主義を共有するための施策を行なって従業員と組織の心的なつながりを強化しています。
ウェルネス部もウェルビーイング促進のために設けられた専門部署です。従業員の心身をサポートする専門の部署で、カフェテリアでの食事提供を通して従業員の健康を内側からサポートしたり、健康を維持するツールとしてフィットネスジムの整備したりしています。
株式会社イトーキ
株式会社イトーキは、事務用品やオフィス家具を取り扱う企業で、それらを活用した働き方やオフィス空間のデザインなども手掛けています。
2018年には、従業員のワークエンゲージメント向上と、ウェルビーイングを実現する新しい働き方を支える新本社オフィスを開設しました。オフィスフロアは、「Activity Based Working」という考えのもと、従業員がいつでも、どこでも、誰とでも仕事ができるフリーアドレスを採用しています。
これにより社員一人ひとりが自分の仕事内容や心身の状態に合わせて働き方や働く場所を選び、自律的に仕事に取り組むというワークスタイルが定着しているそうです。
また、仕事内容や活動にあった場所を選択できるよう、個をテーマにした集中して作業できるブースを配置。他にも、3人以上のグループでも作業しやすい場所などの多様な活動スタイルに合わせた専用のオフィス空間も用意し、より働きやすく、生産性の向上にも役立つオフィス環境を整備しています。
ウェルビーイングの使い方をマスターして積極的に取り組もう
ウェルビーイングは、「身体的、精神的、社会的な関わりにおいて健康な状態こそが幸福だ」という概念のことです。昔は、身を粉にして仕事に取り組むのが一般的でしたが、現在では日本だけでなく世界的にも仕事だけでなくプライベートの時間も大切にする人が増え、仕事や生活に対する価値観が変化しています。
そのため、企業も個人もウェルビーイングを進めることで、仕事に対する意識や取り組み方が変わり、結果として従業員のパフォーマンスの向上や業務効率化につながっていく可能性があります。
ウェルビーイングは使い方次第です。本記事を参考に、「従業員の心身の向上」と「働きがい」を意識しながら、ウェルビーイングを企業経営にうまく取り入れてもらえれば幸いです。
関連記事
-
1on1ミーティングとは? 人材を活かすメリットと効果的な進め方も合わせて解説!
ウェルビーイング
2022.07.12
-
今、さらに注目を集める【well-being(ウェルビーイング)】の意味とは?ビジネスとの相関も解説
ウェルビーイング
2021.05.31