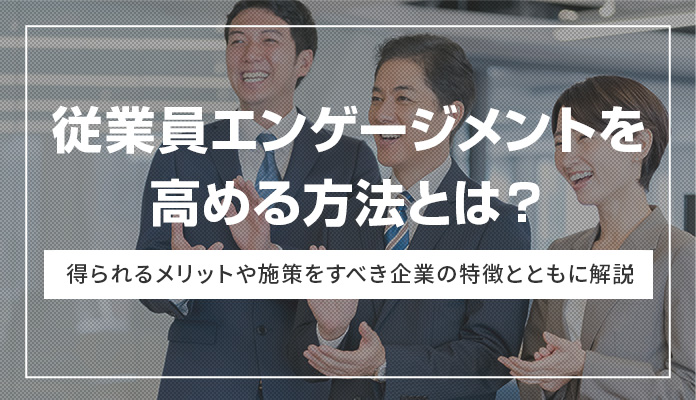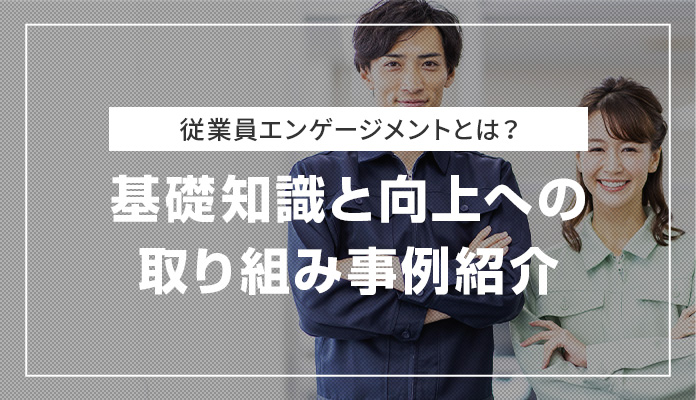健康経営
2022.11.08
心理的安全性の広まりにはGoogleの研究が大きかった!その中身とは? チームの定義や心理的安全性測定の方法などを解説

日本でも心理的安全性に注目し、心理的安全性を高めようと考えている企業が増えているようです。心理的安全性を実質的に広めたのはGoogleの調査・研究だといわれています。効果的なチームの条件において、他よりも重要となるのが高い心理的安全性です。当記事では、心理的安全性を広めたGoogleの研究を中心に、定義や測定方法、メリットや注意点などについて解説・紹介します。
そもそも心理的安全性とは?
チーム内で安全でいられるという安心感
心理的安全性(psychological safety)は、ハーバード・ビジネス・スクールのエイミー・エドモンドソン教授により提唱され、Googleのリサーチ結果発表によって広まったとされる概念です。エドモンドソン教授が提唱した1999年から数えても、2022年現在で23年という比較的新しい概念だといえます。さらに、Googleのリサーチは2012年から始まっており、広く注目を集めるようになってからは10年も経過していません。
心理的安全性は文字が示すように個人の内心における安全性を指す言葉です。具体的にはチーム内における自分の発言や指摘、行動が、他のメンバーから非難されたり反発を買ったり、または不利になったりすることがなく、そのチームの中で安全な立場を維持できる、自由に発言や行動ができるという安心感の共有を意味しています。発言の内容が正しいか間違っているかを問いません。安心感が高ければ心理的安全性が高い状態です。
ただし、根拠なく自分は安全な立場にいると思っているだけでは心理的安全性にはつながりません。心理的安全性の評価は、後述する測定によって検討されるように、そのチームにおける状況が大きく影響します。
心理的安全性が高いといえるためには、遠慮せず率直に発言できることが重要です。表面的には自由だとされていても、その実態が委縮して何も話せないようでは心理的安全性が低い状態だと評価しなければなりません。
また、心理的安全性は、いわゆる仲良しグループを形成している状態とは異なる概念です。仲良しグループは意気投合できるメンバーの集まりであり、目的が必ずしもメンバー間で一致したものとは限らず、目的なく形成している場合もあります。心理的安全性は会社や団体といった組織が企業の目的に向けて進むうえで重要な概念であり、個人の価値観が同じかどうかは関係なく、反対意見を述べたり、議論を戦わせたりすることも当然にあります。
心理的安全性の高低で変わる4つの心理
心理的安全性が高い場合と低い場合では、次に示す4つの心理の高低にも違いがあります。
・無知だと思われることへの不安
ある発言をすることで、他のメンバーから「そんなことも知らないほど無知な人間だ」と思われないかという不安です。この不安は、知らないといえなかったり、わからないことをそのままにしてしまったりといった弊害につながります。
・無能だと思われることへの不安
ミスをすると「こんなこともできないほど無能な人間なのか」と思われるのではないかという不安です。ミスをしていないと主張したり、ミスを隠蔽したりすることが、この不安による主な弊害だといえます。
・邪魔をしていると思われることへの不安
自分の意見を述べることで「邪魔をしている」と思われはしないかという不安です。この不安からは、アイデアや意見の発表を控える、消極的な態度になるといった弊害が考えられます。
・ネガティブだと思われることへの不安
反対意見を述べたり問題点を指摘したりといった言動が「ネガティブな人間だ」と思われるのではないかという不安です。この不安には、問題に気づかないふりをするようになってしまう、課題の改善ができないといった弊害があります。
心理的安全性が高ければそれぞれの不安は低く、心理的安全性が低ければ不安が高くなる関係です。
心理的安全性の測定
エドモンドソン教授が心理的安全性を測定する際には、以下の7つの質問が使われているとされています。(※1)
- ・チームの中でミスをすると、たいてい非難される。
- ・チームのメンバーは、課題や難しい問題を指摘し合える。
- ・チームのメンバーは、自分と異なるということを理由に他者を拒絶することがある。
- ・チームに対してリスクのある行動をしても安全である。
- ・チームの他のメンバーに助けを求めることは難しい。
- ・チームメンバーは誰も、自分の仕事を意図的におとしめるような行動をしない。
- ・チームメンバーと仕事をするとき、自分のスキルと才能が尊重され、活かされていると感じる。
1番目の質問は、無能だと思われることへの不安に通じます。2番目の質問はネガティブだと思われることへの不安に、3番目の質問は邪魔をしていると思われることへの不安に通じるでしょう。4番目の質問は心理的安全性そのものに通じるといったように、心理的安全性の測定に相応しい質問が並んでいます。
7つの質問に対して、上から順に「いいえ」「はい」「いいえ」「はい」「いいえ」「はい」「はい」と答えたなら、心理的安全性は最高レベルです。そのぎゃくに、上から「はい」「いいえ」「はい」「いいえ」「はい」「いいえ」「いいえ」と答えた場合、心理的安全性は最低レベルだということになります。
仮に質問1個を1点として、7点満点とした場合、何点以上で合格といったことではなく、7点を目指し続ける必要があるでしょう。
出典:※1 Google re:Work「効果的なチームとは何か」を知る
コミュニケーション不足が不安を招く
心理的安全性が低くなる要因のひとつとして、新型コロナウイルス感染症拡大を契機に激増したとされるテレワークなどにより、メンバーの接触が減ってしまったことが考えられます。コミュニケーション不足が活発な議論をする環境を遠ざけることで不安感が増し、心理的安全性の低下を招き、それがさらなる不安につながる悪循環に陥りかねません。企業には、心理的安全性を高めるためにも社内コミュニケーションの活性化が求められます。
企業が活躍するためには効果的なチームが必要
Project Aristotle
Googleが行ったリサーチは「Project Aristotle」と呼ばれるプロジェクトで、「効果的なチームを可能とする条件は何か」の答えを見つけ出すことが目的でした。そのために、Googleでは効果的なチームの定義を考え、その前段階としてチームの定義を考えています。
Googleが考えるチームの定義
Googleが考えるチームの定義には以下の条件が含まれています。
- ・特定プロジェクトのために組織された単位
- ・メンバー間に強い相互依存性がある
- ・連携して工程を進める
チームと区別する概念、集まりとしてワークグループを取り上げています。相互依存性が強くない点や組織における役職、上司と部下といった関係性が根本にある点がチームとの違いです。
効果的なチームとはどのようなチームか
Googleでは効果的なチームの定義を考えるうえで、チームの効果性を測る指標、尺度に着目しています。マネージャーとチームリーダー、チームメンバーが存在するチームにおいて、役職によって指標、尺度が異なっていました。
- ・マネージャー…数字などの結果で評価
- ・チームリーダー…ビジョンや当事者意識で評価
- ・メンバー…風土と文化で評価
管理職的な立場にいるマネージャーが結果を重視している点は必然というべきでしょう。チームメンバーが結果よりも環境的な部分を重視している点も納得できるのではないでしょうか。
マネージャーが重視する客観的指標(数字)だけ良ければ効果的なチームといえるのかといった懐疑的な見方ができる反面、客観的指標が弱ければ主観に引っ張られかねない懸念があります。しかし、主観を排除した場合には、一切の事情を斟酌しない冷たい評価が出来上がってしまう点がデメリットです。
そこで、Googleでは両極端を避け、四半期の売上ノルマに対する成績による評価を上記3者の評価に加えています。これにより、結果という動かない指標と個々の事情を考慮した総合的なチームの評価が可能です。この評価が高いチームが、効果的なチームとなります。
メンバーのプロフィールよりも協力関係が重要
Googleのリサーチ結果として、効果的なチームとなるにはメンバーが誰かではなくチームとしての協力が重要であることが判明しています。個別の因子では、心理的安全性が他の因子よりも重要で、5つの重要な因子の順位は以下のとおりです。(※2)
- ・心理的安全性
- ・相互信頼
- ・構造と明確さ
- ・仕事の意味
- ・インパクト
出典:※2 Google re:Work「効果的なチームとは何か」を知る
効果的なチームの成立に影響を及ぼす5つの因子
心理的安全性
前記5つの因子が効果的なチームの成立に影響を及ぼし、その中でもより重要となるのが前述のとおり心理的安全性です。ここでは、5つの因子について解説します。
心理的安全性については、冒頭で詳細に記述したとおり、自分のどのような言動も非難や不利益につながらない、心理的な鎧を脱ぎ捨てられる安心感の共有です。ここでいう言動とは、心理的安全性の高低で変わる4つの心理で示した「無知」「無能」「邪魔」「ネガティブ」と捉えられる可能性がある言動だといえます。高い心理的安全性があれば、このような言動も臆することなく行えるでしょう。
そこにあるのは、メンバーが相互に積極的な意見や質問をし、ミスを認めて相談し、問題点の指摘ができるチームです。その結果、チームの活性化をもたらすことになり、目標達成にも役立ちます。これこそが、心理的安全性が他の因子より重要となる大きな理由です。
相互信頼
2番目に重要な因子が相互信頼です。チームは個人プレーよりも協力して課題の解決を行う集団といえるため、信頼関係がなければ成り立たないでしょう。Googleのリサーチでは、高い信頼関係があるチームは時間内で高品質な結果を出し、信頼関係が低いチームは責任転嫁をするようです。(※3)
構造と明確化
3番目に重要な因子が構造と明確化です。すべてのメンバーが当該職務で求められているもの、役割、目標へ向かう過程や行動の成果を明確に理解していることが重要です。目標の設定に際しては個人目標であれ、チーム目標であれ達成可能な目標でなければならず、達成意欲がわくような意味のある目標を立てる必要があります。(※4)
仕事の意味
4番目に重要な因子が仕事の意味です。構造と明確さで出てきた目標にも通じる部分がありますが、自分が何のためにその仕事をするのか、自分にとっての意味・目的を各自が理解し、当事者意識を持っていることが重要になります。目的は人それぞれで、お金儲けでも自己実現でも何でも構いません。(※5)
インパクト
5番目に重要な因子がインパクトです。仕事そのものへの意義を感じられることが重要になります。仕事の意味と似たような感じを受けるかもしれませんが、インパクトで検討される意義は自分が仕事をする目的ではなく、仕事そのものの意義です。(※6)
出典:※3~6 Google re:Work「効果的なチームとは何か」を知る
心理的安全性が高いチームのメリット
Googleでは離職率が低かった
ここまでの内容から、心理的安全性が高いチームにメリットがあることは間違いありません。Googleが実体験したメリットとしては、離職率が低く、仕事の成果や評価にもつながったことが確認されています。以下は「Google re:Work「効果的なチームとは何か」を知る」からの引用です。
リサーチ結果によると、心理的安全性の高いチームのメンバーは、Google からの離職率が低く、他のチームメンバーが発案した多様なアイデアをうまく利用することができ、収益性が高く、「効果的に働く」とマネージャーから評価される機会が 2 倍多い、という特徴がありました。(※7)
引用:※7 Google re:Work「効果的なチームとは何か」を知る
メリットとして離職率が低い点をあげられるといえば、従業員エンゲージメントが高い企業が思い浮かびます。チームの心理的安全性を高めることで従業員エンゲージメントが高い状態と同様の効果を期待できるといえそうです。
組織の活性化と個人の充実
心理的安全性が高いチームは、組織が活き活きとし、メンバーは充実感をおぼえ、情報交換・共有が進んでいる状態にあるといえます。「無知」「無能」「邪魔」「ネガティブ」この4つの不安がないか、あったとしても極めて僅かな状態です。メンバー全員が知らないことを知らないといえ、質問ができ、ミスの報告も躊躇せず行えます。また、新しいアイデアや意見を積極的に発表し、問題点は適切に指摘できる状態です。
この状態が続けば、組織としてのチームとチームのメンバーにとって好ましいことだといえます。しかし、心理的安全性が高い状態は自動的に保持されるわけではありません。低ければ高くできるのと同様に、高ければ低くなってしまうこともあり得ます。そのため、常に高いレベルで維持する努力が必要です。
品質向上とリスクマネジメントの良化
心理的安全性が高いチームでは、さまざまな報連相が的確に行われることにより、些細と思われるような情報も共有可能です。1人では気づかなくても、メンバー間で共有することにより、問題を早期発見し、品質向上や生産性の向上、リスクマネジメントの良化につなげることができます。
社内コミュニケーションの重要性に通じる
積極的で協調性のある意見交換が成果につながる
心理的安全性が高ければ効果的なチームとなって良い影響が出る理由を端的に表現するなら、積極的で協調性のあるチーム内(社内)コミュニケーションが実現するためだといえるでしょう。目標に向け、計画通りに課題をクリアし、問題を解決するために必要な意見や新しいアイデアをタイムリーに出せ、問題点の指摘もできる職場環境を作っているのもチーム内コミュニケーションです。
心理的安全性が高まり、コミュニケーションが活発化することで仕事の円滑な進行につながる点は、社内コミュニケーションの重要性を再確認させる意味があります。
チームの集まりが企業
自分のチームの心理的安全性が高いといっても、他のチームがそうでなければ企業としては喜んでいられません。各チームの心理的安全性が高まってこそ、企業全体が望ましい方向に向かいます。
仮に企業全体を1組のチームとして見た場合はどうでしょうか。小さなチームを何組も抱えるよりも心理的安全性を高めやすいでしょうか。この点に関連して、多数の研究者による興味深いデータをGoogleが取り上げています。10人未満しかメンバーがいない小さなチームのほうが、大人数のチームより成功しやすいというデータです。
このことから、ある程度の人数を抱える企業においては、小さなチームを編成したほうが社員のパフォーマンスを発揮しやすく、好結果につながる可能性があります。ただし、企業にはそれぞれの特性があり、小さなチームばかりでは事業が成り立たないケースもあるでしょう。そこは実情に応じた対応が求められます。
Googleやエドモンド教授は米国だが日本でもできる
エドモンドソン教授はアメリカの学者であり、Googleもアメリカ企業です。アメリカと日本とではコミュニケーションのとりかたや意見の出し方が異なる点があります。そのため、アメリカと同様に心理的安全性を高める取り組み、コミュニケーションのとりかたができるのか疑問に思うかもしれません。しかし、社内コミュニケーションが重要である点は日米ともに同じでしょう。
目的達成に向けて進む企業においては柔軟さが求められています。グローバル化の並もあって、現代の日本社会は大きく変化しており、アメリカで提唱された概念だから日本では心理的安全性向上への取り組みができないということはありません。
社内コミュニケーションに通じる部分や従業員エンゲージメントに通じる部分からも、日本の企業・チームが心理的安全性を高めて好結果を生み出すことは可能だといえます。心理的安全性を高めるために必要となるのはチームとマネージャーやリーダーを含むチームのメンバーです。他に何かが必要というわけではないため、無料で今すぐにでも実施できます。社内コミュニケーションを活性化する施策を導入するだけでなく、心理的安全性の向上にも目を向けると良いでしょう。
心理的安全性を高めるうえでの注意点
どのような内容でも率直にいえるのか
心理的安全性が高い条件として、言動がどのようなものであっても非難されない点があります。とはいえ、文字どおりの意味で何をいっても構わないということではありません。基本的には不適当な内容であっても非難されないことで心理的安全性が高まるものの、常識的範疇で忌避される発言をすべきでないことは言を俟たないでしょう。
あくまでも、職務上の意見などが間違いであったり、ズレていたりしても問題とならないと考えるべきです。悪意のある発言や明らかに円滑なコミュニケーションを阻害するような言動まで認められるわけではないといえます。
過度な批判はマイナス
適切な批判はすべきであり、そうでなければ活発な議論ができません。しかし、過剰な場合はチームの心理的安全性を低下させ問題となり得ます。Googleのワークショップのロープレシナリオにあるような批判は許されないと考えましょう。
わかりやすいのが「メンバーが出した優良な提案を、マネージャーがメンバー本人のいる、いないに関わらず厳しい批判を繰り返したことで、メンバーが誰も提案をしなくなった」というシナリオです。このシナリオには、マネージャーが出した提案が経営陣に却下されたという落ちがついています。行き過ぎた批判は当事者にとっても、チームにとっても、企業にとってもマイナスにしかならないという見本です。
思いやりをもって接する
心理的安全性が安心感の共有である以上、メンバーはお互いに思いやりをもち、提案に対する批判は建設的なものであるべきです。また、多少困った発言をするメンバーに対しても、頭から否定するのではなく寛容な姿勢で軌道修正を図る必要があります。一発退場というシーンもあり得ますが、まずはチームのメンバー同士で補完しながら前進する姿勢も必要です。
Googleが広めた心理的安全性を高めて目的達成に向かう
心理的安全性を知るにあたって、Googleのリサーチ内容と結果、参考資料などが大いに役立ちます。日本ではまだ広まっていく途中にあるといえる概念で、深い知識が無くてもおかしくありません。Googleのリサーチ結果や解説を参考に自社チームの心理的安全性を高め、目的達成に向けて進みましょう。
関連記事
-
従業員エンゲージメントを高める方法とは? 得られるメリットや施策をすべき企業の特徴とともに解説
健康経営
2022.08.31
-
従業員エンゲージメントとは? 基礎知識と向上への取り組み事例紹介
ウェルビーイング
2021.12.27