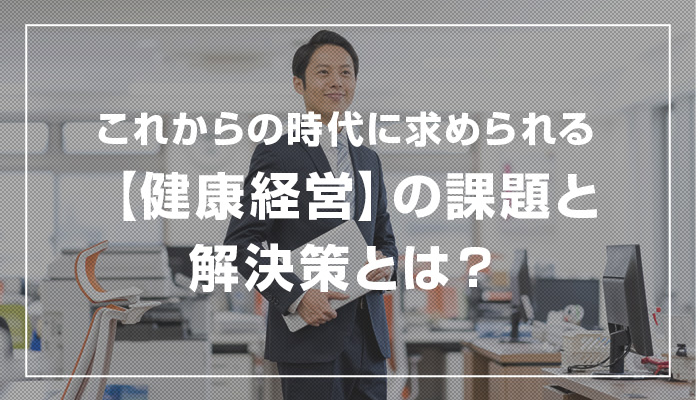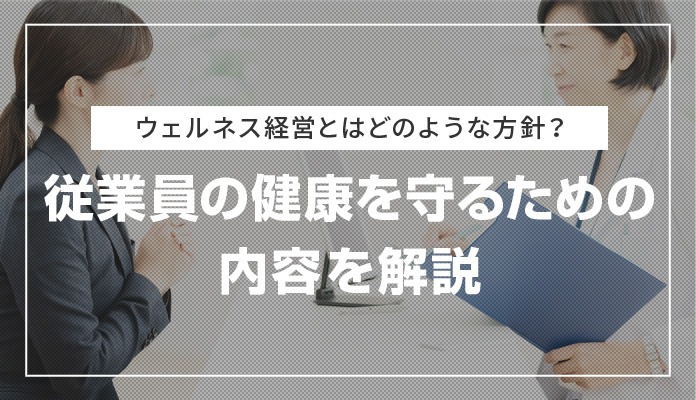健康経営
2022.08.10
HRテックとは? 人事領域で注目される最新のテクノロジーの導入メリットや活用方法を解説!
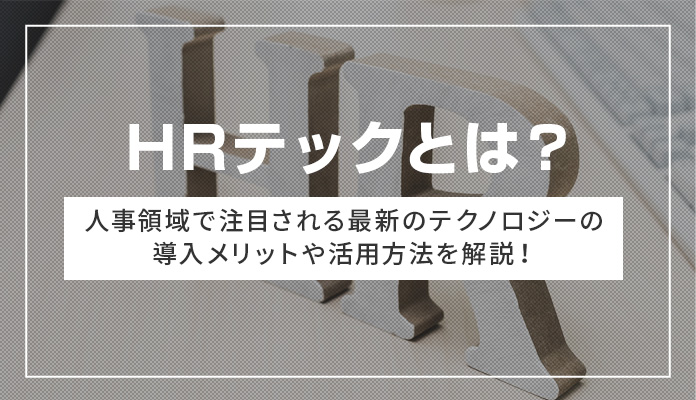
HRテックが人事領域におけるこれからのテクノロジー、サービスとして期待を集めています。採用や教育など人材の活用や評価に関する企画の立案を始め、戦略的で創造的な業務が増えている企業の人事にとって、HRテックは注目の的です。当記事では、定型業務から戦略的な活用法まで、人事で幅広く使用されているHRテックの導入メリットや活用方法、導入にあたっての注意点などについて紹介・解説します。
HRテックは人材に関するテクノロジー
Human Resourceとテクノロジー
HRテックは「Human Resource(人材)」と「テック(tech、テクノロジー)」をかけ合わせた造語です。人事領域における幅広いテクノロジーの総称として、またはそのテクノロジーを活用したサービスを指す言葉として浸透しています。HRテックに該当するテクノロジー、サービスは各分野に多数あり、限定されたものを指すわけではない点に注意が必要です。
HRテックが注目を集めている背景には、この後に述べるAI技術の進歩やビッグデータの活用、クラウドコンピューティングの広がりといった要因があります。HRテックはDX(デジタルトランスフォーメーション)の波に乗って普及しているともいえるテクノロジー、サービスです。
人材に関するすべてが対象
HRテックがカバーする人事領域は、採用や育成、管理や福利厚生といった人事の特徴的で限定的な範囲だけにとどまりません。人材に関するすべての領域が含まれています。ただし、HRテックという言葉自体には統一された定義や用法があるわけではないのが現状で、人によって指し示す範囲が異なります。とはいえ、人事領域という範囲で使用されていることに変わりはなく、細かな違いを気にする必要はないでしょう。
HRテックに欠かせない要素
AIなどの最新テクノロジー
HRテックには欠かせない要素として、主にAIなどの最新テクノロジーがあります。AIは人工知能のことで、ビッグデータの解析などに威力を発揮するテクノロジーです。いまやAIはHRテックに限らず、さまざまな分野で活用されています。人工知能であるAIは人間とは異なり、客観的にぶれない判断をする点が大きな特徴といえるでしょう。
人間が判断する場合は主観的な結果になる可能性があるため、より客観性を重視したい業務は、属人的な管理からHRテックに移行すべきだと考えられます。
クラウドコンピューティング
クラウドコンピューティングとは、インターネット通信を経由して、コンピュータのハードウェアやソフトウェアを利用したり、データを保存したりする利用形態を指す言葉です。自分の手元にシステムを置かずに、クラウドサービスの運営会社が提供するシステムを利用するため、システム分の費用や場所の負担を考える必要がありません。
クラウドの語源について諸説ありますが、雲のようなイメージを持つインターネット上の領域との間でデータをやり取りすることから、クラウド(cloud)と呼ばれるともいわれており、手軽に利用可能です。広く一般が利用できるクラウドサービスをパブリッククラウドと、自社限定で利用するクラウドをプライベートクラウドと呼んで区別しています。ちなみに、手元にサーバーなどの設備やソフトウェアを置く形態をオンプレミスと呼びますが、さまざまな分野でオンプレミスからクラウドへの入れ替わりが進んでいる状況です。
ビッグデータ
ビッグデータは文字どおりビッグなデータではあるものの、どの程度の量があればビッグなのかについての決まりのようなものはありません。また、ビッグデータの定義については、見解を示す人や団体によって違いがあります。たとえば、総務省の情報通信白書などに書かれているビッグデータの定義は、かなり複雑なものとなっているため、簡単に表すことができません。
ただし、一般的に共通している解釈としては、人力や従来型のシステムでは処理できないレベルのデータ群がビッグデータだといえるようです。AIを駆使して解析しなければならないほどの大規模なデータはまさにビッグデータといえます。
また、ビッグデータには量的側面(Volume)と多様性(Variety)、処理速度・頻度(Velocity)の3Vが備わっているといわれているほか、近年では正確性(Veracity)と価値(Value)を加えた5Vを特徴とする意見も出ています。つまり、多様性を持っているなど、量的に多いだけではビッグデータとは呼べないということです。
ビッグデータの分析結果が経営の意思決定に利用されるなど、ビッグデータの存在そのものが価値あるものとして扱われ、資産として考えられている現状において、5Vで考えることは妥当だといえるでしょう。
多様化する社会の人事領域に対応するHRテック
これまでの人事業務は主観が大きかった
従来型の人事では、たとえば上司が部下について評価する人事考課のように主観が入り込む余地が大きかったといえます。むしろ、人事業務の多くが主観によって行われていたといえるかもしれません。
たとえば、日本の採用現場では明確な根拠に基づいて点数化できるペーパーテストや適性検査だけでなく、判断基準がハッキリしない(担当者によって評価が異なる)面接の比重が大きい点などは、人事に主観が大きいことを示す好例といえるでしょう。
しかし、人事業務も効率化や標準化と無縁ではありません。客観的なデータの活用による適正な人事が求められる時代となり、HRの重要性が高まっています。また、ビッグデータを活用しようとすれば、人間の手や従来型の人事システムでは間に合わない状況です。
働き方の多様化に対応するHRテック
現代はテレワークやワークライフバランスを重視した働き方改革などにより、同僚であっても同じオフィス内で顔を合わせる機会が激減している時代です。また、少子化で人材争奪戦が発生する状況にあって、人事部門の役割も大きく様変わりしようとしています。単純な定型業務の機械化は当然のこととして、他社に負けない高度な人事業務を実施できるツールや仕組みが必要ですが、従来からあるシステムだけでは性能や機能が不足する事態になりかねません。
そこで注目されているのがHRテックであり、そのサービスです。戦略部門となりつつある人事部門が専門性を発揮した業務に邁進できるよう、まずは定型業務の負担を軽減します。それに加えて、採用活動の詳細や育成プログラムの作成、適正な人員配置などについても、高度なテクノロジーによってサポートが可能です。
テクノロジーの進歩が後押し
既に述べているように、HRテックが人事領域の業務を強力にサポートできているのは、AIの進化やクラウドコンピューティングの発達など、最新のテクノロジーが存在しているおかげです。この先もITの進化が続くことで、HRテックもより優れたものとなるでしょう。
HRテックの導入メリット
人事関連業務の効率化とコスト削減
企業規模が大きくなったり、人事で管理するデータが増えたりすると、属人的な管理では処理が間に合わないケースが出てきます。また、従来から使っている旧式のシステムではデータベースを構築していても能力的に不足が生じることがあり、その場合はHRテックの導入が最適解です。HRテックによってデータの一元管理や作業の効率化が進みます。
大量のデータ処理を伴う給与計算や労務管理といった定型業務をHRテックに任せることで、人事部門の要因は、よりクリエイティブな業務に集中できるでしょう。
また、オンプレミス型の設備やシステムからクラウドへ移行することにより、保守やリプレイスといった物理的な管理コストの削減が可能です。ここで浮いた資金をより戦略的で効果的な使途に投入可能となります。
採用活動の円滑化
人事業務の効率化によって、クリエイティブな業務にあたることが可能となった人材を採用活動に専念させれば、他社との人材争奪戦が有利に進む可能性があります。少なくとも、人手不足で後手に回るといった事態は回避できるでしょう。前述のコスト削減で捻出した資金を採用活動に投入することも考えられます。
HRテックを採用活動に活用すれば、リモート環境での会社説明会や面接、人材の選別など、採用活動が円滑になります。データの一元管理は当然ながら採用情報についても実現可能です。募集からエントリー、応募者のデータ管理、選考に関する情報など、幅広いデータを一元化して共有管理できます。
かつては大企業が資金力とマンパワーにモノをいわせて勝ち抜いてきた人材争奪戦の現場でしたが、現在ではHRテックを活用した小規模な会社が、大企業を差し置いて優秀な人材を獲得するといった事例も少なくないようです。すでに採用現場は企業規模よりも、いかにHRテックを活用できているかが勝負を決める場となりつつあるのかもしれません。人材確保を確実なものとしたいなら、HRテックの活用を考えるべきではないでしょうか。
客観的で公正な人事評価の実現
属人的ではない組織的なデータ利用とAIによる分析などにより、客観的で公正な人事評価、適材適所の人員配置、人材育成を狙うことが可能になります。人事評価は人材の定着と切っても切れない関係にあり、不正確な低評価は人材流出につながるリスクが高い事柄です。したがって、可能な限り早く、公正な評価ができる環境を整えるべきでしょう。
エンゲージメントの向上
人材のミスマッチが回避され、人材の特性に合致した配置が実現することで、各自の満足度がアップします。また、職務への積極性が生まれることも期待できるでしょう。さらに、結果が的確で公平に評価されることになれば、従業員エンゲージメントの向上につながります。従業員エンゲージメントが向上すれば、離職率が改善され、人材の定着が現実のものとなるでしょう。
生産性の向上と業績アップ
ここまで取り上げた個別のメリットや、その他のメリットが組み合わさることで、HRテックの活用による相乗効果が生まれます。その結果、生産性を向上させ最終的に企業としての業績アップが見込める点が大きなメリットです。営利企業であれば最終目的のひとつが利益を最大化することであり、業績アップにつながるHRテックの導入は正しい判断だといえるでしょう。
代表的なHRテックと活用方法
採用管理システム
ATS(Applicant Tracking System)採用管理システムは、採用に関するほぼすべての機能を備えている製品、サービスを選ぶことで、売り手市場でも戦略的で効率のよい採用活動が可能になります。
(一般的な採用管理システムに搭載されている主な機能の一部)
- ・求人情報の管理や求職者向け求人ページの作成
- ・求人メディアとの連携
- ・エージェント管理
- ・応募者情報管理
- ・面接日程管理
- ・選考進捗管理
- ・選考ステータス管理
- ・フィードバック、レポート機能
採用に関する各種情報の一元化と効率化、さらには分析やダイレクトリクルーティングシステムによる無駄のないアプローチも可能です。
労務・勤怠管理・給与計算システム
HRテックの労務管理システム、勤怠管理システム、給与計算システムは、人事領域の定型業務を効率化してくれます。労務管理では社会保険関係や年末調整、勤怠管理ではオンライン打刻による出退勤管理や休暇申請・承認、シフト管理といった機能が一般的です。
給与計算では給与の自動判定、自動計算、勤怠管理との連携や仕訳連携といった機能で業務効率がアップします。給与計算システムでは、頻繁に改正がある税法などにも対応するため、いつもどおりの操作をするだけでの簡単さです。
また、それぞれのシステムによる一元管理だけでなく、横の連携が可能な点もHRテックの活用がおすすめといえる理由でありポイントとなっています。
タレントマネジメントシステム
タレントマネジメントシステムは、人事情報の見える化に役立つHRテックのカタチです。社員に関する情報を一元管理でき、どこにいる社員であっても目の前にいるかのように顔写真と詳細を確認できます。
たとえば社員情報では、個人を特定するプロフィールデータに加え、採用年月日や異動年月日、異動履歴、役職や現職の継続年数、評価レベルといった項目をひと目で確認可能です。さらに、取得している資格や受講した講座などの情報を利用できます。
タレントマネジメントシステムを活用することで必要な情報を素早く把握し、適性と能力、成長期待度と希望を考慮した配置や教育の成功が可能です。操作も簡単で、目次を選ぶようなイメージで使えます。
社員の個別情報を網羅的に管理して活用したいと考えるなら、タレントマネジメントは外せないシステムです。
健康管理システム
健康経営が重視される時代の人事では、社員の健康管理にHRテックの活用が有力な選択肢となっています。健康管理システムを利用することで、24時間いつでもインターネット上での健診予約が可能です。利用者にマッチした健診コースの選択や、失念防止のリマインド機能など、便利な機能が揃っています。
また、健診結果を残しておいて経年による健康状態の変化をチェックするといった使い方も可能です。さらに、メンタルヘルスが重視されている現在にマッチした、カウンセリングを受けられるシステムも見逃せません。
モチベーションやエンゲージメントの向上
その他のHRテックとして、サーベイツールやコミュニケーションツールも活用したいツールといえます。サーベイツールは、従業員満足度や従業員エンゲージメントを調査するツールです。アンケートの作成から調査、可視化された分析、他社との比較といった機能が搭載されています。
企業にとって従業員のモチベーションを維持し、エンゲージメントを向上させることは、人材の定着と活用に欠かせない要素です。せっかく入社した社員が定着しなければ、採用コストが無駄になるだけでなく、他社との競争で遅れをとることになりかねません。
社内コミュニケーションの活性化もモチベーションやエンゲージメントと深いかかわりがあります。活発なコミュニケーションが企業にとって有意義であることは間違いありません。コミュニケーションツールには無料でありながら高機能に使えるモノもあり、選択肢は多いといえるでしょう。
HRテック導入の流れと注意点
業務の見直しと目的の明確化
HRテックを導入する流れは、これまでの業務内容を見直し、HRテックへ移行する内容を固めることから始まります。いわゆる業務の棚卸を最初に行い、すべての洗い出された業務を必要なモノと不要なモノに分別することが重要です。
古くから残っている業務の中には、何年も前から必要なくなっているにもかかわらず、慣習的に残っているモノがあるかもしれません。これまでもあったからということではなく、これから必要かどうかを考えることが重要です。HRテックの導入を機に、スッキリできるところはスッキリさせましょう。あれもこれも残したままで、そのままHRテックに移行すると、コストアップしてしまう可能性があります。
このとき、導入目的が何かを明確にすることが必要です。導入目的が曖昧なままでは、何を移行させればよいのか判断が不正確なものとなりかねません。そのうえで、確実に進捗するための行程表を作成し、しっかりと実行に移します。
課題解決に適したシステムを選ぶ
HRテックの目的と業務内容に適したシステムがどれかを判断し、複数あるシステム、サービスの中から比較検討のうえで自社に適したモノを選びます。これまで使ったことのないHRテックを導入する際には、公式サイトの記載などを見てもピンとこない点もあるでしょう。選択する前に、実際の動きや操作性を確認したいものです。
多くのサービス、システム提供会社がデモや詳しい資料による説明を行っているため、可能な限り申し込んで体験しておくとよいでしょう。
全社的な取り組みとして行う
HRテックが人事領域の話だからといって、人事部門だけで導入、移行に取り組もうとするとシステム的な知識の不足などから失敗する危険性があります。また、社内のシステム部門との連携が必要になる可能性が高いでしょう。HRテックの導入は、単に人事の問題ではなく企業の根幹にかかわる話です。したがって、経営トップが旗を振って責任をとる全社的な取り組みとして行う必要があるでしょう。
HRテックで戦略的な人事を実現しよう
HRテックは日進月歩のIT技術を背景にして進化を続けています。今は他社に先駆けて先端のシステムを活用しているとしても、すぐに他社も同様に使ってくるでしょう。したがって、これからの人事はHRテック抜きでは語れないという状況になる可能性があります。
人材は企業の財産であり宝です。人材を守り活躍してもらうためにも、HRテックを活用して他社に勝るとも劣らない戦略的な人事を実現しましょう。
関連記事
-
健康経営
2021.05.28
-
ウェルネス経営とはどのような方針?従業員の健康を守るための内容を解説
健康経営
2021.07.05