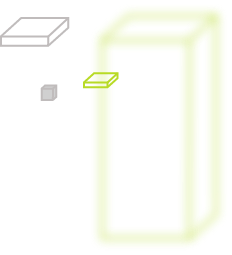Top Interview
100年先も、
人は暮らす。

2022年4月、パナソニックグループは事業会社制に移行し、ハウジング事業はパナソニック ハウジングソリューションズ株式会社として新たなスタートを切りました。今後、独自の優位性を発揮しながら自主責任経営を追求していくなかで、世の中の暮らしにどう貢献していくのか。持続可能な住まいや環境を実現するために必要なこととは。山田昌司社長に、幅広いテーマについて話してもらいました。
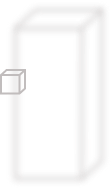
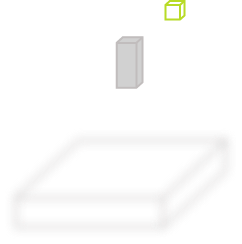
Section.01
パナソニックの暮らし
という強み。
最初に、競合が多いハウジング業界における
パナソニック ハウジングソリューションズの優位性について聞かせてください。
それは極めてはっきりしています。建築物の骨組み、建材、水まわりや外装など、住まいに関わるあらゆる商材を自社開発できることです。お客さまが実現したい暮らしやオフィスに応じてあらゆる商材を組み合わせ、独自のソリューションとして提供することができます。さらにはエコキュートや太陽光発電、配線器具、家電といったパナソニックグループの商材も加えることで、より独自性のあるソリューションを提供することが可能です。
パナソニックグループで全国にショウルームが60カ所あることも大きな強みになりそうです。
住宅設備は気軽に買い換えられるものではないので、お客さまは購入を決断するにあたって、自分が住もうとしている空間を見たいと考えます。個々の商材ではなく『パナソニックの暮らし』という空間全体を肌で感じていただくためにも、お客さまとのリアルな接点となるショウルームの活用は、今後さらに重要性を増していくでしょう。
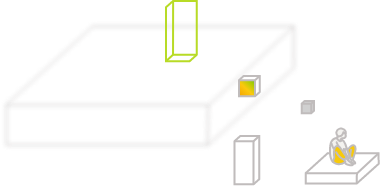
Section.02
スケールの大きな
仕事に挑める
チャンスが十分にある。
ハウジング事業の面白さはどういったものでしょうか?
まず、この事業はすべてがカスタマイゼーションで、提案したものの強みをしっかり説明してご納得いただいたうえで、最後、お客さまのところにまで届ける必要があります。これは、パナソニックグループの中でもユニークなところになります。
ただ商品をつくって売る、というだけでは成り立たないのですね。
加えて、木を扱っているのはパナソニックグループのなかで唯一、この会社だけです。木は鉄やプラスチックと違って、一度形をつくって終わり、というわけにはいきません。お客さまと共に暮らすなかで、環境ごとの温度や湿度で木は動くんです。そうした動きまで制御できるように製造して、しかも動いても品質に問題が生じないようにしなければならない。それには、ものすごいノウハウが必要なんです。
商品を正しくつくり、正しく扱うには、深い知識が求められますね。
だからこそ、きちんとハウジング事業を理解する人材を育成することが不可欠です。あと、私が若い頃から感じているハウジングのおもしろさを、より多くの若い人たちにも味わってほしいという思いもありましたね。
そもそも、社長がハウジング業界を志望した理由はどういったものだったのでしょうか?
今の学生さんほどしっかりした理由ではないかもしれませんが、子どもの頃から車やバイク、プラモデル以上に、自分の部屋の整理整頓や模様替えが好きだったんです。家具の自作なんかも好きで「ここに棚が欲しいな」と思ったら、ノコギリで木を切って自分でつくったりもしていました。高専では機械工学を学んでいましたが、潜在的にハウジングやものづくりへの興味が高かったんでしょうね。入社してからも他の事業部に目移りすることなく、ハウジング事業一本でやってきました。
社長が若手の頃に経験したなかで、特に印象に残っている仕事を教えてください。
20代のときに経験した、5億円規模のパイロットプラントの立ち上げです。「参加させてください」と手を上げたところ、「山田が自分で考えてやってみるか?」と、若手に権限をすべて委譲してくれました。ものすごいプレッシャーでしたけど、60メートルくらいある設備を自分で設計して導入したり、本当に楽しくて仕方がなかったですね。
こうしたスケールの大きい仕事を、今でも若手が経験できる可能性は?
十分にあります。私はいつも一定以上の役職に就く者に、部下のチャレンジに自分の保身だとか私情を挟まないよう伝えています。だから、何かやりたいことを提案されたときに「部下が失敗したら立場が危うくなる」といった暗い考えが持ち込まれることはありません。あらゆる判断が「会社や社員にとってプラスになるか」という基準のもとにされています。
ちなみに、社長になった今でも現場でものづくりをしたいと思うことはありますか?
もちろん。ローコストで高品質なものづくりができる自信もあります。今、工場にいる人たちが聞いたら「やれるもんならやってみろ」ってなるかもしれませんが(笑)。ただ、今でもそれぐらいの気概はありますね。
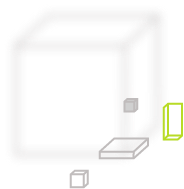

Section.03 住まいとは、普遍的なもの。
次に、社長が考えるハウジング業界の強みや魅力について聞かせてください。
これまで、世の中にはさまざまなイノベーションが起こってきました。近い将来に目をやれば、おそらくクルマが空を飛ぶことが当たり前になっているでしょう。そうした破壊的なイノベーションがハウジング業界で起こせるかといえば、なかなか難しいかもしれない。でも住まいってある意味、普遍的なんですよね。
人が生きていくうえで絶対に必要なものだから、ということでしょうか?
そのとおりです。この先、どんなイノベーションが起こったとしても「住まいが必要なくなる」なんてことは起こり得ない。だから、この先も人々はより良い暮らしを求め続けます。そして、私たちがより良い暮らしを追求して提供し続ける限り、この業界やこの会社は進化し、残り続けていくんです。
より良い暮らしを追求するにあたって、特に重要なことは何だとお考えですか?
「外部環境から人を守る」ということが第一ですね。最近では住宅や非住宅(高齢者施設、学校など)に限らず、太陽光パネルなど再生可能エネルギーの活用を謳うものが増えてきました。それは環境への配慮という意味もあるんですが、レジリエンスの観点を多分に含んでいます。特に、近年は激甚的な災害が多いですしね。
外部環境の変化に応じて、住まいのあるべき姿もどんどん変化しているんですね。
私たちにはその変化を先取りして、価値提供をしていくことが求められています。日本だけではなく、世界中で今、そうした価値提供が求められているんです。その意味で、ハウジング業界の市場はグローバル規模で見ても極めて大きいと言えます。数年で急激に伸びる業界ではないけれど、100年先も事業が持続し、成長する余地がある。だって、人は100年先も暮らすわけですから。
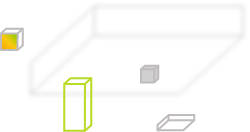
Section.04
世の中が
認識すらしていない、
新しい価値を。
パナソニック ハウジングソリューションズは「住生活に関わる確かな技術で、
領域を広げ、ともにまだない日常を生みだす」というビジョンを制定しています。
このなかの「まだない日常」とは、どういった意味を持つ言葉なのでしょうか?
普段の何気ない暮らしのなかにおける、これまでにない新しい価値。そうした意味合いですね。ただ最初に明言しておきたいのは、快適な設備だとか、掃除がしやすいとか、そういうことではありません。
単に便利で目新しい機能のことを指しているのではないと。
もちろん、高機能な商品の開発には取り組んでいきますし、今後そうした商品はたくさん出てくるでしょう。ただ、それはここで言う「まだない日常」とリンクするものではない。「まだない」と認識すらされていないことが「まだない日常」なんです。
社長が考える「まだない日常」の例を挙げていただくことは可能ですか?
代表的なもので言うと、私たちはエネルギーや環境に配慮したものづくりを重要視しています。ただ、「この家、環境にすごく優しいな」「CO2を削減してつくられているんだな」。現状で、そう感じながら暮らしている人はきっといないでしょう。
そうですね。自分の暮らしが環境に良いかどうか、生活をしていて感じることはないと思います。
つまり、それは現状における「まだない日常」のひとつです。この先、人が日常生活のなかで「自分の暮らしって、ものすごく環境に優しいな」と自覚できるほどのソリューションを提供できたなら、それは私たちが新たに生み出した日常ということになります。人ですら環境に優しいと自覚できるのなら、その日常は地球環境にとっても今までにないくらい優しいものとなるでしょう。私たちはそういう「まだない日常」をつくっていく会社なんです。
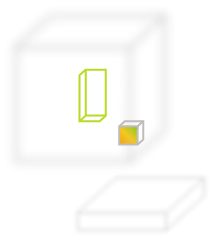
Section.05
イメージを、
リアルにする力。
ハウジング業界で仕事をしていくにあたって、特に求められる素養は何でしょうか?
いろいろありますが、一番は世の中や世界で起こっていることを俯瞰して「こういうことをやっていったらいいんじゃないか」と企てる想像力ですね。
想像力はどういった行動で高められるとお考えですか?
身近なことで言えば、人や世の中に興味を持つことです。例えば電車の中で人を見て「表情が明るいけど、良いことがあったのかな」とか、車窓に流れる建物を見て「瓦が痛んでいるな、どうしてだろう」など、想像や妄想をする。「なぜ、そうなのか」を考えるクセをつけると、商品開発にものすごく役立つんです。
具体的には、想像や妄想は仕事にどう役立つのでしょうか?
何かを開発するにあたって最初に構想書を書くんですけど、構想から入ってもあまりおもしろくならないんですよ。でも、妄想から発想するとすごくおもしろい構想書になる。私がアラウーノを開発したときも「便器をプラスチックでつくれたらすごいな」という妄想から入りました。
アラウーノを妄想から発想していたとは驚きです。
妄想をふるいにかけ、徹底的に練り上げて構想にしていく。すると、妄想のときにはほぼ見向きもされなかったアイデアに共感する人が増えていきます。そうして共感する人が増えるほど、妄想を事業化できる確度が格段に上がるんです。想像や妄想ってファンタジーじゃなくて、自分がつくりたいと思い描く“リアルな世界”のことなんですよ。私は今でもよく人や世の中を観察して、想像や妄想を働かせていますよ。
社長には今、何か妄想していることはありますか?
この会社を、世界を舞台にハウジングソリューションを駆使して住宅供給できる会社にしたいと妄想しています。住宅に限らず、高齢者施設や幼稚園、学校といった非住宅も含めて、木造を主体に世界規模で事業展開をしていきたい。それが一部可能な状況は整っているのですが「最終的にこうありたい」という理想と比較するとまだまだです。これからも、理想をリアルなものとするための取り組みを進めていきます。
ありがとうございました。最後に、学生の方にメッセージをお願いします。
私たちには理想に至れるノウハウや商材があります。パナソニックグループが有する強みをすべて活用して、世界で類を見ない暮らしを提供できる自信もあります。パナソニック ハウジングソリューションズはそんな夢が抱ける会社です。もちろん、理想に至る道のりは格好の良いことばかりではありません。むしろ、しんどいことや泥臭いことの方がたくさんある。皆さんとそうした道のりをともに歩み、まだない日常を創造できる日が来ることを楽しみにしています。