ここから本文です。
データの長期保存におすすめの安全な方法は?メディアごとに解説
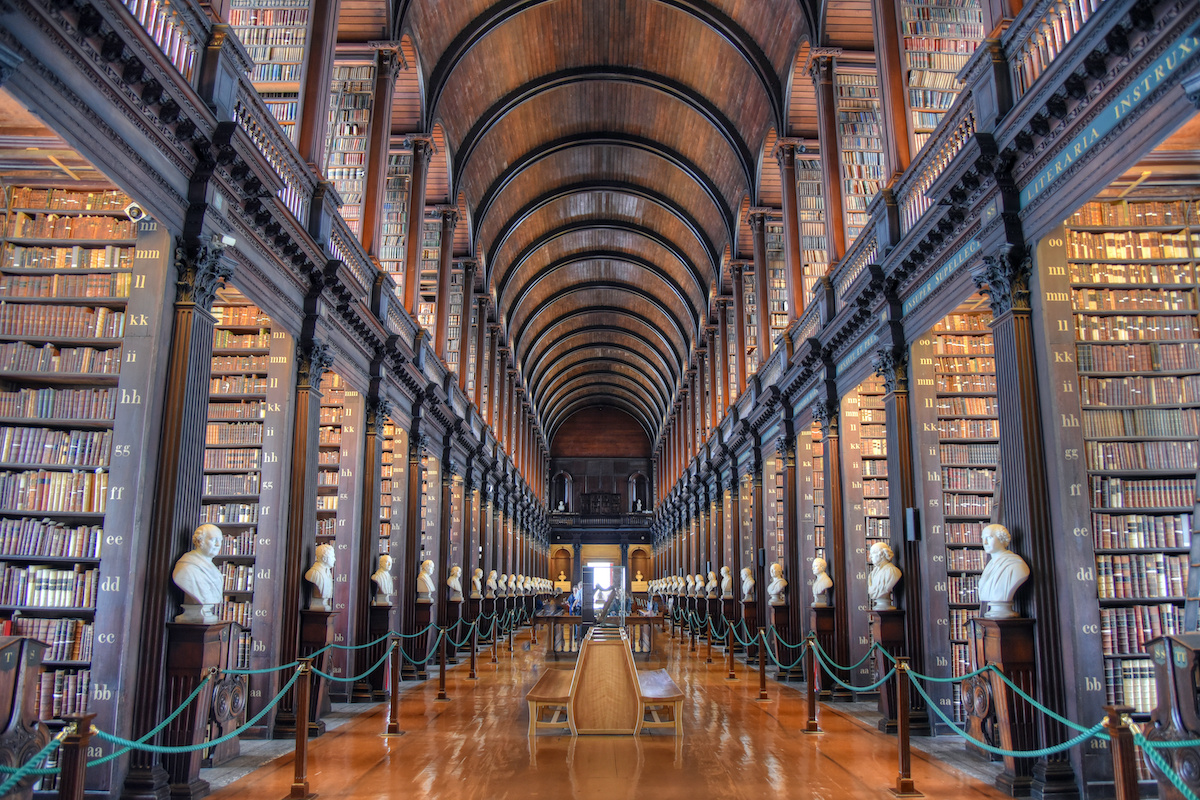
ネットワークシステム、入退室管理システム、カメラシステム構築に関するお問い合わせはこちら
データの長期保存が必要なケースとは?
デジタルトランスフォーメーション(DX)、データドリブン経営といったマネジメント寄りの話題から、ビッグデータ、AI、機械学習まで、現代のビジネスにおけるデータの重要性は改めて説明する必要はないでしょう。日々蓄積されていくデジタルデータは、企業にとってまさに「宝の山」。さらに、取引履歴やPOSデータといった、いわゆるテキストや数字のデータのみならず、顧客の店舗内での購買行動を解析するための動画データ、機械学習に必要な大量の画像データなど、データの種類も広がり、その容量は拡大しています。
データの重要性が飛躍的に大きくなり、データの種類や容量も飛躍的に拡大するなかで、データの保存、特に安全で確実な長期保存は企業にとって新たなテーマとなっています。一例をあげれば、製品開発はもちろん、販売後のリスクマネジメントの観点からも、原材料の調達、製造プロセス、検査に関するデータを保存し、必要なときに即座に利用できるようにしておくことはきわめて重要になっています。企業経営にこれまで以上の透明性が求められている今、データの長期保存は経営の根幹を支えるものといえるでしょう。
データの長期保存に向いている方法

データを長期保存する方法は複数あります。それぞれの特長を見ていきましょう。
長期保存に適したHDDに保存する
HDDは日常的に、最も利用されているデータ保存方法です。しかし、HDDは磁気ディスクを高速回転させて情報を読み書きする構造なため、振動や衝撃に弱く、一般的にはデータの長期保存には向いていないとされています。
しかしHDDのなかにも、データの長期保存に適した耐久性に優れた製品や複数のHDDを組み合わせて、信頼性・耐久性を高めたNAS(Network Attached Storage)、いわゆるネットワークHDDもあります。
オンラインストレージに保存する
インターネット上にデータを保存するオンラインストレージ、あるいはクラウドストレージもデータの長期保存方法の一つです。停電や災害、あるいは盗難などの場合でも、データはクラウド上にあるため影響を受けません。またインターネットに接続できる環境があれば、いつでも、どこからでもアクセスできることも大きなメリットになります。
オンラインストレージも多くの場合、実際の保存手段はHDDですが、厳重なバックアップ体制が取られており、仮に稼働中のHDDにトラブルがあった場合は、バックアップのHDDからデータを復元することができます。HDDのほかに、後述する磁気テープによるバックアップを組み合わせているストレージサービスもあります。
ただし、インターネットを利用してアクセスするため、データの漏洩やデータを第三者に預けることへの不安やリスクは残ります。
光ディスクに保存する
DVDやブルーレイディスク(BD)などの光ディスクもデータ保存手段としてお馴染みのものでしょう。HDDの保存寿命は5〜10年といわれていますが、ブルーレイディスクなどの光ディスクの寿命は10年以上、なかにはデータ保存用に50年以上の耐久性を備えたBDもあります。追記型のBD-Rなら、データを上書きしてしまう恐れもありません。
さらに、DVDやBDよりも、さらに耐久性を高めた光ディスク「M-DISC」が登場しています。M-DISCは記録層に金属系の素材を採用することで、100年以上にわたってデータを保存できるといわれています。M-DISCも上書きできない仕組みになっているため、データを改ざんしたり、誤って消してしまう心配はありません。M-DISCは、データの保存(書き込み)には対応ドライブが必要ですが、読み込みはDVD/BDドライブでも可能です。
磁気テープに保存する
磁気テープは過去の技術のように思われるかもしれませんが、実はデータの長期保存に適した最先端の保存方法です。磁気テープの業界標準規格を利用した「LTOテープ」は、大容量かつ低コストにデータを長期保存できることが最大の特長。2021年発売の最新規格LTO-9では、18TB(圧縮時45TB)のデータを保存できます。寿命は30年、保存状態が良ければ50年といわれます。
さらに低コストも大きな特長です。光ディスクやクラウドと比較した場合、10年間の総コストは圧倒的に低くなります。また汎用性の高さもLTOテープの特長で、テープを1巻ずつ収納するシングルドライブ、複数のテープを収納・自動交換できるオートローダ、数十巻のテープを収納できるライブラリなどの製品があります。大規模なオンラインストレージサービスでは、HDDに磁気テープを組み合わせて、データを長期保存する仕組みを整えています。
データの長期保存に向いていない方法
逆にデータの長期保存に向いていない方法はどのようなものでしょうか。
HDD
HDDは前述したように、一般的にはデータの長期保存には向いていないとされています。可動部分が多く、衝撃や振動に弱いためです。常に電力を必要とすることもデータの長期保存に向いていない理由の1つです。
USBメモリ/SDカード
USBメモリやSDカードは、気軽に使うことができ、データの持ち歩きや、デジタルカメラのデータ保存方法としても広く使われていますが、実はデータの長期保存には向いていません。USBメモリやSDカードの記録媒体として使われているフラッシュメモリは、寿命が3年程度といわれています。
プライベートでは、撮影した写真のデータや動画のデータを、そのままSDカードに入れて保存しているケースがあるかと思いますが、長期保存は期待できないので、注意が必要です。
SSD
最近、ノートパソコンの記録メディアとして使われているSSDもフラッシュメモリを使っているため、USBメモリやSDカードと同様に長期保存には向いていません。最近では耐久性が向上し、寿命はHDDと同程度ともいわれていますが、長期保存に向いているとはいえません。
データを長期保存するためのコツ
データの長期保存は、どのような点に注意すればよいでしょうか。データを長期保存するためのポイント、コツを紹介します。
目的・用途を明確に
今後、データは加速度的に増えることが予想されます。データを長期保存するための手間やコストもそれに比例して増えていくでしょう。なんのために保存するか、どのように活用するかを明確にすることがまず何よりも大切です。目的や用途が明確になれば、データを長期保存するための手法やツールも明確になります。
データのバックアップ体制を構築
データを長期保存するためには、まず日常的にデータをバックアップする体制を構築することが不可欠です。データをバックアップし、活用する体制を整えたうえで、長期保存が不要なデータ、長期保存が必要なデータを見極めます。
利用頻度を見極め、アーカイブ
長期保存が必要なデータも、長期保存したうえである程度の頻度で使用するデータや、文字どおり保管・保存することが重要となるデータがあります。ある程度の頻度で使用するデータは、HDDやオンラインストレージを利用し、利用頻度が低く、保管・保存が最優先となるデータは磁気テープに保存するなど、長期保存の方法・メディアを組み合わせて利用することがポイントになります。
データの長期保存に関するお問い合わせはこちら
パナソニックEWネットワークスは、幅広い事業展開と豊富な実績で製品からワークプレイスの活用提案までトータルでサポートするマルチソリューションカンパニーです。
データの長期保存に関するお問い合わせはこちら。
関連するサービスはこちら
関連情報はこちら
データの長期保存はこれからの企業経営の肝
データの重要性はますます高くなり、データ活用の巧拙が企業の競争力を左右するようになります。そしてデータの長期保存は、データ活用の基盤、大前提。目的・用途に応じて、最適な方法・手段を構築することが企業経営の肝となります。


