3685万人、これは2030年の日本における65歳以上の高齢者人口※1だ。その数なんと総人口の約1/3にあたる。2010年に超高齢化社会へ突入した日本では、今日様々な課題が顕在化しつつある。その解決の鍵は“健康寿命”を延ばすこと。生涯高い自立度を維持しながら健康で長生きできれば、課題の多くが解決できる。そのためにパナソニックが貢献できることは何だろうか。

デザイナーと技術者がひとつになり、たどり着いた答えは、「いつまでも自分の足で歩き続けられる」ためのトレーニングロボットだった。
※1国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口(平成24年1月)」より
INDEX
健康寿命を伸ばすために、自らトレーニングしたくなる気持ちをデザイン
高齢社会で大切なのは “健康寿命”を延ばすこと。そして長く自立して過ごすためには、自分の足で歩けることが重要だ。しかしこの世界トップの長寿国日本において現在、健康寿命を全うし最期まで自立して歩くことが出来る人は1割程度である※2と言われている。筋力維持には歩行トレーニングが有効だが、それも簡単なことではない。トレーニングの継続を促す、心理的にも肉体的にも負担感の軽いものでなければならない。また、医療・介護現場で使ってもらうことを考えると、忙しいスタッフ方々にとっても、できるだけ効率的かつ効果的に行えることが重要なポイントになる。

パナソニックが培ってきたテクノロジーにデザインの力を掛け合わせることで、自らトレーニングしたくなるものが実現できないか。それは、仕方なくトレーニングするものではなく、能動的にトレーニングしたくなる「気持ち」をデザインすることへの挑戦でもあった。
※2秋山弘子(2010)『長寿時代の科学と社会の構想「科学」』岩波書店より
操りたくなる造形を求めて、試行錯誤を繰り返した
まずは使いたいと思ってもらえるカタチをつくること。技術者が先行して作っていた1号機、2号機のカタチを徹底的に見直した。どうしたら使う姿が“かっこよく”見えるか、どうしたら様々な体格や体調の人にも使いやすいものになるか。

高齢者疑似体験装具を身につけ実際に使ってみながら、チューブや緩衝材を貼り付けたりしながら検証し、発泡モデルでカタチを詰めていく。そうして見出されたのが、寄りかからせるのではなく、自然な姿勢で「押す」ポジションになるような、本体の傾斜角度やハンドルの位置。それは狙い通りトレーニングの姿勢まで“かっこよく”見せるものになった。

ハンドルはこだわりの円形状で、個人のステージに合わせて持つ場所を自由に変えられる。また、グリップの最適な太さは、検証の結果、お孫さんくらいの手首に近い太さになった。更に、足回りは前輪を大きくし、操作性と安定性を確保した。
「骨格革新」と「能動造形」をコンセプトに、歩行トレーニングロボのデザインをゼロからつくり直した。

モチベーションの継続に、もっとデザインができること
気軽に使えることと効果の実感、この両立がトレーニング継続には必要だ。ここで重要となってくるのがインターフェースデザインである。

まず歩行中の画面は、状態が分かりやすくて操る喜びが得られる、タコメーター風のデザインを採用。センシングした身体の傾きなどの情報が、大きなグラフィックと配色で直感的に分かりやすい。老眼でも見やすい配置で、歩行中の自分の状態を認識し、改善・向上が意識しやすくなるようにした。
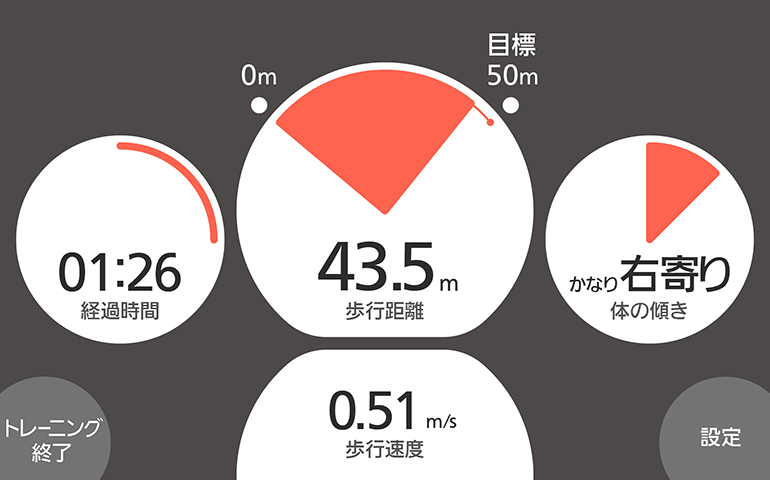
次に、ユーザーの名前を呼びかけたり今日の目標を語りかけたり、コミュニケーションを意識したメッセージで親しみやすいものとしている。更に、運動内容は人型のアイコンで分かりやすく示され、誰もが直感的に使え、また使ってみたくなるものとなった。
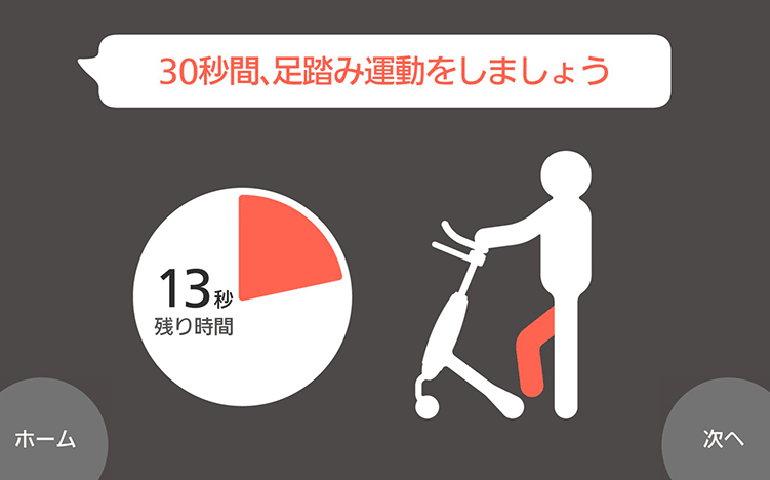
ユーザーを支援する、医療・介護スタッフの気持ちをデザイン
目標や成果が数値化でき、使用者だけでなくスタッフにも分かりやすい指標になっている。ログが残せ、一ヶ月前、一週間前など過去の状態との比較も容易だ。「改善してきたけれど、ちょっと右に傾いているので意識しましょう」といった具体的な指導も可能になる。また補助金申請のために書類作成が必要だが、これもAIで自動化。後で思い出しながら一枚一枚手書き、と大きな負荷になっていた報告書作成作業を大幅に軽減。忙しいスタッフの限られた時間を、その分利用者のケアに充てることができるようになった。現場業務の実情を知ることで、その大変さを軽くする「気持ち」の部分までをデザイン開発に取り入れることができた。
バリアを取り除くことで、高齢者の方々に笑顔を
歩行訓練ロボットを使用して歩き始めるようになると、自然と会話の量が増え、長く消えていた笑顔が再び戻ってきた方もいた。
分野の壁を越えチームとして協力することで、日本の課題に一つの解決策を示すことができたことを誇りに感じている。


