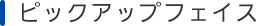「いま、すべきこと」。そして、「次の一手」をも考え抜く姿勢が、運を呼び込む。堅守でチームを支え、シャープにさばく。「流れは渡さない」。苦しい時にこそ、三浦の存在感が大きくなるだろう。
多芸多才ながらも、野球のとりこに

幼い頃の三浦は、野球に水泳、空手、サッカー、書道と稽古事を多才にこなしつつも、学習塾にも通う、文武両道を地でいく少年だった。器用で運動能力に優れ、集中力もある。野球だけではなく、水泳や空手でも優秀な成績を収め、小さい体ながら「怪物」と呼ばれもした。野球は小学1年の時、知り合いに誘われてお寺のお坊さんが監督を務める明通寺涅槃(ねはん)というチームで始めた。お経を読むこと、正座することも練習の一環だった。
2年生で早くも上級生チームの試合に出場した三浦。対峙した6年生のピッチャーにセカンドゴロに打ち取られ、悔し涙を流した。「先輩は三振ばかりなんだから、当てただけですごいよ」と慰められても、気持ちは静まらなかった。5年生の時の「足を痛めながらのランニングホームラン」というエピソードも、人一倍負けず嫌いな三浦らしい。

「小さな怪物」という名のままに活躍した少年時代。投げては、ノーヒットノーランを12度も達成したという。「1週間のうちで、待ち遠しかったのは土日の野球。一つひとつの動作を、力加減やタイミングを考えて連動させる。複雑な動きの中で結果が生まれることが面白くて」と、野球にほれ込んだ少年時代の目の輝きをよみがえらせた。
そんな三浦を、家族は骨身を惜しまずサポートした。野球の「や」の字も知らない父親が、仕事を終えてから練習に付き合ってくれた。2歳下の弟が野球を始めると、家族4人で明かりがついている夜のグラウンドへ出掛けては、消灯するまで練習をした。「家族はいつも、僕がやろうとすることをしっかり支えてくれた」と、温かな表情で振り返る。
野球と向き合う覚悟ができるまで

中学生になり、硬式野球の愛知尾州ボーイズに入団する。軟式野球部との掛け持ちは難しいため、「ここからは硬式を」と決め、学校ではフットワークや反射神経を野球に生かそうと卓球部に入部した。ボーイズでは「僕が強いチームにするんだ」と意気込んだものの、公式戦では負けてばかり。「でも、3年になったとき、新たな出会いがあったんです!」と、三浦は身を乗り出して話し始めた。それは、甲子園出場経験のある藤川コーチの参入だった。
技術や知識が豊富で、何より人として信頼できる魅力あふれる野球人だった。皆、忘れかけていた情熱を爆発させるように己を磨き、チームの士気も高まった。短期間でも、一つ、二つと「勝てるチーム」への成長を実感することができたという。藤川コーチに導かれ、東海大菅生高校へ進学した。しかし入学早々、厳しい練習で腰を痛めた。体作りのため、夕食にご飯3杯、おかず4、5品の完食を義務付けられた寮生活にもてこずった。親元を離れての2カ月で、ストレスから胃潰瘍にもなり、心身共にボロボロになりながらも、落ち込む間もなく鍛錬の日々が続いた。

三浦は経験の少ない「守備」を課題と自覚し、自主練習ではノックを打ってくれる人を捜し求め、キャッチング練習に取り組み続けた。「上手な先輩の捕球プレーを見て研究し、実践してみたら、あるとき驚くほど気持ちよく捕って投げて。『これだ!』と思い、時間を忘れて夢中でボールを捕り続けました」とボールを放るしぐさをしてみせた。ここから先は、センスだけでは通用しない。野球と向き合って人生を歩むには、自らを変える覚悟が必要だった。
恩師との絆をつないで

長嶋茂雄に憧れて、三浦はサードを狙っていた。1年の秋、三浦はベンチ入りを告げられるも、「お前は小さいからセカンドだ」と監督に指示された。新チームのメンバー入りを喜ぶ半面、監督の言い草を真に受けてサード奪取に闘志を燃やした。次第に中継プレーやダブルプレーなど、セカンドの面白みを知り、メキメキと実力をつけていった。2年の夏、甲子園を懸けた日大三高との決勝戦では、センターへ抜ける当たりを好捕し、スタンドをも沸かせた。試合には敗れたものの、三浦いわく「野球人生屈指のファインプレー」だった。
最上級生になり、チームは甲子園出場が期待される実力をつけた。しかしメンバーの故障が相次ぎ、夏の地区大会は4回戦敗退に終わった。個の技術、団結力、そして熱い気持ちもあった。でも勝ち切れなかった――。監督は常々「野球の基本は何だ」と問いかけていた。三浦は結果を振り返り、「それは自己管理能力なのかなと。どこかに潜む油断や隙が、けがを招いたんだ」と悟った。

横井監督は、高校野球の在り方、そして人間としての在り方を生徒に徹底して指導した。監督の厳しい態度の中に、見守ってくれている温かさも感じながら、「強くなるには、勢いに流されず本質を捉えること」と知った。気持ちがはやる時こそ、やるべき基本を忠実に。そうして「一歩先に進む」感覚をつかんだ高校時代だった。
監督の強い勧めで決めた進学先は、スター選手がそろう東海大。不安をかき消すように体をいじめ、筋力を蓄え、走り、打ち込み続けたが、先輩たちの打力には追いつけず、2年間の下積みに甘んじた。3回生の春、レギュラーから離脱者が出たことで、三浦は一念発起。同級生にバッティングの教えを請い、打力を磨いた。オープン戦ではチーム一の打率をあげ、リーグ戦で首位打者争いに食い込む存在感も見せた。しかし大学リーグは甘くはなく、結果は準優勝、首位打者もベストナイン入りも逃した。
最終学年に再起をかけた三浦に、奮い立つ出会いが再び訪れる。高校時代の恩師、横井氏の東海大野球部監督就任だ。監督の人間味に触れた面々は一挙に団結し、チームの本気が凝縮された1年となった。チームは再度準優勝に終わったが、個人では春・秋とベストナインを獲得した。
安定感を増し、人として野球人として成熟を

2009年、パナソニック入社当初は「打率は3割、これはいけるなと思っていた」と告白する。けがをした先輩の代役で都市対抗本選に出場したが、プロ入りも意識した2年目はチーム自体も成績が振るわず、チャンスが巡ってこなかった。月日を重ねるごとに、先輩らの姿から社会人の技術力、そして「ここ一番」の仕事ぶりが見えてきた。そして、自分との差が浮き彫りになり、「今のままじゃだめなんだ」と思い知らされる。
「"いつか打つ"では通用しない。俺に今できることは何だ」と悔しさの原因を自分の中に問い詰めていった。3年目、出した答えはスイッチヒッター。左利きを生かした三浦のチャレンジを、コーチや監督も後押ししてくれた。出場機会は増えたが、打ちどころで打てず、都市対抗本選で補強選手が入るポジションというチーム内の位置づけに変わりなかった。三浦は「もっと当たり前のことを見つめよう」と、さらに考えを深化させた。

ベンチでは、生還した選手を誰よりも先に迎え出る。声を出し、パフォーマンスでチームの活力を球場中にアピールした。ベンチにいる選手にしかできないことを、徹底的に考え抜いて行動した。次第に代走や守備固めの機会が増え、チームのチャンスを得点につなげていった。「試合に出続けるのは、当たり前のことがきちんとできる安心感、安定感のある選手。厳しさと悔しさを味わったからこそ、やっと気づくことができました」と6年目を迎えた心境を話す。
「後輩には厳しさを伝えながらも、持ち味を伸ばしてほしい。野球以外の気配りは自分らの役目」と、中堅としての意気込みを語る。そして自身の目標は「『絶対にエラーをしない』と誰もが認める内野手に」とこぶしを握り締めた。志を定めた三浦の強みは、チャンスへの反応の良さとスタートダッシュの速さだ。今、迷いがないのは経験を積み上げてきたからこそ。素早く状況判断をし、人より速く一歩目を踏み出せる思い切りの良さ、そして偶然をそのままにせず自分のものへと進化させていくのが、師に恵まれ続けた三浦流の野球人としての在り方だ。
三浦の武器は、器用さとセンスのみならず。
一球たりとも、一瞬たりとも無駄にせず、常にチャレンジをし続ける。
助走は十分、「いく」と決めたら誰より速く目標地点まで走り切る。